イスラエルのテルハイ大学(Tel-Hai College)で行われた研究によって、ADHD(注意欠如・多動症)を抱える成人がピアノやギターなどの楽器を練習すると、薬物療法や脳トレに代わる“脳のジム”として働き、認知テストの成績を総じて向上させる可能性があることが明らかになりました。
集中力や計画力を伸ばす新たな手段として音楽を活用できるとしたら、その仕組みはいったいどのように脳を変えるのでしょうか?
研究内容の詳細は『Psychological Research』にて発表されました。
目次
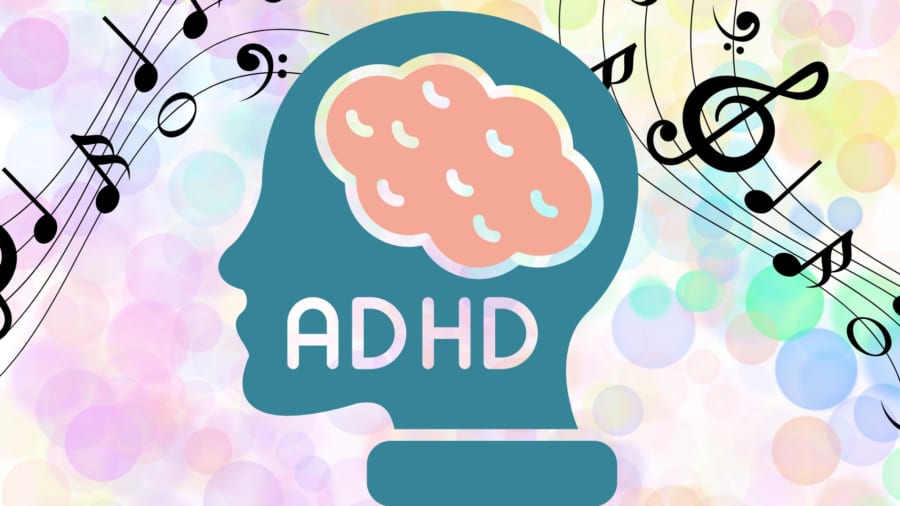
ADHDは注意力の維持や衝動のコントロールが難しい発達障害で、子どもだけでなく大人にも見られます。
大人のADHD当事者は、学業や仕事、人間関係など様々な場面で集中力の低下や不注意による困難を抱えがちです。
その治療には主に薬物療法(例えば神経刺激薬の投与)や行動療法(認知行動療法など)が用いられてきましたが、それだけでは十分でない場合も多く、脳の認知機能そのものを鍛える新たなアプローチに注目が集まっています。
一方、音楽が脳に与える良い影響については以前から知られています。
楽器演奏や音楽訓練は脳の可塑性を高め、記憶力を伸ばし、情動を安定させる効果が報告されています。
例えば子ども時代に楽器を習うと、空間認知や言語、数学の能力が長期的に向上するとの研究もあります。
またADHDでは集中力を維持しにくいとされますが、音楽を聴いたりリズムをとったりしているとき、脳の覚醒度がちょうどよいレベルに保たれやすいという説があります。
音楽を活用することで脳内報酬系を刺激し、注意や集中を助ける効果が期待できるのです。
また音楽はリズム(規則的な構造)を持つため、ADHDで散らばりがちな思考を「枠にはめて」あげる役割も果たします。
音楽療法士98名を対象としたある調査では、87%もの療法士が「音楽療法は薬物療法との併用でADHD治療に有効」と考えており、特に行動面(94%)や心理面(89%)、認知面(69%)での改善を目標に掲げていました。
シニア世代でも、新たに楽器演奏を始めることで言語の記憶力など認知機能が改善したという報告があるほどです。
さらにいくつかの研究では楽器ごとにADHDの症状に異なる影響を与える可能性が示されています。
特に「鍵盤系(ピアノ)が注意 ・ワーキングメモリの改善に効果があり」「打楽器(ドラム)が衝動・タイミング制御に効果がある」 というペアは複数のデータで再現されています。
鍵盤や複雑なコード進行は 両手協調・譜読み・聴覚‐視覚‐運動のマルチタスク を同時に要求します。
結果として前頭前野‐小脳ネットワークを長期的に鍛え、「集中 → 記憶保持 → 制御」 の一連を底上げしていると解釈されます。
またADHD ではミリ秒〜数秒単位のタイミング誤差が衝動的ボタン押しや“フライング発言”につながるとされます。
そのためドラムやメトロノーム練習でリズム誤差を修正すると、脳内の運動時計&抑制回路(補足運動野・基底核)が再調整されるため、衝動行動が減ると考えられます。
しかし楽器演奏という面においては、ADHDへの効果を調べた研究はまだまだ限定的でした。
そこで今回イスラエルのSivan Raz氏らは「楽器の長期訓練がADHD成人の認知能力に関連する改善をもたらすか」を検証することにしました。

研究チームは18〜35歳でADHDと正式に診断された若年成人94名を募集し、楽器演奏歴のあるグループと演奏経験のないグループに分けました。
楽器演奏者グループはピアノまたはギターを少なくとも5年以上継続して習熟している48名で、対照となる非演奏者グループは楽器の正式な訓練経験がない46名です。
両グループは年齢、性別、学歴、社会経済的背景をできるだけ揃え、さらに調査期間中は誰もADHDの薬を服用していない状態としました。
これにより、薬や環境要因ではなく純粋に楽器経験の差が認知機能に表れるかどうかを比較できるよう配慮しています。
全ての参加者は一連の標準化された認知テストを受け、そのスコアで両グループを比較しました。
テストの内容は多岐にわたり、主なものとして次のような項目が含まれます:数字と記号を対応させできるだけ速く書き込む処理速度・注意力テスト(WAIS符号テストに相当)、画面上のシンボルパターンを探す視覚的な注意力テスト、数字の列を記憶して順番どおりまた逆順で復唱する記憶力テスト(数唱)、課題のルールを次々と切り替えて解く柔軟性・マルチタスク能力テスト、そして特定の刺激にだけ反応し他では反応を抑制する持続的注意/衝動抑制テスト(CPT:Continuous Performance Test)などです。
これらにより、注意の持続や処理スピード、作業記憶、認知の柔軟性、衝動の制御といったADHDで課題となりやすい様々な認知機能を測定しました。
結果は明快でした。
ほぼあらゆる指標で、楽器演奏者グループが非演奏者グループを上回ったのです。
まず情報処理速度と視覚的な注意力を測る符号書き取りや記号探しのテストでは、演奏者の方が有意に高得点をマークしました。
これは情報を素早く正確に処理する力や視覚注意の能力が演奏者のほうが優れていたことを示唆します。
また記憶力を調べる数唱(順唱・逆唱)でも演奏者が非演奏者を上回り、ワーキングメモリ(作業記憶)や聴覚的な記憶保持力の強さがうかがえました。
これらの傾向は、これまで一般集団で音楽トレーニングが記憶システムや処理効率を高めるとされた先行研究とも一致しています。
さらに認知の柔軟性を測る課題切り替えテストでは興味深い差異が見られました。
最も難易度の高い切り替え課題において、演奏者は非演奏者より反応時間がわずかに遅れたものの、その代わりエラーが少なく反応のブレも小さいという結果だったのです。
一見「遅い」のは悪いことのようですが、これは慎重で落ち着いた対処を示しており、衝動性が高くミスが出やすいADHDではむしろ望ましい戦略と考えられます。
実際、演奏者グループは素早さよりも正確さを優先する熟考型のアプローチで課題に取り組んでいたと解釈できます。
ADHDの中核症状である衝動性の高さを抑え、ミスを減らすことに成功していたわけです。
衝動性という点では、持続注意・抑制のテスト(CPT)でも顕著な違いが確認されました。
演奏者グループは、反応してはいけない場面でつい反応してしまう「コミッションエラー」の数が非演奏者より大幅に少なかったのです。
このエラーは抑制力の弱さ(衝動的にボタンを押してしまう)を反映しますから、演奏者は非演奏者に比べ衝動を抑える力(抑制機能)が高いことを意味します。
一方で、注意を持続する能力そのもの(決められた刺激に反応し続ける集中力)についてはグループ間の差は小さく、統計的に有意といえるほどではありませんでした。
つまり音楽経験者では特に情報処理や記憶、そして衝動制御といった領域で顕著な強みが示され、一方で持続的な注意力についてはわずかな改善傾向こそあれ同程度だったと言えます。
総合すると、楽器演奏グループはADHDで弱点となりがちな広範な認知スキル(注意配分、ワーキングメモリ、情報処理速度、認知の切り替え・抑制など)において優位に立っていました。
これは「楽器の練習という経験が、ADHD当事者の脳の認知機能を底上げしている可能性」を示唆するものです。
特筆すべきは、参加者の中には17歳を過ぎてから楽器を始めた人もいた点です。
幼少期から英才教育を受けなくとも、青年期・成人期からの音楽訓練であっても、効果が見込める可能性があるという希望を与えてくれます。
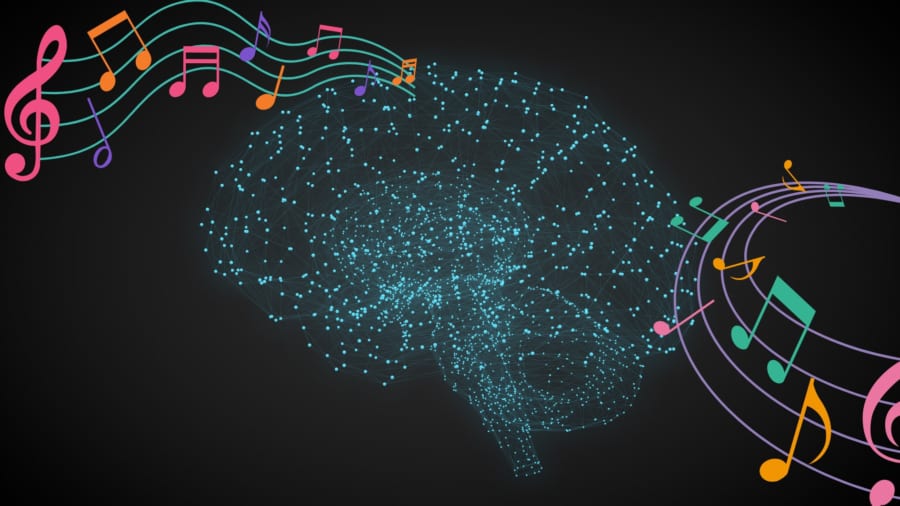
なぜ楽器演奏がこれほど認知機能に好影響を及ぼすのでしょうか。
その理由として研究者らは、楽器練習自体が脳に対する総合的なトレーニングになっている点を指摘しています。
楽器を演奏するには曲に集中し続ける注意力、楽譜や指使いを記憶する記憶力、指先や体の精密な運動協調、そして音や視覚情報を同時に処理する能力など、実に多彩な脳機能をフル稼働させる必要があります。
まさに脳の全身運動と言える活動であり、長年にわたるこうした「認知の筋トレ」が注意や実行機能を司る脳回路を強化するのだろう、とRaz氏らは述べています。
実際、過去の脳画像研究では楽器演奏者の脳構造に一般の人とは異なる特徴が見られます。
たとえば前頭前野(注意や行動制御を担う脳の前部)や小脳(運動制御だけでなく認知面にも関与する領域)に、音楽家特有の構造的な違いが報告されており、これらはいずれもADHDで機能不均衡が指摘される部位です。
音楽訓練によってこうした脳の要所が物理的・機能的に鍛えられ、その結果として認知テストの優位性につながった可能性があります。
加えて、今回の知見は先行研究で考えられていた音楽介入のメカニズムとも合致します。
専門家による包括的レビューでは、音楽活動が計画力・集中力・衝動抑制など実行機能を高め、ADHD児の時間管理やタイミング感覚の発達を助ける可能性があると指摘されていました。
楽器演奏には集中力の持続、複数の感覚の同時処理(楽譜を見ながら音を聞き手を動かす)、練習の繰り返しによる記憶など、多くの認知要素が必要です。
そのため練習によって脳内の注意・実行機能ネットワークが鍛えられた結果がテスト成績に表れたと考えられます。
またリズムに合わせて演奏する訓練は脳内の神経活動を同期させ、認知処理の効率を上げるとも考えられています。
このように音楽には脳内ネットワークを整える作用(過度な興奮をしずめ必要な部分を活性化するなど)があり、それがADHD症状の改善につながり得るというわけです。
音を楽しみながら集中力アップにつながるなら一石二鳥と言えるでしょう。
もっとも、今回の研究デザインは「長年楽器をやってきた人」と「やってこなかった人」の断面比較であり、音楽が直接これらの能力向上を「引き起こした」ことを厳密に示したわけではありません。
言い換えれば、因果関係の証明には慎重さが必要です。
研究チームも「元々認知コントロールが高めの人が音楽を続けやすかった可能性」を完全には否定できないと認めています。
そこで今後の課題として、たとえばADHDの人に新たに楽器練習を始めてもらい、その前後で認知機能の変化を追跡する縦断的研究が望まれます。
実際に音楽トレーニングを導入してみて、時間の経過とともに注意力や記憶力がどう伸びるのかを観察できれば、因果関係の方向をより明確にできるでしょう。
またADHDの亜型(不注意優勢型か衝動多動優勢型か等)による効果の違いや、楽器の種類ごとの有効性も検討の余地があります。
あるタイプのADHDにはリズム楽器が特に効く、といった可能性も考えられるためです。
さらに神経科学的には、楽器訓練による脳内変化を直接見るため脳画像法を組み合わせることも有益でしょう。
どのように脳構造や機能が変わっていくのかを捉えれば、音楽がADHD脳に与える影響を一層はっきりと描き出せるはずです。
今回の発見は、楽器演奏というアプローチがADHDの新たなリハビリテーション手段になり得る可能性を示唆しています。
もちろん薬物療法や行動療法が第一選択である点に変わりはありませんが、その補完的な位置づけとして音楽を取り入れる価値は十分考えられます。
実際、一部の参加者は17歳以降に楽器を始めたにもかかわらず効果が見られたことから、大人になってからでも遅すぎることはないようです。
指先から奏でるメロディーが脳を刺激し、注意力や記憶力を向上させてくれる――そんな副作用のない楽しいトレーニングなら、当事者にとって取り組みやすく自己肯定感にもつながるでしょう。
研究者らは「音楽によるプログラムを療法に組み込めば、楽しみながら認知機能を伸ばすことができ、ADHDの人の生活機能を向上させる非スティグマ的な方法になり得る」と期待を寄せています。
今後さらなる研究が進めば、音楽スタジオがADHDケアの現場の一端を担う日が来るかもしれません。
元論文
Enhancing cognitive abilities in young adults with ADHD through instrumental music training: a comparative analysis of musicians and non-musicians
https://doi.org/10.1007/s00426-024-02048-2
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。
大学で研究生活を送ること10年と少し。
小説家としての活動履歴あり。
専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。
日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。
夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
Be the first to comment