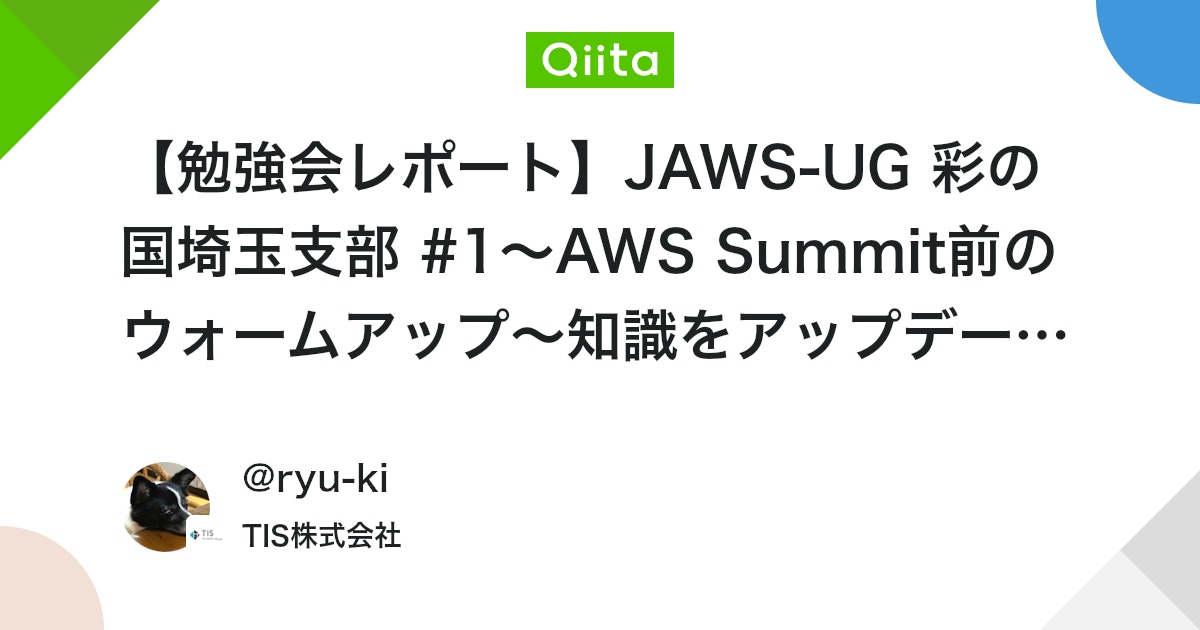
2025/5/10に開催された「JAWS-UG 彩の国埼玉支部 #1〜AWS Summit前のウォームアップ〜知識をアップデート!」に参加させていただきました。簡単ではありますが、イベントレポートを残しておきたいと思います。
本記事は勉強会参加時に作成したメモや、公開されている資料をもとに作成しており、間違いなどが含まれている可能性がございます。誤った説明がされている場合はご指摘いただけると幸いです。
以下の14セッションが実施されました。
- 運営企画セッション
- 「彩の国埼玉支部はこうして新たに創設された!」
- サブイベント 「与野ばらまつり見学会」 実施報告
- 運営LTセッション
- アウトプット0のエンジニアが半年でアウトプットしまくった話 With JAWS-UG
- ANS-C01 2回不合格から合格までの道程
- AWSを利用する上で知っておきたい名前解決の話
- 雑に疎通確認だけしたい…せや!CloudShell使ったろ!
- 公募セッション(AWS Summit Japan 2025のお勧めの楽しみ方)
- セッションだけじゃない AWS Summitのおすすめ
- AWS Summitを楽しむ3つのポイント
- 公募セッション(フリーテーマ)
- Amazon SES外部プロバイダーのドメイン検証に注意!
- 実践:マルチアカウント環境構築
- Amazon Q CLIでMCP Serverを使ってKnowledge Baseを呼び出してみた
- あの日の決意表明から23日。AWS SAAに合格することはできたのか?
- 令和のミニ四駆!? AWS DeepRacerで強化学習に入門してみた
- エンジニアの世界の広げ方 -凄腕エンジニア達が実践する学びの秘密
タイトルの通り、彩の国埼玉支部創設(と#0開催)についてお話しされていました。勉強会開催に向けた準備のお話を聞いて、このような場に参加させていただけてありがたいなという思いがより強くなりました。
また、支部ロゴの発表もありました。語彙不足で申し訳ないのですが、とても良いなと思いました。
今回の勉強会の前に、サブイベントとして「与野ばらまつり見学会」があり、そちらのお話をしていただきました。地域別のユーザーグループですので、このような地域の魅力を共有できる場があるのはよいなと思いました。
それまでアウトプットをしたことがなかったが、インプットの気晴らしに興味のあることについてブログ執筆したことをきっかけに、アウトプットの良さに気づき、積極的にアウトプットすることができるようになったといったお話をされていました。
「初心者にこそ、JAWSがおすすめ」とお話しされていましたが、実際、とてもポジティブな場で皆さんが前向きに話を聞いてくださるので私もその通りなんじゃないかなと思いました。
2023年にANSに2回挑戦するも不合格で、その後2025年1月に再挑戦で合格されたという経験からどのようなことをしたり、感じたりしたのかをお話しされていました。再挑戦のきっかけの1つに、AWS認定資格に関するイベントがあったそうで、私も勉強会などに参加するとすごくモチベーションが上がるので共感できました。
また、実際に受験するにあたって以下の2つのことをされたそうなのですが、それが印象に残りました。
- 試験日を自分の誕生日に設定する
- ホワイトボードを積極的に活用する(当日は2回交換されたそうです)
AWSの各リソースにはFQDNが与えられ、基本的にはそれを用いて通信が行われることから、名前解決のことを知っておくことは重要で、今回はその基本的なお話をされていました。
私自身、資格勉強等でなんとなく知っている部分があるものの、他の人に説明できるほどわかっているのかと言われると正直自身がないので、今回を機に基本的なところから情報を整理したいと思いました。
疎通確認をするためだけに、EC2を立てようとしなくても、CloudShellでできる場合があるといったお話をされていました。私はほぼCloudShellを使う機会がなかったのですが、こういった便利な使い方があるんだなと勉強になりました。
AWS Summitの楽しみ方についてお話しされていました。特に私が印象に残ったことをいくつか記載します。
- 基調講演・スペシャルセッション
- 参加するならメイン会場がおすすめ
- セッション
- 全体的には参加しなくても…?
- 直接体験できることをした方がおすすめ
- ただし、事例セッションは会場でしか聞けない
- 全体的には参加しなくても…?
- GameDay
- 当日枠でのエントリーも可
- 今年はBedrockをいい感じに使う
また、以下の記事やこちらの2025年版も近々投稿されるようなのでこちらも参考になるそうです。
私は今回初参加予定なので、基調講演を聞いてみたり、Ask the expertでAWSの学習相談とかをしてみたりしたいなと思いました。
こちらでも、AWS Summitの楽しみ方についてお話しされていました。こちらも私が印象に残ったことをいくつか記載します。
- 1日目のキーノートは参加すべし
- 盛り上がりを聞いているだけでも楽しい
- AWSを活用している会社の事例も得られる
- AWSの中の人や、AWSを活用している企業のエンジニアと話せる
先ほども書きましたが、当日はいろいろなお話が聞けるといいなと思っています。
SESを本番環境で利用する際に必要なドメイン検証に関するお話をされていました。Route53だとコンソールで簡単にできるそうですが、外部ドメインだと検証コードの発行などの手作業が必要だそうです(AWSを使うならドメインはRoute53で管理しようとのこと)。私もSESは使っているのですが、現状は基本的に送信先が固定でサンドボックス環境を使っているので、今回のお話は今後の参考になりそうだなと感じました。
Control Towerを使って、マルチアカウント環境構築された際のお話をされていました。AWS Black Beltなどを参考にしつつ、Control Tower、Identity Centerは簡単に構築できたそうです。私は以前、勉強会でOrganizationsを使ってマルチアカウント環境を準備したことがありましたが、Control Towerを使ったことはほぼないので触ってみようと思うきっかけになりました。
Amazon Q CLIでのデモを通じてMCPがどのようなものなのかをお話しされていました。私も少し触りだしてはいたものの、プロファイルごとの使い分けなどはまだできていなかったので、実際にどのように動くのかなどを見れて勉強になりました。
また、AIエージェントを見据えたリポジトリ設計が重要というお話もその通りだなと感じました。
参考:共創未来インナーソースマン
JAWS-UG 彩の国埼玉支部 #0でSAAの学習を通じて感じたことをお話しされていたものの、まだSAAの受験すらしていなかったそうで、先日受験し、その結果を今回はお話しされていました。
結果は無事合格だったそうです(おめでとうございます!)。私もまだ3冠しか持ってないので頑張ろうと思いました。
AWS DeepRacerと強化学習のさわりについてお話ししました。2025/12で終了予定ですが、ちょっと触ってみようかなと思っていただいていれば幸いです。
「ベテランエンジニアはなぜキャッチアップが早いのか?」という疑問に対して、その理由についてお話しされていました。以下のようなことを、好奇心・楽しむ心を燃料にして取り組まれているそうです。
- 知識の砂山
- 砂山は下が広くなる(→細く高く積み上げられない)
- 基礎知識がしっかりしていると、新技術についても上に乗せやすい
- 抽象・概念化
似たような話は聞いたことがありましたが、「知識の砂山」という表現は初めて聞き、とても素敵な表現だなと思いました。また、基礎知識をしっかり身に着けたいなと思いました。
以上がレポートになります。私は、全然埼玉に縁もゆかりもありませんでしたが、とても楽しく勉強になりました。思っているよりお家から近かったので(普段出社しているオフィスよりもすこし近いくらい)、予定が合えばまた参加させていただきたいと思います
ありがとうございました。
以下少し自分語りになってしまっているので興味のない方は読み飛ばしてください
今回私はDeepRacerについてLTしましたが、懇親会でなぜDeepRacerの話をしたのか聞かれたので、こちらでも書いておきます。
- LTが募集されているのをみてとりあえず申し込んだ
- もともとDeepRacerの話をしたいと思っていたわけではない
- せっかく話すのだから何かタメになる(もしくはそのきっかけになる)ような話をしたい
- まだAWSを触りだして1年にも満たないので、メジャーなサービスの話をしても、聞いている人のタメにならなさそう
- Claudeくんに相談してみる

- DeepRacerにビビッとくる
- 調べてみると強化学習を学ぶことができるサービス
- もともと学生時代、研究室で機械学習を触っていたので大まかな話は簡単に理解できそう
- 実機を走らせる大会もある
- 去年のSummitでも大会が開催されていた
- Qiitaやspeakerdeckを軽く調べた感じ、ほぼ情報がない
- 認知度はあるが、実際どういうサービスなのかの知名度は低くそう
- 学習結果を見てもらいやすい
- コースを走っている様子を見てもらうと誰でもわかりやすい
- 調べてみると強化学習を学ぶことができるサービス
以上のような形で、今回の発表内容が決まりました。(わかってもらいたい思いが強くなりすぎて資料が多くなり、結局発表時は読み飛ばす形になってしまいましたが…)
ただ、このような変化球を投げ続けることもなかなか難しいと思うので、メジャーなサービスの理解を深めてそちらで何か面白いことができればと思います。
Views: 2


