最近『リバース:1999』というゲームのプレイを再開した。ストーリーが売りのゲームではあるが、飽きて1度プレイを止めた。そして再開した形だ。今ではガッツリ楽しんでいる。しかし周りでプレイしている人がおらず好き語りができない。ならば布教せねばなるまい。一度止めたゲームを再び楽しめている、その理由を含めて。本稿はそういう趣旨の記事である。
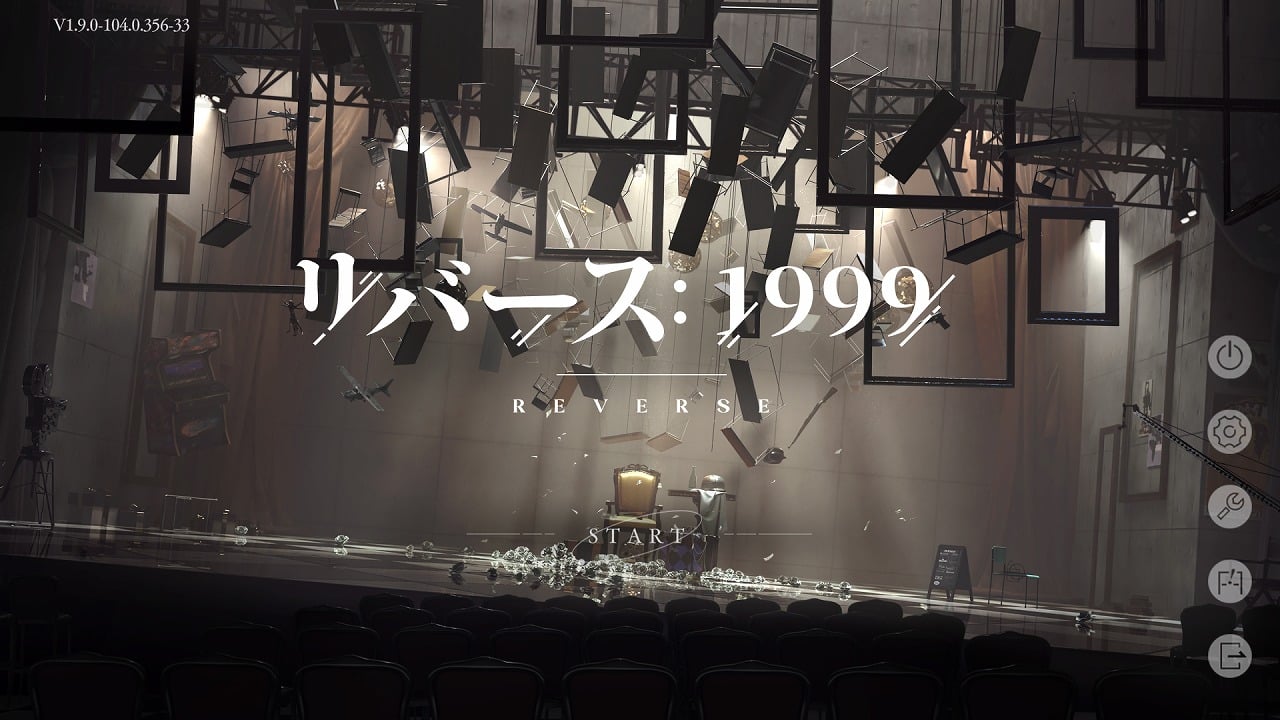
本作は気軽にオススメできるクオリティのゲームではない、という印象をかつての私は抱いていた。なぜなら、各種ゲームモードの出来が悪いと思っていたからだ。たとえば、本作のメインコンテンツであるコマンド式戦闘とキャラクターデザインに関して。プレイしていた当時のプレイ環境では強すぎるキャラの実装により、早々としたキャラの型落ちの発生を感じたほか。あまりにキャラが強すぎるため、ゲームルールが粉々に破壊されてしまっていた印象があった。専用ステータスをスタックして火力を出せば勝てる……高難易度なボス戦においても画一的な体験のゲームだと感じていたた。
これに連動する形で影響を受けていたのが、本作に実装されていたローグライトな戦闘コンテンツである。このコンテンツはステータスに影響を与えるアイテムを獲得し、パーティを強化。ダンジョンを攻略していくゲームモードである。しかしながら、キャラクターがもともと強いため、標準的な難易度においてステータス強化の影響がわかりづらく、ゲームモードならではの体験を提供できているとは言えなかった。昨今の類似作品に付き物である、エンドコンテンツ参加までの繋ぎとして機能するミニゲームについても同様のことが言える。本作には簡易な謎解きゲームと、月替りのイベントに合わせて実装されるミニゲームが用意されているが、筆者としては楽しめていなかった。
本作は文字とライブ2Dによる映像演出を中心とした物語体験を売りにしているが、あくまでベースはコマンド式戦闘のRPGであるため、体験から上記の内容を切り離すことはできない。。ゆっくりとモチベーションを削がれた私は、次第にプレイを止めてしまったのだった。しかし、情報は追いかけていた。とにかくスピーディに体験の改善を行っていることは確認していた。ゲームテンポの高速化だけでなく、既存キャラの強化や、新たなバトルコンテンツの実装。それに合わせたメカニクスの変貌。なるほど面白そうだ。やがて私は戦闘の攻略にハマり、本作をビジュアルノベルからRPGと認識を改めて今に至る。

では『リバース:1999』の戦闘はどのように変わり、何が面白いのか。端的に言うと、「パーティ全員で戦う」戦闘を展開するようになった。従来のRPGにお馴染み、ロール毎に職務を遂行するという戦いの発展型として、パーティ全体を使った戦法、キャラクターシナジーの形成を採用するようになった。本作はもともと、最大4人パーティのターン制で戦闘を行う。攻撃担当、補助担当、回復担当、+αに分かれる形だ。1ターンにつき行動権はパーティの人数分……最大4回になるため、攻撃担当の動きをいかに最大化させるか/他の担当に行動権を取られないか、が戦略の軸になっていた。この仕様は極めて分かりやすい一方で、能力のインフレや体験の没個性化を加速させた。というのも、本作はこのルールを書き換えることができていなかったのだ。
基本的に、ターン制コマンド式戦闘の主目的は「1ターンにおけるダメージ量の最大化」となる。用いられる手段は「ダメージ回数を増やす」「ダメージ量を増やす」に収束する。この手段に対し、さまざまなルールを使って、ゲームはそれを妨害する。しかしそのルールは、プレイヤーが敷いた新たなルールでもって、書き換えられる。(たとえば、行動権を消費しない攻撃コマンドなど)この「プレイヤーが自らルールを書き換える」プロセスのバリエーションこそ、ターン制コマンド式戦闘における体験のバリエーションになっている。ルールを破ることにより、キャラクターもまた職分に縛られない活躍をすることができるようになる。言ってしまえば、コマンド式戦闘においてルールは破るためにあり、破り方の数だけ面白さがあるのだ。

かつて本作はルールに忠実な戦闘形態を採用していた。各キャラクターは職分以上の仕事をする必要がないため、サービス開始から1年にも関わらず性能のインフレが激しくなりがちであった。しかし、カウンターやスリップダメージによる戦法を採用しはじめたのを皮切りに、ターンの概念を無視するキャラクター「アンジョナナ」が登場。潮目が変わった。やがて、4人パーティ全員でルールを破り、ダメージ量を最大化するというスタイルにキャラクターデザインが変わっていく。あるルール破りのコンセプトに則る形で全員が攻撃役であり、全員が補助役である、という方向性だ。現時点では行動権の無視や、自傷によるギミック発動、スリップダメージ特化といった「ルールの破り方」が用意されている(もちろん、これまで通り職分に特化したパーティも強い)。
この方向性に合わせて、ゲームが提供するルールにも変化が生じた。職分に直接影響を及ぼすだけでなく、ルールを破ることにメリットが及ぶようになった。たとえば「この戦闘では行動権を使わないコマンドを強化する」といった具合である。こうした方針によって、キャラクターにおける職分の差は曖昧になり、パーティ構築の幅も広がった。普通に戦うゲームからルールをめちゃくちゃに破るゲームに変わったのだ。キャラクターを活かして戦場を支配し、ルールを破る感覚は非常に心地よい。現行のデザインが適用される以前のキャラクターにも性能の変更調整が入っており、使いづらい高レアリティキャラクターはかなり少なくなっているのが嬉しい。

しかし気になるのは、「戦闘の面白さが分かるまでにいくら課金する必要があるのか」だろう。本作は先述した4人全員で戦うデザインの都合上、使用するキャラクターの数は多い。なかでも高難易度コンテンツはさまざまなコンセプトを要求され、少なくとも3パーティは用意したいため、やりこむ場合は可能な限りキャラをゲットしたほうが良い(いわゆる凸については大抵好みの範疇だ)。だがそうではないのであれば、最大レアリティの確保自体は難しくない。60~70連以内に排出されるため、毎日プレイ可能なら、月額610円のデイリー報酬で済む。ピックアップキャラを外した場合の保障もある。また、本作は育成素材の入手スピードに制限をかけており、これをどこまで解決するかによって、かかる金額は異なる。筆者のオススメは「ほえほえジュークボックス」というバトルパスだ。月額1480円である。計2090円で、『リバース:1999』は快適にプレイ可能だ。
このほか、問題点として挙げたミニゲームのクオリティやローグライトコンテンツも改善が入っている。育成と経営をメインにした放置コンテンツ・ニューバベル魔精社は、イベントを楽しみ終えた空白期間に遊ぶ分には丁度よく、ローグライトコンテンツに導入されたキャラ専用バフアイテムは、低レアリティに活躍の機会を提供したり、ダメージの凄まじい上振れなど、ゲームモード専用の体験を生んでいる。正直なところ、本作のゲームメカニクスに関してはまだまだ改善の余地がある。そしてそのことを開発運営は認識しているようだ。プレイヤーの声を聞き、更新を続けている。つまり、本作の戦闘は単なるマネタイズの手段ではなく、構成要素の1つであることの現れであり、ゲームとして入力体験を生み出すメカニクスに拘るその姿勢こそ、本作を再度プレイし続けてみようと思えた何よりの理由である。
とはいえ『リバース:1999』最大の魅力は、時を越えて歌われ続ける人間讃歌を表題にした、物語体験にほかならない。文化大革命や雨傘運動を下地に、異能力者と非異能力者の間で「自分らしく生き続ける」ことの難しさが描かれる。本作は時代を超えるSFではあるが、故に語られる内容の普遍性が際立つ。「なぜ自分と他人は違うのか」。「なぜ世界は自分の思い通りにならないのか」。生きていれば必ずといっていいほど直面する問題であり、生涯戦い続けることになる宿命そのものでもある。
「男/女っていつもこうだ」「〇〇は善で〇〇は悪」「Aをすれば絶対儲かる、人生うまくいく」というように、私も含め、人はいつだって世界をシンプルに分かりやすく捉えたがる。その心地よく魅力的な衝動に抗い、考えて考え続け、懸命に混沌を突き進む、未来への歩みを止めない者たちの物語である。この表題は世界を覆う神話が死に、推し活という形で新たな神話の読者となることを求めがちな現代の世風にマッチしている。自分を読者にするのではなく、主人公と認識し、他人や別世界に憧れ/恐怖するのではなく、理解をする。他者を尊重し、自分らしく在る。作中一貫して語られるその難しさと厳しさは少なくとも私の心にムチを打ち、背筋を奮い立たせ続けるものだ。
この語りを他人ごとで終わらせないために、本作ではさまざまな歴史的事件や著名なフィクションをモチーフとして、徹底的に引用している。リアリティを高め、題材を自分の延長線上にあると認識させる手法だ。同様の手法を採用している作品は『アークナイツ』や『ウマ娘 プリティーダービー』などが存在するが、本作は時代を超えるSFということで、舞台背景に即した芸術や生活に即した表現の引用が多い。これは文章や映像表現だけではなくキャラクターの造形にも用いられている。

たとえば本作にはピクルスという犬の哲学者がいるが、これは1966年に起こったリメ・カップ窃盗事件の解決に貢献した名犬ピクルスが元になっている。ボイジャーというキャラクターはその名の通り、ボイジャー1号に接触した宇宙人であることが匂わされており、サキュバスのアンジョナナはマタ・ハリの妹だ。さまざまな時代に生きていた異能力者を、時を超えて連れてきているという設定のため、彼らの魅力を理解するには彼らが生きていた時代の理解……世界史の素養が必要となる。なぜその時代において、その人物像が形作られたのか。深掘りのしがいがあって、好き者にとっては本当に楽しい。
特に音楽に関する拘りには並々ならぬものがあり、音楽関係者が主要人物としてたくさん登場する。歌を口ずさむキャラクターも多い。ロックスターが最初に仲間になったかと思えば、ウィーンが舞台であればオペラを演じ、南アメリカが舞台となれば、ワールドミュージックがBGMとしてかかる。
「歌は世につれ世は歌につれ」とは言われるが、音楽は各時代、国ごとに結びつくものが異なる。世界を表現することもあれば、権威の象徴だったこともある。祭りの会場でも戦場でも鳴り止むことはなかった。音楽は絶えずうねる時代を縁取るものだ。ゆえに本作が提供する体験において、音楽が果たしている役割は大きい。多彩なLive2D表現に決して勝るとも劣らないパワーを持ち、舞台となる国の音楽を調べておくと、より楽しめることだろう。
こうした「作品を楽しむために深堀りを半ば強制させる」姿勢は、本作の物語体験と強くリンクしている。自らままならぬ世界を知り、一喜一憂する。それはヴェルティ一行が作中で毎度直面するドラマそのものだ。このほか細かいところだと、ログイン時に確認可能なカレンダーに、その日何が起きたのか記されていたりする。日々のちょっとした楽しみである。運営から送られてくるお知らせメールも物語設定を踏襲する形で洒落ており、世界の描写に対するこだわりがよく分かる。
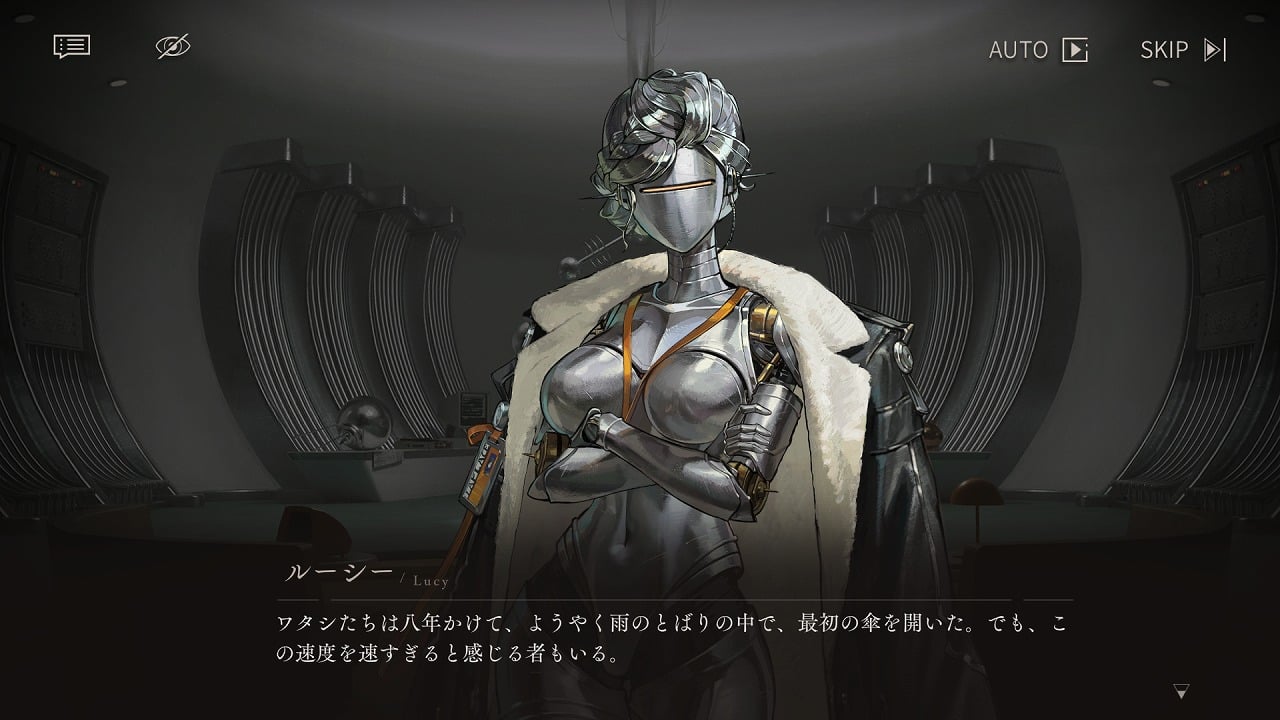
『リバース:1999』はまだサービス開始から1年半。最近になり1.5周年を迎えた。物語にしても、ゲームシステムにしても、ようやく「自己紹介」を終えた段階であり、雨雲立ち込めるこの旅が何処に向かうのかは検討もつかない。しかし本作に込められた泥臭い熱量は、私にとって歩みを続けるための確かな動機になっていると同時に、他者へ本作を勧めたくなる動機にもなっている。開発陣が自作品に向けた真っ直ぐな姿勢に則り、私も飾らない言葉で本稿を締めくくりたい。『リバース:1999』は本当に良いゲームである。だから是非ともプレイしてみて欲しい。
Be the first to comment