コロナ禍で落ち込んだ国際クルーズ船の入港が回復。長崎に外国人観光客が戻ってきました。旅行の形態が“団体旅行”から“個人旅行”へ変わる中、それを迎える長崎の課題を考えます。長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン。今週のテーマは「長崎にアイが足りない?」です。【住吉光アナウンサー(以下:住)】 コロナ禍が収束し、長崎港に国際クルーズ船が戻ってきました。クルーズ船の増加は地域経済にとって大きなチャンスですが、同時に様々な課題も見えてきています。今回は観光案内について取り上げます。【平家達史NBC論説委員(以下:平)】 旅行者の価値観や好みが多様化し、インターネットやスマホなどの普及によって情報収集も簡単になってきていることもあり、旅行の形態は、予め決められた観光名所や食事などを周る「団体旅行」から、自分で調べ、好きな場所を訪ねたり、体験したりするといった「個人旅行」にシフトしています。 「個人旅行」は、費用面では「団体旅行」より高くなりますが、旅の自由度が格段にあがりますし、外国人観光客にとっても、インターネットを利用して海外から事前予約が可能なこともあって、近年は個人旅行が好まれる傾向が強まっています。
クルーズ船の楽しみの一つは寄港地での観光ですが、外国人観光客は長崎でどう過ごしているのでしょうか。団体旅行から個人旅行へ 観光形態がシフト4月7日、長崎で建造されたクルーズ船、ダイヤモンド・プリンセスが入港しました。イギリス船籍で乗客の定員は2,706人です。入国審査を済ませ、出港する夕方まで乗客らは寄港地での観光を楽しみます。上陸客:「団体旅行で島原城に行くの。(島原城?)そうよサムライ(武家)の村」上陸客:「陶器店に行ってから平和公園に行く予定」上陸客:「個人ツアーガイドで、原爆資料館や城にいくつもりなの」この日は長崎市内観光のほか、島原、有田、ハウステンボスを訪ねるツアーが用意されていました。一方、最近はスマートフォンを片手に、徒歩や公共交通機関を使い、個人で市内をめぐる人の姿も多く見かけるようになりました。【住】2020年頃には、新型コロナの世界的な感染拡大で、クルーズ船を含む旅行需要は大きく落ち込みましたよね?【平】はい。その後、コロナ禍が収束し、長崎港でも2023年3月からクルーズ船の来航が再開しました。2023年以降の「月別のクルーズ船の入港数」を比較したグラフです。毎年、入港数は増えていて、今年の3月、4月は、ほぼ毎日、クルーズ船が来港するまでになっています。今年2月以降は「コロナ禍前」の2019年を上回るペースでクルーズ船が入港しています。クルーズ船客の動向とガイド不足【住】大きく落ち込んだクルーズ船による観光需要がようやく回復してきたということですね?【平】ええ、私も4日、クイーン・エリザベスが入港した日に、長崎市のグラバー園に行ってみました。入港時間は朝の8時でしたが、私がグラバー園に行ったのが11時頃で、ちょうど松ヶ枝埠頭からグラバー園に多くの外国人観光客が入園する時間帯でした。
ご夫婦、ご家族、小グループで動かれている人々や通訳ガイドに引率された10名ほどのグループといった単位で動かれていましたが、通訳ガイドの話を真剣に聞いていたり、展示物を熱心に見ていたりと、西洋の窓口としての長崎の歴史・文化を吸収しようとしている姿が見られましたし、展望台から海をゆっくり眺める人もおられました。【住】長崎に来る外国人観光客は、どの国の人たちが多いのでしょうか?【平】長崎国際観光コンベンション協会がクルーズ船来港時に行ったアンケート調査によると、昨年度(令和6年度)は国別では中国が32.9%と最も多く、ついでアメリカで19.4%、以下フィリピン、インドネシアなどが続いています。また、長崎市を含むクルーズを選んだ理由としては「被爆地だから」が最も多く、「日本、西洋、中国の文化が融合している」など長崎市の歴史・文化への興味や景観の魅力を挙げています。長崎市内での訪問先としては、原爆資料館・平和公園が最も多く、2人に1人が訪ねています。館内が“ほぼ外国人”の時間帯も…ダイヤモンド・プリンセスが入港した日の長崎原爆資料館です。通訳ガイドに連れられて分刻みで次々とクルーズ客がやってきます。船の規模や時間帯によっては、資料館内の見学者がほぼ外国人ということもあります。観光案内だけはなく、スケジュール通りにツアーを催行するのも通訳ガイドの役目です。ガイドは個人事業主が多く、旅行会社などと個別契約しています。クルーズ客が増加する中、長崎では通訳ガイドの数が足りていないといいます。福岡在住の通訳ガイド 其田秀樹(74)さん: 「今の時期(3~4月)はやっぱりどうしても長崎はガイドさんの数が足りないってこともありまして」福岡も長崎と同じようにクルーズ客は増えていますが、事情が異なるといいます。繁忙期には依頼の7割を断ることも其田さん: 「福岡の場合は、どちらかというと韓国とか中国からのお客様が多いと思うんですね。ショッピングがメインだと言うことで。長崎の場合、見るものが非常にふんだんに、しかもコンパクトにまとまっているという(観光地としての)アドバンテージをお持ちだ、というふうに思います」通訳ガイドの手配も行っている九州通訳・翻訳者・ガイド協会によると、長崎で実務を担っているのは約20人ほどで、需要に追いついておらず、九州以外の地域からも呼び寄せているといいます。九州通訳・翻訳者・ガイド協会 理事 龍里宗一さん: 「私が先週ガイドした時もですね、北海道からのガイドさんが来てましたね。いろんな旅行会社さんらがもう2年先、3年先の予約をしてしまうんですよ。(通訳ガイドに)声をかけても『すみません、もう仕事が入ってます』と言うことで、なかなか空きを見つけるのが難しい。他地域から呼ぶことも叶わない場合は、残念ながらお断りするしかないんですよね。ひどい時ですと7割ぐらいはお断りする時期もあって…例えば繁忙期とかですね」長崎観光の強みと課題、そして解決策は?【住】長崎は通訳ガイドが不足しているのですね。【平】そうなんです。それは観光地としての長崎の特性も関係しています。「長崎の観光地としてのアドバンテージ」を龍里さんに聞きました。まずは、歴史が「重層的」であるということです。
▶16世紀の南蛮文化
▶17世紀、禁教令下の潜伏キリシタン
▶19世紀、造船を中心とした産業革命遺産
▶20世紀、原爆投下とそこからの復興
そして、これらの場所をバスや路面電車で10~15分で移動できる“コンパクトさ”を挙げておられました。
つまり、「重層的な歴史」を持つだけに説明すべき事柄が多いうえ、多くの観光地を回りやすいため、説明すべき場所も多いということです。【住】長崎では需要に対して通訳ガイドが不足しているだけでなく、知識とそれを通訳する語学力が必要ということなんですね?【平】はい。こうしたなか、増える個人ツアーに対する通訳ガイド不足に対応しようと長崎国際コンベンション協会は、九州通訳・翻訳者・ガイド協会と連携して通訳ガイドの育成を始めました。具体的には──▶2024年9月から英語ガイド「NagasakiCrew(ナガサキクルー)」の育成を開始しました。
▶参加者は研修会で長崎の歴史や文化、風習の違い、緊急時の対応などを学び▶Nagasaki Crewとして認定された人が、個人客らに“プライベートツアー”を提供します。
今年2月末からはクルーズ船来港時に松が枝国際ターミナル近くにブースを設置し、3時間ほどの「英語ガイドツアー」販売しています。おもてなしのアイ《愛》と《i》【住】どんなツアーなのでしょうか?【平】NagasakiCrewの「ツアー商品」は
▶全部で6種類(当日ブースではこのうち2種類を受け付け)
「諏訪神社の御祈願」1人:210ドル(約3万1,500円)
「平和公園で折り鶴献納」1人:170ドル(約2万5,500円)
▶キャッシュレス決済
▶4月14日までに12回ブースを出し、11本催行しています。【住】通訳ガイドが不足していることはわかったのですが、他に課題はあるのでしょうか?【平】はい。まさに今日のテーマである「おもてなしのアイ」なんです。ある重鎮が今の長崎の観光について「アイ」がないとおっしゃったのですが、「アイ」とは旅行者へのおもてなしである“愛”。
通訳ガイドの不足も含むと思いますが、もう一つの「アイ」はインフォメーションの“i”です。旅行の形態が「団体⇒個」へ変わりつつあるなか、この“i”もまだまだ足りないと思います。「旅行情報の入手先」についてみると──
「旅行前」はなにが一番多いかというとSNSです。(上位5つ 長崎国際観光コンベンション協会調べ)これが「滞在中」だとSNSは2位となり、最も多いのは「観光案内所」なんです。何と、およそ3人に1人が観光案内所を利用しています。【住】つまり観光案内所も充実させなければならないということですね?【平】そうですね。観光客に必要な情報を提供する「観光案内所」の機能ももっと充実させるべきだと思います。他の観光地と比べると長崎は観光案内所が少ないと感じます。ただ、立派な観光案内所を作るとなると、コストも時間もかかりますので、タブレットを持って、人の集まる場所に出ていくといった「出前コンシェルジュ」のような運用で対応することも必要だと思います。DXが発達した現在ならば十分可能だと思います。いずれにしても「アイ」のあふれる長崎になるためには──
・多言語に対応できるガイドの育成
・観光案内所の質と量の両面の機能強化
・タブレットを活用した「出前コンシェルジュ」
・シビックプライドの醸成も兼ねた学生の活用など他都市で行われていることで参考にできることはまだまだあると思います。「おもてなしの“愛”」や「地元ならではの“i”」で旅行者に「長崎ならではの体験」を満喫してもらい「長崎にもう一度、来てみたい」と感じていただき、それをSNSで発信してもらうことで、さらに多くの観光客を呼び込むことに繋がることに期待したいと思います。今回は観光案内所について詳しく解説する時間がありませんでしたが、3月末に発行された長崎経済研究所の「ながさき経済春号」に観光案内所の現状と求められる機能について掲載していますので、ご覧いただければと思います。
詳細は NEWS DIG でも!↓
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/1859317
source
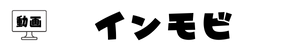
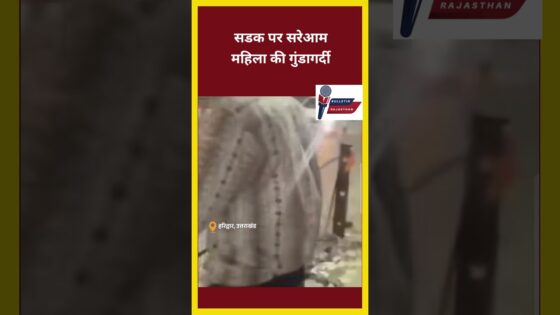




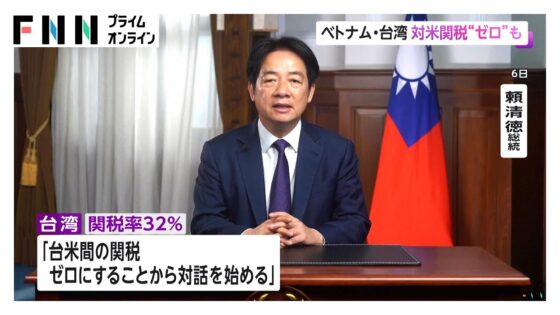



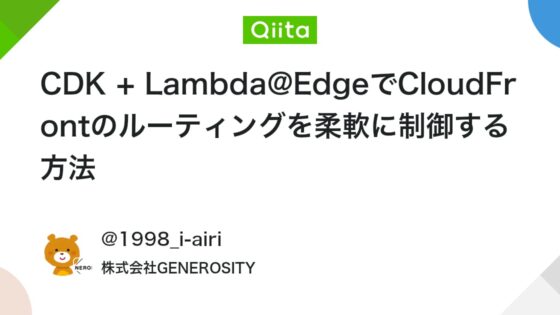
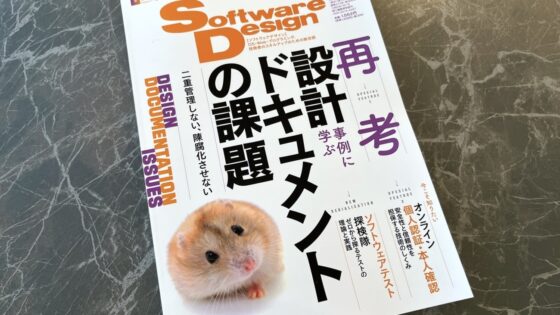

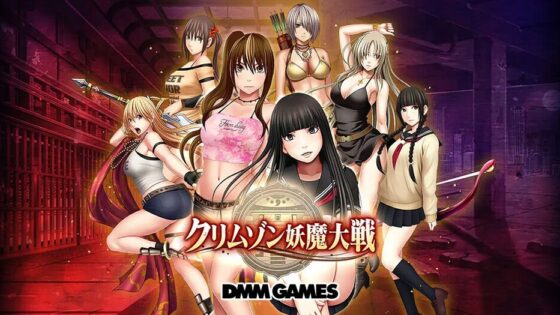

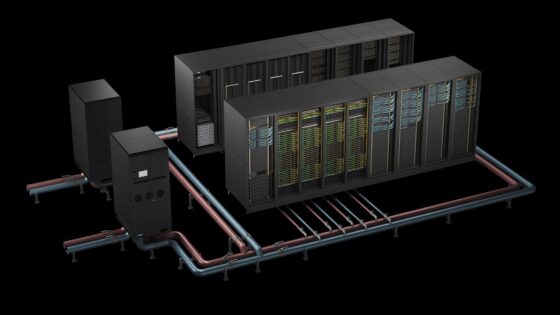
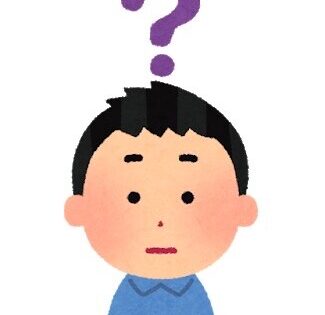


Be the first to comment