住宅の確保が難しい高齢者や低所得者に、相場に比べて安い家賃で住宅を提供している会社がある。どのようにして低家賃を実現しているのか、その取り組みを取材した。
■立ち退き迫られ住居探し
入居希望者 Aさん(45)
「なんか面白いな。普通の家とは違うね」
住宅支援事業を行う 松本知之さん(45)
「多分、事務所とかで使っていたと思います」
京都市の中心部にある築36年のアパートの内見に来たのは、日雇い労働者のAさん。
松本さん
「入居って最短(いつから希望ですか)」
Aさん
「(入居)できればいつでもいいです」
Aさんには他の不動産会社に頼れないある事情があった。
Aさん
「コロナになって心臓の機能がちょっと弱っている。今は派遣会社なんですけど、どうしても体が動かない時とかあるんですよ」
新型コロナの後遺症により仕事を休む日が増え、現在住んでいる家の家賃を滞納。立ち退きの期限が迫っていたためNPO法人の紹介でこちらを訪ねたという。
Aさん
「冷蔵庫置けるかな」
松本さん
「こっちでもいいと思いますよ」
■物件貸し出し始めたきっかけ
不動産関係の会社「リノベーター」を経営する松本さんはおよそ6年前から、高齢者や低所得者などのなかでも、住む所が確保できない「住宅確保要配慮者」と言われる人々を中心に物件を貸し出す会社を経営している。
現在、入居希望者からの問い合わせは年間およそ1000件。その半数を「市役所」や「社会福祉協議会」などからの紹介が占めている。
松本さんがこうした人たちに物件を貸し出し始めたきっかけはサラリーマン時代に所有していたマンションの一室を貸そうとした際のある出来事だった。
松本さん
「物件を誰かに貸そうとした時に『ご高齢の人だめですか?』『外国籍の人だめですか?』みたいなことを(不動産仲介業者に)当たり前のように言われる。すごく違和感があるなと」
不動産業界で敬遠され、家を借りづらい人たちがいることを身を持って知ったという。
■相場より安い理由は?
今回Aさんに紹介した物件は、築36年だがキッチンや床はリフォーム済み。近くにスーパーがあり、駅も徒歩圏内。その賃料は…。
松本さん
「4万円。広さは30平米強ぐらいはあると思います。(相場だと)5万円超えてくるんじゃないですか。京都駅まで歩けますし、4万円なんか(他に)絶対ないです」
相場よりも安い物件。その理由は…。
松本さん
「空き家とか、あとは空室が埋まらないアパートとか。安価で自分たちでリフォームして、ご高齢の人とか家探しに困っている人々にご提供して…」
松本さんは、「空き家」や「空室」に悩むアパートなどの持ち主から購入したり借りたりした物件を自分たちでリフォーム。
住人が退去した際も清掃を自分たちで行い経費を削減。そうすることで物件を安く提供できるという。
Aさん
「やっぱり家賃負担っていうのが(出費のなかで)一番大きい。生活保護とかも考えたんですけど、それはちょっと自分のなかで違うなと。生活立て直したいっていうのもあるんで一からやり直します」
■食料支援など入居後もサポート
現在では関西を中心に450以上の物件を提供している松本さん。そのなかには、Aさんのように家賃の滞納で退去させられた人もいるというが、トラブルなどは起きていないのか?
この日、松本さんは部屋を貸し出している人の元へと向かった。
松本さん
「こういうのがあったらうれしいとかあったら言っておいてください。カップ麺とかもいっぱいある、(他に)焼きそばもあるし」
入居者
「いただけるだけでうれしいので。今ちょうどチョコレートとか食べたかったんで」
松本さんが手渡していたのは、フードバンクから提供されたカップ麺や菓子など。こうした入居後のサポートも行っている。
入居者
「先日も、水の調子が悪くなった時に連絡してすぐ来ていただいた」
松本さん
「食料を単純にもらうというだけじゃなく、気持ちの面での信頼関係というのも大きいと思います」
顔を合わせ、関係を築くことが家賃滞納やトラブル防止にもつながっているという。
松本さんは今後10年以内に提供する物件を1万件に増やすことを目指している。
松本さん
「やっぱり(物件の)数というのが僕は重要だと思っていて。例えば関西のエリアだけで1万件物件供給というような形になれば、『民間賃貸住宅』『公営住宅』と『リノベーター』という第3の選択肢になれるんじゃないかなと思っています」
■自治体と連携するケースも
住宅の確保が難しい高齢者や低所得者への支援だが、実は民間が行ったほうが継続しやすいという。
NPO法人の支援だと、寄付や補助金での支援のため規模を拡大することはなかなかできないが、取材した住宅確保の支援を行う松本さんは「住宅確保の支援が適正な利益を出す事業として成り立てば、より多くの人たちを救うことができる」という。
ただ、入居者の多くは賃貸契約を結ぶことが困難だが、どのようにして利益を生み出しているのだろうか。
松本さんによると逆転の発想で、賃貸契約を結ぶことが困難だからこそ同じ物件に長く住み続ける傾向があるため、家賃収入を安定的に得られるという。
入居者の収入が途絶えるなどした場合も、家賃の支払いに関して相談して期限を延ばすなど柔軟に対応するそうだ。密にコミュニケーションをとることで家賃の滞納は1割未満に抑えられていて、事業として成り立っているという。
そして、自治体と松本さんの会社が連携するケースもでてきている。
京都市は、市営住宅の空き物件を有効活用するため、松本さんの会社に物件の貸し出しを行っている。
また、大阪府寝屋川市の社会福祉協議会は、住宅確保が難しい市民に松本さんの会社を紹介しているという。担当者は「行政だけで対応すると入居までに時間がかかるが、申し込みの当日でも入居できる場合もあり対応が早い」と話している。
■東京都 民間とファンド設立へ
そうしたなか、行政が民間と協力してビジネスモデルを新たに生み出す動きもでてきている。
東京都は、低所得者層などを対象にした安価な賃貸住宅を供給するため、今年度の予算に100億円を計上している。
都と民間と連携し、最大で200億円規模のファンドを立ち上げ、その資金をもとに空き家や中古マンションを活用した住宅を供給する方針だ。
番組で東京都産業労働局の担当者に聞いたところ「社会貢献を重視する投資家からの出資を集め、見返りの収益を抑え、なるべく家賃を低く設定するようにしていきたい」と話していた。
将来的にはビジネスモデルとして確立することを目指すということだ。
(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年4月8日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
source
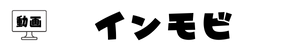

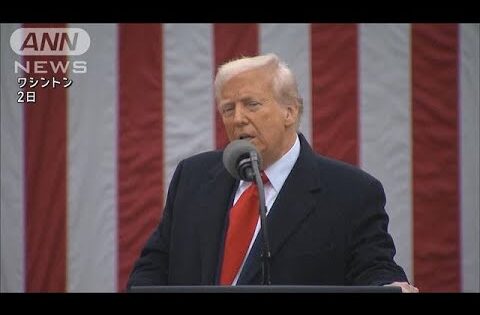









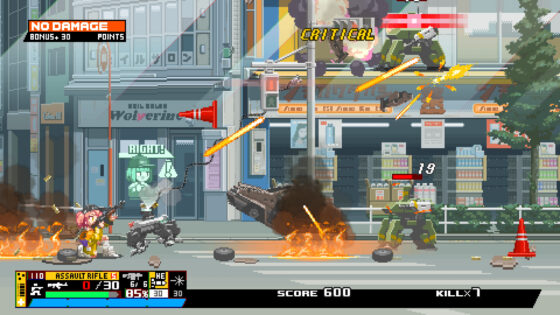





Be the first to comment