関税を巡る日米の初協議に、トランプ大統領が急遽、参戦するという異例の展開となった。「私も出席する」と、トランプ氏がSNSで表明した現地時間の4月16日朝、赤沢経済再生担当大臣は米首都ワシントンに向かう機中だった。赤沢氏は、ホワイトハウスでトランプ大統領と約50分、続けて、ベッセント財務長官らと協議。日本側は、米国の一連の関税措置を極めて遺憾とし、投資や雇用への悪影響を訴え、措置の見直しを求めた。
トランプ氏は協議の中で、米国製自動車の日本市場での販売不振に強い不満を表明した。2024年の実績によると、日本に輸出された米国ブランドの自動車はわずか2万台弱に留まる一方、北米市場では、日本製自動車が約590万台を記録した。トランプ氏は、米国ブランドの自動車が日本市場で極めて低いシェアにとどまる現状を「不公平」と厳しく非難。同時に、日本の厳格な安全基準などを非関税障壁と指摘し、米国車の市場アクセスを阻害していると主張してきた。トランプ氏は、2024年の米国の対日貿易赤字は685億ドル(約9.7兆円)に達している現状を問題視し、対日貿易赤字の解消を要求した。
トランプ氏は、在日米軍の駐留経費負担についても、日本に対する厳しい見解を示した。トランプ氏は、日本が駐留経費を十分に負担していないと幾度も指摘し、日米同盟の財政的側面における不公平を強調した。しかし、日本側は2022年度から2026年度までの5年間、年間平均2110億円を駐留経費として負担することで、既に日米間で合意に至っている。この合意にもかかわらず、トランプ氏は、日本の貢献を過小評価する姿勢を強調した。中谷防衛大臣は4月18日、ヘグセス国防長官との協議を踏まえ、「米側から具体的な要求もなければ、数字的な提示もない。関税の問題とは別個の問題である」と述べ、在日米軍の駐留経費に関する米国からの具体的な要求がないことを主張した。
赤沢氏とベッセント財務長官による交渉は、米国通商代表部(USTR)がまとめた貿易障壁報告書を基に進められ、米国側は、関税以外の制約や規制の緩和を日本側に迫った。米国は農産物の対日輸出の拡大に言及し、牛肉、コメ、魚介類、じゃがいもなどを重点品目として挙げ、これらの輸入における関税以外の障壁や規制の撤廃を要求した。赤沢氏は、「米国側には具体的な優先順位を示してほしい」と回答した。日米関税交渉の次回会合が4月中に開催される方向で調整が進んでいる。対日交渉を主導するベッセント氏は、「非関税障壁という『悪魔』を完全に取り除くには、時間を要する」と述べ、日本の非関税障壁の解消に向けた交渉に取り組む姿勢を示した。中野国土交通大臣は4月4日、「我が国の自動車基準及び認証制度は、国連の基準に完全に合致しているとの認識を持っている」と述べており、日本の現行基準が国際標準に準拠していることを強調していた。日米交渉の実施を受けて、石破総理は18日、「次回の協議において、具体的な前進が得られるよう、政府部内の検討・調整を加速するよう、直接指示を出した」と語り、日米交渉での成果に強い意欲を示した。
日米間の為替政策を巡る閣僚級協議が、4月24日にワシントンで開催される方向で調整が進んでいることが明らかになった。加藤財務大臣とベッセント財務長官が顔を合わせ、為替市場の動向や通貨政策に関する議論を行う予定。赤沢氏は18日の時点で、「米国側から為替の議論は現時点で提起されていない」と述べたうえで、米国から要請があれば、加藤財務大臣が適切に対応するとの立場を示していた。トランプ氏は3月3日、日中首脳に対し、「通貨を押し下げ続けることはできない」と警告する発言を行い、為替政策を巡る米国の強い懸念を改めて主張していた。この発言の背景には、2019年の日米貿易協定交渉で米国が、「意図的な通貨安誘導」を阻止する「為替条項」の導入を求めたが、最終的に協定に盛り込まれなかった経緯が指摘されている。
トランプ氏が、連邦準備制度(FRB)のパウエル議長の解任に言及し、金融政策を巡る対立が再び表面化した。トランプ氏は4月17日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で、「今すぐにでも利下げすべきだ。パウエル議長の解任が一刻も早く実現してほしい」と投稿。さらに同日、記者団に「私が辞任を求めれば、彼は出て行くと思う。彼の仕事ぶりには不満だ」と述べ、強い不信感を示した。これに対し、パウエル議長は同日、シカゴでの講演で、「経済状況を慎重に見極め、データに基づく判断を行う」と述べ、FRBの独立性を強調し、政治的圧力には屈しない姿勢を改めて表明した。
一方、ベッセント財務長官は4月14日、ホワイトハウス当局者に対し、パウエル議長の解任は「金融市場の不安定化を招く危険性がある」と繰り返し警告した。市場関係者からも、FRBの独立性に対する懸念が高まっており、トランプ氏の発言が株式市場や債券市場に波乱を引き起こす可能性が指摘されている。パウエル議長は、自身の任期について、「法律上、任期中の解任は認められていない。トランプ氏から辞任を求められても応じない」と明言。2026年5月の任期満了まで職務を全うする意向を示している。トランプ氏の主張は、自身の関税政策によるインフレ圧力と経済成長の鈍化懸念が高まる中、FRBに早期の利下げを迫る狙いがあるとみられる。しかし、パウエル議長は、関税が「少なくとも一時的なインフレ上昇」を引き起こすと警告しており、「利下げのタイミングは慎重に判断される」と強調している。
★ゲスト:ジョセフ・クラフト(経済・政治アナリスト)、峯村健司(キヤノングローバル戦略研究所主任研究員)
★アンカー:末延吉正(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
source
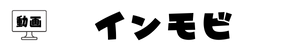
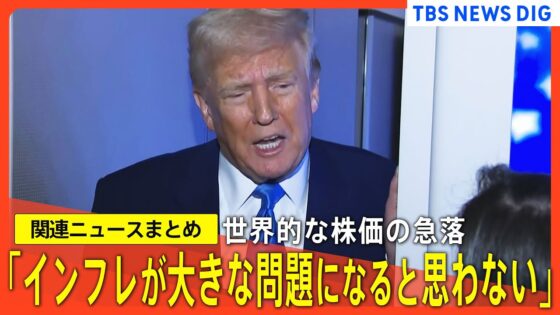



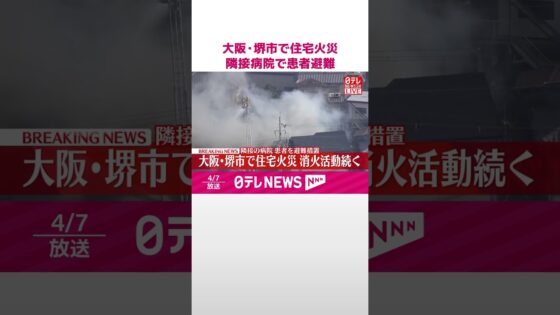





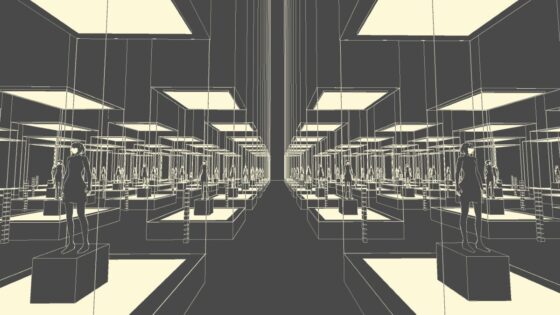
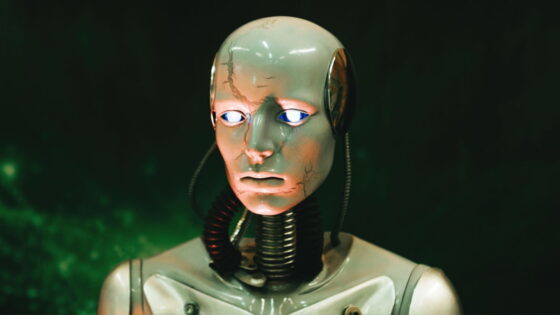

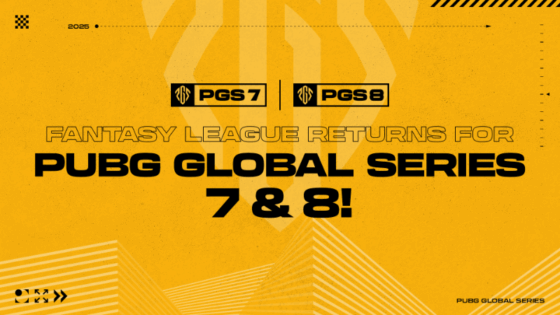


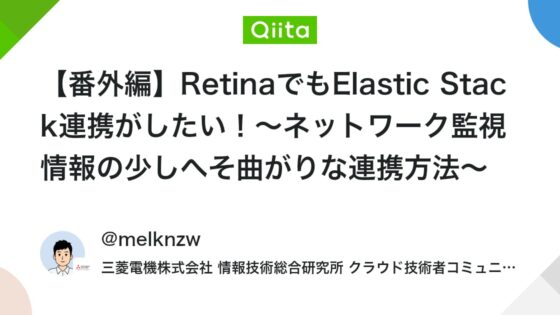
49件のコメント
@sasa-ti7hd
1日 ago米不足は計画通りか
@田中一-l9w
1日 agoただのアメリカからの脅迫だろう 中国を見習って輸出規制したり戦うべきだと思う これで譲歩なんてしたらただの腰抜けだ
@zoo-i5b6w
1日 agoまた、農産物… 農業者をバカにしているね。いつも自動車を守るために農産物購入を差し出している
@ガラテア-r4j
1日 agoコメの多少の自由化はしても良いかもね…国内農家の命と引き換えになるけど。でも5000円以上が本来相場なんだ、なんて言い方し始めるコメ業界に国際競争力があると思えない。
@yamanokanata
1日 agoトランプが中国に対する攻撃を開始した。
尖閣諸島に張り付いて挑発し占領を狙っている中国は明らかに敵国である。
かつて習近平はオバマに対して太平洋を分割支配しようともちかけた。
日本は中国のものと思い込んでいる。「中華思想」の現れである。
その思想によれば「天下」のもとでは一人の支配者しか認めないとすれば中国にとってアメリカは「邪魔者」である。「天下」は中華のもとで統一支配されなければならないのである。日本を占領したのち日本には2つの省を設け支配する秘密の計画が漏洩したことがあった。
尖閣挑発や日本侵略を止めるまでトランプにならって高関税政策と小口貨物課税化と国内郵送料無料化中止が必要である。
アメリカと同様に中国問題は日本の「国防上の問題」である。
石破政権と公明党は中国の下僕である事を隠そうとしない。中国と心中しかねない態度を改めようとしない。相当の利権供与されているのだろう。
中国のダンピング輸出、迂回輸出、過剰生産によって相手国産業を破壊している。迂回輸出を許している国には敢えて高関税をかけ迂回させないようにしている。日本も迂回輸出に利用されていることは中国側から公言されている。
中国からの商品に「メイド・イン・ジャパン」のラベルを付けてアメリカへ向けて輸出している。「メイド・イン・ジャパン」のラベルは厳密に資格付与しなければならない。罰則付きも必要である。中国による迂回輸出される国に対してアメリカは高額な関税を課さざるを得なくなっている。大迷惑である。
中国製の投票機でトランプ再選を妨害し、コロナをアメリカに流行させフェンタニルという麻薬を流通させ多くの米国人を殺した。
かつて中国の国防大臣の遅浩はアメリカに病原菌をばら撒いてアメリカの軍事力に対抗すると秘密会で述べていた。
日本では日本に潜入し土地や不動産を買い漁っている。日本は中国の不動産は購入できない。しかも相続税が免除されているため土地など買い放題である。
そこで用いられる手段は迂回輸出と同じで、名義を日本人名(親中派など)に変えて日本の法律をすり抜けている。メディアを支配するのも同様な手口である。日本在住の中国人は中国の法律によってスパイになる事を義務つけられている。偽装帰化人もその対象である。日本の官庁への出入りを監視する監視カメラは殆どが中国製であり、監視情報が中国に送られる危険性がある。
中国で生産されたソーラパネルを日本全国に張り詰めたのは中国である。そのせいで日本の風土が汚染され電気料金に上乗せされて日本人は対価を払わされている。
中国は人民を計画的に日本に送り生活保護や医療や高福祉や教育サービスを受益している。「人道主義」を掲げて日本への侵略を擁護しているのは官僚である。小役人の浅知恵というほかはない。
偽装結婚や同姓婚や夫婦別姓は中国による潜入を容易にする。
大学入学への外国人枠を設定し外国人留学生に対して多額の支援金を支出しているのは憲法違反であり日本人差別である。同盟国のアメリカにならって中国からの留学生への優遇や制限を設ける必要がある。中国人留学生を優遇してスパイを養成する様なばかげた事にしないようにする必要がある。
中国に「超限戦」の概念があり日本に関わらずアメリカ、オーストラリアはその戦争の最中であることを知らねばならない。現外務大臣の岩屋は中国から賄賂を貰ったことをアメリカによって明らかにされている。
中国の「一帯一路」の謳い文句に騙されたのは大阪維新の会であった。
日本の土地購入に便宜をはかっていたのは国土交通省を牛耳る公明党である。
トランプの高関税に呼応して中国による侵略(サイレントインベイジョン)を防ぐ必要がある。
中国に尻尾を振る政治家の正体を明らかにし中国によるメディアの支配を止めさせねばならない。改めて強調すべきは中国は「敵国」である。
敵国の中国によって起こされている「超限戦」の実態を白日のもとに晒す必要がある。今こそ「日本を豊かに強く」するための行動を起こす時期である。
@leparfumdugrosboss4216
1日 ago日本で米国車は売れないって、米国の問題じゃない?売れる車を作ってみれば?
@宇宙の起源
1日 agoアメリカは日本に車を売る気が無いだけです!売る気があれば売 れる車を造るはず😊
@suzuyui
1日 agoもうコレはトランプ主席によるアメリカ文化大革命😅😅😅
@oomoroo-c5r
1日 ago「売らない買わない」を徹底すれば全てが上手くいくのでは?
ブラジルやインドや東南アジアとの貿易を拡大していけばいいのでは?日本は車の為にどんだけ犠牲をうむつもりなんだよ。他の産業はもう限界だよ。
@matsumatsumatsu.t
1日 agoグチったのは、確かトランプでは??
@luorobert-t3t
1日 ago日本完全可以走独立自主的道路,这样世世代代被美国掌控不难受吗?
@越智弧慕零
1日 ago消費税に関しては意図的に情報隠し報道
@Kewatagamo1
1日 ago24:56
私は駐留経費に関してなんら日本側の瑕疵のあるところだとは考えておりませんが、ふわっとトランプが言うから問題があるんだろうとするのではなく、この方の考えをぜひお聞かせ願いたいところです
@00kumakuma
1日 ago金融のトリレンマ、為替相場の安定、金融政策の独立性、自由な資本移動の3つのうち、同時に達成できるのは2つだが
中国は自由な資本移動は禁止にして為替を取っているので圧倒的為替有利の中国に関税以外で対抗できない。
80年に1元150円あったが今は20円台
ドル円でいえば1ドル600円みたいな話。
こんな為替レートで自由貿易は出来ない。
関税は世界にかけているわけではなく中国狙い撃ちで中国と中国から迂回輸出が見込まれる国への関税、日本が関税回避しようとすれば中国に関税をかけるのが最も有効
@ゴーポケモン-g8r
1日 agoアメリカ車も韓国車も売れてないだろ。
根本的な性能の問題だよ。
@明るい明日-x8u
1日 ago日本の国益を売り飛ばせ、と言わんばかりの各コメンテーター 酷い動画です。
@hyakuman8789
1日 ago当のトランプ氏本人もアメ車は個人で所有してなくて欧州車ばかりですが、取材してますか?
@ariari9567
1日 ago貿易赤字0は貿易をしないと赤字にならないよ😅トランプ大統領🎉
@beansyamada1626
1日 ago「ウィンカーの色」って、アメリカ住みですが、ウィンカーなんてほとんど出してないですよ。そういう車文化のやつらに合わせる必要ないって
@Kaosaiダイスキー
1日 agoANN=「朝日新聞」=「東亜日報」半島コミンテルンネットワーク放送局朝日
@esse9081
1日 ago貿易障壁について、2019との大きな違いは為替状況。これで自動車など輸出産業のボロ儲け。まずは為替の回復でしょ。アメ車の努力不足は、強者日本の奢りでもある。農業は明らかに強者アメ。アメ車の努力不足を言うなら、アメ農を開放すべきだろう。
@くあたも
1日 agoトランプってバカだから、事実を知らない。
@ソフィアソフィー
1日 ago米国も力落とすし中国も力落とすし世界はこれから21世紀大変。世界の国々生き残るので必死になる
@つよしふなつき
1日 ago日本は過去、えげつない貿易黒字で、ある程度アメリカも容認していた。
@copen2270
1日 agoオイオイ、トランプは呼び捨てで、習キンペーは氏をつけるのか? 公正公平な報道姿勢に疑問!
@山田太郎-y7d6r
1日 agoF-35で使われるレアアースの量
@user-un7ty2jx9s
1日 agoアメ車、SUV欲しいがデカすぎプラス高すぎて日本の道路事情だと地方都市でしか乗れない。日本だけでなく欧州でもアメ車少ないように物理的な地理問題と生活様式の違いがかなり大きい。
@Mark-sq6tx
1日 agoアメリカのトヨタやホンダから車を輸入すれば良いって話なんだろうけれどな。
@gangu123-f3g
1日 ago交渉の最中に、トランプが厳しく対抗している中国に石破政権がのこのこ行っているのは愚かすぎる。親中を続ける限り、日本への要求は益々厳しくなって行く。
@gangu123-f3g
1日 ago交渉とは結局、人と人との信頼関係が影響する。安倍元総理を失った損失が大き過ぎる。安倍元総理に替わる人材は日本にはいない。
@RoadsterZYT
1日 ago貿易赤字が出た分、使い物にならない米国車よりも原潜とICBMの購入することで相殺するってのはどうか?
@妹尾満
1日 agoGM,フォードが国外へ出て生き残ったら売れる車を作るかもしれないですね。
@カズヤ-g4o
1日 ago日本の車検は、自動車産業を支える1つですよ😅無くす事は出来ないが緩和する事は全然出来る😊
私用車、商業車と車保険、消費税車限定で
@磯崎智-u1n
1日 ago何故ルーズベルトは日本に戦争を、仕かけたのか。
海軍偏愛主義者として太平洋を、独占した海にしかった。中国に主導権をとりたかった。さらには、侵略によって得たハワイを、侵略から守った地にしたかった。リメンバーパールバーでハワイ太平洋を、永遠の正統性にしたかった。
@Mom018-q1h
1日 ago関税により、会社が休みになったりして、給料が減る。
消費税廃止にすれば、日本もアメリカも満足やのに、財務省の言いなりか😒💢
@NickuJagger
1日 ago例の🟥キャップ、中国🇨🇳製とか(W)😁😁😁😁😁😁😁😁😁
@naokiman-g8y
1日 ago米に関していえば、農家から卸に卸す値段まで関税引き下げたらいいんじゃないですか?
JAが買い占めて価格釣り上げてるんですよね。JAが利ザヤ変に抜いてるだけらしいです。
ジャスミンライスやタイ米、カリフォルニア米を食べたい人だっているからそれぞれ関税下げたらいい。
減反もしなくていい。余った米は海外でブランド米として売れるらしいから。JAいらないですよ。
@大天使猫のミケエル
1日 agoいらないものは買わないよねぇ。日本人は国産大好きだし特に
@danpeitange2471
1日 ago貿易赤字の解消って、何年でやれと言っているのか?いきなりはできないんだぞ。
@danpeitange2471
1日 ago68歳の爺いですけど、私の親父の時代も含めてアメ車が崇拝の対象だったことは記憶にない。親父が最初に乗った車はルノーで、次がトヨタ・パプリカで、その次がトヨタ・カローラ。ワシはトヨタ・カリーナ一本。
@眞弓善夫
1日 agoヨーロッパ車が日本で売れているか、アメリカでなぜ日本車が売れているかを考えて見るべき
@ytfanlingeric
1日 ago日本の高官もMAGAの帽子を被ってるんですね。関税について、MAGAであれば、日本はどうなる?
@user-my6to2jr1f
1日 agoクラフトさんの「愚痴」には笑った👍
@RedSyou
1日 ago非関税障壁が無ければ普通にアメ車ほしいけど
マッチョな車はきんたま付いてないと好きにはならんよ
@poro260
1日 agoおそらくトランプは中国との貿易戦争で生じる全ての不利益を日本を筆頭とした弱い国々への恐喝で埋めるつもりだろうね。
@一哉田中-x3i
1日 agoホワウェエでなく、ハウウェイだよ
@ganxxxta24
1日 ago欲しいアメ車はあるけども、自分の欲しいアメ車は、値段高いし維持費も高いしデカイし左ハンドルだし年式は古いし日本の安全基準に引っかかるし で良い事が無いのよなぁー🤦♀️
@enmp8065
1日 agoアメ車……デカイし、性能も日本製が上なんだが…
@yokot638
1日 ago赤澤とイタリア首相の椅子の違い😮部屋も、赤澤じゃなくとも石破でも軽い扱いだろうな。