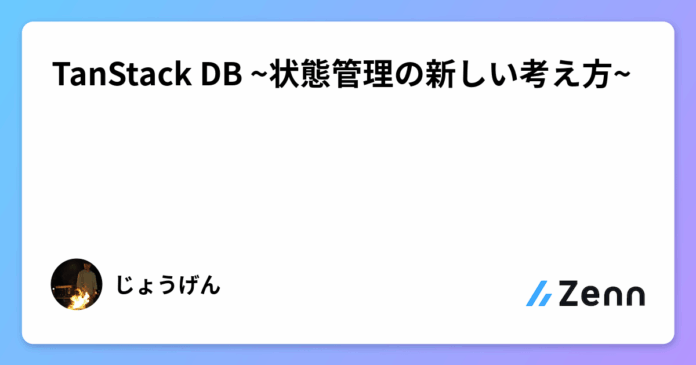はじめに
TanStack が新たに公開した TanStack DB について調べたので、その概要を紹介します。
TanStack DBとは
TanStack DBは、フロントエンドに 永続化層(DB) を設け、コンポーネントから直接クエリできる仕組みを提供します。
従来は、バックエンドのDBを正とし、フロントエンドはそれを定期的に問い合わせる形が一般的でした。
TanStack DBはこれを逆転させ、フロントエンドがデータの主導権を持つ 形にします。
つまり「DBをフロントエンドに持ってきた」感覚で使えるのが魅力です。
TanStack DBは何が嬉しいのか
楽観的更新の自動化
同じTanStackシリーズのTanStack QueryはデフォルトではUIの楽観的更新をしません。
つまり、失敗することを前提に、成功した場合だけUIが更新されるということです。
楽観的更新に対応したい場合は手動で仮の更新、ロールバック、再フェッチを実装する必要がありました。
TanStack Queryによる楽観的更新の例
const mutation = useMutation({
mutationFn: updateTodo,
onMutate: async (newTodo) => {
await queryClient.cancelQueries({ queryKey: ['todos'] });
const previousTodos = queryClient.getQueryData(['todos']);
queryClient.setQueryData(['todos'], (old) => [...old, newTodo]);
return { previousTodos };
},
onError: (err, newTodo, context) => {
queryClient.setQueryData(['todos'], context.previousTodos);
},
onSettled: () => {
queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['todos'] });
},
});
このような処理を毎回書くのは面倒ですし、ミスも起こりやすいです。
TanStack DBでは、ローカルのCollectionを直接更新するだけで、楽観的更新が自動的に行われる ため、上記のような複雑なコードを書く必要がありません。
TanStack DBによる楽観的更新の例
const updateTodo = async (id: string, newTodo: TODO) => {
await todosCollection.update(id, (draft) => {
draft = newTodo;
});
await tx.isPersisted.promise;
};
快適なUIを実現するうえで、楽観的更新は重要な要素です。
処理が失敗することは稀である場合が多いため、成功を前提にUIを即座に更新することで、ユーザー体験が向上します。
永続化層を自由に差し替え可能
フロントエンドでストレージを扱う場合、localStorageやIndexedDBなど様々な選択肢があります。
また、バックエンドと同期する場合はSupabaseやFirebase、GraphQLなどのSaaSを利用することもあります。
そして、それらをフロントエンドから利用する場合はラッパーライブラリを使用するのが一般的です。
例えば、IndexedDBの場合はDexie.js、GraphQLの場合はApollo Client、FirebaseはFirebase SDKなどです。
これらはそれぞれに独自のAPIのため、使い方が異なり、学習コストがかかります。
TanStack DBは特定のストレージ技術に依存しません。アダプタを差し替えることで、様々なストレージに対応できます。
- localStorage
- インメモリ
- REST API
- Electric SQL
- TrailBase
また、標準でサポートされているアダプタ以外にも、独自にアダプタを実装できます。
Supabase, IndexedDB, DuckDB Wasmなどのアダプタも技術的に実装が可能なため、登場が期待されます。
バックエンド実装を簡素化できるかも
フロントエンドが欲しいデータを直接クエリできるため、バックエンドの実装を簡素化できる可能性があります。
TanStack DBを使えば、バックエンドがやるべきことはデータベーススキーマの設計と、Row Level Security(RLS)の設定、認証の実装程度に留められます。
上記で上げた、Electric SQLとTrailBaseは、フロントエンドのDBとバックエンドのDBを自動的に同期する仕組みを提供しています。
従来も、SupabaseやGraphQLのHasura, PostGraphileなどを使えば同様のことが可能でした。
しかし、これらの技術はそれぞれに独自のAPIがあり、学習コストが発生してしまいます。
フロントエンド側のロジックが特定のSaaSに依存し、将来UIライブラリやバックエンドのどちらかを変更したいとなった場合、移行が困難になるリスクがあります。
TanStack DBであれば、アダプタを差し替えるだけで済むため、特定のストレージ技術に依存しないで済みます。
どのバックエンドを採用していたとしても、フロントエンド側の実装は変わりません。
しかも、UIライブラリもマルチフレームワークに対応しているため、ReactからSvelteに乗り換えたくなった場合でも差し替えが容易です。
使い方
早速使い方を説明していきます。
今回はReactでの利用をベースに解説していきます。
TanStack DBのパッケージは以下の通りです。
npm install @tanstack/db @tanstack/react-db
Collectionの定義とクエリ
まずはデータを永続化するためのCollectionを定義します。
import { createCollection, localStorageCollectionOptions } from "@tanstack/db";
import * as v from "valibot";
const drawCalcSchema = v.object({
id: v.string(),
name: v.string(),
gameTemplate: v.string(),
result: v.string(),
createdAt: v.date(),
updatedAt: v.date(),
});
export const drawCalcCollection = createCollection(
localStorageCollectionOptions({
storageKey: "tcg-tool-draw-calculations",
id: "draw-calculations",
getKey: (item) => item.id,
schema: drawCalcSchema
}),
);
type DrawCalc = {
id: string;
name: string;
gameTemplate: string;
result: string;
createdAt: Date;
updatedAt: Date;
};
export const drawCalcCollection = createCollection(
localStorageCollectionOptionsDrawCalc>({
storageKey: "tcg-tool-draw-calculations",
id: "draw-calculations",
getKey: (item) => item.id,
}),
);
このCollectionはSQLでいうテーブルに相当します。
型定義は型パラメータとして渡しても良いし、ZodやValibotなどのランタイムバリデーションのスキーマを渡して推論させることもできます。
続いて、クエリでデータを取得します。
import { useLiveQuery } from "@tanstack/react-db";
import { eq } from "@tanstack/db";
const { data } = useLiveQuery((q) =>
q
.from({ calculations: calculationsCollection })
.where(({ calculations }) => eq(calculations.id, calculationId))
.select({
id: calculations.id,
name: calculations.name,
result: calculations.result,
})
.orderBy(({ calculations }) => calculations.updatedAt, "desc"),
);
useLiveQueryを利用することで、ストレージをリアルタイムで購読し、その変更に応じてコンポーネントが再レンダリングされるようになります。
イメージとしては、ReduxのuseSelectorと同じですが、そのセレクター部分がSQLライクなクエリで書けるようになっています。
ReduxのセレクターはJavaScriptで記述するため柔軟性がありますが、その分アクセス方法が定まりません。
ここをSQLライクなAPIで統一することにより、効率の良いデータ取得と認知負荷の軽減が期待できます。
これは目から鱗の発想でした。
派生Collection
クエリをあらかじめ定義した「派生Collection」も作れます。
export const drawCalcHistoryCollection = createLiveQueryCollection((q) =>
q.from({ calculations: drawCalcCollection })
.orderBy(({ calculations }) => calculations.updatedAt, "desc"),
);
export const createDrawCalcByGameCollection = (gameTemplate: string) =>
createLiveQueryCollection((q) =>
q.from({ calculations: drawCalcCollection })
.where(({ calculations }) => eq(calculations.gameTemplate, gameTemplate))
.orderBy(({ calculations }) => calculations.updatedAt, "desc"),
);
これにより「利用頻度の高いクエリ」を再利用可能な形でまとめられます。
コンポーネントでの利用
親コンポーネント
const CalculationList = () => {
const { data } = useLiveQuery((q) =>
q
.from({ calculations: calculationsCollection })
.select({
id: calculations.id,
})
);
return (
>
{data.map((item) => (
CalculationItem key={item.id} calculationId={item.id} />
))}
>
);
};
子コンポーネント
const CalculationItem = ({ calculationId }: { calculationId: string }) => {
const { data } = useLiveQuery((q) =>
q.from({ calculations: calculationsCollection })
.where(({ calculations }) => eq(calculations.id, calculationId)),
);
const [calculation] = data
if (!calculation) return FallbackItem />;
return (
Card.Root>
Card.Header>
{calculation.name}
Card.Header>
Card.Body>
{calculation.result}
Card.Body>
Card.Root>
);
}
このように、コンポーネントの中で直接クエリを書き、部分的に購読可能です。
おまけ
状態管理のベストプラクティスを変える
これまでデータフェッチやバックエンドとの同期を主軸に書いてきましたが、ローカルな状態管理もTanStack DBが置き換えてしまうのではと考えています。
今までJotaiやZustandなどで状態管理していた部分です。
これらは複雑なデータ構造を表現しようとすると、状態の正規化やセレクターの実装が必要になり、認知負荷が高くなりがちです。
データのあるべき姿をスキーマで定義し、操作をSQLライクなクエリで行うことができるため、状態管理のベストプラクティスを大きく変える可能性があります。
そして、それらをそのままバックエンドに同期できる点も見逃せません。
想定されるユースケース
では一体どんな場面で使うと効果的なのか、少し考えてみました。
-
リアルタイム性が求められるアプリケーション
チャットアプリやコラボレーションツールなど、データの変更が即座に反映されることが重要な場合。
例えば、MiroやFigma、Google Spreadsheetのような共同編集ツール。 -
オフラインでの利用が求められるアプリケーション
ネットワークが不安定な環境でも快適に動作することを求められる場合。
例えば、建設業、フィールドワーク、医療現場など。 -
大容量のデータの分析や可視化が求められるアプリケーション
大量のデータを効率的に処理し、ユーザーに分かりやすく提示することが求められる場合。
例えば、ダッシュボードやBIツール、株取引アプリでの利用など。
実際に触ってみた
Claude Codeと一緒に既存アプリをTanStack DBに載せ替えてみました。
このアプリケーションはlocalStorageのみにデータを保存するシンプルな計算アプリですが、状態管理アプリを採用せずにTanStack DBだけで実装できました。
書き心地が良く、状態管理とデータ保管が統合されているため、コードがシンプルになりました。
まとめ
- TanStack DBは「フロントエンド中心のデータ設計」を加速する
- すべてのServer Stateの抽象化レイヤーになりうる
- 状態管理とデータ保管を統合し、バックエンド設計にも影響を与える可能性がある
今後のアップデートでどのように進化していくか非常に楽しみです。
Views: 0