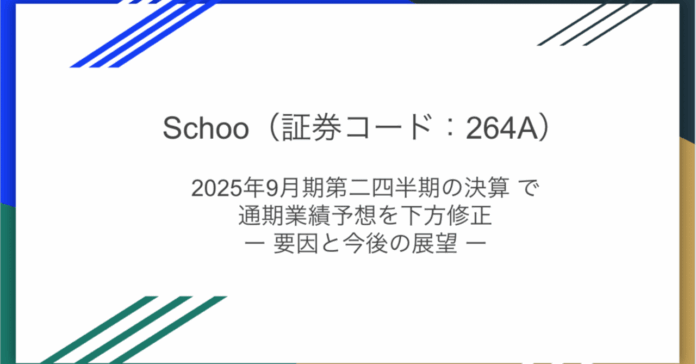🧠 概要:
記事の概要
Schooは2025年9月期第2四半期決算で業績予想の下方修正を発表し、売上高と純利益の見通しが大幅に引き下げられた。これに伴い、株価が急落した。主な要因としては、新規顧客獲得の鈍化や既存顧客からのアップセルが期待を下回ったことが挙げられる。今後の展望としては、新規顧客獲得チャネルの再構築やハイブリッド型研修サービスの展開が鍵になると考えられている。
要約ポイント
- 業績予想の下方修正: Schooは2025年9月期の売上高予想を3,902百万円から3,361百万円に、純利益予想を503百万円から142百万円に引き下げた。
- 株価急落: 発表後、Schooの株価はストップ安となり、一時35%以上の下落を記録。
- 主な原因:
- 新規顧客獲得の鈍化:法人向けサービス「Schoo for Business」での新規獲得が期待を下回った。
- アップセルの停滞: コロナ後、対面研修の需要が回復し、オンライン学習のアップセルに影響。
- 中長期的視点: 経営陣は短期間での成長回復が難しいとし、中長期的な改善策に注力。
- 成長の鍵:
- 新規顧客獲得チャネルの再構築: リスティング広告中心から多様な手法への転換。
- ハイブリッド型研修サービス展開: オンラインと対面型の組み合わせで新サービスを開発中。
- 競争優位性の確立: 商品力、サービスモデルの成功が今後の成長に向けた試金石。
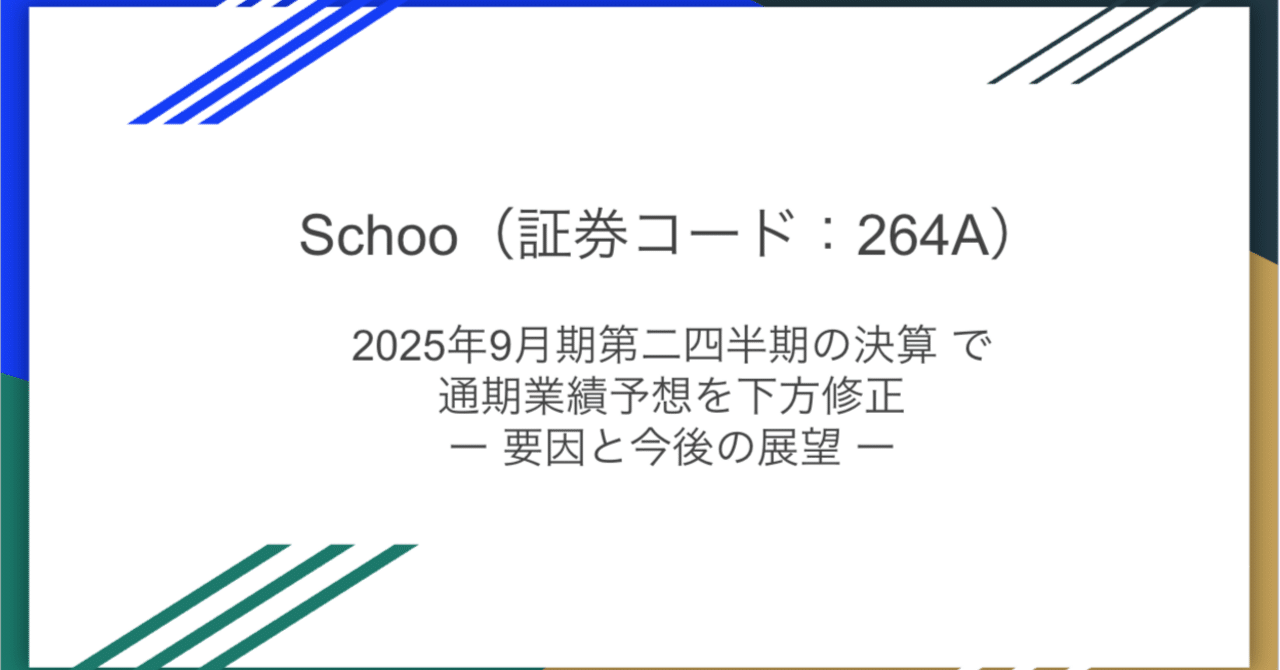
※ 出典は特記なき限り2025年5月15日に公表されたSchooの適時開示資料に基づきます。また、この記事は株式投資を推奨するものではありません。
東証グロース上場のオンライン学習企業Schoo(証券コード: 264A)は、2025年9月期第2四半期決算において通期業績予想の下方修正を発表しました。
売上高見通しは従来の3,902百万円から3,361百万円へ、純利益見通しも503百万円から142百万円へと引き下げられており、売上・利益ともに大幅な下方修正となっています。
この発表を嫌気した市場は敏感に反応し、翌営業日の株式市場ではSchoo株がストップ安まで売られる急落となりました。
結果的に週間の値下がり率ランキングで同社は1位となり、一時35%以上の株価下落に見舞われています(diamond.jp)。
こうした業績修正に際し、投資家や業界関係者の間では「なぜ今回下方修正に至ったのか」「その要因は一時的なものなのか、それとも構造的な課題によるものか」といった点に注目が集まっています。
そこで本レポートでは、まずSchooの業績予想下方修正の背景となった主な要因を事実ベースで整理し、筆者の見解も交えながら今後の展望について考察します。
業績下方修正の要因
新規顧客の獲得、既存顧客の取引拡大の進捗が想定を下回る
今回の通期予想下方修正の主因は、同社の売上の90%以上を占める主力事業である法人向け動画学習サービス「Schoo for Business」の成長鈍化にあります。
同社は当初、この法人向けサービスの高い成長を前提に大幅な増収増益を計画していましたが、蓋を開けてみると新規顧客の獲得および既存顧客の取引拡大(アップセル)の進捗が想定を下回り、業績の伸びが計画未達となる見込みであることが判明しました。
実際、以下の表に示すように、2Q末の契約社数は2,433社、ARPA(平均月額売上)は10.0万円 といずれも1Q末(2,481社/10.4万円)から低下しただけでなく、契約社数については、2024年9月期通期決算時の2,491社をピークに2期連続の減少となっています。
Schoo 決算説明資料 より筆者作成
上記のことから、新規契約社数の増加は鈍く、既存顧客からの追加売上も計画ほど伸びなかったことが業績予想の下振れ要因となっています。
新規顧客獲得の鈍化 ー 中長期的に苦戦中か
Schoo が通期予想を下方修正した主要因の一つとして、新規顧客獲得に想定よりも苦戦したことにあります。
同社は「リスティング広告・検索流入を主とする新規顧客獲得が想定を下回った」と説明していますが、本質は広告パフォーマンスの揺らぎではなく、上場以来あった“新規開拓力の弱さ”が数字に現れたのではないかと予想します。
そのように予想する根拠としては、同社の戦略やIRでのコミュニケーションの取り方です。
まず、同社はNet Revenue Churn Rate という指標を使用しております。定義としては以下の注釈に示すようになります。
※{今月新規法人MRR(当月獲得)-(今月総法人MRR-前月総法人MRR)}/ 前月総法人MRR の12ヵ月平均で算出
同社は、カスタマーサクセスが顧客の解約を防ぐ守りの視点だけではなく、顧客の利活用を促進し1顧客ID数増加のアップセルを重要視しているため、解約だけでなくアップセルの効果を反映する指標としてNet Revenue Churn Rateを採用したと説明しております。
確かに同社の戦略を考えても、納得感のある理由なのですが、一方でこの指標は 「既存顧客からの追加売上」で解約・ダウンセルを打ち消す ため、新規顧客獲得やロゴベースの離脱がやや弱くても数値は良く見えてしまいます。
上場SaaS企業がチャーンレートはグロスで算出することが多い中で、ネットチャーンレートを採用したという点は、同社の新規獲得の弱さ を示す裏返しであり、同社は当初から新規純増を語りにくい体質を抱えていたのではないでしょうか?
そして、新規開拓に難があれば、既存顧客深耕に舵を切るのは合理的です。Schoo はまさにその道を選んだと言えます。
実際、同社は「まず部署単位で小口導入し、カスタマーサクセスの伴走で全社展開へ拡大する」というアップセル戦略を採用しました。
公式事例では、新入社員研修向けに数百 ID で始まった導入が、最終的に約2万人規模の全社利用へ広がったと紹介されているなど、「まず部署単位で小口導入し、カスタマーサクセスの伴走で全社展開へ拡大する」同社の戦略は一定は上手くいっていました。
もう一つが競争が比較的緩やかな市場の選択です。
Schoo は2015年に福岡市・千葉市と連携して以降、現在までに全国56自治体と提携し、離島向け遠隔授業や職員研修を展開しています。
実際、公共機関のマーケットは、競争が限定的で契約期間も長め、安定売上の源泉になり、かつ社会的意義も大きい、素晴らしい展開です。
しかし、研修市場は首都圏の民間大手企業の予算がほとんどを占めているのが実態で、裏を返せば競合がひしめくが、市場規模は大きい市場を避けたとも考えることができます。
そして、後述に示す通り、大手企業へのアップセルに苦戦し始めた結果、従来より課題だった“新規開拓力の弱さ”が数字に現れたと考えられます。
アップセル停滞——対面研修回帰に追いつけず
さらに、主要因の2つ目である、既存顧客へのアップセルが思うように進んでいない要因として、コロナ禍後の対面研修ニーズ再燃にも触れておく必要があります。
コロナ禍で企業研修は一時オンライン化が急速に進みましたが、2022年頃から新人研修を皮切りに対面型の集合研修需要が回復傾向を見せています(yano.co.jp)。
矢野経済研究所の調査によれば、研修市場では現在ハイブリッド(オンラインと対面の組み合わせ)が主流となりつつあり、対面ならではの教育効果を求める動きが広がっているといいます。
このような市場環境の中、オンライン動画学習に強みを持つSchooの従来サービスだけでは顧客企業の「対面研修を含めた人材育成ニーズ」に十分応えきれなくなっている可能性があり、ここがアップセルの増加を妨げている要因になっているのではないかと推察できます。
実際、Schooも「対面学習との組み合わせなどニーズ多様化への対応」を課題に挙げ、従来のオンライン研修「Schoo for Business」にオプションを加える形で独自の企業研修プログラムを開発する計画です。
 Schoo 2025年9月期 第2四半期決算説明資料 より筆者作成
Schoo 2025年9月期 第2四半期決算説明資料 より筆者作成
今後の展望
短期での大崩れはないが、急成長の難易度も高い
今後の業績展望についてですが、サブスクリプション型のビジネスモデルである同社は急激な業績悪化が起こりにくい反面、短期間で成長率を元に戻すことも容易ではありません。
経営陣も「既に改善施策に着手しているものの、リカーリング型収益モデルの特性上、上期の未達分を下期に短期間で挽回するのは困難」と述べており、中長期的な視点で業績回復シナリオを描いています。
しかし、アカウント数を多く保有する大手クライアントがチャーンするとなると、従来低水準で推移していたネットチャーンレートも大幅に悪化するなどのリスクも抱えております。
また、大幅な成長を再現するには新たな付加価値提案やサービス拡充によって既存顧客・新規顧客双方への訴求力を高める必要があるなど、業績回復に向けて予断を許さない状況であると言えます。
新規顧客獲得チャネルの再構築とハイブリット型研修サービスの展開が鍵に
成長軌道に再び火を付けるためには、新規顧客獲得チャネルの再構築と現在準備中である対面型研修サービスの展開が鍵を握ります。
前者について、同社はこれまでリスティング広告や検索流入によるインバウンド獲得が中心でしたが、今後はそれ以外の多様なリード獲得手法の開発が急務となるでしょう。
実際、Schooは資料の中で「新たなマーケティング施策の検討・実行」「販売代理パートナーの拡大」などに着手するとしており、営業チャネルのテコ入れを図る方針を示しています。
後者については、既に「対面学習との組み合わせ」によるサービス強化策に言及しており、従来のオンライン研修「Schoo for Business」にオプションを加える形で独自の企業研修プログラムを開発する計画です。
対面型研修の提供はSchooにとって新たな挑戦ですが、ポストコロナの企業研修ニーズに対応する上で避けて通れない施策と言えるでしょう。
特にハイブリット型研修サービスの成否が分水嶺
その意味で、同社の営業力強化と提供サービスの成功が今後の分水嶺となりそうです。
社内の営業リソース強化やソリューション提案力の向上はもちろん重要ですが、上場間もない同社が短期間で大手研修会社並みの営業体制を築くのは容易ではありません。
大企業への導入拡大には高度な提案力と信頼性が求められ、営業面でのハードルは高いのが実情です。
そのため、最終的な勝負所は「商品力」と「サービスモデル」になる可能性があります。
豊富なオンラインコンテンツ資産に加え、現在開発中のハイブリッド型のソリューションで他社にはない価値を提供できれば、営業力の不足を補って市場での競争優位性を確立できるでしょう。
同社が持ち前の企画力・コンテンツ力を武器にどのような新サービスを創出できるかが、今後の成長再加速に向けた試金石となりそうです。
※ 出典は特記なき限り2025年5月15日に公表されたSchooの適時開示資料に基づきます。また、この記事は株式投資を推奨するものではありません。
Views: 0