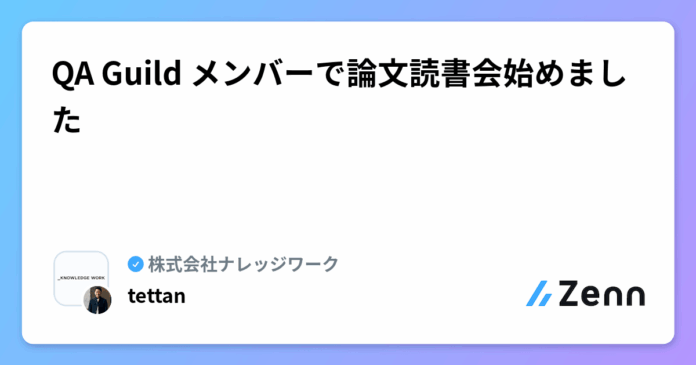はじめに
この記事は、「KNOWLEDGE WORK Blog Sprint」第 4 日目の記事になります。ナレッジワークの QA エンジニアの tettan です。ナレッジワークでは新規プロダクトや新チームの QA の立ち上げをやっていることが多く、他には、QA や品質の観点で横断的な改善活動を進めています。
今回は、ナレッジワークの QA エンジニアが集まる組織である QA Guild で読書会を開始したので、その背景や目的、読書会の流れをお伝えします。ところで、QA Guild という聞き慣れない用語が出てきたので、少しだけ補足しておきたいと思います。
ナレッジワークでは、以前 QA Group という組織が存在し、QA エンジニアはその Group に所属していましたが、スケーラブルで自律的な開発体制を目指すために 2024 年 7 月から QA エンジニアも各開発 Group に所属することになりました。ただ、同じ QA エンジニアという職能で集まり、情報共有や技術交流、横断的な意識決定を行う組織として QA Guild を同じタイミングで組成し、組織運営を行っています。今回は、この QA Guild における 1 つの取組み事例として読書会についてお伝えしていきます。
読書会の背景と目的
まず、ナレッジワークはイネーブルメントをテーマに掲げる企業であり、我々、QA エンジニア自身も体現したいという考えがベースにあります。
私が入社して半年強がたった 2024 年 2 月あたりに、当時は QA Group だったんですが、QA 組織の中長期ビジョンという大体 3 年くらいのライムラインで QA エンジニアがイネーブルメントするためのロードマップを策定しました。そのロードマップ上で勉強会の開催を計画していました。
ただ当時は、QA エンジニアを積極採用しており採用が落ち着いたタイミング、つまりメンバーがある程度固定化される時期で勉強会をスタートしたほうが良さそうということで、様子を伺ってました。そして、今年の頭あたりに QA エンジニアの採用がクローズしたこともあり、私が企画を動かし始め、5 月くらいに具体化に向かいました。(その後、QA エンジニアの採用は再開し、現在積極採用中です。詳細知りたい方はこちらをご覧ください。)
当初は技術書を読み進める勉強会を週 2 回 30 分でガシガシ進める予定でしたが、参加したいけど、毎回参加できないという声がちらほら出ていたので、スポットで参加しても大丈夫なように、毎週一回、クイックに 30 分で論文を読む読書会にすることになりました。特にほとんど目にする機会のない海外の論文をピックアップすることにしました。近年、AI の発展により、英語論文の翻訳は手軽に行えるようになり、一気に英語論文を読むハードルが低くなりました。
さて、実務家が英語論文もしくは論文を読む目的・メリットは、以下の 3 点と考えています。
- 海外の最新の動向をチェックできる
- 実務に役立つ研究を知ることができる
- 論文の型が理解できる(将来的に自身が論文を書く際に役立つ)
以上のような経緯で英語論文の読書会をスタートしています。とはいえ、英語論文を皆で読みましょうと言っても中々うまく進まないので、次章では読書会の進め方をお伝えできればと思っています。ちなみに、このブログが公開される段階で、すでに 6 回開催してますので、なんとか運用に乗ってきました。
読書会の進め方
まず初めにお伝えしておくと私は少しだけ研究者としてのバックグランドがあります。なので、今回の英語論文の読書会の運営がスムーズに進んだのかもしれません。
さて、まず読書会開催にあたり、事前にいくつか準備しました。
読書会のハンドブックの作成
いきなり読書会を初めても、参加者が迷子になってしまうので、背景や目的、読書会の進め方を記したハンドブックのようなものを作成して事前にそれに目を通したうえで参加してもらうようにしました。また、読書会を設計するにあたり、エクストリームリーディングという方法を参考にしました。
読書用のテンプレートの作成
単純に読み進めるだけだと、あっという間に 30 分が過ぎてしまいます。なので、コンパクトの論文の全体像が理解できるように、テンプレートを用意しました。例えば、以下のような点を確認しながら読み進めます。
- 題名からどんな研究なのかを推測する(当たりをつける練習をする)
- 著者(筆者の所属先)を確認する
- 論文は仮説検証タイプか、問題解決タイプか
- 論文が書かれた背景
- 論文・研究の目的
- 目的達成のために何をやったのか
- 結論は何なのか
- 学術界・産業界への貢献
- コメント・感想
読書会の流れ
そして、読書会は、以下のような流れで進めています。
1. 論文のピックアップ
私が ICSE(International Conference on Software Engineering)や ICST(International Conference on Software Testing, Verification and Validation)などのトップカンファレンスの本会議のセッションから業務に役立つかという観点で論文をピックアップしています。
2. 読書会
読書:20 分
- 参加者の使い慣れた AI ツールに英語論文を読み込ませたうえで、AI ツールと壁打ちしながらテンプレートの各項目を埋めていきます
- 皆が使うAIツールにバリエーションがあるため、共有のときに違う視点のコメントがあって面白いです
共有:10 分
- 参加者がテンプレートに記載した内容やコメント、感想を共有していきます
- 時間も限られるため特に議論は行わず、共有することにフォーカスします
おわりに
英語論文の読書会を開催するにあたり、以下のような点を意識しております。
-
広く浅く読む
- 研究者ではないため深く読むというよりは、新しい研究分野やトピックを知ることが大事だと考えています
-
30 分以上追わない
- 読書会を継続するためにも、消化不足でも読書会は 30 分で終わりにしています。もちろん、読書会のあとに気になる人は個人で消化不足は解消することは問題ないです。
-
朝一に開催する、そして毎週開催する
- 朝一以外の時間にすると業務都合や割り込み作業で参加が難しくなるので毎週木曜 10:00~10:30 で開催してます。また、読書会や勉強会は継続することが非常に重要なので、予定が合わない場合は、他の曜日に調整して開催する。
また、以下の読書会の目的・メリットに対して現在の参加者向けにヒアリングを行いました。
- 海外の最新の動向をチェックできる
- 実務に役立つ研究を知ることができる
- 論文の型が理解できる(将来的に自身が論文を書く際に役立つ)
ヒアリングの結果、最新の動向をチェックするまでは至っていませんが、実務へのアイデアやヒントを得ることができ、また参加者のほとんどが論文に馴染みがなかったため、型の理解という点で一定の効果があったようです。引き続き、目的に照らし合わせて、会の進め方をブラッシュアップしていきたいと思っています。
今後は、論文のピックアップ作業を他の参加者でもやれるように冗長化することを考えています。また、今後中長期的に継続運用できたら、その結果をブログでお伝えできればと思っています。
Views: 0