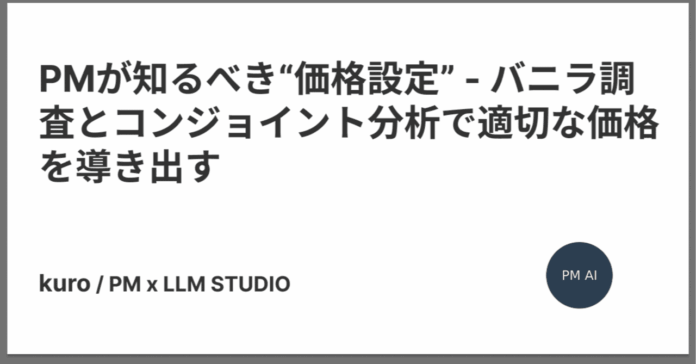🧠 概要:
以下は、記事「PMが知るべき“価格設定”」の概要と要約です。
概要
この記事では、プロダクトマネージャー(PM)が価格設定を行う際に重要な手法として、バニラ調査とコンジョイント分析を紹介しています。架空のHRテックサービス「TalentWorks」を例に、ユーザーの心理や行動をリサーチし、適切な価格戦略を構築するプロセスを詳述しています。
要約箇条書き
- 価格設定の重要性: 売上やブランドイメージに直結するため、PMは価格戦略に積極的に関与すべき。
- 架空ケース「TalentWorks」: 中途採用に特化した候補者管理プラットフォームの価格見直しを開始。
- バニラ調査:
- 価格感覚を掴むための手法としてVan WestendorpやGabor-Granger法を活用。
- TalentWorksのバニラ調査結果から、月額3~10万円が心理的許容レンジと判明。
- コンジョイント分析:
- 複数の価格と機能を評価する手法で、ユーザーの価値感を定量化。
- チャット連携と分析レポートのセットが高評価との結果。
- ユーザーインタビューとログ分析:
- アンケートだけでは得られない実態を把握するために重要。
- 行動ログを用い、実際の利用状況とのギャップを確認。
- 新プランのリニューアル案: スタンダードプラン廃止、新しい「Proプラン」を設定し、機能とサポートを強化。
- 社内合意形成: 定量データと定性データを用いて、社内の意思決定をスムーズに。
- 施策後のモニタリング: KPIsを追い、必要に応じてプラン内容や価格を調整。
- まとめ: 複数のリサーチ手法を駆使することで、納得感のある価格設定が可能に。
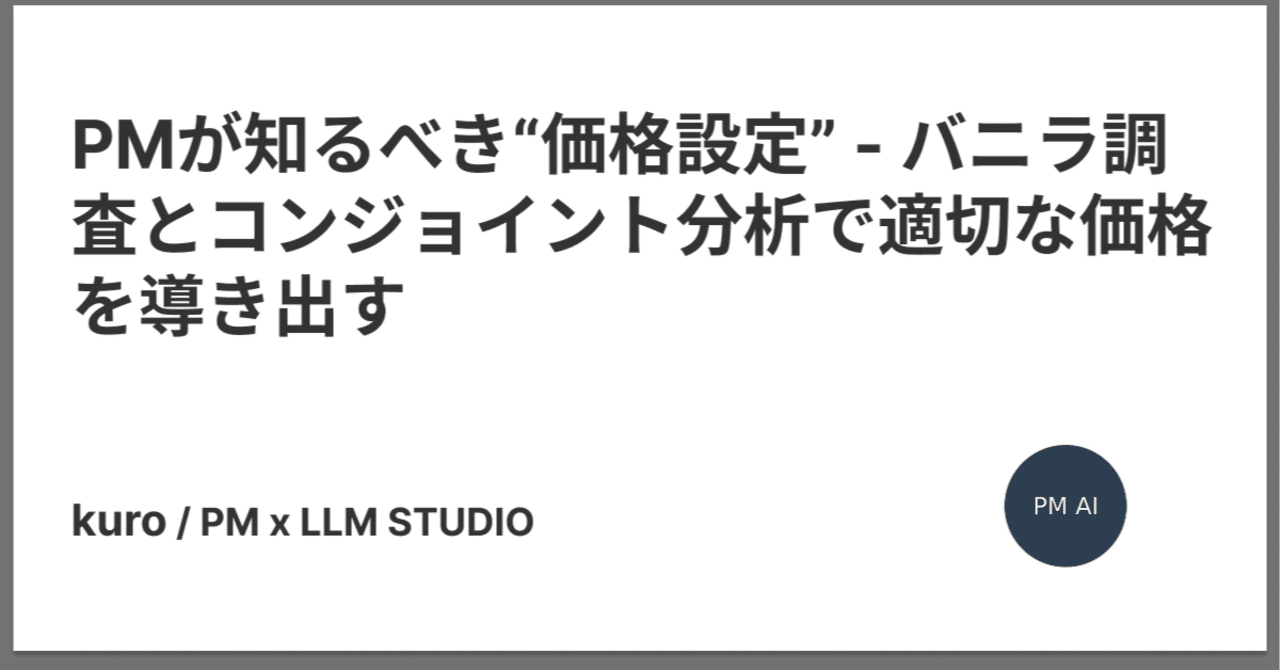
本記事は僕が運営するPM x LLM STUDIOからの転載です。詳細や最新の情報を知りたい方は、ぜひこちらのオリジナル記事もあわせてご覧ください(本は本記事を少し変更しています)。
なぜ価格設定リサーチが重要か?
僕たちプロダクトマネージャーにとって、プロダクトの価格をどう決めるかは非常に大きなテーマですよね。売上や利益率への影響がダイレクトに表れるうえ、価格次第ではユーザーが離れてしまったり、ブランドイメージを損ねてしまうリスクがあります。そのわりに、マーケティング部門や経営層に任せきりになりがちな領域ではないでしょうか?
実は、僕自身もtoCスタートアップで価格設定を担当した経験があり、「誰にどんな価値を届けるか」という肌感覚をしっかり把握しているPMこそ、価格戦略に深くコミットすべきだと痛感しています。本記事では、価格リサーチの具体的な手法と、それを理解するための架空ケースを組み合わせながら、実践的なプロセスを解説していきます。
架空ケース「TalentWorks」のシナリオ
ここでは、HRテック系の架空SaaS「TalentWorks」を例にとって、価格リサーチの進め方を紹介します。TalentWorksは中途採用に強みを持つ企業向けの候補者管理プラットフォームで、管理画面で応募者をトラッキングしたり、チャットで候補者とやり取りしたりするのが特徴。
現状、「フリー」「スタンダード(月額5万円)」「エンタープライズ(月額15万円)」の3プランを提供しているのですが、最近のユーザーインタビューやログ分析によると、
-
スタンダードプランの利用率が低い
-
フリーから有料プランへの転換率が想定より低い
という課題が浮上。ここを改善するため、そもそもの料金プラン自体を見直そうというシナリオです。
第1章:まずは“バニラ調査”でおおよその価格レンジを掴む
1-1. バニラ調査とは?
価格リサーチと聞くと、高度な統計分析に目がいきがちですが、まずはユーザーが感じるざっくりとした価格帯を把握するのが王道。そのためによく使われるのがいわゆる“バニラ調査”です。
代表的な手法として、
-
Van WestendorpのPrice Sensitivity Meter(PSM)
-
Gabor-Granger法
などがあります。PSMだとユーザーに以下の4つの質問をするのが定番です。
-
「高すぎて買わない」と思う価格はどこから?
-
「安すぎて品質が心配」と思う価格はどこから?
-
「まだ安いと感じる」価格はどのあたり?
-
「高いとは感じるが、買うか迷うレベル」の価格はどこまで?
これらの回答をグラフ化すると、ユーザーが心理的に受け入れやすい価格レンジがざっくり分かるんです。
1-2. TalentWorksの例:PSMでわかったこと
TalentWorksのターゲットは従業員規模50~300名程度の企業。オンラインアンケートでPSMを実施すると、
-
月額3万円以下だと「機能やサポート面が不安」という声
-
月額10万円付近から「さすがに高いかも」と感じる層が増える
という結果が得られました。要するに3~10万円あたりがユーザーの心理的許容レンジだと分かったわけです。
1-3. バニラ調査を設計するときのポイント
バニラ調査はシンプルで使いやすい反面、以下のような注意点があります。
-
回答が抽象的になりやすい
-
稟議プロセスや経営者の意向など実態が反映されにくい
そこで、回答した背景や理由を一緒に書いてもらうとか、後から追加でインタビューするといった工夫をするとデータの解釈精度が高まります。アンケート結果だけではわからない「なぜその価格帯が嫌なのか」を聞き出すためですね。ユーザーインタビューの設計についてはこちらも参照するといいでしょう。
第2章:複数機能を含む“プラン”を評価するConjoint分析
2-1. バニラ調査だけじゃ足りない理由
PSMなどで「いくらなら導入するか」は大枠を把握できますが、「機能AとBはどちらがより価値が高いか」までは見えにくい。そこで、複数の機能・価格帯・契約期間などを組み合わせた選択肢をユーザーに評価してもらうConjoint分析を使うと、ユーザーがどの属性にどれくらいの価値を感じているかを定量的に知ることができます。
2-2. TalentWorksにおけるConjoint分析の設定
TalentWorksの例で言うと、「チャット連携機能」「分析レポート機能」「カスタマーサポートの有無」「月額3万円/5万円/10万円/15万円」などを属性・レベルとして設定。ユーザーに複数のプラン案を見せて「どれが一番魅力的か」を比較してもらいます。
結果、「チャット連携+分析レポート」がセットになっているプランに高い価値を感じるユーザーが多いと分かりました。また、サポートの充実度や契約期間のディスカウントに対しては追加料金を払う意欲があるとの結果が出たのも大きな発見。
2-3. Conjoint分析の流れと注意点
大まかなステップは
-
調査設計:どの機能を属性に含めるか、価格の選択肢は何通りにするか
-
調査票・シナリオ作成:ユーザーが評価しやすいように組み合わせパターンを設計
-
データ収集:アンケートや対面セッションで「どのプランを選ぶか」を集計
-
分析:統計モデルなどで、機能や価格がユーザー選好に与える影響度を算出
注釈として、組み合わせが多すぎると回答者の負担が大きくなるので、効用最大化設計などを使って効率よく選択肢を絞るのが一般的。また、Conjoint分析で得られるのは“相対的な好み”の値なので、最終的には他のデータも踏まえて総合的に判断する必要があります。
第3章:インタビュー+ログ分析で“本音”を確かめる
3-1. 定量と定性を行き来すると精度UP
バニラ調査やConjoint分析は多くの場合アンケート形式になるため、回答がどうしても表面的になりがち。また、「安いほうがいい」と答えがちでも、実際には機能性を優先して高めのプランを選ぶユーザーもいます。
そこで、アンケート結果の背後にある心理を探るためにユーザーインタビューを行うのが効果的です。たとえば「高いプランを嫌うと回答したが、チーム全体で割ると月あたり○円だからそこまで高くないかも…」と思っている場合があるかもしれません。
3-2. 行動ログとの突き合わせ
TalentWorksが提供するSaaSの管理画面ログや利用頻度データを見れば、実際にどの機能がどれだけ使われているかが分かります。アンケートで「レポート機能使わない」と言っているユーザーが、実は毎日閲覧している可能性も。こうしたギャップを埋めるには、ログ分析→ユーザーインタビューの流れが役に立ちます。
第4章:架空ケースの結果とプラン改定案
TalentWorksでの調査結果をまとめると、以下のような知見が得られました(※架空シナリオ):
-
バニラ調査(PSM):3~10万円の月額が心理的許容レンジ
-
Conjoint分析:チャット連携+分析レポートのセットが高評価。サポートや契約期間ディスカウントに追加料金OKな層も
-
インタビュー&ログ分析:スタンダードプランは中途半端、フリーから有料への移行障壁は「サポート不足」「どのプラン選べばいいか分からない」など
これを踏まえ、
-
スタンダードプランを廃止
-
新しい「Proプラン」(月額8万円)を設定し、「フル機能+レポート+チャットサポート」をまとめる
-
フリープランからの移行を促進するため、オンボーディング支援を強化
といったリニューアル案が浮上。価格帯はPSMの範囲内、Conjoint分析で高評価の機能を盛り込み、サポート充実で“導入後の離脱”を防ぐ方向に進めるわけです。
第5章:社内合意形成とリリース後の検証
5-1. エビデンスをもとに意思決定をスムーズに
価格改定には社内でも慎重な議論が必要。セールスチームは「値下げ」を望むかもしれないし、経営陣は「もっと高く設定できるのでは?」と考えるかもしれません。そこを説得するには、今回のように定量データ(PSM、Conjoint)+定性データ(インタビュー)をしっかり提示すると納得感が高まります。
5-2. リリース後もKPIをモニタリング
新プランをローンチしたら、数カ月は継続的にKPIを追うことが大切。申込率や解約率、アップセル率などを見つつ、またユーザーに短期フォローアップのインタビューを行うことで、想定と違う動きがないか早めに察知できます。必要ならプラン内容や価格を微調整するアジャイルな姿勢が成功を左右します。
まとめ:多層的なリサーチが“納得感のある価格”を導く
価格設定はユーザー心理が絡むため、「単に原価に利益を乗せる」以上の難しさがあります。だからこそ、
-
バニラ調査(PSMやGabor-Granger)でざっくりと許容価格帯を把握
-
Conjoint分析で機能価値・価格を複合的に評価
-
ユーザーインタビュー&ログ分析で実際の動機・行動を裏付け
というプロセスをPMが主導することで、**「どうしてこの価格なのか」**をユーザーや社内に説得しやすくなります。結果的に、価格と機能が噛み合わずユーザーが離れるリスクを下げ、“プロダクトの価値を適切に評価してもらえる”状態を作れるはずです。
参考情報
-
Van Westendorp, P. (1976). NSS-Price Sensitivity Meter (PSM).
-
Gabor, A. & Granger, C. W. (1966). Price as an indicator of quality. Economica, 33(129), 43-70.
-
Green, P. E., & Rao, V. R. (1971). Conjoint measurement for quantifying judgmental data. Journal of Marketing Research, 8(3), 355-363.
今日から実践できるアクション
-
バニラ調査でざっくりレンジを把握
-
PSMやGabor-Grangerなど、簡易なアンケート調査をしてユーザーの価格感覚をつかむ。
-
-
Conjoint分析で機能価値を定量化
-
SaaSなど複数プランがある場合、ユーザーがどの機能にどれだけの料金を払いたいかを掴む。
-
-
インタビュー+ログ分析で裏付け
-
数値だけでは把握しきれない心理的障壁や利用実態を確認するため、継続的に定性調査を行う。
-
-
エビデンスを揃えて社内合意形成
-
新プランや価格改定を社内で決める際、得られたデータをわかりやすくまとめて経営陣やセールスと議論する。
-
Q&A
Q1. バニラ調査はシンプルだけど信頼できる?
A1. シンプルがゆえに概算の許容価格を把握するには十分。ただ、実際の購買行動や契約稟議の流れを完全には反映できません。インタビューで理由を深掘りするなど、他の手法で補完するのが大切。
Q2. Conjoint分析には何人くらいのサンプルが必要?
A2. 多ければ多いほど精度は上がりますが、必ずしも大規模でなくても大丈夫。対象セグメントを絞り、必要十分なサンプルを確保すれば、傾向を掴むには十分です。
Q3. 価格改定で既存ユーザーの反発が心配です…
A3. 事前告知のタイミングやアップグレード時のメリットを分かりやすく説明するのが重要。インタビューで「ここに価値を感じるはず」という感覚を得ておけば、説得材料を用意しやすくなります。
「価格」はユーザーの行動と直結するからこそ、PMとしてもしっかりリサーチして、根拠をもって設計したいところ。バニラ調査+Conjoint分析+インタビュー+ログ分析という多層的なアプローチで、ユーザーにとっても、社内にとっても納得感ある価格を作り上げましょう。僕もこれまで価格戦略で何度も苦労してきましたが、丁寧なリサーチのおかげで結果的にはスムーズに導入が進んだ経験があります。皆さんもぜひトライしてみてください。
Views: 2