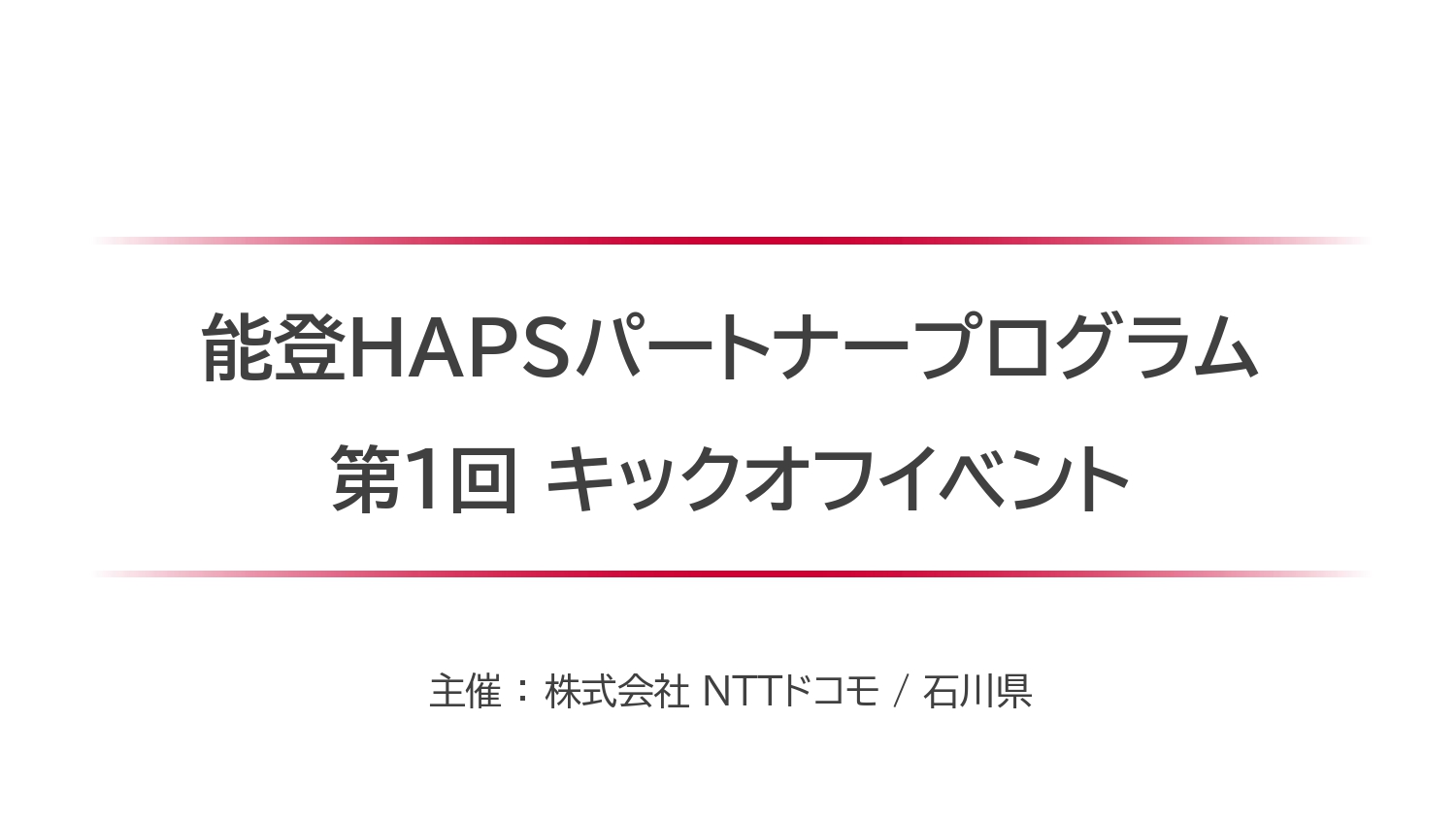NTTドコモが3月に発表した「能登HAPSパートナープログラム」。その第1回ミーティングが21日に開催された。
能登半島では、度重なる災害からの復旧と、より強靭な未来型通信インフラの構築に向けた取り組みが加速している。NTTドコモは石川県と連携し、2024年11月に協定を締結。この協定に基づき、「未来へつなぐ」「地域をつなぐ」「思いをつなぐ」の3本柱のもと、復興支援と将来を見据えた通信インフラ整備を推進している。
同社は、災害発生時の迅速な復旧に向け、陸上のみならず船舶やスターリンクを活用した衛星通信など、多様な手段を講じてきた。災害からの早期復旧には、多様な通信手段が不可欠であるとの認識を示している。
具体的な取り組みとして、NTTドコモは地域住民への情報提供とコミュニケーションの活性化に注力している。輪島市のコミュニティセンターにはデジタルサイネージが設置され、平常時は地域情報やエンタメを、災害時には避難情報を提供する。この仕組みは、平時から利用されることで、災害時にも自然に情報源として機能することを目指している。
また、地域住民の移動手段確保としてAI運行バスの導入も進められている。羽咋市での導入に続き、4月には志賀町でも導入が開始された。このバスは、利用者が希望する時間・場所に合わせて柔軟に運行できるシステムである。加えて、オンライン診療の提供や、ドコモショップでのデジタル防災教室の開催も進められており、地域の医療支援や防災意識の向上にも貢献している。
能登地域のドコモショップ7店舗すべてにはスターリンクが配備され、災害時の通信確保体制の強化が図られている。
石川県:創造的復興を支えるデジタルの力
石川県の浅野大介副知事は、能登半島地震と奥能登豪雨という2度の災害の経験を踏まえ、デジタル技術による創造的復興の重要性について講演した。
副知事は、災害時における通信の重要性を痛感したとし、地震・豪雨の双方で通信の脆弱性が課題となったことを指摘。特に能登半島地震では、デジタルによる被災支援の立ち上げに時間と労力がかかり、平時からの準備不足が浮き彫りになったと述べた。避難所での支援システムの稼働までに10日を要し、被災者データベースの構築には月単位の時間がかかったという。加えて、発災直後にはドローン活用も間に合わなかった。
これらの教訓をもとに、平時から利用でき、災害時には即座に切り替えられる「デジタルライフライン」の構築が不可欠であると訴えた。この構想は国の「デジタルライフライン全国総合整備計画」にも組み込まれている。
一方で、デジタルライフラインの実現には、通信環境の整備、特に電波環境の改善が前提であると強調。国の会議において、馳浩知事が通信インフラの根本的な課題を指摘し、通信事業者のみならず国としての取り組みを求めたことを明かした。
奥能登豪雨の際には、地震の教訓を活かし、県が通信事業者との連携を主導。スターリンクの配備などにより、3日で通信の支障をほぼ解消するという進歩があったという。しかし、浅野副知事は「3日で満足するのではなく、支障が出る期間を1日でも短くすることを目指す」と述べ、今後の課題とした。
孤立が懸念される避難所には、スターリンクと非常用電源の整備を進め、通信基盤のさらなる強靭化を図る。また、デジタルサイネージによる情報発信と共有体制の整備を通じて、避難者の安心感向上にもつなげたい考えを示した。
副知事は、通信環境整備は「点」ではなく「面」でとらえる必要があるとし、スターリンクのような局所的支援と、衛星通信など広域的カバーの組み合わせの重要性を強調。あらゆる技術の冗長性を確保し、技術革新にも柔軟に対応できるよう、NTTドコモとの協定のもと、HAPSを含む多様な技術の導入に意欲を示した。
最後に、電波環境の改善には国の協力が不可欠であるとしつつ、石川県としては大学・研究機関、市町、県庁が連携して技術実証を積極的に展開し、通信環境の向上を図る方針を表明。将来的には、マイナンバーカードの活用など、さらなるデジタル活用を見据えている。スマートフォンが普及した社会への円滑な移行に向け、地域密着型のドコモショップの役割にも期待を寄せた。
総務省の支援:通信復旧と強靭化に向けた取り組み
総務省もまた、能登半島における通信インフラの復旧・強靭化を強力に支援している。北陸総合通信局 情報通信振興課長の川井徹氏は、能登半島地震がこれまで以上に通信の重要性を浮き彫りにした災害であると述べた。
災害発生時には「総務省・災害時テレコム支援チーム(MIC-TEAM)」を派遣し、移動通信機器や移動電源車の貸与を実施。実際に能登半島地震や豪雨災害に際しては、職員を石川県庁に派遣し、自治体や通信事業者との連携を図った。
被災自治体への通信機器の貸し出しも積極的に行われており、スターリンクは地震発生直後から設置が進み、最大時には660台以上が稼働した。
復旧・復興支援策として、総務省は補助金制度を拡充。「災害時における携帯電話基地局等の強靭化対策事業」や「ケーブルテレビネットワーク対災害性強化支援事業」などを通じて、通信インフラの強化を後押ししている。川井氏は、HAPSや衛星通信など非地上系ネットワーク(NTN)が災害時の有効な通信手段であるとし、その早期国内展開を推進していると述べた。
さらに、被災地での衛星インターネット機器設置における課題を踏まえ、官民連携による通信復旧支援チームの設立も進めている。
NTTドコモのHAPS戦略:マルチレイヤネットワークの実現
NTTドコモ ネットワーク部NTN推進室の井上雅広氏は、同社のNTN戦略について説明。静止衛星(GEO)、低軌道衛星(LEO)、高高度プラットフォーム(HAPS)を組み合わせた「マルチレイヤネットワーク構想」を推進し、いつでもどこでも繋がる社会の実現を目指すと語った。
HAPSについては、2026年の商用化に向けて準備が進行中で、スマートフォンによる直接通信の実現や、ペイロードを柔軟に変更することで多様なサービス提供が期待されている。ドコモは既にHAPSの実証実験に成功しており、今後も飛行・通信実験を重ね、技術の確立を目指すとしている。
Views: 0