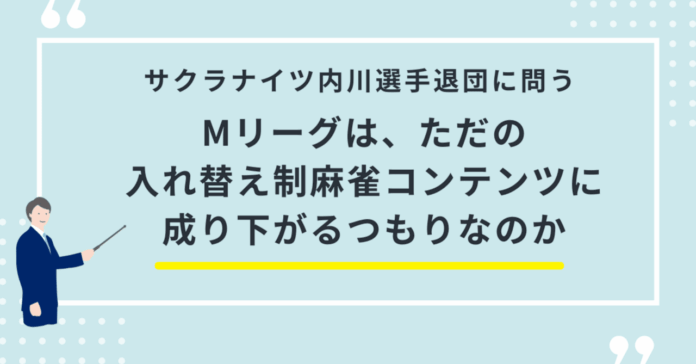🧠 概要:
概要
この記事は、MリーグにおいてKADOKAWAサクラナイツの内川幸太郎選手が退団したことを受け、その影響や意義について考察しています。特に、Mリーグが選手の入れ替え問題やブランド価値をどう維持すべきかという視点から、ファンとの関係性や物語の重要性について触れています。
要約の箇条書き
- 内川選手の退団が発表され、ファンからの驚きと落胆を引き起こした。
- Mリーグには地域性がなく、選手と物語がブランドの根幹を成している。
- 選手の入れ替えには、成績以上にチームの物語を構築する視点が必要。
- ドリブンズや雷電のように、一貫したストーリーテリングがファンを引きつける。
- サクラナイツは内川選手の退団に対する説明が不足しており、ブランド価値を損ねる可能性がある。
- ブランディングは記憶の連続性を設計することが重要であり、選手の入れ替えにはそれに対する語りが必要。
- 麻雀をチーム競技として興行化した意味を再考することが求められている。
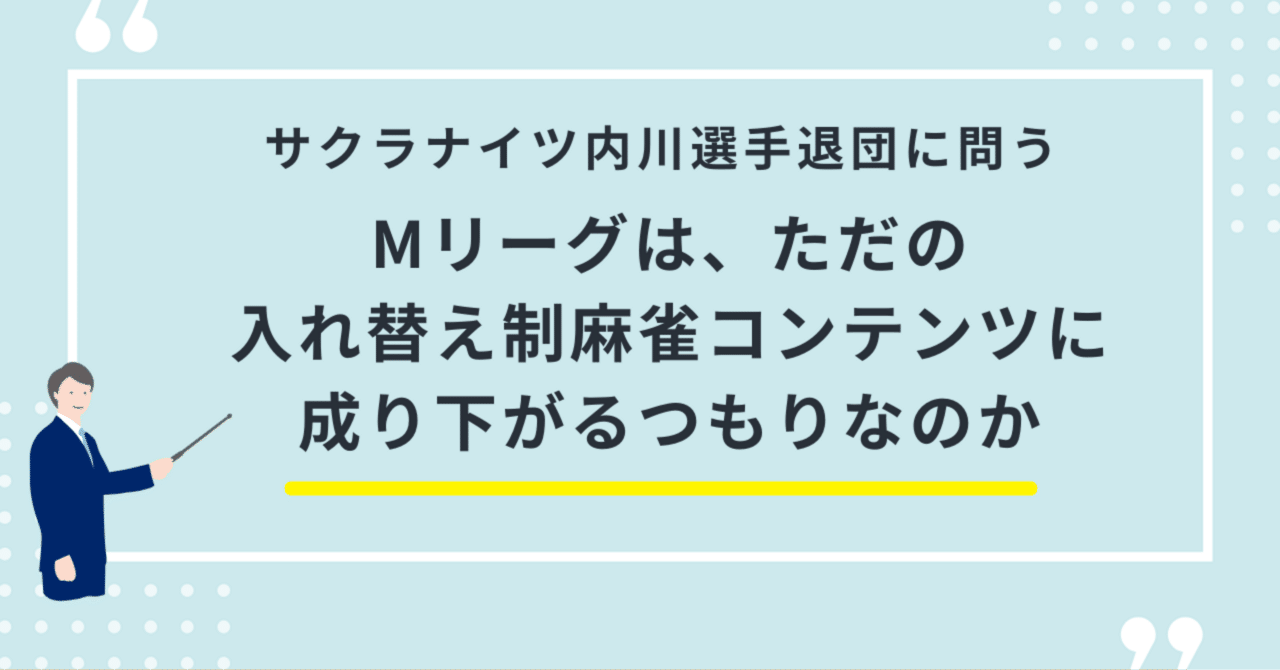
Mリーグに“地域性”はない。だからこそ「選手」がブランド
サッカーのJリーグ、野球のNPBでは、地域との結びつきがファンを支える。浦和レッズの“赤い魂”、広島カープの市民球団神話。それらは地域が生み出す熱狂だ。一方、Mリーグには地域性がない。企業がチームを持ち、ファンは地元ではなく“選手”や“物語”に惹かれて応援する。これはF1に似ている。F1も地域密着ではなく、グローバルスポーツだ。しかし不思議なことに、F1ファンは推しのドライバーが引退しても離れない。なぜか?それはチームに哲学があり、シリーズとしてのストーリーテリングが巧みだからだ。勝者が交代しても、“物語”が継続する限り、ファンは残る。
だから「選手を切る」には覚悟が要る
選手の入れ替えが悪いとは言わない。だが、“誰を切るか”は単なる成績の話ではなく、“どんな物語を残すか”の話だ。ドリブンズは象徴的だった。昨季、渡辺太を迎え入れたが、単なる補強に留まらなかった。彼の加入は「勝ち筋の再設計」であり、「合理麻雀の再解釈」だった。しかもYouTubeチャンネルでは全試合を生配信。チームの試合を“自分たちの手で語る”。これはコンテンツ運営としても、ブランディングとしても非常に洗練されている。雷電もまた、「語ること」を怠っていない雷電は結果だけを見れば、Mルールに対して不利な打ち筋の選手が多い。だが彼らは、一貫してメンバーの入れ替えをしてこなかった。萩原聖人という明確な顔があり、瀬戸熊直樹や黒沢咲といった“魅せる麻雀”の個性派を揃え、その上で本田朋広という”超攻撃的麻雀”がチームを牽引する。「華があるが不器用」な戦い方がチームカラーとして打ち出されている。勝ち負け以上に、「雷電らしさとは何か」という問いに対して、答えを持っているチームだと言える。
サクラナイツの“無言の交代劇”に漂う空虚
内川選手の退団は、あまりにも“説明”がなかった。ファンの為に必要なのは「勝てないから切ります」ではなく、「チームとしてどんな進化を目指すのか」というビジョンだった。あるいは、「どんな物語を紡いでいくのか」という情熱だった。それを語ることなく選手を切るのは、ブランドを自ら削り取るような行為である。
ブランディングとは“記憶の連続性”を設計すること
マーケティングにおけるブランディングとは、ロゴやキャッチコピーではない。それは「人々の記憶の中に、どういう意味を持って存在しているか」を設計する営みだ。Mリーグにおいては、「どの選手が、どんな打ち筋で、どんな物語を背負っていたか」こそが記憶の源泉であり、唯一の資産だ。だからこそ、選手を切るのであれば、その代わりに「語ること」が必要なのだ。
それがないならば、ファンの信頼を裏切り、ブランドを毀損するだけだ。
麻雀をチーム競技にした意味を再考せよ
Mリーグは、地域性のない構造ゆえに、“選手”と“物語”が唯一の資産だ。F1のように、それでもファンが残るためには、シリーズ全体の語りと、チームの明確なビジョンが必要不可欠だ。今回のサクラナイツの動きは、ビジョンも物語も提示しないまま、静かに主人公を降ろした──それが“ファンを置き去りにした”と感じさせる所以である。
ブランドとは、物語の連続性だ。 その物語を意図的に断ち切るのであれば、「そもそも麻雀という個人競技を、なぜチームスポーツとして興行化したのか」という原点に立ち返り、その意味をいま一度問い直してほしい。
Views: 4