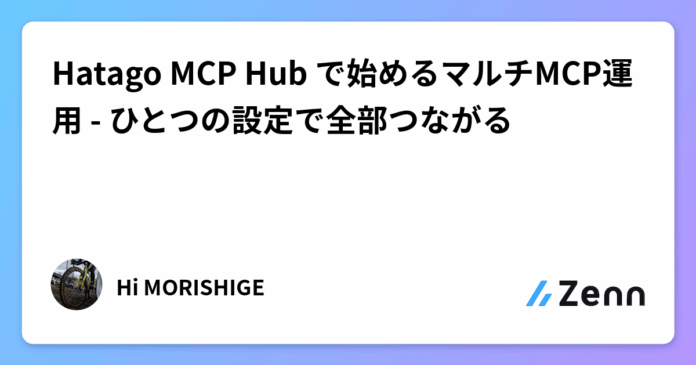はじめに
🏮 Hatago(旅籠) MCP Hub は、複数の MCP サーバーを 1 つにまとめ、Claude Code / Cursor / Windsurf / Codex CLI など複数の AI クライアントから横断的に扱える 軽量 MCP Hub です。Hono の上にミドルウェア的に配置することで、複数の MCP サーバーを統合して、より柔軟に運用できる仕組みを提供します。本記事では、設計の背景からアーキテクチャ、設定方法、運用方法、現状の制約を紹介します。
なぜ Hatago MCP Hub を作ったのか
MCP サーバーが増えるほど、クライアントごとの設定ファイル管理が面倒になりませんか。.mcp.json を更新したのに、別のツール(TOML 設定の Codex CLI)では更新を忘れていた、ということも珍しくありません。同じような用途を果たすライブラリやツールも存在しています。たとえば、Docker Hub MCP Server でまとめればいい、という声もあるでしょう。ただ、個々の現場の制約で Docker Desktop が使えない、あるいは 自由に MCP サーバーを選びたい というニーズは根強く、結局それぞれのクライアントに対して個別設定を続けることになります。
こうした「設定の分散」を落ち着かせるために、1 つの MCP サーバー(Hub)にまとめてしまい、クライアント側は Hatago だけを使う── この方針が Hatago MCP Hub の出発点です。MCP の学習目的で始めた小さな実装でしたが、ツール名の衝突回避や進捗通知の中継、ホットリロードなど、いろいろと実運用に必要な要素を検証していった結果、今の形に落ち着きました。
Hatago MCP Hub の全体像
Hatago は Hub コア、MCP レジストリ(Tools/Resources/Prompts)、トランスポート層の 3 層からなります。AI クライアントと複数の MCP サーバーの間に入り、JSON-RPC/MCP のやりとりを中継します。特徴としては、トランスポート非依存の設計にしている点です。STDIO でつなごうが、Streamable HTTP/SSE/WebSocket でつなごうが、上のロジックは同じように動きます。
内部的には、Hub が各 MCP サーバーから提供されるツール群を取りまとめて統合カタログを形成します。ここで重要になるのが ツール名の衝突回避 です。Hatago は AI ツールへの公開名として serverId_toolName の形式を採用し、実行時には元の MCP サーバーに対して 正規のツール名 でリクエストを委譲します。クライアントから見れば、公開名は常に一意で、どのサーバーに属するかも分かりやすい、というわけです。
もうひとつの要点は 進捗通知(notifications/progress)の透過中継 です。時間のかかる処理を走らせると、下位サーバーからプログレスが飛んできます。Hatago はそれをそのままクライアントに中継するので、上流の体験は損なわれません。サンプリング(sampling/createMessage)の橋渡しも同様で、下位が LLM 生成を要求してきたら、上位クライアントへ安全にバトンを渡し、結果を折り返します。ただ色々な MCP サーバーで検証してみたところ、まだ notifications/progress を利用している MCP サーバーは少なそうです。また sampling を利用できる AI ツールもまだ少ないですが、そういうツールが増えることを想定して Hatago はそれらをサポートしています。
セットアップ:最短ルート
Hatago は CLI を含み、プロジェクト直下でも、専用リポジトリでも、どちらでもすぐに試せます。まずは設定ファイルを生成し、STDIO か Streamable HTTP のどちらかで起動するだけです。
npx @himorishige/hatago-mcp-hub init
npx @himorishige/hatago-mcp-hub init --mode stdio
npx @himorishige/hatago-mcp-hub init --mode http
生成される hatago.config.json に接続したい MCP サーバーを列挙します。npx や node で動かすローカル MCP はもちろん、Streamable HTTP/SSE のリモート MCP も同じファイルで管理できます。{"${VAR}"} や {"${VAR:-default}"} のように 環境変数展開 にも対応しており、開発・本番を通して 1 本の設定を使い回せます。
hatago.config.json
{
"$schema": "https://raw.githubusercontent.com/himorishige/hatago-mcp-hub/main/schemas/config.schema.json",
"version": 1,
"logLevel": "info",
"mcpServers": {
"filesystem": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "/tmp"],
"tags": ["dev", "local"]
},
"deepwiki": {
"url": "https://mcp.deepwiki.com/sse",
"type": "sse",
"tags": ["dev", "production", "documentation"]
},
"api": {
"url": "${API_BASE_URL:-https://api.example.com}/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer ${API_KEY}" },
"tags": ["production", "api"]
}
}
}
起動はシンプルです。1 クライアントで使うなら STDIO、複数クライアントから共有したいなら Streamable HTTP を選びます。設定変更を監視しながら動かす --watch も用意しています。
hatago serve --stdio --config ./hatago.config.json
hatago serve --http --config ./hatago.config.json
hatago serve --stdio --watch
プロファイル管理:タグで環境を切り替える
Hatago の タグ機能 を使うと、開発・本番・テストなど、用途に応じて MCP サーバーをグループ化し、起動時に必要なものだけを選択できます。1 つの設定ファイルで複数の環境を管理できるため、チーム開発や個人の環境切り替えが格段に楽になります。
タグの設定方法
hatago.config.json の各サーバーに tags フィールドを追加するだけです。一応日本語タグもサポートしているので、直感的な名前を付けられます。
hatago.config.json
{
"mcpServers": {
"filesystem-dev": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "./src"],
"tags": ["dev", "local", "開発"]
},
"github-api": {
"url": "https://api.github.com/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer ${GITHUB_TOKEN}" },
"tags": ["dev", "production", "github"]
},
"database-prod": {
"command": "mcp-server-postgres",
"env": { "DATABASE_URL": "${PROD_DB_URL}" },
"tags": ["production", "本番", "database"]
},
"test-mock": {
"command": "node",
"args": ["./mocks/test-server.js"],
"tags": ["test", "テスト"]
}
}
}
タグによる起動
--tags オプションで、起動するサーバーをフィルタリングできます。複数のタグを指定した場合、いずれかのタグを持つサーバーが起動します。
hatago serve --tags dev
hatago serve --tags production
hatago serve --tags dev,test
hatago serve --tags 開発,テスト
実運用シナリオ
シナリオ 1:個人開発での環境切り替え
朝は軽量な開発環境で作業し、デプロイ前には本番相当の環境でテストする、という使い分けが簡単になります。
hatago serve --tags local --watch
hatago serve --tags local,production
シナリオ 2:チーム開発での役割別プロファイル
フロントエンド開発者とバックエンド開発者で、必要な MCP サーバーが異なる場合も、同じ設定ファイルを共有できます。
hatago serve --tags frontend,mock
hatago serve --tags backend,database
hatago serve --tags frontend,backend,database
クライアント別の使い方
Claude Code
Claude Code からは、hatago を 1 件の MCP サーバー として登録するだけで、Hatago 配下のすべての MCP ツールが統合リストとして見えるようになります。設定例は以下のとおりです。
STDIO
.mcp.json
{
"mcpServers": {
"hatago": {
"command": "npx",
"args": [
"@himorishige/hatago-mcp-hub", "serve", "--stdio",
"--config", "/ABS/PATH/hatago.config.json"
]
}
}
}
Streamable HTTP
.mcp.json
{
"mcpServers": {
"hatago": {
"url": "http://localhost:3535/mcp",
}
}
}
ツール名の衝突は Hatago 側で公開名に名前空間を付加して吸収し、実行時には正規のツール名で該当サーバーに委譲します。設定を変更したときは --watch で自動反映され、クライアントへ notifications/tools/list_changed が飛ぶので、リストが自動的に最新化されます。
Codex CLI
Codex CLI は設定が TOML なので、Hatago に一元化する効果がより大きく感じられます。STDIO 起動での接続例は次のとおりです。
STDIO
codex.toml
[mcp_servers.hatago]
command = "npx"
args = [
"-y", "@himorishige/hatago-mcp-hub", "serve",
"--stdio", "--config", "/ABS/PATH/hatago.config.json"
]
Streamable HTTP
[mcp_servers.hatago]
command = "npx"
args = ["mcp-remote", "http://localhost:3535/mcp"]
2025/09/01 時点では HTTP には未対応のため mcp-remote が必要です
複数クライアントから同時利用(HTTP 利用)
チームで共通の Hatago にアクセスする場合は Streamable HTTP モードが便利です。Claude Code、Codex CLI、Cursor、Windsurf など複数クライアントが 同じ URL に接続し、各自は Hatago だけを設定すれば、配下の MCP サーバーを一括で共有できます。運用上の更新は hatago.config.json を 1 か所触れば十分です。
タグ機能との組み合わせでさらに便利に
タグ機能を活用すると、同じ Hatago インスタンスを複数起動して、用途別のエンドポイントを提供できます。開発チームでは開発用サーバー群、運用チームでは本番監視ツール群、といった使い分けが可能です。
この構成により、各チームは自分たちに必要な MCP サーバーだけを見ることができ、不要なツールでリストが煩雑になることを防げます。
hatago serve --http --port 3535 --tags dev,test
hatago serve --http --port 3536 --tags production,monitoring
プロファイル切り替えのフロー
タグによるプロファイル切り替えは、起動時だけでなく、設定ファイルの変更と --watch オプションの組み合わせでも実現できます。
Node と Workers の住み分け
Hatago は Node ランタイム ではローカル MCP(npx や node で動かすもの)を含め、すべてのタイプを接続できます。一方で Cloudflare Workers のようなサーバーレス環境ではプロセス spawn ができないため、HTTP/SSE で公開されたリモート MCP をぶら下げる形が基本になります。設置場所は違っても、クライアントから見れば同じ Hatago です。
設計の詳細
-
ツール名の衝突回避では、既定で
namespace戦略(serverId_toolName)を採用します。公開名は常に一意で、実行時は元サーバーの正規名に戻して委譲します。 -
進捗の中継は、
notifications/progressを受けて上流へそのまま転送します。progressTokenが付く場合は二重配信を避ける最適化を行います。 -
サンプリングの橋渡しでは、下位サーバーの
sampling/createMessageを上位クライアントへ橋渡しし、レスポンス/プログレスを反射します。 -
ホットリロードは、設定ファイルの変更を検知して安全に再接続し、反映後に
notifications/tools/list_changedを送出します。
ここは MCP の仕様に沿って素直な実装で積み上げています。ルーティングやレジストリの整備、イベントの流れを透過的に保つことが最終的な使い心地に直結します。
運用のコツ
設定ファイルでは 意味のあるサーバー ID(github-api, filesystem-tmp のような名前)を付けておくと、公開名から所属がすぐ分かります。環境変数の展開を活用すれば、API のエンドポイントやトークン差し替えも一本化できます。
MCP サーバーへの処理がタイムアウトする場合
notifications/progress に対応していても、実装されていない MCP サーバーではタイムアウトしてしまう可能性があります。その場合は、Hatago の設定ファイルを編集して、タイムアウト時間を延ばすことができます。
hatago.config.json
{
"mcpServers": {
"api": {
"url": "${API_BASE_URL:-https://api.example.com}/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer ${API_KEY}" },
"tags": ["production", "api"],
"timeouts": { "requestMs": 60000 }
}
}
}
できないこと(現状の制約)
Hatago は 認証をビルトインしていません。OAuth にも対応していないため、Bearer Token や Cookie ベースの認可は Hono のミドルウェア、あるいは Cloudflare Zero Trust などの上位レイヤーで実現する方針です。OAuth 必須のリモート MCP をぶら下げる場合は、相手の仕様に合わせて個別の拡張が必要になります。ここは各環境で要件がまちまちなので、まずはシンプルに通す、という哲学です。
ライブラリとしての利用
Hub ロジックはパッケージ(@himorishige/hatago-mcp-hub/node、@himorishige/hatago-mcp-hub/workers)としても提供しており、Hono など既存の HTTP アプリケーションに Hatago の Hub 機能を組み込む こともできます。API ゲートウェイや社内ポータルに軽量に溶け込ませて、チーム共通の MCP 集約ポイントを用意する、といった構成も現実的です。詳しくはリポジトリの examples ディレクトリ を参照してください。
まとめ
MCP の導入が進めば進むほど、設定の分散と運用コストは地味に増えます。Hatago MCP Hub は、その増加分を 「Hub 1 本に寄せる」 ことで、日々の開発体験を保ちます。ツール名の衝突回避、進捗の透過中継、ホットリロード、内部ツールによる点検 ── どれも地味ですが、「使い心地」を確実に底上げできるのはないでしょうか。
まずは小さく、hatago.config.json に 2〜3 本の MCP をぶら下げて試してください。クライアント側の設定は Hatago を 1 件登録するだけ。その後は、たとえば「利用する MCP が 5 本を超えて管理が煩雑」「ツール名の重複が発生」「遅延が目立つクライアントを分離したい」といった具体的なタイミングで、サーバーを追加・削除して最適化していくと運用しやすいと思います。
Hatago MCP Hub を気軽に使ってみて、ぜひフィードバックをいただけると嬉しいです。
Views: 2