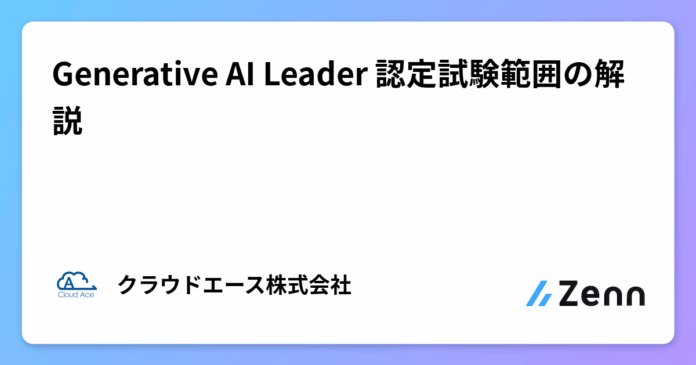こんにちは。クラウドエース株式会社で Google Cloud 認定トレーナーをしている廣瀬 隆博です。最近、ヘヴィメタル界隈では大変著名な方がお隠れになり、にわかメタラーな私も少しアンニュイな気持ちになっています。彼の新たな歌声を聞くことは叶わなくなってしまったのですが、昨今の IT は進歩が目覚ましく、過去のデータから新しいものを生成する AI が日々成長しています。いつかは彼の歌声で「世間に存在しなかった楽曲」が歌われる日が来るかもしれません。
そう、昨今は 生成 AI が真っ盛りです。「猫も杓子も生成 AI」と言っても間違いではないでしょう。私自身も生成 AI に仕事を奪われるのではなく、生成 AI を用いて新しい仕事を生み出したいと、にわかエンジニアながら考えたりもします。そんなエンジニアの始めの一歩とも言える認定資格 Generative AI Leader が Google Cloud から登場しました。私はこれまで AI 領域が大変苦手でしたが、これを機に勉強しようと筆を取りましたので、良ければ最後までお付き合いください。
本記事は Generative AI Leader の認定試験範囲について解説するものであり、生成 AI に対してある程度の知識・経験を保有している方に向けた内容となっています。どなたにも理解いただけるように、なるべく平易な表現を心がけておりますが、あらかじめご了承ください。
解説を始める前に、そもそもどんな試験なんだ? ということに少し触れておきましょう。
試験ガイドによると、生成 AI がビジネスをどのように変革し、その中でどのように活用できるか についての包括的な知識が求められるようですね。また、特徴的なのが 技術的な実装ではない と書かれており、組織への AI 導入を加速させるための知識が問われる と表現されている点ですね。
Cloud Digital Leader もそうですが、末尾に Leader と付く試験は Google Cloud の入門者に向けた資格であり、非技術者でも学ぶべき知識が問われます。今後も生成 AI を用いたビジネスは加速していくことが予測されるため、この記事で体系的な知識を得るための助けとなれば幸いです。
この試験は入門者向けということもあり、生成 AI の基礎から始めていきます。そのあとは関係する Google Cloud の生成 AI 関連サービスについて学び、生成される結果をコントロールするためのテクニックについても少し触れていきます。
生成 AI の基礎
試験ガイドによると、約 30% 出題される 生成 AI の基礎 を解説していきます。基礎なのに出題割合が結構大きいのが、入門編の資格らしさを感じますね。
AI の種類
そもそも、生成 AI とは何でしょうか。私は 新しいコンテンツを創り出す ものだと理解しています。従来の AI は識別や予測を目的としていましたが、生成 AI は文字通り何かを生成するという感じですね。順に解説していきましょう。
従来の AI
従来の AI は、与えられたデータをカテゴリごとに分類したり、データの傾向から将来を予測するためのもの でした。技術要素と活用例の組み合わせを以下に記載します。
- 分類 : メールの内容や送信元といった特徴を学習し、「迷惑メール」か「通常のメール」かという定義済みのカテゴリに 分類 する
- 回帰 : 過去の販売実績、広告費、季節変動といった要因をインプットとして、将来の売上高を 予測 する
- クラスタリング : 年齢や性別といった属性情報、購買履歴データなどをもとに、顧客を明確な共通点を持つクラスターに グループ分け する
- 異常検知 : クレジットカード保有者の「普段の利用パターン」を学習し、そこから大きく外れた決済(深夜の高額決済など)が発生した際に、それを 異常として検知 する
生成 AI
本試験の主題である生成 AI は、膨大な量のテキスト、画像、音声、コードといったデータを事前に学習し、そのデータに潜むパターンや構造を理解します。そして、その知識をもとに、ユーザーからのテキストや画像での指示(以下、プロンプト)に応じて、これまで世の中になかった新しいコンテンツを生成 します。
- テキスト生成 : 新製品の特長やターゲット顧客の情報を AI に与えることで、広告のキャッチコピー、SNS の投稿文といった テキスト案を生成 する
- 要約 : オンライン会議の録画データを AI に与えることで、主要な決定事項、担当者、納期などを 要約 した議事録を生成する
- 画像生成 : 「自社の新しいジュースが、太陽の光が降り注ぐビーチのテーブルに置いてある、リアルな写真」といったプロンプトから、広告用の高品質な 画像を生成 する
- 動画生成 : 「新作のトレンチコートを着た女性が、雨上がりのパリの街を歩いている 15 秒の動画」といったプロンプトから、広告用の高品質な 動画を生成 する
- コード生成 : 「sales_data テーブルから、地域別の売上を取得して棒グラフで表示したい」といったプロンプトから、SQL クエリや Python のグラフ描画に必要な コードを生成 する
- 対話生成 : 顧客からの曖昧で複雑な問い合わせに対して、マニュアル通りの回答ではなく、文脈を理解した 自然な対話を生成 する
Google の生成 AI モデル
モデル とは、機械学習の結果として生まれたプログラムの事です。生成 AI の活用例を理解したところで、Google が提供する生成 AI モデル を確認しましょう。Gemini が有名ですが、他にも色々ありますよ。
- Gemini : Google のフラッグシップ モデルであり、汎用的な 基盤モデル として、とても強力な性能を発揮する
- テキスト、画像、音声、動画、といった 異なる種類の情報を同時に理解 し、それらを元に高度な対話や論理的思考を行う「ネイティブ・マルチモーダル」が最大の特徴である
- 複雑な問題解決や、専門的なコード生成、多角的なデータ分析など、さまざまな場面で活躍する
- Gemma : Gemini と同じ技術基盤から作られた、軽量でオープンなモデル
- 開発者や研究者が自身のノート PC やワークステーション上で、比較的容易に実行できるよう設計されている
- オープンソースであるためカスタマイズの自由度が高く、学術研究の基盤として利用するのに向いている
- Imagen : 写実性と表現の忠実性を追求した、高品質な画像生成モデル
- テキストでプロンプトするだけで、現実と見紛うような画像や、アーティスティックなビジュアルを自在に作成できる
- Veo : テキストや画像の指示から、高品質で長時間の動画を生成するモデル
- 単に映像を生成するだけでなく、「スローモーション」「タイムラプス」といった映画的な表現の指示を理解する
- 一貫した世界観やキャラクターを保ったまま、滑らかな動画コンテンツを作成できる
機械学習の基礎
ここまでに生成 AI の基礎を学びました。大量のデータで機械学習したモデルを元に新たなコンテンツを生み出すのが生成 AI ですが、ここでは 機械学習の基礎 にも触れていきます。
あくまで本試験の範囲での解説ですので、もっと詳しいことが知りたい方は Professional Machine Learning Engineer の範囲を学ぶと良いですね。
機械学習とは
機械学習とは、大量のデータから 人間が事前に定義していなかったルールを発見する 仕組みです。迷惑メールを分類する例を前述しましたが、これは大量のメールを学習させることで「迷惑メールの特徴をルール化」し、新たに受信したメールをルールに従って分類しているわけですね。
ラベル付きデータとラベルなしデータ
機械学習に用いるデータには ラベル付きデータとラベルなしデータ があります。ラベル は 答え だと考えてください。
教師あり学習
例えば、ひまわりの画像に「ひまわり」というラベル、チューリップの画像に「チューリップ」というラベルを付けます。ひまわりやチューリップのデータを大量に学習させることで、ひまわりとチューリップの画像を分類できるようになります。これは、教師あり学習 と呼ばれます。
教師なし学習
ラベルの付いていないデータを用いた例として、前述のクラスタリングが挙げられます。例示したものは「与えられた購買データから顧客の特徴を分析し、顧客をグループ分け」といった内容ですが、これは「明確な答え」を添えて機械学習させるものではありません。この例の場合、「答えが分かっていたら苦労しない」ですからね。このような「答えを持っていないデータ」を用いる方法は 教師なし学習 と呼ばれます。
強化学習
ここまでの学習とは異なり、「特定のルールに従った行動を繰り返させて、より良い結果が出るように」する方法を 強化学習 と呼びます。対戦ゲームや自動運転などの AI 開発に用いるものですね。
例えば対戦ゲームの場合、目的はもちろん勝つことです。強化学習の報酬(Reward)をゲームの勝利、罰(Penalty)をゲームの敗北と設定して学習を繰り返させます。AI は「なるべく多くの報酬が得られる」ように学習します。
対戦ゲームの例として囲碁や将棋を思い浮かべると分かりやすいのですが、「次に自分が取れる行動」には制限があります。囲碁や将棋のルールを無視しても、それはゲームとしては敗北と言えますね。
ここまでの内容を理解すると、強化学習は「教師ありや教師なしの学習とは違うアプローチであり、状況判断を繰り返す AI の実現に必要不可欠な技術」だということが理解できるかと思います。
構造化データと非構造化データ
機械学習には何かしらのデータを用いますが、大きくは 構造化データ と 非構造化データ に分かれます。以下のような違いがあります。
- 構造化データ : 行と列で整理され、列ごとの役割が定義されたデータ
- スプレッドシートのような形式である
- CSV ファイルも構造化データの一種である
- 非構造化データ : 形式が定義されていないデータ
- 構造化がされていないものは非構造化データと考えて良い
- 画像、動画、音声などが該当する
- テキスト形式であっても、メールは非構造化データである
機械学習のライフサイクル
機械学習の種類や、それに用いるデータについて学習しました。では、それらを実際にシステム化する際には、どういった考慮が必要でしょうか。機械学習のライフサイクル と題して、データを取り込んだり学習することから始まり、その結果出来上がったモデルをどのように管理・運用していくのかまで解説していきます。
データ準備
収集した直後の加工していないデータ、いわゆる 生データ は、ノイズや欠損が多く、そのままでは使えないことがほとんどです。このフェーズでは、データの品質を高め、モデルが学習しやすい形式に整える「前処理」 をします。具体的には、データのクリーニング、不要な情報の削除、そしてモデルが特徴として認識しやすい形への変換といった工程が含まれます。
機械学習のシステムにおいて最も重要であり、最も大変な工程といわれます。Garbage In, Garbage Out(ゴミからはゴミしか生まれない) という言葉があることからも重要さが感じられますね。
なお、こういった学習に用いるデータにおいて、企業独自のものは ファーストパーティ データ と呼ばれることも覚えておきましょう。
モデルのトレーニング
準備されたクリーンなデータを使い、機械学習アルゴリズムにデータのパターンを学習させる工程が トレーニング です。このプロセスを通じてモデルが作られます。最適な性能を引き出すために、様々なアルゴリズムを試したり、その設定を調整したりします。前述した教師あり学習・教師なし学習・強化学習といった仕組みは本工程に含まれます。
モデルのデプロイ
学習済みのモデルを、実際のアプリケーションで利用できる状態にする工程が デプロイ です。トレーニングしたモデルが以前より良くなっているかは、試してみないと分からないですよね。事前に検証環境などで内部向けにデプロイし、その品質を確かめてから本番環境へデプロイしたりします。
モデルの管理
モデルは「作って終わり」ではありません。時間の経過と共にデータが変化し、モデルの予測精度が低下することがあります。継続的に新しいデータを準備し、そのデータでトレーニングし、それをデプロイするといったライフサイクルを繰り返して品質を維持・向上させます。そのためにはモデルを適切に管理・運用していく必要があります。
Google Cloud の生成 AI に関する取り組み
機械学習の基礎を学んだところで、Google Cloud の生成 AI に関する取り組みを解説していきます。
AI ファースト
Google は 2016 年に AI ファーストを宣言しています。以下のブログにも We will move from mobile first to an AI first world.(私たちはモバイル ファーストから AI ファーストの世界へと移行します。) とありますね。本記事執筆時点で宣言から 10 年目であり、長年に渡って AI の分野で存在感を発揮しているのも、長期的な取り組みの成果によるものでしょう。
ビジネス活用
生成 AI は革新的な仕組みですが、それをビジネスで活用するためには様々な要求をクリアする必要があります。各要素を順に解説していきます。
責任ある AI
AI は様々な成果を生み出してくれますが、その内容に責任が持てなければビジネスでの活用は難しいでしょう。例えば、AI の生み出した成果は公平であり、説明できなければなりません。説明可能な AI とも表現されますが、Google はモデルの透明性を提供しています。
以下の公式サイトにて、責任ある AI への取り組み を公開しています。ぜひ一読しておきましょう。
安全な AI
AI には企業独自のファーストパーティ データを与えることで、そこから生み出される成果の価値が高まります。AI のセキュリティが不十分であれば、与えるデータや成果が漏洩する懸念が生まれるため、安全な AI であることはとても重要です。
Google は セキュア AI フレームワーク を公開しています。安全な AI を実現するためのノウハウが詰まっていますが、本試験の範囲では詳細をすべて把握していなくても大丈夫です。興味のある方は公式サイトを訪れてみてください。
プライベートな AI
生成 AI が登場した当初、「チャットに書いた情報は収集される」ことが話題になったと記憶しています。これは今でも変わっておらず、無償版では収集されることが公式ドキュメントからも読み取れますね。これは有償版に切り替えることで回避可能であり、Gemini の Web 画面の下部に「<組織名> 全メンバー のチャットはモデルの改善には使用されません。」といった表記が出ていることで判別可能だとご存じの方もいるのではないでしょうか。
これは Gemini に限らず、他のエンタープライズ向けのサービスでも同様です。顧客のデータは顧客のものであり、サービスの提供元である Google が許可なく勝手に使うことはありません。
信頼性の高い AI
先進的であっても、そのサービス提供が不安定であれば、ビジネスでの活用は限定的なものとなるでしょう。Google の AI サービスにはサービスレベル契約(以下、SLA)が提示されているものが多く、その 信頼性の高さ を示す根拠と言えますね。
例えば Gemini for Google Cloud であれば、本記事執筆時点で 99.9% 以上の SLA であることが公式ドキュメントに明記されています。
スケーラブルな AI
AI を用いたサービスが大人気となってアクセスが集中し、レスポンスが目に見えて低下してしまうのは避けたいですね。Google の AI サービスは処理能力を柔軟に調整することが可能であり、負荷に応じて自動調整が可能なサービスもあります。ビジネスで活用する場合、こういった スケーラブルな AI であって欲しいですね。
Google の AI エコシステム
Google は、既存の製品やサービスにも生成 AI を統合し、AI エコシステム の構築を進めています。最近では Gmail など Google Workspace 関連サービスにも生成 AI が統合されて、メールの要約や返信案の生成が可能となりました。Google Cloud では、システムを監視する Cloud Monitoring に生成 AI が統合され、自然言語で AI と会話しながらログを解析することができます。
チャット形式で対話しながら生成するだけではなく、ビジネスの様々な場面で生成 AI が活躍してくれるのは、それらのサービスを包括的に提供している Google の強みと言えますね。
Google のオープンなアプローチ
Google は、AI に限らず様々なサービスで オープンな仕組み を取り入れています。例えば、Google が開発した機械学習ライブラリの TensorFlow は、オープンソースとして広く公開されています。そのため、ベンダー ロックインを懸念する企業の戦略とも合致しますね。
非エンジニアの AI 開発
本格的に AI を開発するためには、機械学習のアルゴリズムを深く理解する必要があります。しかし、機械学習の得意なエンジニアが在籍している組織ばかりではありません。そういった組織でも AI を活用できるように、Google は様々なサービスを提供しています。
- 事前トレーニング済みモデル : 自らトレーニングしてモデルを用意するのではなく、事前にトレーニングされたモデルをアプリケーションに組み込む方法
- 例えば「音声から文字を起こす」目的であれば、独自のデータを学習させる必要はなく、文字起こし用にトレーニングされたモデルを利用すればよい
- ノーコード / ローコード ツール : 機械学習の知識が限られていたり、コードを書くエンジニアが在籍していない場合に独自のモデルを開発する方法
- 例えば「自社の生産ラインで製品不良を画像から検知したい」場合、画像データは独自で用意してトレーニングするが、その際にはノーコード / ローコード ツールを用いて省力化したモデル開発に取り組む
Google 生成 AI サービス
いよいよ、具体的な 生成 AI サービス を見ていきましょう。ここまでに少し名前の出ていたサービスもありますが、ここではもう少し深く触れていきます。
Gemini アプリ
Gemini アプリ とは AI アシスタントです。Gemini と聞いて誰もが思い浮かべるサービスそのものではないでしょうか。チャットのような対話形式で様々なコンテンツを生成することができます。
Gem
Gemini アプリの便利な機能として Gem があります。生成 AI の活用に慣れてくると「この場面では必ずこのプロンプトを与えたい」と思う事があります。例えば本記事においても「一般的な企業の技術ブログとして、不適切な表現が無いかチェックして」と生成 AI にレビューしてもらいますが、これは技術ブログを書くたびに必ず与えたいプロンプトです。そういった場面で活躍するのが Gem なので、是非とも有効活用しましょう。
なんなら、試験対策とは関係なく皆さんに使っていただきたい機能ですね。
NotebookLM
Gemini は便利ですが、慣れてくると「都度テキストで情報を与えるのが面倒だ」と思うこともあります。そこで、情報が含まれたドキュメントを与えることで、それに基づいた分析や対話が可能となる NotebookLM が役に立ちます。
「xx というシステムの開発で使ったドキュメントから、yy という不具合が含まれる可能性のあるソフトウェアを探してください」といった使い方ができて便利ですね。
Google Agentspace
Gemini や NotebookLM は便利ですが、使いこなしてくると「自組織の情報はあらかじめ把握しておいてほしい」と思うことがあります。そういった要望に応えるのが Google Agentspace です。組織内に散在する多様なデータを理解し、タスクを実行するカスタム AI エージェントを提供するためのプラットフォームを構築することができます。
NotebookLM のように事前にドキュメントを提示せずとも、「xx という企業に提案した yy システムの概要を教えて」みたいな事が可能になるので、とても便利ですね。
Gemini for Google Workspace
前述したように、Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなどの Google Workspace アプリに AI を統合したサービス です。メールの下書き作成、会議内容の要約、データ整理などを支援し、日々の業務を効率化します。
メールの返信って、個別に考えているようで「自分の中でのテンプレートが半分を占めている」と思いませんか。私は「案外そうだな」って最近思っています。これは生成 AI に任せることができる業務かもしれませんね。
Vertex AI Studio
Google Cloud が提供する、機械学習モデルの構築、デプロイ、管理を統合的に行うためのプラットフォームが Vertex AI Studio です。ここまでに紹介したサービスとは異なり、開発者やデータ サイエンティストといったプロフェッショナル向けのサービスと言えますね。
AutoML
非エンジニアの AI 開発として前述したノーコード / ローコード ツールが AutoML です。Vertex AIは、プロフェッショナルが使うカスタム トレーニング機能から、専門知識がなくともモデル開発が可能なこの AutoML までを内包した、統合的なプラットフォームです。
Google AI Studio
Google AI Studio は、開発者が Gemini などの生成モデルを迅速にプロトタイプ化し、実験するためのウェブベースのインターフェースを提供します。本番環境向けにVertex AI Studio を用いた堅牢な開発環境へ移行する前に、モデルの機能を理解するのに役立ちます。
生成 AI モデルの出力改善
生成 AI に慣れてくると、「もっと良い結果を出力したい」と思うようになります。少なくとも、私はそう思うようになりました。ここでは、生成 AI をうまく扱う為の知識を学びましょう。
基盤モデルの限界
Gemini などの基盤モデルは汎用的に作られているため、それに伴う限界があります。極端に言えば、私の好きな酒のつまみは知らないはずです。具体的な用語と共に解説していきます。
データ依存症
AI の出力する内容は、与えたデータに依存します。 「ゴミからはゴミしか生まれない」と前述しましたが、同じ話ですね。データの準備が最も大事とも記載しましたが、できるだけ高品質なデータを与えることは常に意識しましょう。
私の好きなおつまみの情報を与えると、前述の限界は突破できますね。
知識のカットオフ
知識のカットオフ とは、モデルがトレーニング データの終了後に発生したイベントに関する情報を欠いている状態を指します。機械学習のライフサイクルで解説したように、継続的にデータを準備してモデルをトレーニングし、その結果をデプロイして品質を保ちましょう。
私の好きなおつまみは年を経るごとに変化しているので、カットオフされないように継続的に教えていくことにします。今のブームはイカの一夜干しですね。
バイアス
バイアス とは、モデルがトレーニング データに含まれる歪んだ視点や不公平な表現を反映することを指します。公平性が保たれたデータを準備してトレーニングするようにしましょう。
私は基本的に海産物のおつまみが好きですが、ビールには鶏の揚げ物だと思っているので、バイアスがかからないようによろしくお願いします。
エッジケース
エッジケース とは、モデルが適切に処理できない可能性のある、稀な、あるいは通常とは異なる入力やシナリオのことです。生成 AI は大量のデータからパターンを学習して新たなデータを出力しますが、そのデータにはほとんど含まれない稀な状況や、論理の穴には弱い特徴があります。
責任ある AI でも解説したように「生成 AI の生み出した成果は公平であり、説明できなければならない」ので、エッジケースから無責任な結果が出力されないよう、安全性や信頼性の観点からもテストを重ねましょう。
「朝一の飲酒に最適なおつまみは何ですか」と聞かれても、朝一で飲酒することは一般的ではないですし、そもそも私は朝一から飲酒したことがないので、これはエッジケースかもしれません。
ハルシネーション
生成 AI と言えば ハルシネーション です。個人的な感想ですが、言い切ります。生成 AI が「もっともらしい根拠と共に出力するが、事実とは異なるもの」を示します。「生成 AI に嘘をつかれた」と個人的には表現しています。
Gemini でも画面下部に表示されているのですが、「Gemini は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください。」という前提のもとに取り扱うのが生成 AI です。
「朝一の飲酒に最適なおつまみは納豆です」と言われても、「嘘だ!それは朝一のご飯に最適なおかずだ!」と言い返すようにします。
基盤モデルの限界に対処する
ここまでの解説で私のおつまみに詳しくなった皆さんは、その知識を持って 基盤モデルの限界に対処 したくなるでしょう。その手法を解説していきます。
グラウンディング
グラウンディング とは、生成 AI に信頼できる情報源を与えることで回答の正確性を高めることを指します。グラウンディングの手法として、社内ドキュメントのようなデータソースを与え、その情報を元に出力させる手法は 検索拡張生成(RAG) と呼ばれます。
前述した NotebookLM でグラウンディングを手軽に体験することができるので、是非とも試してみてください。
プロンプト エンジニアリング
プロンプト エンジニアリング とは、生成 AI の出力を導くための効果的なプロンプトを作成することを指します。指示を明確にしたり、例を示したり、役割を与えたりするようなテクニックがあります。
ファイン チューニング
ファイン チューニング とは、既存の基盤モデルに、特定のデータセットなどを追加で学習させ、モデル自体を調整する手法を指します。生成 AI の応答スタイルを特定の口調にしたり、専門用語への理解を深めたりするなど、生成 AI の振る舞いを特定の用途に合わせてカスタマイズすることができます。
ヒューマン・イン・ザ・ループ
ヒューマン・イン・ザ・ループ とは、AI と人間の知能を統合したワークフローを構築する手法です。金銭を取り扱う業務など、特に正確性が必要で結果の説明が必要なシステムに用いられます。AI が出力した結果を人間がチェックし、問題なければワークフローを進めるような仕組みですね。
温度
生成 AI における 温度 とは、出力される結果のランダム性を調整するための設定値です。この数値を 0 に近づけると事実に基づくようになり、1 に近づけるとランダムで創造的になります。例えば法的な文章であれば温度を下げたほうが事実に基づく結果が出力されやすく、小説のアイデア出しような独創的な目的であれば温度を上げたほうが多くのアイデアが得られるでしょう。
これまでには Professional レベルの認定試験を解説する記事を多く書いてきましたが、改めて Leader レベル(入門レベル)の資格を執筆してみると、明確に受験対象者の違いを感じました。これからの生成 AI 時代を生きていくには、非エンジニアの方々も知っておくべき知識だと定義されているのも納得の内容ですね。カタカナ用語が多く日本人には覚えづらいという側面もありますが、今後も発展が続く技術のため、多くの方が学ぶ助けとなれば幸いです。
クラウドエース株式会社 Google Cloud 認定トレーナーの廣瀬 隆博がお届けしました。また次の記事でお会いしましょう。
Views: 0