
東京株 一時2800円超の値上がり
Source link
Views: 0

「大人になんてなりたくない」は本日4月9日にリリースされたアルバムのタイトル曲。映像ではedhiii boiが3月に東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)で行った自身最大規模のワンマンにて、この曲が1曲目に披露された様子を観ることができる。
またセルフフォトブランド・Photomaticではedhiii boiとのコラボレーションが4月20日まで展開されている。期間中、「大人になんてなりたくない」のデザインとリンクしたフレーム全8種が選択可能。渋谷道玄坂店は店舗がedhiii boi仕様になっている。
edhiii boiは5月から6月にかけて東名阪ツアー「edhiii boi 1st TOUR “大人になんてなりたくない”」を行う。チケットぴあでは先行抽選予約を4月10日から18日まで受け付ける。
2025年5月31日(土)大阪府 BananaHall
2025年6月1日(日)愛知県 ell.FITS ALL
2025年6月7日(土)東京都 Spotify O-EAST
この記事の画像・動画(全5件)
Views: 0
AIチャットボット・Claudeを開発するAnthropicが2025年4月8日に、大学生がAIをどのように利用しているかについてまとめたレポートを公開しました。
New Anthropic research: How university students use Claude.
We ran a privacy-preserving analysis of a million education-related conversations with Claude to produce our first Education Report. pic.twitter.com/apwAqH1ol3
— Anthropic (@AnthropicAI) April 8, 2025
Anthropic Education Report: How University Students Use Claude \ Anthropic
https://www.anthropic.com/news/anthropic-education-report-how-university-students-use-claude
今回のレポートの作成にはユーザーのプライバシーを保護しながらClaudeとの会話を自動分析できるツール「Clio」が用いられました。AnthropicはClioを利用して、大学のメールアドレスに紐付けられたClaude.aiのアカウントによる匿名化された会話100万件を調査。これらの会話を学生と学術の関連性でフィルタリングした結果、57万4740件の会話が抽出されました。Anthropicはこれらの会話をグループ化した上で分析を行っています。
分析の結果、57万4740件の会話のうち、39.3%の会話でエッセイの編集や学術資料の要約など、分野を超えた教育コンテンツの作成および改善が行われていることが判明しました。また、AIと協力してコーディングタスクのエラーのデバッグおよび修正、プログラミングアルゴリズムやデータ構造の実装、数学の問題に利用された会話が33.5%、データの分析と視覚化に使われたのは11.0%、研究デザインとツール開発のサポートが6.5%、技術図の作成が3.2%、コンテンツの翻訳および校正が2.4%でした。
以下は「コンピューターサイエンス」「自然科学および数学」「ビジネス」「社会科学および歴史学」の分野でClaudeに最も頻繁に寄せられるリクエストを抽出したもの。「C++のプログラムを作成、デバッグして」「統計問題を解決、説明して」「会計の概念や問題についてサポートして」「国際関係についての学術的文章の作成をサポートして」といったリクエストが多く寄せられています。
続いて、AnthropicはClaudeがどの学術分野で最も頻繁に使用されるかについて調査を行いました。その結果、Claudeを最も頻繁に使用するのは「コンピューターサイエンス」の分野で、すべての会話のうちコンピューターサイエンス分野のリクエストが占める割合は38.6%に達することが明らかになりました。Anthropicは、アメリカ国内でClaudeを使用する全大学生のうち、コンピューターサイエンス分野の学生はわずか5.4%だったことから、「コンピューターサイエンス分野の学生の数と比較すると、この結果は不釣り合い」と述べています。
対照的に、全大学生のうちビジネス関連の教育を受ける学生は18.6%を占めるにもかかわらず、ビジネス関連の教育に関するClaudeでの会話は、わずか8.9%でした。こうした結果から、Anthropicは「ビジネスや健康、人文科学を学ぶ学生によるClaudeの学術ワークフローへの統合があまり進んでいない一方、コンピューターサイエンスを学ぶ学生はClaudeを早い段階から採用している可能性があります。これは、コンピューターサイエンス分野の学生間でClaudeの認知度が高いことや、コンピューターサイエンス分野の学生が行うタスクに対するAIシステムの習熟度の高さが要因であると考えられます」と説明しました。
以下はClaudeに寄せられた質問の学術分野とその割合(オレンジ)と、アメリカの大学に通う学生の専攻分野の割合(青)を示したグラフです。コンピューターサイエンスを専攻する学生の割合に対し、同分野での質問が非常に多いことが確認できます。
さらに、Anthropicは学生がAIとどのように対話するかを分析し、4つの異なる対話パターンを特定しました。Anthropicによると、学生のリクエストは「問題や課題をできる限り早く解決しようとする『直接型』」「目標達成に向けてモデルとの対話を積極的に試みる『協調型』」「質問に対する解決策や説明を求める『問題解決型』」「プレゼンテーションやエッセイなどの長い出力を作成しようとする『出力作成型』」の4つの組み合わせで成り立っているとのこと。
また、AIとどのような関わり方をしているのかをAnthropicは分野別に分析しています。その結果、自然科学および数学分野では「段階的な計算で特定の確率の問題を解く」「課題や試験の問題を段階的に解く」など、「問題解決型」のリクエストが多く寄せられました。また、コンピューターサイエンスやエンジニアリングなどの分野では「協調型」のリクエストが多く、人文科学やビジネス、健康分野では「直接型」「協調型」が均等に分かれていました。以下のグラフは分野ごとのリクエストを分類したもので、左から「直接型」「出力作成型」「協調型」「問題解決型」となっています。
Anthropicは今回の分析について「Claudeの使用が教育における全体的なAIの使用と比較してどの程度異なるかは不明です」「私たちは、大学のメールアドレスに紐付けられたアカウントの会話を分析しました。そのため、学生と見なされたアカウントが実際にはスタッフや教員のものである可能性があるほか、大学以外のメールアドレスに紐付けられたアカウントでも教育分野の会話が行われている可能性もあります」「プライバシーへの配慮から、直近18日間の会話のみを分析しました。そのため、年間を通じて分析すると、結果が異なる可能性もあります」といった課題を示しています。
この記事のタイトルとURLをコピーする
・関連記事
チャットAIの用途の調査結果をClaudeの開発企業が公開、コンピューターや教育関連に使う人が増加中 – GIGAZINE
「みんなのAIの使い方トップ10」がClaudeの分析ツール「Clio」で判明、日本人のAI使用法は「アニメとマンガ」制作 – GIGAZINE
Anthropicが大学向けAIチャットボット「Claude for Education」を発表 – GIGAZINE
AIの頭の中ではどのように情報が処理されて意思決定が行われるのかをAnthropicが解説 – GIGAZINE
ChatGPTなど数々の高性能AIを生み出した仕組み「Attention」についての丁寧な解説ムービーが公開される – GIGAZINE
Views: 0

可能な限り生産的な日々を送るために、どのようにプランニングするかを考えるのは大変です。
そこで、RPM(ラピッド・プランニング・メソッド)を取り入れるのがおすすめです。
RPMは、日々のプランニング・プロセスを合理化し、アクション・ステップに早く取りかかることで、全体的な生産性を高めるのに役立ちます。
また、RPMはかなりわかりやすく、簡単に取り入れられるので、継続できる可能性が高くなります。
このテクニックは、有名なモチベーショナル・スピーカー、トニー・ロビンズのプログラム「Time of Your Life」の中で概説されています。ロビンズの評判は少し安っぽいかもしれませんが、RPMにはその実力があります。
RPMはRapid Planning Methodの頭文字をとっただけでなく、結果志向かつ目的志向で、大規模な行動計画を特徴としており、あなたの1日がどうあるべきかのガイドになるのです。
このテクニックは、毎朝、あるいは毎週、一貫して、自分に3つの質問をすることからはじめます。
これらの問いに対する答えをノートなどに書き出してもいいですし、ただ心に留めておいてもOKです。
いずれにせよ、これらは、効率的で最終目標の達成につながる行動へとあなたを駆り立てるためのものです。
なお、最良の結果を得るには、答えを手帳に書き留めることをおすすめします。そうすれば、指針となる原則を常に目にする場所に貼り付けることができるでしょう。
生産性を高める方法は世の中にたくさんありますが、RPMの利点は、あらゆるメソッドと簡単に組み合わせることができること。
たとえば、全体的な行動計画の一部として、1-3-5のToDoリストを実行することができます。RPMの特徴は、目標や願望を常に前面に出し、それを中心にして努力し、行動を整理することです。
その中心的な計画を心に留めておくだけで、時間を浪費するような熟考をすることなく、重要でないことを除外し、優先したいことに注力できます。
SMART目標を使うのと同じように、RPMを使うことで、日々の仕事に目的意識や使命感を持たせることができ、集中して仕事に取り組むことができるでしょう。
──2024年8月7日の記事を再編集のうえ、再掲しています。
Source: Tony Robbins
Views: 0
ぶらり川越 GAME DIGGは、ゲームクリエイター、ファン、
そして街を訪れる全ての人々が交わる、日本の埼玉県、川越市で開催されるオープンタウン型のゲームイベントです。
Burari Kawagoe Game Diggは、日本の季節県カワゴー市で開催されるオープンタウンスタイルのゲームイベントで、ゲームクリエイター、ファン、そして街へのすべての訪問者が集まります。
会場はコエトコ(旧栄養食配給所)と、りそなコエドテラス。
どちらも100年以上の歴史を持つ文化財建築でインディーゲームを展示予定です。
会場はコエトコとレゾナコエドテラスです。どちらも100年以上の歴史を持つ歴史的な文化遺産の建物であり、インディーゲームは両方の場所で展示されます。
フォーミュラHP
http://formula.com/hp https://burarikagoegamedigg.jp
Source link
Views: 0
長い時間がかかったことで、今週はitch.io-favoriteの完全なリリースをマークします Dicey Dungeons。インディースーパースターのテリーカバナ(およびチーム)は、パズルとアクションから、最もアクセスしやすいルートの1つであるものを私のお気に入りで複雑な2つのジャンルの2つのログリケとデッキビルダーに作り上げました。
Dicey Dungeonsについて何か知っているなら、おそらくそれがサイコロによって完全に支配されているゲームであることを知っているでしょう。がらくたのようではありません。さまざまな標準的なファンタジーの役割において、プレイヤーが探求し、戦い、最終的には、危険と可愛らしさのサイコロをテーマにしたゲームショー全体を克服し、最終的に克服し、最終的に克服します。それは本当に魅力的なデザインであり、サイコロのランダムな性質を受け入れ、そのイライラする側面のいくつかを滑らかにします。
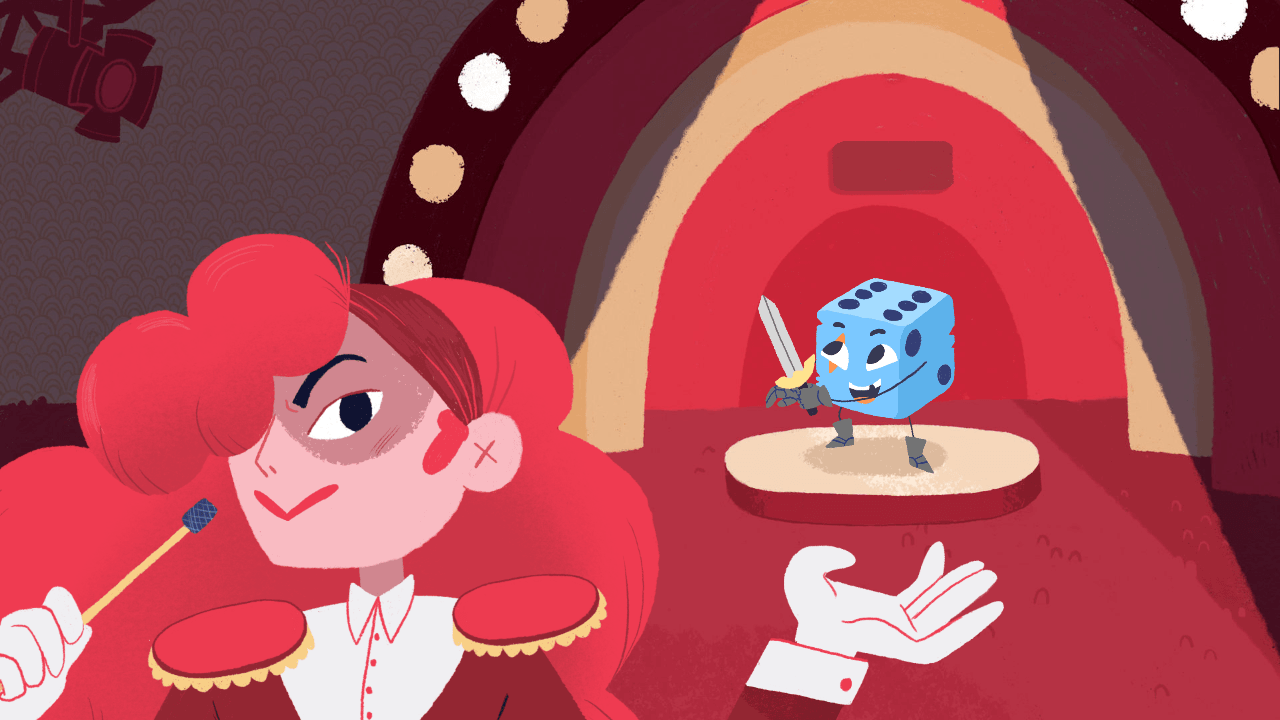
初心者にとっては、roguelikesは威圧的な悪夢になる可能性があります。従来のroguelikesは、複雑なインターフェイス、コンテキストがほとんどないオプションのビュッフェ、および潜在的に最も見当識障害のあるランダム化コンテンツで知られています。これの多くは、他のより近代的な融合にまで及び、個々のレベルデザインではなく、システムに進行を学習と理解しているジャンルを引き受けます。 Dicey Dungeonsについて私が気に入っていることの一部は、これらすべてのシステムを削減したことから、ゲームを面白くするものになります。大きなオープンマップの代わりに、ゲームのピーナッツバターとチョコレートのジャンルフュージョンの後半の間の機械的相互作用の間の大きなオプションのパレットを減らす小さな生成ダンジョンを取得します。デッキビルディング。

わかりました、私はDicey DungeonsがDeckBuildingを紹介する他のジャンルを呼んでいますが、それはそれを賢くラウンドアバウトの方法でそれに取り組んでいます。統計やユニークなアイテムを備えたRoguelikeでは、相乗効果の概念は、パワーアップの最も重要な要素の1つになります。 Roguelikesでの私の成功のほとんどは、私のキャラクターが「何をするか」を理解し、このコア相互作用が何であれ使用するために私のすべての選択をすることから来ています。 Dicey Dungeonsには、スキルのピックに似たシステムがありますが、デッキビルディングを教えているのは、ゲームの中核のサイコロにあります。戦闘中の各ターンは、サイコロを「描画」してから、さまざまな攻撃やブーストに費やすことができます。これは、サイコロに数字がない状況を構築しようとしていることを意味します。デッキビルディングゲームをプレイするように人々に教えることで、これは私がコミュニケーションをとるのに最も苦労しているという概念であり、どうにかしてダンジョンがこのコアアイデアの最もシンプルでアクセスしやすいバージョンを絶対に釘付けにするという概念です。
私は以前に早期アクセスしていたときに、このブログでDicey Dungeonsについて書いたので、私はこれで自分自身を繰り返しているかもしれませんが、Dicey Dungeonsは微妙に素晴らしいゲームであり、その知性を言葉にするのは難しいと思います。ゲームを見ると、そのかわいいアートスタイルが表示されるかもしれませんし、Lets Videoで戦闘の要点を得るかもしれませんが、それを再生して、それがどのように機能するかを学ぶのに時間を費やして、新しいスキルセットで反対側を吐き出します。 Dicey Dungeonsには、怠zyな講義やイライラするテストに陥ることのない教育があります。それは、邪魔にならないようにして、反射だけで自分自身を明らかにするため、とても良いデザインです。
Views: 0

エージェントへの期待が高まる一方、スキル人材/ガバナンス/LLMメスなど課題は山積
2025年04月10日 09時00分更新
ユニバーサルAIプラットフォームベンダーのDataiku(データイク)が、2025年2月に発表した企業調査レポート「2025年の生成AIトレンド TOP5」。このレポートでは、生成AI活用によるビジネス変革を目指して多くの企業が投資を加速させる一方で、これからの“AIエージェント時代”に進むためには、さまざまな課題が山積していることも指摘されている。
同レポートが「やがては“AIエージェントの無秩序状態”が来る」とも予言する中で、どのように状況を整理し、備えればよいのか。Dataiku Japanの佐藤豊氏に、Dataikuとしての見解や同社ソリューションでの対応を聞いた。
佐藤氏は、2022年末から2023年の華々しい登場と期待の高まりを経て、2024年は「生成AIのカオス(混沌)」があらわになった年だったと振り返る。
具体的に言えば、AIのビジネス活用に対する期待が高まる一方で、いざ大規模な活用段階に踏み込もうとすると「AIスキル人材の不足」が実現をはばむ。AIベンダーからは矢継ぎ早に新しいモデル(LLM)が登場し、わずか数カ月のうちに「技術の陳腐化」が進む。経営層からはAI導入に対する定量的なROI(投資対効果)が求められるが、それを明確に出せる「AI導入のフレームワーク」が確立されていない。――AI活用の取り組みを積極的に進める企業ほど、そうした課題に直面して「カオス」に飲み込まれることになった。
企業がこのカオスから脱却するためには、企業自身がしっかりと「コントロール」できる環境を持つことが大切だと、佐藤氏は強調する。これが、Dataikuが現在考えるソリューションの方向性だという。
「Dataikuでは、企業におけるAIの価値創出にとってまず重要なのは『コントロール』だと考えている。具体的には、AIの導入規模をスケール(拡大)できるよう組織をコントロールする、AIのベンダーロックインを防ぎ自由度を確保できるようコントロールする、生成AIやAIエージェントのリスクをプラットフォーム側でコントロールする、そういったことだ」
佐藤氏は、現状で直面しているいくつかの課題を取り上げながら、Dataikuが考える解決策と製品/ソリューションを紹介した。
たとえば、冒頭で触れたDataikuの調査レポートでは、現在のトレンドのひとつとして「LLMメス」が挙げられている。「メス(mess)」は「乱雑に散らかった状態」を表す言葉だ。
エンタープライズ(年商10億ドル以上)を対象とした同調査によると、すでに73%の企業が、2つ以上のLLMを活用する「ハイブリッドLLM」のアプローチをとっているという。それぞれのLLMを適材適所で使いたいという理由だけでなく、新たなモデルやLLMベンダーが次々に登場してくる中で、特定のLLMに依存する(ロックインされる)のは将来的なリスクであるという、戦略的な理由もあるようだ。
この状況が、2025年には「AIエージェントの無秩序状態」へとさらに悪化する――というのがDataikuの見方だ。やがて企業が多数のAIエージェント(アプリケーション)を構築し、それぞれの目的に合ったLLMやバックエンド(ベクターストアなど)との接続、さらにはAIエージェントどうしの接続が必要になってくると、「散らかった」レベルでは済まない「無秩序状態」が生まれかねない。
この状態を整理するために、プラットフォーム型の「LLMメッシュ」を構築すべきだ、というのがDataikuの提案だ。Dataikuでは、生成AIアプリケーション構築のための“生成AIデリバリープラットフォーム”を提供しているが、その中にはLLMメッシュのコンポーネントが含まれる。セルフホスト型も含むあらゆるLLM、ベクターストアとのセキュアな接続を管理する。
佐藤氏は「LLMメッシュだけでなく、LLMのコストや安全性(AIセーフティ)、品質をしっかりコントロールするガードサービスも提供している」と説明した。こうした仕組みを備えることで、全体のガバナンスを効かせながら、AIアプリケーションやエージェントの活発な開発を促す環境が提供できる。
Views: 1
ドキュメントナビゲーションにジャンプします
これがオリジナルのクリップです YouTube グレッグブロックマンはそれを見せてくれます。最終的にGPT-4はHTML出力を生成し、Gregはそれを披露するためにCodepenにコピーしました。
なんて大きなリリースでしょう! ショーン・ワンはノートします:
これがどれほど予想されていたかについての簡単な測定値を使用するために、GPT-4はすでに11番目に投票されたハッカーニュースストーリーです いつも、 開発者のライブストリームは、20時間で150万回の視聴を獲得しました(現在はYouTubeのすべてで5位トレンドビデオ)と発表 ツイート ChatGptの場合は、2022年の最大のストーリーであるChatGptよりも4倍のいいねを得ました。
確かに、このコード・フォー・ミー・アングルは人々とクリックしています!
私はGPT-4に飛び込んで尋ねました:
ボタンをクリックしてランダムなウィキペディアページに移動するHTMLページを作成します

これは実際にかなりうまく機能します:
私はそれについて知りません Arial そこに選択肢がありますが、そうでなければ、よくできました。
私は最初に「絵を描く」ことを試してみたいと思っていましたが、 どうやら、それはまだ私たちにはまったく開かれていません。
ChatGptが優れた作業コードを作成した例をもっと見たい場合は、 ここにコレクションがあります。
Views: 0
世界有数のスマホゲーム大国である日本において,現在最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けする本連載。今週の国内収益ランキング1位は「PokémonTradingCardGamePocket」となった。今回は,昨年10月〜12月の全世界DL数ランキングも紹介しよう。
Source link
Views: 0
CNET Japanは2月26日、年次イベント「CNET Japan Live 2025」をオンラインで開催した。2025年は「イノベーションが導く社会課題解決」をテーマに、ICT、製造、宇宙、AIと多岐に渡る分野で6セッションを展開。各分野における特徴的なイノベーションへの取り組みを披露した。
ここでは、NTTコミュニケーションズ株式会社 プロデュース部門長を務める黒田和宏氏が登壇したセッション「ExTorchが描く共創の未来~社会課題解決の実践事例とその可能性~」の内容をお届けする。スタートアップとの共創で社会課題の解決を目指すオープンイノベーションプログラム「ExTorch(エクストーチ)」の5年間に渡る軌跡とその実績を紹介した。
日本における最も代表的な企業群と言えるNTTグループ。その一員であるNTTドコモグループ傘下で、主に法人向けの事業を展開しているのがNTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)だ。登壇した黒田氏は、R&Dとしての機能をもつ同社イノベーションセンターに所属している。
黒田氏が所属するプロデュース部門は、社会課題の解決に向けたビジネスを作る「社内イノベーションの推進支援」を主なミッションの1つとし、「docomo STARTUP」と「ExTorch」という2つのイノベーションプログラムを実施している。前者のdocomo STARTUPは、社員のアイデア起点のボトムアップ型の新規事業創出プログラムで、後者のExTorchは社外との共創型プログラムとなる。
今回のセッションの主題となったExTorchの目的は、NTT Com自身やNTTグループがもつアセットなどを、スタートアップをはじめとするパートナー企業のユニークなアイデアや技術と掛け合わせることで、顧客の課題や社会課題の解決につながるソリューションを社会実装していく、というもの。
それにあたりExTorchの運営事務局では、NTTグループ内のベンチャーキャピタルなどとも連携して日常的に世界中のスタートアップの情報を収集するとともに、年1回のピッチ・マッチングイベントを開催。勉強会や情報共有といった社内向けの活動も行っている。
一方で、社外のパートナー企業にとってExTorchの最も特徴的なポイントといえるのが、膨大なアセットや手厚い支援が受けられることだ。法人事業に強みをもつNTT Comならではの販売網から、NTTグループのクラウド、ネットワーク、セキュリティ、IoT、AIなどのICTサービス、データセンターや通信局舎のような設備まで、多様かつ大規模なアセットの利用機会が得られる。
また、実際に共創を進めていくところでは、企画立案段階での壁打ちや伴走、調査レポートの提供をExTorch事務局が行う。業界動向調査、ビジネスモデルなど事業戦略の検討、事業立ち上げに向けたPoCの支援、外部メンターの起用といった、共創の成功率を高める充実したサポートも受けられる。事業化を果たした後も、ビジネス拡大に向けた営業・マーケティング活動の最適化などの面で協力が得られるとする。
スタートした2019年から2年間の第1期では6つのプロジェクトを、2021年から2年間の第2期では5つのプロジェクトを、それぞれ採択するなど順調な滑り出しを見せたExTorch。しかし黒田氏は、イベント形式で実施してきたことで、課題が見えてきたと話す。
NTT Comの提示するテーマに対してスタートアップが応募する公募制で、「応募いただいた以外のスタートアップとマッチングできない」ことが1つ。共創開始からゴールまで2年はかかり、イベント型では「公募期間以外で他のスタートアップが参加できない」のもネックだった。また、反対にNTT Comとしてもスタートアップを探す活動がしにくく、「社内から新しいアイデアが生まれてもそれをマッチングさせることが難しい」悩みもあった。
そうした課題を解決するべく、2022年の中途からは期間を区切らず、通年の共創マッチングプログラムにリニューアル。公募ではなく、社内やグループからのニーズに応じてスタートアップとのマッチングを行う現在のスタイルに移行したという。
それによって「社内やグループの事業部に寄り添って伴走できるようになった」と黒田氏。「事業部が目指している方向性や課題について、スタートアップとうまくマッチングさせることで新しいビジネスにつなげるという、本来の活動ができている」とも話し、手応えを感じている。
そのように大きく方針転換したExTorchにおいて、事業化を果たしたプロジェクトも生まれてきている。1つは、グループ会社であるエヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社にて提供中の 「Beamo(ビーモ) 」 。市販の360度カメラとスマートフォンを使って商業施設や生産施設などを撮影し、そのデータを一元管理できるようにするサービスである。組織内で建物や空間に関するビジュアル情報を共有する際、従来は作業工程が多くデータ管理も煩雑だったが、これにより大幅に省力化できるという。
2つ目はプライバシーに配慮しながら人流解析できる「butlr(バトラー)」。温度を検知するサーモセンサーによって人の位置を把握する仕組みで、監視カメラを不要としているのが特徴だ。電池で動作するため天井に設置するだけで使い始めることができ、AIによって人とそれ以外を高精度に判別する。
すでにNTT Com社内でも導入しており、「オフィススペースの利用状況を継続的に把握することで、どのように什器を配置すればより効果的な施設利用につながるのかなど、検討していきたい」と話す。
3つ目は、マリス creative design 社が開発した歩行アシスタントAIカメラ「seeker」のプロジェクト。seekerは頭部に装着したカメラとセンサーからの情報をエッジAIで処理して周囲の状況を検知し、振動で歩行者に危険を知らせる仕組みで、視覚障がい者や高齢者の外出をサポートする。
このプロジェクトでは、そこにNTT Comのアセットである「Smart Data Platform」を組み合わせている。カメラとセンサーから得られたデータをセキュアなネットワークを通じてクラウドに蓄積することで、外部からの見守りなどを想定した機能提供を行っているという。
実績を積み重ねつつあるExTorchだが、目下の課題は認知度を上げることだ。NTT Comによるオープンイノベーションプログラムの存在はいまだ広く知られているとは言えず、2024年度は国内外のスタートアップを招待するマッチングイベントを開催したり、オウンドメディアを通じて発信したりなどプロモーションにも力を入れてきた。特に社内に対しては「泥臭く社内を回って、どんなニーズがあるか話を聞かせてもらいながらExTorchの認知拡大に努めている」ところ。
こうしたオープンイノベーションで新規事業創出を目指していくうえで、黒田氏は「熱意が一番大事」と話す。「事業を作っていくのは一見華やかに見えて、泥臭いことも多く、大変なことも多い。そういった中でもくじけず粘り強くやっていくためには、これを実現したいんだという熱い思い、熱いビジョンみたいなものが大事だと思う」と続ける。
それと同時に、ビジネスとして「お互いに利益がある状況を作り出していくこと」も重要であると付け加える。「われわれの共創はスタートアップと社内組織をマッチングし、その上でお客様にソリューションを提供するもの。三方良しのWin-Win-Winの形を作らなければいけないし、結果的にわれわれもWinになる『四方良し』を狙わなければいけない」と決意を新たにしていた。

2005年、NTTコミュニケーションズ入社。OCNサービスの企画・運営、人事部での若手育成策定を経て、2016年よりNTTコム オンラインへ出向。「空電プッシュ」事業責任者として売上を約10倍に成長させ、認知拡大にも貢献。2024年よりイノベーションセンターにて新規事業創出およびオープンイノベーションプログラム「ExTorch」の責任者を務める。
Views: 0