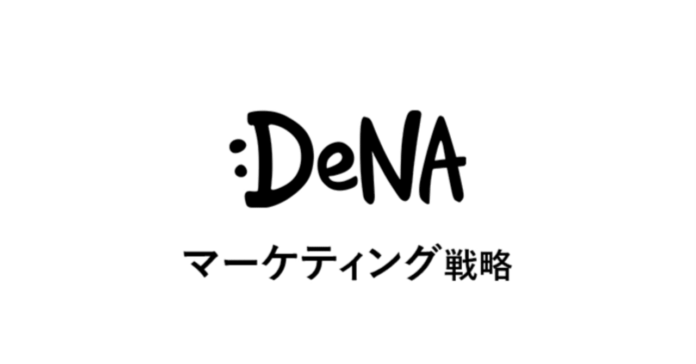🧠 概要:
概要
DeNA(ディー・エヌ・エー)は、元々モバイルゲームプラットフォームの運営を通じて成功を収めましたが、ゲーム市場の競争激化を受けて、“生活インフラ型ブランド”への進化を目指しました。これにより、ヘルスケアやスポーツ、交通などの事業へ多角化し、人々の生活をより良くすることをビジョンに据えたマーケティング戦略を展開しています。この戦略の核心には、事業の多様化とブランドの一貫性の確保があります。
要約(箇条書き)
- DeNAは、もともとモバイルゲーム「Mobage」で成功した企業である。
- ゲーム市場の成熟化と競争激化で、単なるゲーム会社からの脱却を図る。
- 目指す方向性は「生活者の暮らしに密着するインフラ的ブランド」への進化。
- マーケティングの核は“事業の多角化”と“ブランドの一貫性”。
- 主要な事業分野はヘルスケア、スポーツ、交通、エンタメなど。
- 統一されたビジョンは「人の生活を前向きにするテクノロジー活用」。
- 新たに「日常に役立つ信頼性の高い企業」としてのイメージを構築。
- コーポレートミッションは「Delight and Impact the World(世界に喜びと驚きを)」。
- 主要課題には、収益構造の偏り、ブランド固定化、信頼性欠如、メッセージの混乱がある。
- DeNAは、これらの課題を乗り越えるために、生活者との関係性を見直すマーケティング戦略を採用している。
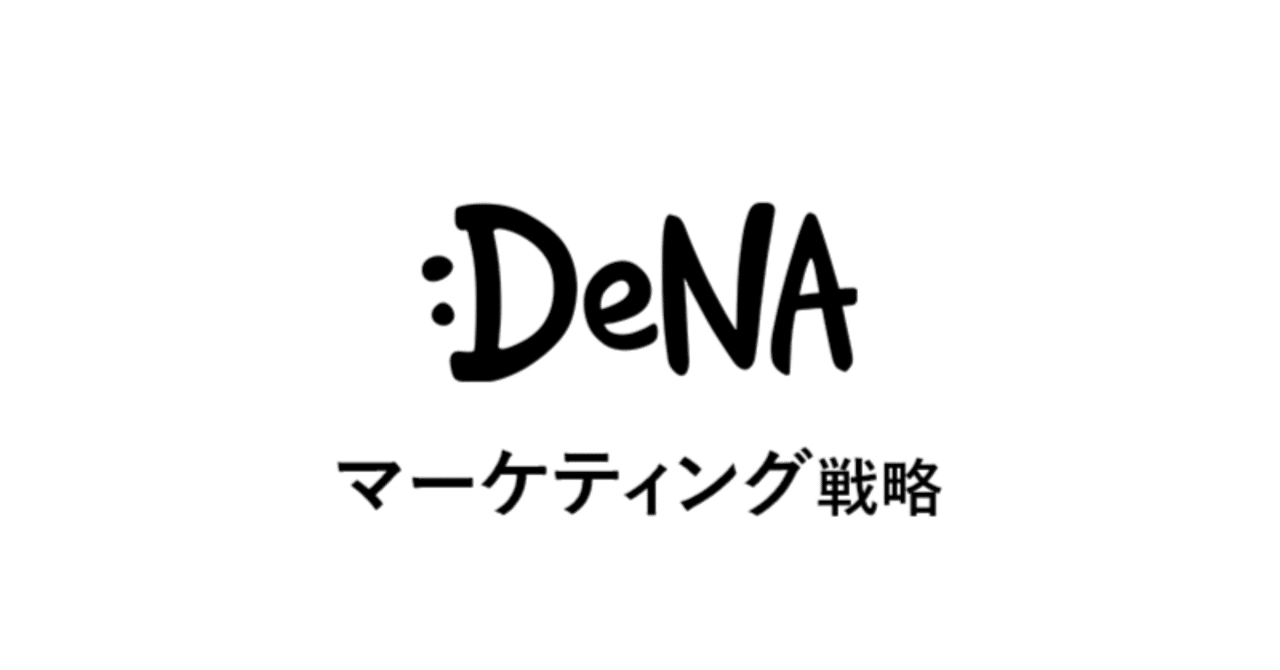
DeNA(ディー・エヌ・エー)は、もともとモバイルゲームプラットフォーム「Mobage(モバゲー)」で一世を風靡したインターネット企業でした。しかし、ゲーム市場の成熟化と競争激化を背景に、同社は単なる“ゲーム会社”からの脱却を図ります。その過程で選んだ道が、「生活者の暮らしに密着するインフラ的ブランドへの進化」でした。
このマーケティング戦略の核となるのが、“事業の多角化”と“ブランドの一貫性”を両立させる設計です。具体的には、ヘルスケア(MYCODE、ヘルスケア事業)・スポーツ(横浜DeNAベイスターズ)・交通(タクシーアプリ「MOV」※現在は他社と統合)・エンタメ(マンガボックスなど)など、多岐にわたる分野でサービスを展開しています。
これらの分野は一見バラバラに見えますが、DeNAは一貫して「人の生活を前向きにするテクノロジー活用」というビジョンを軸に、ブランド全体を統合。その結果、ユーザーから見たDeNAは「ただのゲーム企業」ではなく、「日常に役立つ複数のサービスを持つ、信頼性の高い企業」という新たなイメージを確立しました。
“技術”ではなく“人の生活”を起点にしたブランド再設計――これこそが、DeNAが成功をおさめた現代的マーケティングの本質です。
DeNAとは?
DeNAの事業内容
DeNA(ディー・エヌ・エー)は、インターネットとAIを軸に多角的な事業を展開するテクノロジー企業です。主力のゲーム事業ではスマートフォンゲームの開発・運営を手がけ、「プロ野球スピリッツA」「逆転オセロニア」など人気タイトルを保有しています。
しかし近年では、ヘルスケア(MYCODEや歩数計アプリ「カラダのキモチ」)、交通(タクシー配車アプリ「MOV」※現在はGOへ統合)、エンタメ(マンガボックス)、さらにはプロ野球球団「横浜DeNAベイスターズ」の運営など、“人々の生活の一部”を支える事業へと領域を拡大。
単一事業ではなく、“生活をより豊かにするプラットフォーム群”を提供する総合サービス企業として進化を続けています。
DeNAが掲げるビジョン
DeNAは「Delight and Impact the World(世界に喜びと驚きを)」をコーポレートミッションに掲げています。これは単なる技術提供を超えて、人々の心を動かし、社会を前向きに変えていくことを企業の存在意義とする宣言です。
このビジョンに基づき、DeNAは事業ごとのKPIだけでなく、“人の行動変容を促す”ことを指標としたサービス設計を重視。たとえば、健康系アプリでの歩数改善や球団経営における地域活性など、実生活に根ざしたインパクト創出を重要視しています。
また、AIやデータを活用しながらも「テクノロジー偏重ではなく、“人を中心に据える”姿勢」を貫いており、これは全事業に共通するDeNAブランドの軸となっています。
DeNAの歴史
DeNAは1999年、南場智子氏によって創業され、当初はネットオークションやECサービスを提供していました。2000年代前半にはモバイルインターネットに早期から注目し、フィーチャーフォン向けゲームプラットフォーム「モバゲータウン」(現Mobage)を立ち上げ、ソーシャルゲームブームを牽引する存在へと急成長します。
2011年には横浜ベイスターズ(現・横浜DeNAベイスターズ)を買収し、IT企業によるプロ野球運営という業界の常識を覆しました。
その後はスマホゲームの伸長とともに一時は業績が停滞する局面もありましたが、2010年代後半からはAI・ヘルスケア・交通・スポーツといった領域への本格参入を加速。“ゲームに強い企業”から“暮らしに強い企業”へとブランドイメージの転換を図る戦略が、現在のDeNAの核となっています。
DeNAが直面した課題
DeNAは創業以来、時代の先を行くインターネットサービスを次々と展開し、ソーシャルゲームブームの象徴として躍進してきました。
しかしその成功の裏側では、成長市場への依存やイメージの固定化、競争激化による収益構造の歪みといった、深刻な課題が浮き彫りになっていきました。
以下では、DeNAがブランドと事業の再定義に向けて直面した、4つの重要な課題を取り上げます。
1. ソーシャルゲーム依存による収益構造の偏り
DeNAの飛躍的成長を支えたのは、モバイルゲームプラットフォーム「Mobage」によるソーシャルゲーム市場での成功でした。
しかし2010年代中盤以降、スマートフォン普及によってアプリ市場が急成長すると、App Store/Google Play経由のネイティブアプリが主流に。
これにより、従来のフィーチャーフォン時代のゲームプラットフォームモデルは急速に陳腐化し、DeNAは収益の柱を見失いつつある状態に陥りました。
自社開発・他社パブリッシュ含めたタイトルのヒット数にもムラがあり、特定タイトルに依存した売上構造の不安定さが経営課題として顕在化。特にガチャ依存型の課金モデルは、社会的批判を浴びやすく、長期的ブランド構築とは乖離する側面もありました。
この「短期的な収益」と「中長期的な信頼形成」のバランスは、DeNAにとって大きなマーケティング的ジレンマとなっていきます。
2. ブランドイメージの固定化:ゲーム会社という認識からの脱却
DeNAは創業以来、多様なサービスを展開してきたにもかかわらず、「ゲーム会社」というイメージが強く根付いていました。
その結果、たとえばヘルスケアや交通分野に進出しても、ユーザーやパートナー企業からの認知が追いつかず、“なぜDeNAがこの事業を?”という疑問が常につきまといました。
ブランドとは、“何をしている会社か”ではなく、“何のために存在している会社か”の認識です。DeNAはゲーム市場の先駆者として知られる反面、「社会貢献性のある生活インフラ企業」としての認知は非常に薄かったのです。
このブランドの認知と実態のギャップは、事業多角化を加速する上での大きな障壁となっていました。
3. ヘルスケア・交通領域における“信頼性”の欠如
DeNAが生活密着型サービスに進出する中で直面したのが、高い信頼性と透明性が求められる業界特有のハードルです。たとえば、医療・健康領域では「遺伝子検査サービス(MYCODE)」や「健康管理アプリ」などを展開しましたが、2016年には医療情報サイト「WELQ」の不適切な記事掲載問題が発覚。
これは外部ライターの低品質な記事が事実上の医療情報として公開されていたもので、情報の信頼性を損なったとして大きな社会的批判を浴びました。
また、タクシー配車アプリ「MOV」でも、ライドシェアとの住み分けや地域連携の課題があり、“生活インフラ”を担うには慎重さと地域理解が足りないとの評価を受けたこともあります。
つまり、“IT的な速さ”と“社会的な信頼”の両立が、DeNAの新規領域進出における本質的な課題となっていたのです。
4. 多角化による事業メッセージの分散
DeNAはゲーム・スポーツ・ヘルスケア・交通・エンタメと幅広い事業を展開しているため、“DeNAは何の会社か”というメッセージが一貫しにくい問題も抱えていました。
各サービスごとにブランドが独立して存在するため、全体としてのシナジーや顧客導線が見えづらく、ユーザー体験がサービス単位で断絶してしまう状態が続いていたのです。
また、広報やブランディングも個別最適化されやすく、「点」での発信はできても、「線」や「面」でDeNAらしさを伝える仕組みが不足していました。
これは、企業としての一体感や共通哲学をユーザーに届けるための“ブランドアーキテクチャ設計”が必要不可欠であることを示していました。
DeNAは“多角化の成功モデル”のように語られることもありますが、実際には収益構造の崩壊、ブランド認識との乖離、信頼性の問題、メッセージの分散など、極めて本質的なマーケティング課題を抱えていました。
これらにどう立ち向かい、“生活インフラ型ブランド”として再構築していったのか――次のセクションでは、その戦略的解決策を5つの視点で分析します。
DeNAはどうやって課題を乗り越えた?
多角化とブランドの再構築を同時に行うには、「何をするか」以上に、「何のためにするか」という企業哲学の言語化と共有が不可欠です。
DeNAは、単なる事業の切り替えではなく、“生活者との関係性そのもの”を見直すマーケティング戦略を選びました。以下では、その戦略的アプローチを5つの解決策として解説します。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
Views: 0