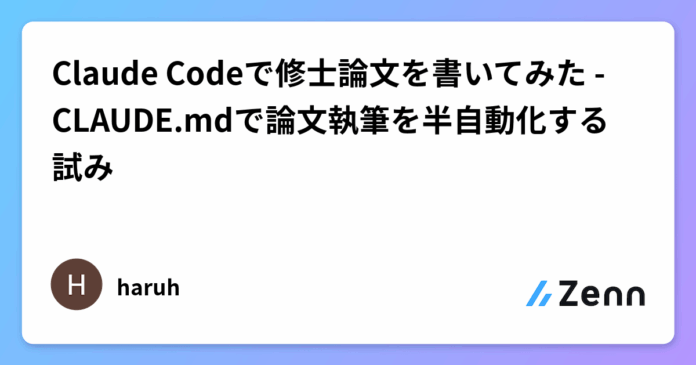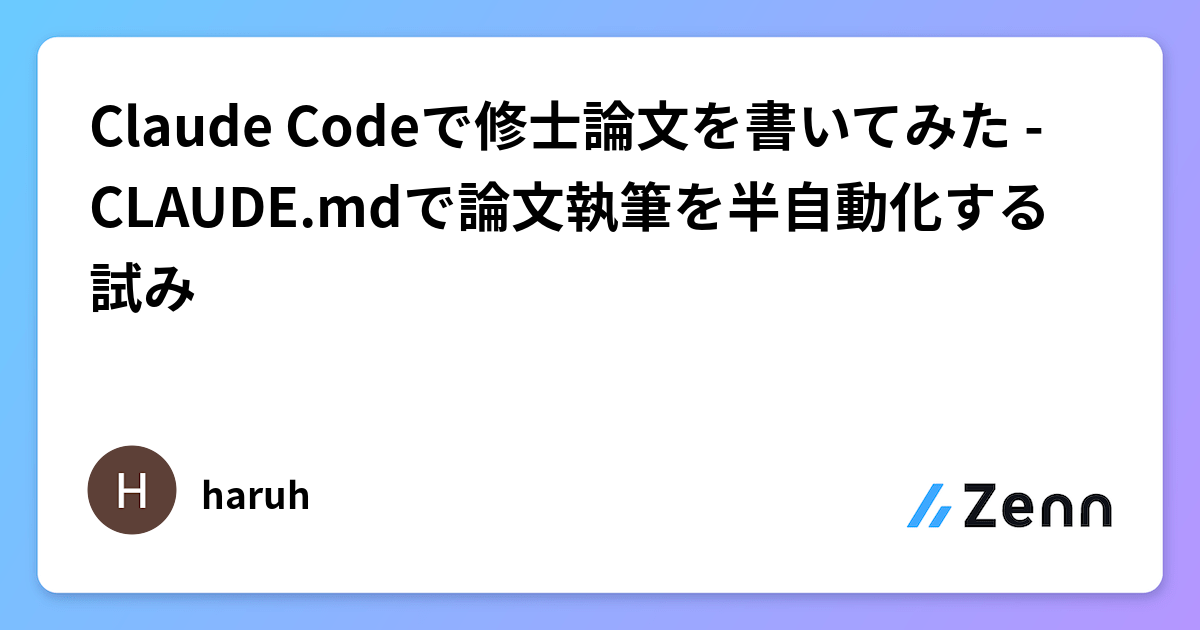
- Claude Codeはプログラミング用だが、CLAUDE.mdを使えば論文執筆にも活用可能
- 学術論文特有の文体ルール(断言的表現回避、受動態使用等)をCLAUDE.mdに記述
- 人間が構成・方向性を決定(3割)、AIが中間品質を担保(7割は最終的に人間が調整)
- 重要:AIは責任を持たないため、最終品質保証は人間が必須
修士論文執筆でClaude Codeを使ってみました。Claude Codeはプログラミング支援ツールですが、CLAUDE.mdという設定ファイルを活用することで論文執筆にも応用できることがわかりました。
ただし最初に注意点を述べておきます。AIは責任を持たないため、最終的な品質保証は人間が行う必要があります。AIである程度の品質まで持っていくことは可能ですが、学術論文として提出する最終版は必ず人間がしっかりとチェックし、責任を持って調整する必要があります。
Claude Codeはソフトウェア開発向けに設計されており、そのままでは論文執筆に適していません。学術論文は一般的な技術文書とは異なる特殊な文体を要求するためです。
主な問題点
-
断言的表現の多用
- プログラミングでは「この関数は○○を実行する」のような明確な記述が好まれる
- 学術論文では「○○を示唆する」「○○と考えられる」のような控えめな表現が必要
-
技術文書の文体
- 能動態中心の記述
- 代名詞(it、this、these)の多用
- カジュアルな接続詞(But、So、Also)
-
学術的配慮の欠如
- 査読者への配慮
- 先行研究への適切な言及
- 再現性への配慮
これらの問題を解決するため、CLAUDE.mdファイルに論文執筆用のライティングルールを記述しました。
設定内容の例
### 学術的文体の基本原則
- 客観性の維持: 主観的判断ではなく実証的事実に基づく記述
- 控えめな主張: 過度な形容詞や断定的表現を避ける
- 精密性: 曖昧さを排除し,測定可能・検証可能な表現を使用
### 文体改善の具体例
× "powerful method" → ○ "has been used"
× "proves" → ○ "suggests," "indicates"
× "It is obvious that" → ○ "The results suggest that"
なぜ直接指示ではダメか
Claude Codeに直接「学術的に書いて」と指示しても、プログラミング向けの文体に引きずられてしまいます。CLAUDE.mdに詳細なルールを書くことで、適切なコンテキストとニュアンスを理解し、一貫した文体で執筆してくれます。
論文構成の事前設計
CLAUDE.mdには修論の詳細な構成も記述しています:
1. 序論:プログラム理解におけるXXXは有用だが分析が困難
2. 関連研究:従来研究はXXXという問題がある
3. 提案手法:提案手法ほげほげを提案
4. 実験・結果・考察:提案手法の評価と知見
専門用語の統一
研究分野特有の用語も統一ルールを設定:
- プログラム理解 (Program Comprehension)
- 機械学習 (Machine Learning)
- etc.
修論執筆における作業分担は以下のような感じです:
人間の役割(3割 + 最終調整7割)
- 論文構成の設計:章立て、論理展開の設計
- 研究方向性の決定:何を主張し、どう証明するか
- 最終品質保証:学術論文として提出可能なレベルへの調整
AIの役割(中間品質担保)
- 文章生成:構成に基づいた各章の執筆
- 文体調整:CLAUDE.mdのルールに従った学術的表現への変換
- 既存論文の参照:過去の研究成果の適切な引用と整合性確保
この手法で修論執筆を行った結果:
- 構成の一貫性:事前に設計した論理構造に沿った執筆が可能
- 文体の統一:学術論文らしい控えめで客観的な表現に自動調整
- 効率化:最低限の品質までの到達時間を大幅短縮
ただし、最終的には人間による詳細なチェックと調整が不可欠です。特に実験結果の解釈や考察部分は、研究者自身の深い理解と判断が必要となります。
AIの限界
- データの捏造や推測は行わない設計になっているが、最終確認は必須
- 専門分野の最新動向への対応には限界がある
- 査読者の期待やコミュニティの慣習は人間が判断する必要がある
学術倫理と開示義務
AI支援執筆について学会投稿時は適切な開示が必要です:
- IEEE等の学会では、AI生成コンテンツの使用箇所と使用レベルの明示が義務
- 文法チェック程度であれば開示不要ですが、内容生成に使用した場合は開示必須
- 投稿前に必ず該当学会の最新ガイドラインを確認してください
最終責任
繰り返しになりますが、学術論文の内容について最終的な責任を負うのは人間です。AIは作業効率化のツールとして活用し、内容の正確性や妥当性は必ず人間がチェックしてください。
Claude CodeとCLAUDE.mdを組み合わせることで、論文執筆の効率化が可能です。特に修論のように既存研究をまとめる性質の文書では、適切な構成設計と文体ルールがあれば、ある程度の自動化が実現できます。
ただし、これはあくまで執筆支援ツールとしての活用であり、研究内容の妥当性や学術的価値については、研究者自身が責任を持って判断する必要があります。
実際に使用したCLAUDE.mdは以下のような構成になっています:
- 基本方針:ペルソナ設定、役割、言語と文体
- LaTeX記述規則:基本構文、コード表記
- 専門用語統一規則:研究分野固有の用語定義
- 論文構成と研究品質:構造化された執筆指針
- 学術的文体の原則:具体的な表現改善例
- 修士論文執筆の参照ファイル:具体的な論文構成と執筆状況
このような詳細な設定により、一般的な文章執筆ツールを学術論文執筆に特化させることができました。
Views: 1