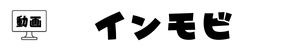🧠 概要:
概要
AI短編小説『無人棚の罪』は、無人コンビニでの不気味な体験を通じて、現代の人間の罪と向き合わせる物語です。主人公は、同僚から聞いた無人店を訪れ、封筒の中に秘められた内容と向き合うことで、自身の過去や他者の秘密が明らかになる様子を描いています。物語は、罪の重みとそれを知ることの困難さについて考えさせられる構造になっています。
要約の箇条書き
- 同期の橘が無人コンビニについて語る。
- 無人店舗は客がいない状態で、袋に中身の見えない封筒だけが並ぶ。
- 主人公は好奇心からその店を訪問し、封筒を持ち帰る。
- 中から出てきたのは社内の機密情報に関するメールのコピー。
- 主人公は橘に問い詰め、彼の封筒には主人公の過去の解雇歴が記載されていた。
- 店に通ううちに、さまざまな「見てはいけない秘密」が封筒に詰まっていることを発見。
- ある日、過去に匿名掲示板に書いた投稿が封筒に現れ、ショックを受ける。
- 封筒の売上が上がる一方で、様々な人々がその中身に狂わされていく。
- 橘は店の前で亡くなり、彼の財布には未開封の封筒があった。
- 最終的に、主人公のデスクに無人店の封筒があり、「次は、あなたの番です」とのメッセージが書かれていた。
- 物語は、個人の「罪」が他者に影響を与える様子を描き、無人店の正体が人間自身であることを暗示する。

「最近できた無人コンビニ、知ってるか?」
そう言ったのは、同期の橘だった。昼休み、社員食堂の隅。茶碗に残った味噌汁の最後の一滴をすすりながら、私は首を傾げた。
「無人って、あれだろ?支払いがセルフのやつ。別に珍しくは――」
「いや、そうじゃない。完全に“無人”なんだよ。客も、いない。」
客がいない無人店舗。空きテナントか、閉店したばかりの店のことだろうかと思ったが、橘の顔は真剣だった。彼はスマホで店の外観を見せてきた。
それは、都内のとある商店街の奥まった路地にぽつんと佇む、看板のないガラス張りの建物。ガラス越しに見えるのは、明らかに陳列された商品棚。そしてその棚に並ぶのは、雑貨でも食品でもなく――無数の「封筒」だった。
「売ってるのがさ……中身が見えない茶封筒なんだ。宛名も差出人もなくて、ただ無造作に置かれてる」
彼は続けた。
「で、値段も書いてない。けど、防犯カメラがあるわけでも、警備員がいるわけでもない。誰も見てないのに、みんな金を払って、買っていくんだとよ」
私は鼻で笑った。くだらない都市伝説だ。が、橘は首を横に振った。
「俺も最初はそう思った。でも、実際行ってみたら……なんていうか、“何か”が、いた」
“何か”。曖昧な言葉が私の耳に残った。
***
好奇心と軽い暇つぶし、それにちょっとした不眠症も重なり、私は橘が言っていた無人店を訪れた。
夜十一時。商店街の灯りはまばらで、店の周囲は静まり返っていた。
ガラス扉を開けると、小さな鈴の音が鳴った。だが、誰の「いらっしゃいませ」もない。
棚には、確かに封筒が置かれていた。一枚一枚、同じようなベージュ色の、やや古びた紙質。手に取ると、ずしりとした重みがあった。中に何かが入っているのは確かだった。
が、やはりどこにも値段表示はない。レジもない。あるのは、入り口脇の木箱だけだった。
「お気持ちをどうぞ」
手書きの札が、箱にぶら下がっている。
悪趣味なギミックだ、と思った。とはいえ、手ぶらで帰るのも悔しい。私は財布から百円玉を三枚取り出して箱に放り込み、ひとつ封筒を持って帰った。
帰宅後、封筒を破ると、紙が数枚出てきた。それは――社内メールのコピーだった。
差出人:部長の小野件名:採用候補者の裏リストについて本文:――例のA候補は学歴詐称が疑われる。外部リークだけは避けるように。
また、B候補は部長のお気に入りだが、どう見てもパワハラ気質。採用後は注意が必要――
思わず目を見開いた。これ、うちの部署の話だ。
念のため文書をスマホで撮影し、検索してみたがヒットしない。つまり、外部には漏れていない。完全な内部機密だ。
私は翌日、橘を問い詰めた。
「おまえ、これ……どういうことだ?」
彼は笑わなかった。ただ、「俺の封筒には、君の過去の解雇歴が書いてあった」とだけ言った。
そのときの橘の目に宿っていたものが何だったのか、今でも思い出せない。怒りだったのか、哀れみだったのか。あるいは、赦しだったのか。
***
その後、私は何度も店に通った。買った封筒は十を超えた。中には、芸能人の不倫写真。官僚の賄賂リスト。大学教授の論文盗用の証拠。小学生のいじめ動画まであった。
「見てはいけないもの」ばかりだ。だが、人は見てしまう。知ってしまう。
一度知ってしまえば、戻れない。目を閉じても、脳裏に焼き付いた映像がまぶたの裏に浮かぶ。眠れなくなり、飯がまずくなり、けれどまた店に足が向く。
ある晩の封筒に、私は見覚えのある筆跡を見つけた。
それは、私自身が五年前に書いた、ある匿名掲示板への投稿のプリントアウトだった。――会社の同期の女が、部長に媚び売って出世してる。俺が左遷されたのはアイツのせい。――今も殺してやりたいと思ってる。
投稿者名は「匿名」。だが、ログ情報まできっちり記載されていた。
吐き気がした。五年前、鬱屈した夜、酒に任せて書いた。忘れていたつもりだったが、誰かが見ていた。
私が“誰か”に見られていたのか。あるいは、“店”に見られていたのか。
封筒の重みは、そのまま罪の重さだった。棚に並んでいたのは他人の秘密ではなく、自分の“懺悔”だったのだ。
***
封筒の売上箱には、いつからか「最低額:1,000円」とメモが貼られていた。人が殺到したのだろう。
封筒は時に、人を狂わせた。
同僚の一人は、他人の不倫写真を晒してネットで炎上した。ある主婦は、息子の担任の不正会計を告発し、家庭崩壊を招いた。
そして橘は――あの店の前で、血を吐いて死んだ。
彼の財布には、三千円と、新品の封筒が入っていた。未開封だった。
私には、橘が封筒を開けられなかった理由が、わかる気がする。自分の“真実”に、踏み込めなかったのだ。
あるいは、踏み込むことを赦されなかったのかもしれない。
***
あれから、店には行っていない。
が、今朝、会社のデスクの上に、あの“茶封筒”が置かれていた。宛名はなかった。
中には、一枚の紙だけ。
《次は、あなたの番です》
そう書かれていた。
私は、見なかったふりをして、そっと封筒を引き出しの奥にしまった。けれど、背後に誰かが立っているような気配が消えない。
あの店に、“誰か”がいたという橘の言葉を、今になって理解した。
“誰か”ではなく、“なにか”だったのだ。私たちの“罪”を、棚に並べて売る何か。それはもう、無人ではなかった。
それは、私たち自身だったのかもしれない。
【了】
Views: 0