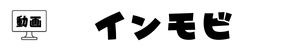🧠 概要:
概要
小説『地下鉄眠り譚』は、東京に住む春田が、独特の「うとうと地下鉄」に乗る体験を描いています。この地下鉄は、眠っている人しか乗れず、目を覚まさない限り降りることができません。春田は様々な「駅」に立ち寄りながら、自身の意識と現実の状態を問う旅をすることで、人生の選択や後悔について考えさせられる物語です。
要約
- 春田は居酒屋で「うとうと地下鉄」の話を聞く。
- その地下鉄は、眠っている人しか乗れない不思議な存在。
- 満員電車の中で眠ってしまい、目を覚ますと見知らぬ地下鉄の車両にいる。
- 乗客は全員眠っており、車内は異様に静かで清潔。
- 駅名表示は「まだ寝ていたい人の駅」となっている。
- 春田は、自分も降りられないことに気づく。
- 途中、様々な駅名が表示され、各駅にいる人々の表情が異なる。
- 彼は「眠ること」や「目覚めること」の意義を考え始める。
- 最終的には、現実と夢の境界が曖昧になり、思考が続く。
- 結末で、春田は「もう二度と目覚めない」との選択がどこへ向かうのか問いかける。

その地下鉄は、他のどの路線図にも載っていない。
東京に住んで三十年の春田(はるた)でさえ、その存在を知ったのは、つい一週間前だった。
きっかけは、居酒屋で隣に座った男が「うとうと地下鉄って知ってます?」と訊いてきたことだ。
「いや、聞いたこともないが」
「ええ、当然です。眠ってる人しか乗れませんから」
奇妙な冗談だと思い、酒の肴に聞き流していたが、男はまったく笑わなかった。
その顔の白さは、長年蛍光灯の下にいた人間のようだった。
「眠っていれば、乗れる。起きていれば、降りられない。変な地下鉄なんですよ」
春田はその話を忘れたわけではなかったが、忙しさにまぎれて思い出すこともなかった。
だが、四日後の朝、満員電車の中でつい立ったまま眠ってしまったとき、何かが変わった。
目を開けると、そこは地下鉄の車内だった。
見たことのない車両。妙に静かで、妙に清潔。
広告も一切なく、つり革はすべて新品のように輝いていた。
乗客は全員、眠っていた。
ある者は口を開けて、ある者はスマートフォンを握ったまま、全身から力を抜いていた。
誰一人、目を覚ましている者がいない。
春田は、寝過ごしたのだと思った。が、車窓に駅名表示はなく、ホームすら見えない。
アナウンスもない。車内モニターも消えたままだ。
——これは夢だ。そう思った。
だが、夢にしては質感が生々しい。空気に匂いがあり、スーツの襟が首を締めつけてくる。
何より、眠っていたはずの自分が「今、起きている」という矛盾が気にかかった。
やがて列車が止まり、ドアが開いた。
駅の名前は表示されず、代わりに——ただこう書かれていた。
《まだ寝ていたい人の駅》
数名がゆっくりと、立ち上がることもなく、体を斜めにしたまま流れるようにホームに出ていった。
ホームには白いソファが並び、そこに人々はぐったりと横たわっていった。
ドアが閉まり、再び発車する。
「……これは、変な冗談じゃ済まないな」
春田は立ち上がり、隣の人に声をかけた。
「ここは、どこなんでしょうね」
だが、相手は寝息を立てたまま、返事などする気配がない。
ためしに肩を叩いても反応はない。まるで人形だ。
そうして数駅を通過し、次の表示が現れる。
《後悔している人の駅》
ホームに降りた者の表情は、いずれも曇っていた。
目を閉じたまま、彼らは列をなし、奥の暗がりへと歩いていく。
春田は、ようやく自分が地下鉄の話を居酒屋で聞いたことを思い出した。
あの時の男が言っていた。「眠っていれば、乗れる。起きていれば、降りられない」
起きている自分が、降りられない。
確かに、立ち上がっても足がホームへ出ることはなかった。体が床に縛られたように動かない。
ただ、座っているのなら苦ではない。眠ることを選べば、もしかしたら——降りられるのかもしれない。
彼は座り直し、深く息を吐いて、目を閉じた。
車両はまた走り出す。
《現実に戻る駅》
ドアが開く。ホームの光は他の駅よりも強く、そこに立っている人たちは皆、目を開いていた。
新聞を読んでいる人。腕時計を気にする人。
みんな、普通の通勤者に見えた。
春田も立ち上がり、歩き出そうとした。が——体はびくともしない。
腕が動かない。足が床に貼り付いている。
何かが違う。なぜ彼は、起きているのに降りられないのか。
ふと、車内の鏡に目が止まった。
そこには、閉じた目をした春田が、静かに眠っていた。
——起きていると思っていたのは、夢の中での話だった。
車両は、また走り出す。
今度の駅は、こう表示されていた。
《気づいてしまった人の駅》
ホームに立っていたのは、先日、居酒屋で隣にいた男だった。
彼は目を閉じたまま、ゆっくりと笑った。
——そして、彼はそのまま車内へと入ってきた。
その後、春田は何駅もの表示を見た。
《夢を見たい人の駅》《忘れたい人の駅》《やりなおしたい人の駅》。
乗客は変わることなく、ただ静かに眠り続けていた。
そして、春田は気づいた。
この列車には、始発も終点もない。眠ることも目覚めることも、すでに乗客の意志では選べない。
いま自分が思考しているこの時間さえ、目覚めている夢なのか、眠っている現実なのか、判別がつかない。
車窓には、外の景色など映らない。
あるのは、ずっと同じ黒い壁と、わずかに映る自分の顔。
誰かが言っていた。
「眠っていれば、乗れる。起きていれば、降りられない」
では——「もう二度と目覚めない」とは、どこに向かうのだろうか。
車両は、止まることなく進み続けている。
【了】
Views: 0