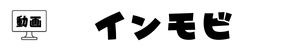🧠 概要:
概要
AI短編小説『午後のレールは血のにおい』は、主人公の千波と彼女の友人毬屋が、消えた廃駅を目指して未知の旅に出る物語です。彼女たちは「ここじゃない」と感じ続ける日々から逃れるため、目的もなく電車に乗り込み、廃屋と謎の写真の束を発見します。物語は、彼女たちの自己探索とともに、危険な運命の暗示が絡み合っています。
要約
- 夏の終わり、千波と毬屋は行き先を決めず電車に乗る。
- 毬屋は「死にたくなるくらい遠くへ行きたい」と提案。
- 2人は「消える駅」と呼ばれる廃駅を目指すことに決める。
- 廃駅に到着すると、不気味な空気が漂う。
- 毬屋が「血の匂い」を感じると、周囲の色が変わる。
- 駅近くの廃屋に入ると、大量の写真が残っており、そこに写る女性たちが彼女たちを見つめている。
- 毬屋は自分が写真の中にいるかもしれないと語る。
- その晩、千波は駅へ戻らず、後日誰もその駅を見つけられなかった。
- 廃屋の写真の束が唯一の証拠として残り、それに写った少女と無表情の女は千波と毬屋だった。
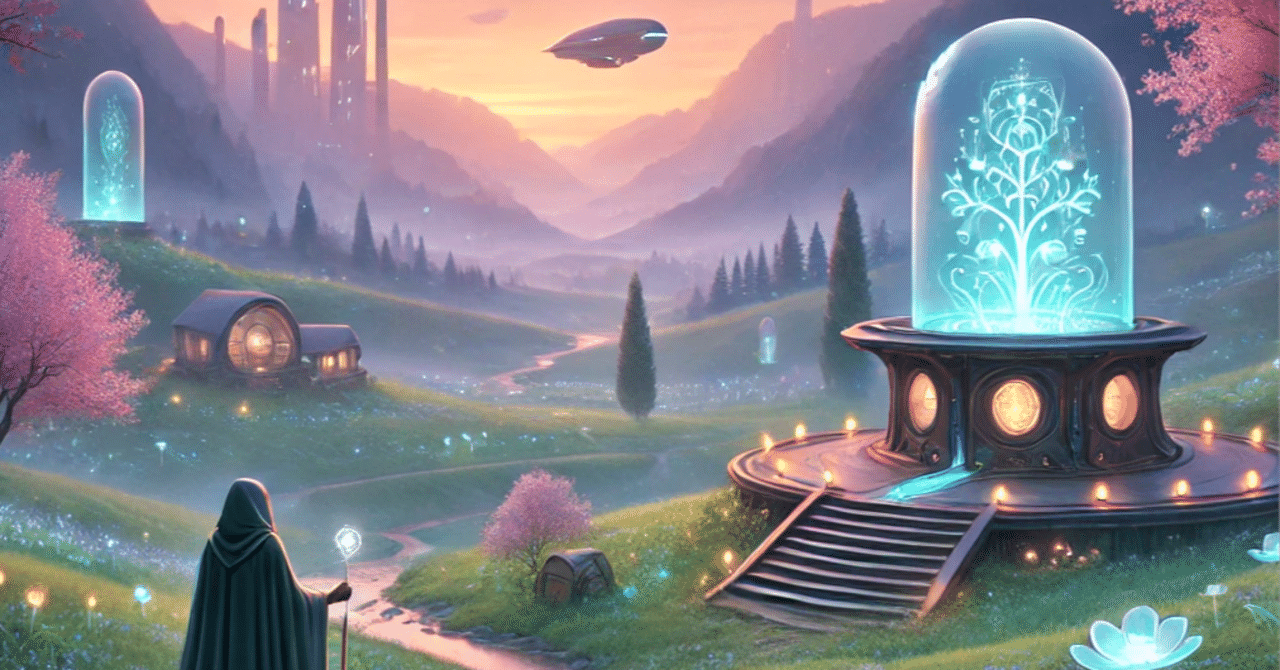
夏の終わりに、私は彼女と電車に乗った。
行き先は決めていなかった。ただ、どこか遠くへ行こうという共犯めいた合意だけがふたりの背中を押していた。
発案者は、毬屋(まりや)だった。白く細い指でスマホを弄りながら、ふと視線だけを私に向けて、
「ねえ、千波(ちなみ)。たまにはさ、死にたくなるくらい、遠くへ行ってみない?」
そんなことを言ったのだ。
私は笑い返した。「死にたくなるくらい」ではなく、「死にたくないから」行くんだよ、と。だけど、その笑いは少し遅れてやってきたようで、電車の窓に映った私の顔は、きっと笑っていなかった。
鈍行列車の中、車内は昼下がりの光で溶けかけた飴玉のように、やわらかく濁っていた。向かいに座る毬屋は、さっき買ったアイスコーヒーを膝の上でくるくると回しながら、意味のないようで意味のありそうなことを呟いた。
「ここじゃない、ってずっと思ってたの。高校のときからずっと。授業中も、夜のファミレスでも。たぶん、どこにいても“ここじゃない”って思ってた」
「どこならいいの?」
「わかんない。でも、そういう場所があるんじゃないかって、今でも思いたい」
そのとき、私の頭に「ある場所」のことが浮かんだ。かつてニュースで話題になった、廃駅のことだ。ある日突然、時刻表から削除された無人駅。鉄道会社も撤去理由を明かさず、マニアの間では“消える駅”として語られていた。
毬屋に話すと、彼女の目がほんの少しだけ光った。「ねえ、そこ行こうよ」
私はうなずいた。そこへ行けば、なにかが終わる気がした。もしくは、なにかが始まる気がした。もちろん、その両方が起きる可能性もあった。
ふたりとも、同じものを見たくて旅をしていたのではない。ただ、日々の中で見えなくなってしまった“なにか”を、探していたのかもしれない。
◆
列車を何本も乗り継ぎ、地図にもないその駅へ向かうには、ある裏技が必要だった。切符のルートをわざとミスリードするように買い、分岐点で乗り換えずに車内に残る。
やがて、車内アナウンスのないトンネルを抜け、電車は滑るように目的の駅にたどり着いた。駅名標は外されており、ベンチは崩れかけ、雑草が覆っていた。風の音が妙に耳に残った。まるで、人の囁きのようなかすれ声が、風にまぎれて聞こえた気がした。
無人のホームに降りた瞬間、毬屋が小さくつぶやいた。「あ、匂いがする」
私は鼻をすする。風のにおいだと思った。しかし彼女は違った。
「血の匂い。ひとの。それもね、自分で出したやつじゃなくて、だれかに出された血の匂い」
その言葉に、鳥肌が立った。空の色がすうっと変わった気がした。夕暮れのはじまりに似た、絶望的な色だった。まるで、この土地だけが時間から外れているような、静止した空気が周囲を満たしていた。
ふと、背後で列車のドアが閉まる音がした。振り返った時にはもう遅かった。列車は、音もなく発車していた。
「……置いていかれたね」
「戻るつもりだったの?」
毬屋はそう言って、笑った。唇の端が持ち上がるその笑みは、今まで見たどんな表情よりも自然で、そして異質だった。
◆
駅から少し歩いたところに、廃屋があった。扉は壊れていたが、テーブルと椅子、そして壁に貼られた大量の写真だけが、風雨にさらされず残っていた。
写真には、若い女性ばかりが写っていた。笑っている。泣いている。ある者は倒れていた。そこに写る彼女たちの眼だけが、まるでこちらを見つめ返してくるかのようだった。
毬屋がぽつりとつぶやいた。「ねえ、千波。この中に私、いるかもしれないと思わない?」
冗談だろうと思った。だが、彼女の声はとても穏やかで、真実のように響いた。
「わたしたちって、もしかして……もう、誰かに選ばれてるのかも」
「なにに?」
「終わる順番に」
そのとき、不意に背後から、カチリという音が聞こえた。振り返っても、誰もいなかった。だけど、足元の影だけが、ほんの少しだけ、揺れていた気がした。
◆
その日、私は帰らなかった。もとより、戻る列車はなかった。
後日、その駅を調べた人が何人かいたという。だが誰も、そこへ至る線路を見つけることはできなかった。地図にないのはもちろん、地形にも痕跡すらなかったという。
ただひとつ、廃屋の中にあったという、写真の束だけが証拠として回収された。うち一枚に、白いワンピースの少女と、無表情の女が並んで写っていたそうだ。
女の名は、千波。
少女の名は、毬屋。
そしてふたりの影は、異様に長く、黒かったという。
Views: 0