「卵子は精子を“選ぶ”らしい」――そんな話を耳にしたら、驚く方も多いのではないでしょうか。
学校で習う受精のイメージといえば、数えきれないほどの精子が一斉にスタートし、最速で卵子にたどり着いた一匹だけがゴールイン……という“精子同士の競争”でしたよね。
ところが近年の研究によれば、卵子は単に受け身で待っているわけではなく、「この精子なら受精させてもいい」と自ら選り分けている可能性があるというのです。
実際、生物学ではこれを「隠れたメスの選択(cryptic female choice)」と呼び、メス(女性)が交配後のオス(男性)由来の精子を密かにコントロールしている、という見方が注目されています。
つまり、精子はひたすら競争するだけではなく、卵子から“選ばれる”必要がある――そう考えると、ちょっと意外でドラマチックに感じませんか?
そこで今回は、精子が卵子のもとへたどり着くまでの道のりを「就職活動」にたとえて紹介することで、受精のプロセスがぐっと身近に感じられるはず。
読み終える頃にはきっと、「精子って大変なんだなあ」と思わず同情してしまうかもしれません。
目次

悲しいことですが、一次試験の前に大半の精子が運によって振り落とされてしまします。
というのもまず、女性の体内で卵子を“募集”するタイミング、すなわち排卵期が到来しなければ就活(受精)自体が成り立たないからです。
排卵期には卵巣から卵子が放出される準備が整い、女性の体内は精子を受け入れる環境を整えます。
就職活動にたとえるなら、「採用情報が正式にオープンした」段階がこの排卵期と言えるでしょう。
一方、精子の側もタイミングが合わなければ、いくら優秀でも次のステップへ進むことはできません。
実際に性交のタイミングが排卵期とかけ離れていれば、到着した精子が膣や子宮頸管で力尽きてしまう可能性が高いからです。
こうして適切な時期に応募することで、精子たちはいよいよ次の関門に臨む準備ができるわけです。
運よく排卵期という“募集スタート”に恵まれた精子たちは、まず女性の膣内という非常に過酷な環境へ足を踏み入れます。
膣内は酸性度が高いうえ、射精直後に精液が数秒でゲル状になって固まるのは、こうした酸から精子を守るための防衛策。
その後、30~60分ほどで再び液体化し、精子たちは自由に泳ぎ出せるようになります。
とはいえ、膣内で力尽きてしまう精子も多く、次のステップである子宮頸管まで到達できるのは射精時の精子総数のうちごくわずかだといわれています。
就職活動でいえば、「募集要項に気づき、ちゃんと応募したはいいが、ここで大半が第一関門を突破できずに脱落してしまう」イメージです。
こうして“企業研究”をクリアし、膣内を乗り切った精子だけが、次なる難関である子宮頸管へと進むことができます。

膣内の関門をくぐり抜けた精子が次に直面するのは、子宮の入口である子宮頸管です。
ここには粘液が満ちていて、普段は精子や細菌の侵入を防ぐ“フィルター”のような役割を果たしています。
しかし排卵期が近づくと粘液がゆるみ、精子にとって通りやすいルートに変化。
それでも粘液の流れが強いため、泳ぐ力の弱い精子はこの段階で足止めされてしまいます。
さらに近年の研究では、子宮頸管の内壁には“マイクログルーブ”と呼ばれる細い溝があり、この溝を上手に泳げる精子ほど子宮までたどり着ける可能性が高いとわかってきました。
要するに、運動性能に優れた精子しかここを突破できないのです。
就活にたとえれば、基礎的な健康や運動能力のテストと言えます。
膣内(応募受付)をくぐった大量の“応募者”のうち、基本条件をクリアする精子だけがここでふるい落とされずに通過できるのです。
実際、子宮の奥へ到達できる精子は最初の数億匹中ほんのわずか。
就職活動のES選考と同じように、ものすごく狭き門だというわけですね。
こうして体力テストを通過した精子たちだけが、次なる“面接会場”ともいえる子宮へと向かうことになります。

子宮頸管を突破して子宮の広々とした空間に入った精子たちも、まだまだ気は抜けません。
なぜなら、次は女性の免疫システムが待ち受けているからです。
私たちの体は、基本的に「外から侵入してきたもの」を排除するよう設計されています。
精子も例外ではなく、子宮内に入った時点で白血球などの免疫細胞から攻撃を受け、多くがここで脱落してしまうのです。
さらに、左右2本ある卵管のうち“正解”の卵管へ向かわないと、そもそも卵子に出会えない可能性もあります。
たとえば右側の卵管に卵子がいないときにそちらへ突き進んでしまえば、いわば「不採用」になってしまうわけです。
とはいえ、子宮はただ厳しいだけの環境というわけでもありません。
女性がオーガズムに達すると子宮が収縮し、精子をぐっと卵管へ押し上げるように手助けしてくれることもあるのです。
つまり子宮は、不必要な精子を淘汰しつつ、有望な精子には先に進む手助けもしているのです。
その証拠に、マウスの実験では子宮内で精子を殺す物質が作用し、特定のタンパク質でコーティングされた精子だけが生き残って卵管へ到達できることが報告されています。
このようにオス由来の精液成分が精子を防御し、メス由来の攻撃をかわすことで子宮内での競争的選抜が行われているのです。
この子宮内での関門は、さしずめ就活の適性検査に相当すると言えるでしょう。
免疫というセキュリティチェックを潜り抜け、環境への適応力を示した精子だけが次のステージに進めます。
さらに、ここまでたどり着いた精子は生存力だけでなく質の面でも選び抜かれています。
例えば精子の持つ遺伝情報の損傷具合(DNA断片化の有無)は、その後の受精や胚発生に大きく影響しますが、女性の生殖器官内を生き残れる精子にはDNAが健全なものが多いと考えられます。
この段階までの過酷な選抜によって、体内にはより優れた性質を持つ精子集団が残るのです。
また、精子はこの旅の途中で受精能力を高める「受精能獲得(capacitation)」という成熟過程を完了します。
いわば本番の受精に向けた実地トレーニングを積んだわけです。
実際、性交後ごく早く卵管に到達した精子はまだ十分に成熟しておらず、受精には与れないことが多いとされています。
こうして適性検査を突破し受精準備も万端に整えた精鋭たちが、最後の舞台である卵管へと挑むのです。
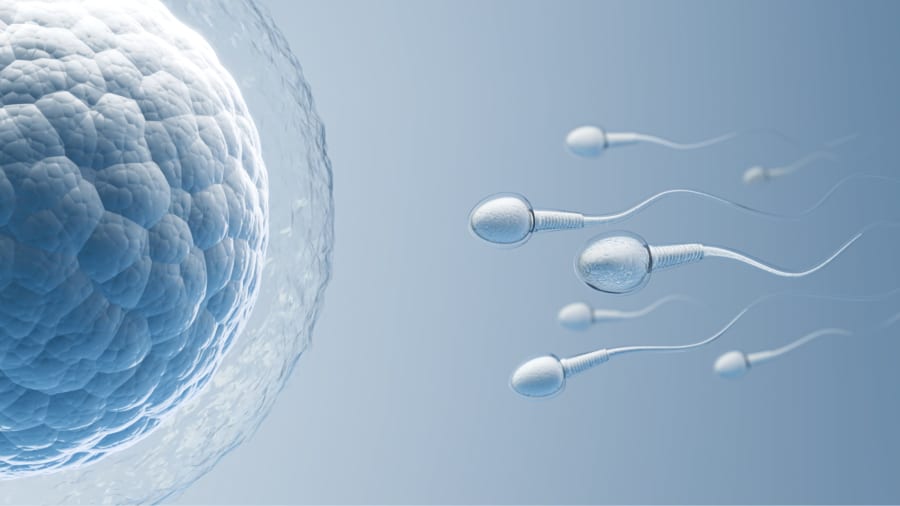
受精の主舞台である卵管に入れる精子の数は、最初の数億匹からぐんと減ってわずか数百匹ほどになると推定されています。
就活でいえば「最終面接に呼ばれた候補者」といったところ。
そこへ、卵巣から放たれた卵子が卵管内へ到着すると、いよいよ両者の“直接対面”が始まります。
おもしろいのは、卵子の方から「化学物質」のシグナルを発して精子を呼び寄せているらしいという点です。
これは「化学走性」と呼ばれ、卵子が出す匂いのような物質を精子が感知し、誘導されるように卵子の周囲に集まってくる仕組みです。
しかも最近の研究では、卵子が発する化学信号に「好み」があって、ある精子には強く反応するのに、別の精子にはそうでもない……という現象が示唆されています。
まさに「面接官(卵子)のお眼鏡にかなった精子」だけが、最終候補として呼ばれている可能性があるのです。
ここまでの難関を突破しやっとこぎ着けた面接の基準が、面接官の個人的好みというのも生物学の厳しさの1つと言えるでしょう。
さらに、女性と男性の遺伝的な相性(免疫関連のHLA型)によって、女性の卵管内で精子の活発さが変わるという報告もあります。
言い換えれば、遺伝子的に相性の良い相手の精子ほど、ここで元気に泳げるようになるのかもしれません。
卵管で行われるこのプロセスは、まさに「最終面接」に例えられるでしょう。
卵子という採用担当者が“相性も含めてベストな候補”を見極めるシーンなのです。
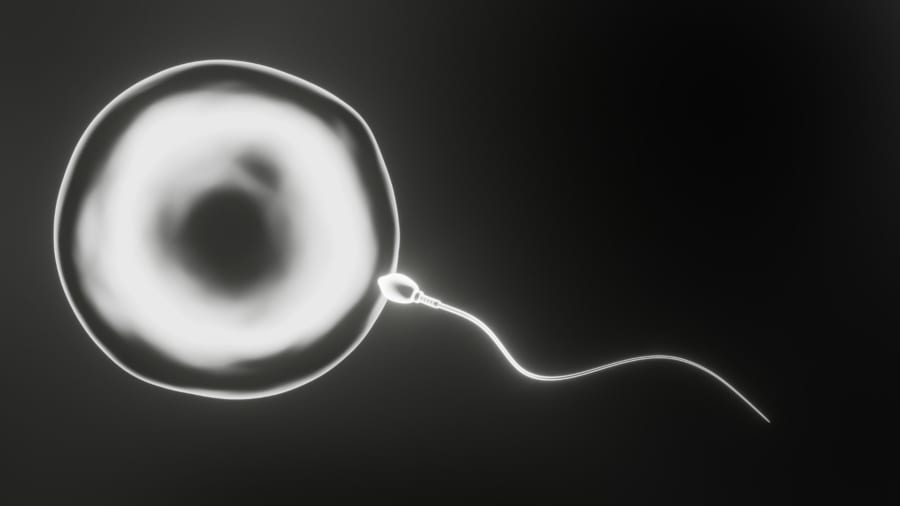
こうして数百匹程度まで絞り込まれた精子の中から、最後に“内定”を勝ち取るのはたった1匹。
卵子の周囲には透明帯(ゼリー状の膜)や卵丘細胞の層といったバリアがあり、精子は尾を激しく振りながらそれを突破しようとします。
そして見事に膜を破り、卵子本体の細胞膜と融合できた瞬間、「一番乗り」の精子だけを受け入れるために卵子の膜が固くなる仕組みが発動。
他の精子が侵入できないようブロックするのです。
これは「多精受精」を防ぐための大切なプロセスで、受精卵(胚)が正常に発生するためには欠かせません。
こうして卵子と融合を果たした精子は、数億ものライバルをくぐり抜けた“エリート”ともいえる存在。
最終的には卵管内に200匹ほどが残り、そのうち1匹だけが「内定」を得る――文字にすると壮絶な競争ですよね。
これこそが、新たな生命が誕生するための厳粛かつ神秘的な選抜ドラマなのです。
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。
大学で研究生活を送ること10年と少し。
小説家としての活動履歴あり。
専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。
日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。
夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
Be the first to comment