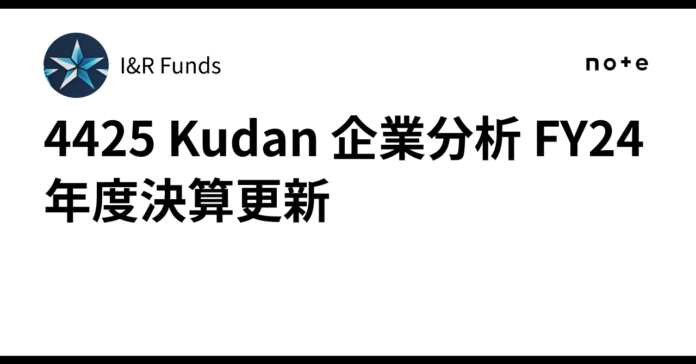🧠 概要:
概要
この記事はKudanのFY24年度決算に関する分析を行っています。Kudanは自動運転技術、AR/VR、ドローン、ロボット工学、IoTなどにおいて、人工知覚技術を用いたコンピュータビジョン技術の開発とライセンス提供を行っている企業です。この記事では、業績、製品化の進捗、損益分岐点、そして将来の見通しについて詳述しています。
要約(箇条書き)
- Kudanは自動運転やAR/VR、IoTなどに特化した人工知覚技術を開発するテクノロジー企業。
- FY24の売上高は当初の予測から大幅に下方修正され、5.2億円に留まる。
- 販売管理費の増加により、赤字幅が拡大し、黒字化の目標が遠のく印象。
- 製品化は進んでいるが、売上に寄与するまでには至っていない。
- 研究開発が進む中で、SLAM専業のビジネスモデルのマネタイズの難しさが明らかに。
- 今後は新技術の採用や事業のリバランスを進める方針だが、SLAM単体では成り立たない可能性あり。
- 赤字拡大を回避するためには、戦略転換が必要であるとされる。
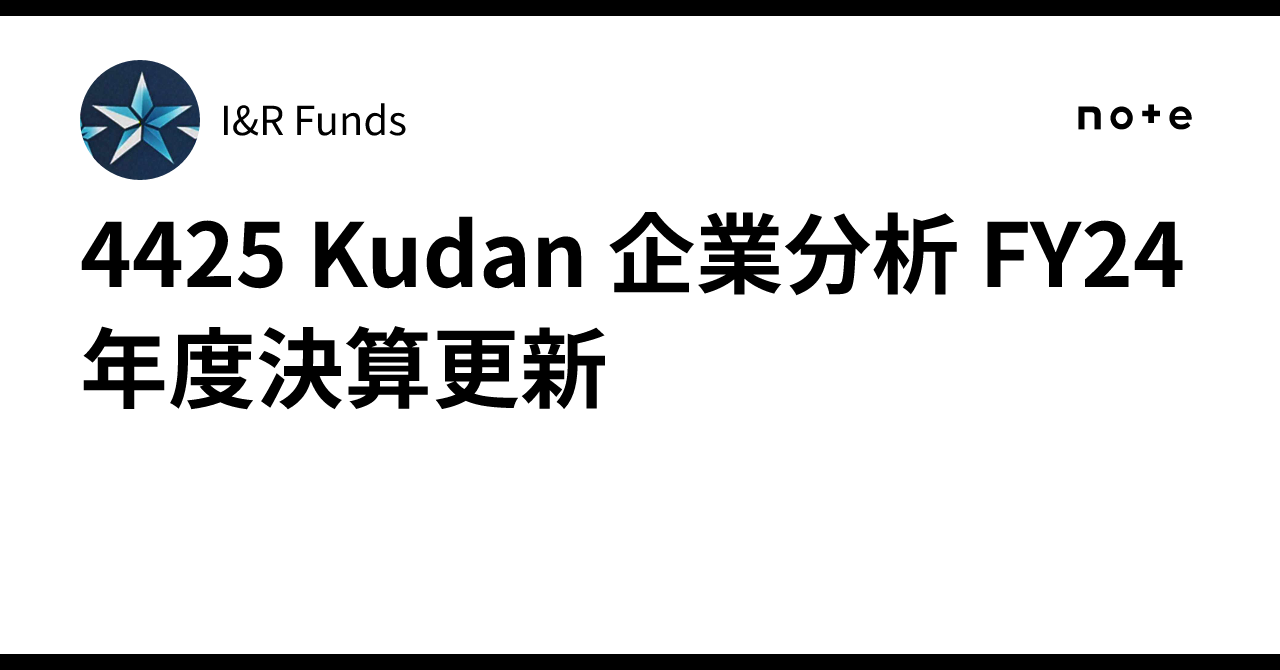
こんばんは、本日は宝くじ銘柄だと個人的に思っているKudanの分析したいと思います。
前回の続きとしてFY24年度決算をUpdate
1.企業概要
自動運転・AR/VR・ドローン・ロボット・IoT・デジタルツイン等への応用を目的に人工知覚技術によるコンピュータビジョン技術(SLAMアルゴリズム)の開発とライセンス提供。コンピュータやロボットの「眼」に相当する人工知覚(AP)のアルゴリズムを専門とするDeep Techの研究開発企業。
先端要素技術に特化、イギリスを研究開発拠点に人工知覚技術を開発、シリコンバレー型の事業を展開。カメラ搭載可能なデバイスを対象とした立体認識技術ソフト「SLAM」(リアルタイムの3D点群生成、位置認識のアルゴリズム)により自動運転やドローン・ロボット向けに位置情報DXソリューションを提供。
AIやIoTとの技術統合に向け知覚ニューラルネットワーク、SLAMとAIの統合、Lidarとビジュアルの統合、デジタルツイン、GrandSLAM(主要センサーの密結合)に関する研究開発を推進。2020年Artisense社と業務提携(2021年子会社化)。2023年Whale Dynamicと資本業務提携。
ライセンス提供だけではなく、市場への普及を促すためにソリューション事業(システム設計からPMまで請け負う)を展開。
2.業績推移
下図通り、売上は着実に増加しているものの販管費も増加フェーズにあり、赤字幅は拡大。大手取引先との開発状況や製品化状況など事業進捗を示す形で継続して個人投資家からの期待は保ちつつ、継続的なワラント実施により資金調達を実施しながら事業運営をしている状況。
期末に売上偏重の傾向があるとの説明もあるが、本来ビジネスが軌道にのれば顧客製品の販売による継続的なライセンス収入がコアとなるようなSaaS型のビジネスモデルとなるため、まだPoCのフェーズのものが多いともいえる。FY23はWD社への出資・大口でのライセンス販売240百万円が期末に計上され、378百万円となっている。
今年度年間見通しと3Qまでの累積の売上高との差分から275億円が4Q売上と見込まれるが、この売上の内訳は精査したい。
一部上記にも記載しているが各チャートのポイントは下図内に記載、詳細を確認したい方は最後までご一読いただきたい。
3.製品化リスト
下図通り、製品化は着実に増加。ドローン企業や自動搬送ロボットなどの主に産業用途のものが中心。各製品がどの程度売上に寄与しているかは細かくはわからないが、台数が多く出るようなものではないためまだ大きく業績が急拡大するようなフェーズではないと思料される。
Intelの商用化は非常に興味深かったが、最終顧客製品に組み込まれた際は初回は何らかのアナウンスをすると言っていた中でまだそういったリリースがないことを鑑みるとマネタイズの難しさは感じられる。
4.損益分岐点分析
粗利までを変動費の要素、販管費を固定費として実施。詳細は下図にて実施しているが、販管費は年々増加傾向で粗利率もライセンス販売だけではなく、市場への普及を促すことなどのため、様々なビジネスを展開した結果低下傾向にある。
黒字化が目先の財務的な目標だと私は考えているが年々遠のいている印象もあり、投資のタイミングは黒字化後ではなくその目途が実績ベースでイメージ出来た時だと考えているため、もう少し先だと考えている。
5.FY24年度決算について
実績評価
FY24実績について、会社当初計画売上高7.0億円、営業利益▲4.3億円から大幅な下方修正となり、売上高5.2億円、営業利益▲8.0億円となった。
理由としては先進的な顧客製品化が市場に対し先行しすぎたこともあり、顧客製品の普及速度は想定を下回るということで主に補完技術やエコシステムの成熟不足もあり、ロボティクスは製品化案件の製品ライセンスが伸び悩み、デジタル ツインでも欧州公共案件で遅延とのこと。
SLAM専業のビジネスのマネタイズの難しさと足元の市場環境を見誤っていたことが製品化とともに露呈したような印象。
研究開発型企業によくある今よりも良いものだから売れるはずという考えと実際にビジネスの現場としては現状稼働しているものを止めるわけにはいかず、マイナスの影響を嫌うという心理との乖離が大きくなっているのではないかと考える。
見通し
足元の売上が想定のように伸びないことに対しては、
・新技術・補完技術を拡大
・事業リバランスによるコスト削減、選択と集中による最適化
コア技術であった人工知覚(AP))に加えて、人工知能(AI)にも取り組むことで技術を拡張していく。
ということだがこれはSLAMのみではビジネスとしては成り立たないことの裏返しともいえるのではないだろうか。これまでAPとAIはアプローチが全然違うので非なるものという説明をChat GPTが出てきたときに説明していたことを踏まえるとこの変化は理解しておきたいところ。
加えてソリューション志向を強めるということだが、これも深層技術としてのSLAMではビジネスは成り立たず、上流へアプローチし認知・導入を自ら進めなければならなかったことの裏返しと捉えることもできる。
買い目線としては、アプローチが変わったことは残念ともいえるが、このまま売上低迷、赤字拡大が続くことを回避するための戦略転換と捉える必要があると思う。
SW(SLAM)専業のKudanがHWの要素も社外から調達しビジネスをしていくという成長戦略が新たに明示された。これもSLAM専業としてのビジネスのマネタイズの難しさから出された戦略と思料される。
ソリューション事業もそうだが、他社に販売を任せていてはビジネスが成り立たないということではないか。

とはいえ、空間知覚やSW/HWが新規のような表現ではあったものの改めてMappingした案件一覧をみれば、過去から取り組んでいた案件も含まれているようなので、再定義しただけで大きな変化ではないのかもしれない。

収益構造の改善について、これは前回ので説明した損益分岐点にも関わるところではあるが、固定比率の低減により黒字化の閾値が低くなることということだと思う。
以降の有料記事にてUpdateしたい。

6.損益分岐点売上高のUpdate
Views: 0