🧠 概要:
概要
第3章「商品の選ばれ方――回転ダーツとプレファレンス」では、消費者の意思決定過程を「回転ダーツ」という比喩を用いて説明し、マーケティングにおけるプレファレンス(好み)の影響を探ります。著者は、消費者が商品を選ぶ際に直感に基づく決定を行うことを解説し、この選択過程が確率的であることを論じています。また、選ばれるためには「選択肢の中に入ること」と「ブランドの面積を広げること」が重要であると述べています。
要約(箇条書き)
-
消費者の意思決定:
- 日常生活で人は一日に3万回以上の意思決定を行うが、ほとんどは直感で処理される。
- 商品選択も直感が大きな役割を果たす。
-
回転ダーツの比喩:
- 意思決定は確率に基づき、脳は同様に「回転ダーツ的」に商品を選ぶ。
- 消費者の好みの強さが、選ばれる確率を左右する。
-
プレファレンスの変動:
- 商品の割引、新商品の追加、特殊な選択状況によって、消費者の好み(プレファレンス)は変動する。
- この変動は一時的なもので、長期的には安定する傾向がある。
-
選ばれるための2つのステップ:
- 選択肢の中に入れ: 消費者の「エボークトセット」に自社商品を追加する。
- 面積を広げよ: ブランドの好意度を高め、脳内での面積を増やす。
-
プレファレンスを高める要素:
- プレファレンスは「価格」「製品パフォーマンス」「ブランドエクイティー」に影響される。
- ブランドエクイティーは、消費者の心に強い影響を与える要因で、長期的な価値を生む。
-
事例:PayPay:
- PayPayは、強力なマーケティングキャンペーン(100億円還元キャンペーン)で市場に迅速に浸透。
- 消費者の選択過程に大きな影響を与え、ブランドの面積を拡大。
- ブランディングの重要性:
- ブランドエクイティーを高めることが、プレファレンスを最大化するためのカギ。
- 消費者の本能を理解し、それに基づいた提案を行うことが重要とされる。
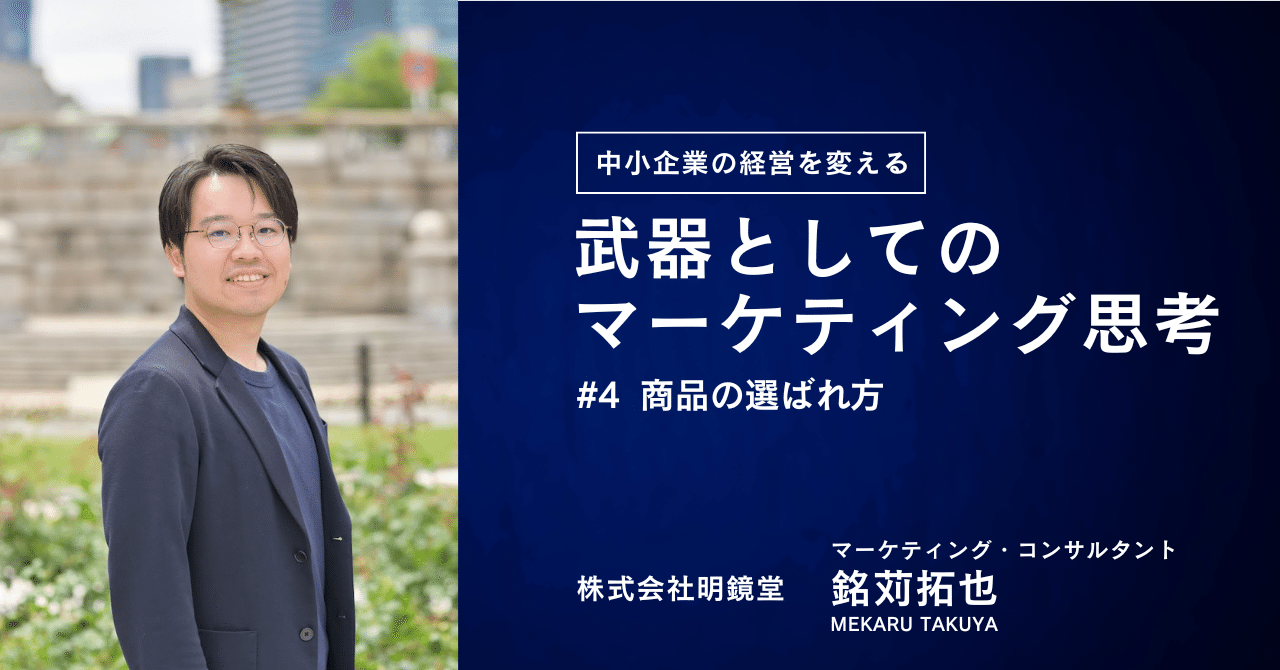
第一章と第二章では、商品のもつ「違い」こそが買い手に評価される(選ばれる)理由であるということを学びました。しかし、本当に消費者がさまざまな商品について詳しく情報収集をしたり比較検討したりしているのかは、感覚的にやや疑問が残ります。
そこで第三章は商品そのものではなく、商品を購入する人物に焦点を当て、買い物をする人の脳がどのように意思決定しているのかを明らかにします。脳の意思決定とは商品を比較検討し、購入を決めるまでの一連の流れのことです。
意思決定は「確率」である
脳は一日に約3万回以上の意思決定を行っています。人間が日々決定しなければならないことは、何を食べるかやどの道を通るかといった些細なことから、仕事や人間関係にまつわる大きなことまでさまざまです。しかし、その一つ一つをいちいち合理的か否か検討するのは膨大な労力が必要です。ですから、決定のほとんどは「直感」によって処理されているといわれます。このような脳の働きは、日常的に買うものだけに限りません。自動車のように高額で十分な比較検討を行う商品でも、単純にエンジンや荷室のスペックと金額のコストパフォーマンスだけで選んでいるわけではありません。加速感や静寂性、内装・外装のデザイン、近隣道路との相性なども検討材料となり、考えれば考えるほどどれがいいのかわからなくなることもあります。最終的には「直感」で決めていることも多いのではないでしょうか。暮らしのために必要な商品については、ほとんどの場合「直感」によって購入を決めているといってよいでしょう。最新のマーケティング研究では、人間の脳が商品を「直感的」に選ぶ性質を数学的に理解する試みが行われています。キーワードは「確率」です。人間の意思決定とは、ちょうど回転ダーツを回して出た目を読むようなものです。かつてTBSで放送されていたバラエティー番組「関口宏の東京フレンドパーク2」で、ゲスト出演者が番組の最後にダーツを投げるコーナーを覚えていますか。くるくる回る回転ダーツの的には様々な家電や旅行券などの景品のラベルが貼られていて、ダーツの矢でラベルを射抜くことができれば景品獲得。外すと何ももらえません。「パジェロ!パジェロ!」という掛け声に押されて出演者が矢を放つ瞬間、会場が一体となっていきを呑みしんと静まり返る。的に矢が刺さって木を叩くような鈍い音が響き、カメラが確認するとそこには「たわし」の3文字、そして爆笑が巻き起こる……という定番コーナーです。回転ダーツ(的)の大きな面積を「たわし」がしめているため、多くの出演者が図らずも豪華景品ではなくたわしを射当ててしまうのが名物でしたね。実は、人間の脳が意思決定をするときも、東京フレンドパーク2のダーツコーナーとほぼ同じように回転ダーツを回し、買う商品を決めているということができます。市販の缶ビールを例に説明しましょう。コンビニやスーパーの缶ビールコーナーの前にたち、1本だけビールを買うときを想像してみてください。冷蔵庫の前に立つ人の脳の中では、回転ダーツがくるくる回っています。ダーツの的は、ちょうどこの図のように円グラフの形をしていて、扇形の各ゾーンにはいくつかのブランドが書かれています。各ブランドが占める面積の広さは、消費者が好きだと感じている度合い(専門用語でプレファレンスや相対的選好度といいます)によって決まっています。具体的な例で考えてみましょう。こちらの図をご覧ください。(図)これは、筆者が個人的に好きなブランドでルーレットを塗り分けたものです。面積が広い順に、キリン一番搾り、サントリー生ビール、アサヒ生ビールマルエフ、ザ・プレミアム・モルツで、それぞれ40%、30%、20%、10%の割合で塗られています。扇形の面積の割合はそれぞれダーツが当たる確率と同じです(フレンドパークとは異なり、矢が的から外れることはないこととします)。筆者が回転ダーツに向かって矢を放つと、的の中のエリアのどれか一つだけに矢が刺さります。当たる確率は、的の各エリアの面積の割合と同じ。つまり、この人は40パーセントの確率で一番搾りを選び、30%の確率でサンナマを選び、20%の確率でマルエフを選び、10%の確率でプレモルを選ぶということです。消費者が商品棚の前に立つときには、脳の中でこんなふうに回転ダーツが回り、ランダムに意思決定が行われています。どうでしょう。意思決定を確率として理解するイメージはつきましたか。近年のマーケティング研究は数学(統計学)と密接に関わっていて、このような確率論的な意思決定を前提に様々なモデル(計算方法)が考え出されているのです。「いやあ、それでも納得できないなあ」と感じている方は、このように考えてみるのはどうでしょうか。
過去1年間のビールの購入履歴をすべて集計します。その結果を円グラフで表すと、一番搾り、サンナマ、マルエフ、プレモルがそれぞれ40%、30%、20%、10%ずつの割合になりました。さてこの人がきょうコンビニで買うビールは何でしょうか?……それは、この円グラフの割合と同じ分の確率で決まると考えられるでしょう。ひとまず「意思決定は確率で決まっている」と理解しておいてください。
確率はしばしば変動する
回転ダーツの的には各ブランドのエリアがあって、消費者の好み(プレファレンス)の順に区割り(塗り分け)されています。ですが、そのエリアの区割りは絶対不変のものではありません。時と場合によって、エリアの塗分けはしばしば変動します。代表的な例を3つご紹介します。
①商品の割引があるとき商品が定価よりも特別に安く販売されているときや、ポイントの形で割引が行われるときは、その商品を買う確率が高まり、ほかの商品を買う確率が下がります。「この商品限定で、今日だけポイント2倍」「レジにて30円引き」などが割引の例です。割引を知らせるポップが目に留まると、消費者の頭の中ではダーツの区割りがちょっと変わります。「普段はプレミアムモルツをあまり買わないけれど、今日は3本買って30円引きになるなあ」と頭の中で考えます。すると、プレミアムモルツのエリアがぐぐっと広がり、ほかの商品のエリアが狭くなるのです。確率も同様に動きます。
②的の中に新商品が加わるとき
これまで存在しなかった商品を新たに買うとき、新しい選択肢が的の中に追加されます。たとえばサントリー生ビール(サンナマ)の発売は2023年4月。それまでは一切飲んだことのない未知のブランドでした。つまり、的には「サンナマ」のエリアがない状態でした。発売日、筆者はたまたまスーパーの店頭で特売になっているサンナマを目撃します。そこで、的の中に「サンナマ」のエリアができました。「試しに飲んでみるか」と購入しました。飲んでみると、結構好みの味わいです。再び購入するようになりました。やはりいい。しかも、店頭ではしばしばキャンペーンのセールが行われているから選びやすい。このように「サンナマエリア」の面積はどんどん広がっていき、逆にこれまで大きな存在感のあった一番搾りやマルエフの面積は小さくなっていきました。
③特殊な状況で商品を選ぶとき
通常、商品は消費者が自分の好みで選んで購入するものですが、友人や親戚のために購入するなどの「特殊な状況」では話が変わってきます。ダーツの的の中にエリアを持っていなかった商品が、特殊な状況では一瞬だけ的の大部分を占拠してしまうのです。たとえば筆者はスーパードライの味があまり好みではないため、的の中にはスーパードライのエリアがありませんでした。しかし時折親戚や友人と会うときは、相手が好きなビールを手土産として持参することがあります。自分のためではなく相手のためにビールを買う場面では、しばしばダーツの的ががらりと姿を変えて、高い確率でスーパードライを選んでいるのです(スーパードライは日本で一番売れているビールなので、無難な選択肢です)。
このように的の中にあるブランドは、常に一定の割合を保っているわけではなく、商品を購入する場面によってしばしば変動することがあります。ただし、その変動の幅が変動するのは一時的なケースも多く、長い時間で見れば一定です。回転ダーツの区割りは、本質的にはそれぞれのブランドが「どれぐらい好きか」という割合によって決まっていることを思い出してください。スーパードライを購入したのは非常に特殊な状況でビールを選んだ「一晩の恋」であり、本当にスーパードライが好きになったわけではないのです。
回転ダーツで「当ててもらう」ためには
さて、ここまでの議論を一度おさらいします。人間の意思決定は「確率」によって決まっていて、商品を選び購入することはちょうど「回転する的に向かってダーツの矢を投げる(回転ダーツ)」ようなものだというお話でした。
そう考えると、消費者に自社の商品を選んでもらうためには二つの「関門」を突破しなくてはいけないことがわかります。一つ目は「選択肢の中に入れ」。そもそも、消費者が回す回転ダーツの選択肢(区割り)の中に私たちの商品が入っていなければ、選ばれることは決してありません。二つ目は「面積を広げよ」。仮に消費者の選択肢の中に私たちの商品が入っていたとしても、その割合が回転ダーツ全体のほんの一部に過ぎなければ、選んでもらう確率は非常に低いということです。逆に言えば、消費者の意思決定を思うように左右することも難しくはありません。消費者が買ってもいいなと思う選択肢の一つになって的(円グラフ)の中に登場し、その面積をできるだけ大きくしていけば、高い確率で購入してもらえるということです。すなわち世の中のマーケターたちは、消費者一人ひとりが持っている「脳内回転ダーツの的」の中で自社のブランドのエリアが一番大きくなるように、様々な施策を考えているのです(具体的な実務の姿は「実践編」にてお伝えします)。「選択肢」と「面積」という二つの関門を突破するための考え方について、もう少し掘り下げてみましょう。専門用語が登場しますので少し難しいかもしれませんが、実体験に即して考えれば理解がスムーズになると思います。
①「選択肢に入れ」
消費者の頭の中には常に、「買ってもいいな」と思うさまざまなブランドの組み合わせ(選択肢)があります。たとえば砂糖入りの炭酸飲料というカテゴリでは「コカ・コーラ、ファンタ、ペプシ、三ツ矢サイダー」といった商品が、消費者の頭の中に浮かびます。こうした「買ってもいいな」と思う選択肢のことを、専門的な用語で「エボークトセット」といいます。「(何も見なくても勝手に)思い浮かぶ」というのがポイントです。「(勝手に)思い浮かぶブランド」は普通、カテゴリーごとに3-5種類ぐらいしかありません。もちろん実際の店舗に設置された商品棚には、これらのエボークトセットに含まれていない様々な商品が並んでいます。消費者はまれに「冒険してみよう」と思って未知の商品を購入することがあります。でも、たいていは馴染みのブランド(エボークトセット)の中から選びます。馴染みのブランドなら「買って後悔した……」という事態を避けられるからです。
「選択肢に入る」とは、消費者一人一人の持っているエボークトセットの中に、自社のブランドを一つ追加してもらう……つまり、「最初の1回目に買ってもらい、評価してもらう」ということです。新商品を発売した企業のインタビュー記事などを読むとよく「1度でいいから試してほしい」と書かれていますが、「1度買ってもらわなければエボークトセットの中に入らないので、永久に買ってもらえない」危機感の裏返しでもあります。
新商品ではない定番商品でも、未購入の消費者が少なからずいるのならば、どうにかして最初の1回目を買ってもらわなければなりません。たとえば、資生堂から発売されている日焼け止めクリーム「アネッサ」は1992年の販売から30年が経過し、認知度も非常に高いブランドですが、今でもテレビCMや店頭広告に力を入れています(執筆時点で最新のCMでは、俳優の小松菜奈さんが出演しています)。しかしUVケア市場は競合製品がとても多く、「アネッサは知っているけど、買って使ったことがない」という人もまだまだたくさんいます。資生堂のマーケターはそれを理解しているので、すでに評価を確立したと思われるブランドであるにも関わらず、現在もアネッサの広告宣伝に注力を続けているのです。
②「面積を広げよ」
たくさんの消費者に1回目の購入をしてもらうことができましたとしましょう。1回目の購入を済ませ、実際に商品を使ってみた消費者は、善し悪しの評価を下します。購入者の何割かは「もう買わない」と考えますが、残りの消費者は「また買ってもいい」と思います。すると彼らの脳内にある回転ダーツの的の中には、晴れて私たちのブランドのエリアが設定されます。とはいえ、まだ消費者は商品を1回だけ買ってくれただけですから、エリアの面積はあまり広くありません。ダーツで当たる確率がまだまだ低いということです。では面積を広げていくにはどうすればよいのでしょうか。
少し話は遡りますが、ダーツの面積は「相対的な好意度(プレファレンス)」によって決まるという前提がありましたね。端的に言えば、回転ダーツの面積を広げるということは、「プレファレンスを高める」ということです。「プレファレンス」を英語で書くと「Prefer-ence」であり、日本語に直訳すれば「好み」。消費者自身は自分の言葉では説明できないかもしれませんが、様々な商品の体験を脳の中で処理し、「どの程度好みか」を評価して、その結果をダーツの的に反映させています。つまりプレファレンスを高める施策とは、「ブランドのことをもっと好きになってもらうための施策」にほかなりません。
ではブランドのことをもっと好きになってもらうにはどうすればよいのでしょうか。……実は、これは大変難しい問題です。人から好きになってもらうということを一つの法則のように説明することはできません。カップルの数だけ馴れ初め(恋のエピソード)があるのと同じです。異性に好かれたいからと言って、髪形を変えたり、ダイエットに励んだりするのは悪いことではありませんが、それらが恋を成就させる唯一の方法とはいえませんよね。人に好かれるために一番大事なことは、やはり相手ときちんと向き合って、相手のことをよく知り、相手の思いを想像し、相手のために自分が行動することです。
ブランドのことをもっと好きになってもらうための方法も同じです。商品を購入してくれた人や、これから購入してほしい人ときちんと会話をし、その言葉から思いを想像し、施策に落とし込むことが重要なのです。この本の最初に解説をした「リサーチ→コンセプト化→商品化」という、マーケットに向かうプロセスとも通じるところがあります。
ただし、どれほど人に好かれたいからと言って「相手の言いなり」になるのは良くありません。消費者に話を聞くと、たいてい「もっと安ければうれしい」とか「こんな機能がついていたらうれしい」といった感想が出てきます。ですがこうした声を単に鵜呑みにすると、競合商品との「違い」が見えなくなり、しまいには価格競争へ突き進むことになります。第1章と第2章で学んだように、商品を買ってもらうには「POD(ポイント・オブ・ディファレンス、差別化のポイント)」が必要です。消費者の声をそのまま採用するのではなく、いったん受け止めて、自分たちなりのPODを見つけ出すまで、徹底して考え抜くことが大切です。
ここまでの内容をまとめておきましょう。回転ダーツで「当ててもらう」ためには、まず回転ダーツの中に自社のブランドの「エリア」を設置してもらわなければいけません。それは「最初の1回買ってもらい、評価してもらう」ということです。続いて、より高い確率で商品を選んでもらうために回転ダーツの的に描かれたエリアの面積を広げることが重要です。そのためにはプレファレンスを高める必要があるということです。
(事例)人間の意思決定を「乗っ取った」PayPay
消費者の意思決定を(半ば強引に)操作して生き残ったサービスの一つに、ヤフーが提供しているQRコード決済アプリのペイペイ(PayPay)があります。2018年8月に提供開始された時点では、複数の競合アプリが先行していて、やや劣勢での参入でした(引用:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38955830U8A211C1EA6000/)

ペイペイがQRコード決済に参入するしばらく前、日本ではキャッシュレス化の推進が急務とさかんに議論されていました。諸外国に比べて現金への信頼の厚い日本人たちは、財布に現金を入れて持ち歩く習慣にほとんど抵抗がなく、キャッシュレス化の進捗が非常に遅いことが問題視されていたのです。「フィンテックに乗り遅れると、日本は再び国際競争に負けていよいよ大変なことになるぞ」という言説が当たり前のように飛び交っていました。今振り返るとなんだか大げさだったような気もしますけれども、それぐらいの切迫感があったのです。というのも、2017年はすでに中国や韓国で決済の9割がキャッシュレスに移行していました。その他の国々でもスマートフォンアプリを使った決済が世の中に浸透していましたから、金融行政上のさまざまな問題のために変化できない日本社会にたいして、度の過ぎた焦りがあったのかもしれません。それほど大きな議論を巻き起こしていましたから、日本でもキャッシュレス決済の市場が拡大するのは誰の目にも明らかでした。この表は、2014年から2018年にかけて市場に新規参入したQRコード決済アプリです。当時の最後発アプリだったことがうかがえます。ペイペイの提供開始から間もない2018年10月の調査では、ペイペイの認知度はようやく50%を超えたところ。QRコード決済というジャンルの中ではラインペイや楽天ペイ、d払いなどのライバルに大きく水をあけられていて、一刻も早い巻き返しが必要でした。
(引用:https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00089/00008/?i_cid=nbpnxr_child)

とはいうものの、QRコード決済を普及させるには相当の手間がかかります。たとえ認知度が高まりアプリのインストール数が増えたとしても、対応する店舗が多くなければ、利用者はいずれ離れていきます。QRコード決済市場で生き残るためには、競合サービスに比べてはるかに多くの中小零細企業にも協力してもらう必要があり、そのためには、国家規模でペイペイの利用を促進するほど決定的な一打が必要だ、というわけです。そこでペイペイのマーケターたちが考案したのが「100億円還元キャンペーン」。ヤフーが100億円の原資を用意して、利用者の支払い代金のうち20%をキャッシュバックするという、空前絶後の販売促進運動でした。従来のQRコード決済のキャンペーンの還元率は最大でも10%程度で、還元総額自体もそれほど多くありませんでしたから、このキャンペーンはメディアの関心を大いに集めることに成功しました。
何といっても、ペイペイで買えばあらゆる商品が「2割引き」という、特大バーゲンセールなのです。還元の上限は5万円と設定されていましたが、それでも「家電量販店で20万円のパソコンを買うと、4万円がもらえる……」もはや異次元です。新聞紙面はもちろん、連日連夜のニュース・ワイドショーの格好の材料となり、3か月分として確保されていた還元原資の100億円はわずか10日で底をつきました。期間中に170万人がペイペイを利用し、サービス開始から半年で利用者は700万人突破。藤井博文マーケティング本部長(当時)は「ソフトバンクグループの歴史を振り返っても、類を見ない早さで認知と利用者を獲得できた」と話しています。(引用:https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00159/00003/?i_cid=nbpnxr_index)
その後も高還元率のキャンペーンを続けたペイペイの利用者数は、きわめて高い伸び率で増え続け、2024年7月までに約6400万人を突破したと発表されました。日本経済新聞の調査では、2023年に国内でQRコード決済が行われた回数は93億回、そのうち7割弱の61億回がペイペイによって行われたと報じられています。(引用:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC179CN0X10C24A6000000/)
別の調査でも、「メインで利用しているQRコード決済」というアンケート調査で半数近くの人がPayPayを利用していて、トップシェアを握っている様子がうかがえます。
(引用:https://ecnomikata.com/ecnews/42590/)それではこの事例を踏まえて、一つ考えてみましょう。なぜキャンペーンからすでに5年が経過してもなお、ペイペイはQRコード決済の王者で居続けることができているのでしょうか。たしかに、提供開始時は最後発のアプリだったペイペイが、ユーザー獲得競争を勝ち抜くために「100億円還元キャンペーン」を実施し、メディアの関心を集めて、国家規模の利用促進を成功させたことは事実です。ですが一度にたくさんのユーザーを獲得したからと言って、ユーザーがその後も数年にわたり継続してサービスを利用してくれるとは限りません。2023年7月、フェイスブックを運営するメタ社は、イーロン・マスクさん率いるX(旧ツイッター)へ対抗するアプリとして「スレッズ」を発表しました。スレッズの利用者数は、提供開始からわずか5日で1億人を突破するという驚異的なスピードで伸びていましたが、7日目にはアクティブユーザー数(実際にサービスを使っている人の数)が半減したと報じられています。一時の話題をさらうだけでは、継続してサービスを利用してもらうことはできないのです。また、ペイペイが初回のような異次元レベルのキャンペーンを連発してきたわけでもありません。「100億円還元キャンペーン」の後も大がかりなキャンペーンは何度もありましたが、その規模は徐々に縮小しました。そもそも百億規模のキャンペーンは何度も連発できるものではありませんし、あからさまに「大金で顧客を釣る」という手法を繰り返すことは企業本体の経営に深刻な悪影響を及ぼします。利益率を圧迫するにとどまらず、実際に現金が流出するためキャッシュフローも悪化します。株主が黙っていません。さらに言えば、競合も厳しい対抗措置を講じてきました。アプリの楽天ペイやd払い、ラインペイは「100億円還元キャンペーン」を受けて、後を追うように同様のキャンペーンを連発し、顧客の獲得競争は激しさを増す一方した。そういうわけですから、大規模なキャンペーンを成功させてから5年も経過した現在でもなお、ペイペイが高いシェアを維持していることには、単に「キャンペーンでメディアへの露出に成功した」以上の理由があると考えられるのです。ここで、本章の前半で、人間の意思決定が回転ダーツによって行われるという解説を思い出してみてください。人間は何かを選択するときに、頭の中でいくつかの選択肢の書かれた回転ダーツをくるっと回し、ダーツの当たった選択肢を選ぶというお話でした。回転ダーツを用いて説明するならば、次のようになります。「ペイペイは最初の「100億円還元キャンペーン」のときに大量のメディア露出を確保することで、多くの消費者の脳内にある的に「ペイペイ」というエリアを作らせた。当時はまだQRコード決済市場が小さかったため、ペイペイだけでなく競合サービスを含め、利用者は少なかった。また、登録店舗もそれほど多くなかった。したがって、ペイペイは認知度を高めるだけで、多くの消費者のエボークトセットの中に入ることができた。また、ペイペイは小規模事業者の支払手数料を0円とすることで大量の事業者を獲得し、さらに高額なポイント還元キャンペーンによってペイペイを使うことを推奨し続けた。こうして消費者の頭の中に「ペイペイ=便利でポイントがたくさんたまるお得な決済サービス」という連想を作り出すことに成功した。消費者それぞれがもっている回転ダーツの的の上では、「ペイペイ」の面積だけがどんどん広がり、ほかのブランドの存在感は埋没。とうとう脳内にある的を「ペイペイ一色」に染め上げ、人間の意思決定を「乗っ取った」。」
この規模のマーケティングは大半の企業にまねできるものではありませんが、ペイペイのマーケターたちの考えていたことは基本に忠実であり、学ぶところが多くあります。市場で成功を収めるためには消費者の意思決定に深く関与することが重要だということを理解し、エボークトセットの中に入り込み、プレファレンスを高めて圧倒的な存在感のブランドを作った、歴史に残る事例でした。
プレファレンスを高める「ブランドエクイティー」
経営学者の楠木健先生は、著書やインタビューでしばしば次のように述べています「経営には自然科学のような法則はない。しかし論理はある」。マーケティングにも、地球上のあらゆる場面で一般的に通用する「運動方程式」のようなものはありません。しかし「何かをすれば、状況はこう変化するだろう」と考えることはできます。たとえば「テレビに広告を出稿したら、視聴者の一部は商品に興味を持ってくれる」という、矛盾のない予想です。そのように考えた事柄を鎖のようにつなげていくと論理が出来上がります。先に述べた通り、ブランドをもっと好きになってもらう「法則」はありません。ただしプレファレンスに影響を及ぼす要素を掘り下げてみると、ブランドをもっと好きになってもらう「論理」は見えてきます。森岡毅さんの著書『確率思考の戦略論』によれば、プレファレンスに影響を及ぼす要素は3つしかありません。「価格」「製品パフォーマンス」「ブランドエクイティー」の3つです。一つずつ見ていきましょう。「価格」は、商品に付けられている値段そのものです。当たり前ですが、価格の安い商品のほうが、高い商品よりも購入しやすいですよね。ですから「価格」はプレファレンスに影響を与える要素の一つです。「製品パフォーマンス」とは、商品の機能のことです。同じ値段の商品であれば、より機能が優れているほうが選ばれるということです。もし一般的な洗濯機とドラム式全自動洗濯機が同じ値段で販売されていたら、ほとんどの人はドラム式洗濯機を選ぶようになるでしょう(家の間取りや搬入経路など個別の問題は考慮しないこととします)。ところが、「価格」や「製品パフォーマンス」の改善によってプレファレンスを高めることには、問題があります。たとえば、価格を下げるとその瞬間は売上が向上するものの、消費者はすぐに値段を当然のことと受け入れてしまいます。しばらくすると「安物のブランド」「いつも安売りするブランド」だとみなされ、定価で販売したり値上げをしたりすることが従来よりも一層難しくなります。価格を変更することでプレファレンスを向上させる施策には、一時的な効果と、大きな副作用の二面性があります。見過ごすことのできない問題です。「製品パフォーマンス」の改善にも限界があります。代表的な例はかつての家電の王様、テレビです。テレビが普及し始めたころ、テレビには「電波を拾ってモノクロの映像を画面に映す」機能しかありませんでした。それから徐々に高機能化が進み、カラー映像の表示やリモコン操作への対応、外部機器との接続、デジタル放送への対応、など機能が追加されていきました。ところが、この10年ほどのテレビに機能面で大きな変化は感じられません。もちろん細かい話をすればたくさんの機能が増えていますが、利用者は気づいていません。必要のない機能をたくさんつけても、プレファレンスは向上しないのです。多くの消費者は今のテレビにおおむね満足していますから、これ以上製品パフォーマンスで差別化するのは難しいでしょう。製品パフォーマンスの改善自体が難しい商品もあります。究極は「水」です。各社が販売している「いろはす」(コカ・コーラ)、「南アルプスの天然水」(サントリー)、「エビアン」や「ボルビック」(いずれも仏ダノン社)をコップに注ぎ、目隠しをして飲み比べてみてください。ソムリエでもなければ、違いはまずわかりません。ともすれば水道水との違いさえ分からないと思います。一般消費者にとって、水は水でしかないのです。「価格」依存もだめ。「製品パフォーマンス」依存もだめ。すると、プレファレンスに影響を与える3つ目の要素「ブランドエクイティー」が重要な意味を帯びていることがわかります。ブランドエクイティーは、一般的に「ブランド力」と呼ばれているような、ブランドの持つ目には見えない不思議な力のことです。「エクイティー」という言葉は日本語で「資産」という意味であり、「ブランド」には、事業を有利に進めるための経営資源(無形資産)のような意味があるという趣旨で「ブランドエクイティー」と呼びます。
ブランドエクイティーこそ、プレファレンスに多大なる影響を与えるものの正体です。
ブランドエクイティーがいかに顧客の購買行動を左右するのか、実際の商品の例で学んでみましょう。以下に、「定番」と呼ばれる8つのブランドを並べています。それぞれのブランド名を見て、脳裏にぱっと浮かんだものや、感じたものをメモ書きしてみてください。単語の羅列でもかまいません。
-
コカ・コーラ
-
おーいお茶
-
ポカリスエット
-
キユーピーマヨネーズ
-
カゴメトマトケチャップ
-
マクドナルド
-
吉野家
参考までに、筆者はこのようなことを想像しました。
-
コカ・コーラ:クリスマス、赤いマフラー、プシュ、シュワー、くびれたボトル、夏フェス、ビーチ、水着、ホースから噴き出す水
-
おーいお茶:大谷翔平、茶畑、茶摘み、静岡、緑色、農作業、麦わら帽子、ひまわり
-
ポカリスエット:青春、青、黒髪の女子高校生、制服、走る、青空と入道雲、熱中症、かぜ
-
キユーピーマヨネーズ:キユーピー人形、おもちゃの兵隊の曲、愛は食卓にある、白と赤の模様、キユーピーハーフ
-
カゴメトマトケチャップ:トマト、トマト畑、トマト缶、ビニールハウス、トマト農家、トマトジュース
-
マクドナルド:M、子供のころ一番楽しかった場所、ハッピーセット、おもちゃ、月見バーガー
-
吉野家:はやい、やすい、うまい、牛肉薄切り、独身、スピード、仕事の限界
もうお気づきかと思いますが、このように「ブランド(ブランド名、ロゴ、パッケージなど)」を目にした瞬間から、脳の中には猛烈な勢いで様々な連想が浮かび上がります。この「連想させる力」こそがブランドエクイティーの威力です。「連想させる力」を持てるブランドと、持たざるブランドは圧倒的な力の差が生じます。端的に言えば、持てるブランドほど売れ続け、持たざるブランドは認知の獲得に苦労します。一般に「定番商品」と呼ばれている様々な商品は、とても強硬なブランドエクイティーを持っています。それゆえにプレファレンスが相対的に大きくなり、競合品や代替品の猛追にもびくともしない「優位性」を持つのです。こうした商品は、値引きをしたり製品機能のアップデートをいちいち行ったりしなくても、常に売れ続けます。どうでしょう。あなたの商品はブランド名こそついているかもしれませんが、顧客に「連想させる力」を与えるほどのものになっているでしょうか? もし顧客から「定番」と言われるブランドがあるならば、それはブランドエクイティーができている証しと見て差し支えありません。
ブランドエクイティーを作り上げることを「ブランディング」といいます。そしてブランディングこそプレファレンスを最大化する施策なのです。
※ただし、近年のブランディング支援業者の仕事は単に「デザイン」を言い換えただけのも少なくありません。ロゴを作ったりイメージカラーを決めたり、WEBサイトを作ったりすることを「ブランディング」と呼んで代行する業者は数多くありますが、肝心の「プレファレンス」を高めるものでなければ何の意味もありません。皆さんの周りに、ロゴマークやスローガンを一新してテレビCMや新聞広告などでアピールしている企業を見たことがあるでしょう。しかし、それによって好意度は変化していますか(そのブランドのことを、今までよりももっと好きになりましたか)? もし好意度が変わっていればブランディングは成功ですが、「単にリニューアルしたんだな」と思われただけならば、その変更は全く役に立っていません。ブランディングとは本質的に、ブランドエクイティーを形成することでプレファレンスを高めるものでなければならないのです。
それでは、本来の意味でブランディングを実施したいときに、どのような考えをすることが重要なのでしょうか? これも簡単な問題ではありませんが、一つだけ言えることがあります。森岡さんの言葉を借りれば「本能にぶっ刺されば、当たる」。どれほど理性が発達したとしても、人間はしょせん動物です。動物的な欲望(本能)から逃れることができません。また、経済活動という人間の行為自体が、商品を購入することで自身の欲望を満たすものです。商品を作ることや販売することは、消費者の「本能」の動きを察知して、適切に理解し、自分たちなりの提案としてまとめ上げることといえます。これは、「リサーチ→コンセプト化→商品化」という本書の提案するマーケティング過程にも通じるものです。
ですから、「定番商品」と呼ばれるような高いプレファレンスを形成するほどのブランドエクイティーを作りたいのであれば、商品を販売したい相手の「本能」を深く洞察し、それに即した提案として「ブランド」を用意しなければいけません。第4章では、「本能にぶっ刺さる」ブランドエクイティーを作る方法を解説しています。引き続きよろしくお願いいたします。
Views: 0



