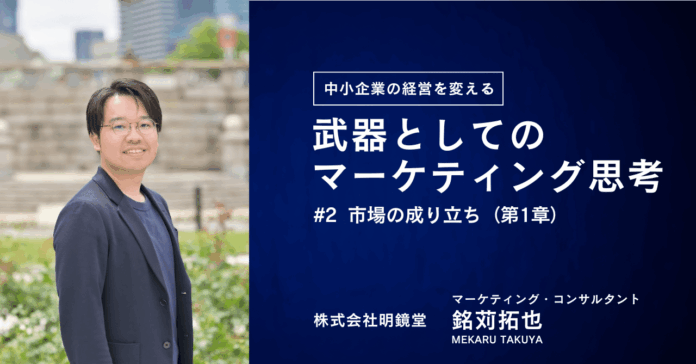🧠 概要:
概要
『武器としてのマーケティング思考』の第1章では、マーケティングの歴史とその重要性について述べています。著者の銘苅拓也は、マーケティングが商売を成功に導くための重要な考え方であり、古代から現代にわたる経済史を通じてその本質を理解することが重要だと強調しています。特に、製品の「違い」を創造することの重要性を論じ、価格競争を避けて持続可能な利益を確保するための戦略についても触れています。
要約(箇条書き)
- マーケティングは人々の認識が異なる広範な概念だが、商売を成功させるための考え方として共通している。
- 人類は物々交換から始まり、約1万年前に市場の概念が登場した。
- 18世紀に「経済学」が誕生し、市場メカニズムが体系的に解明される。
- 市場メカニズムでは、同一商品間での価格競争が利益を圧迫する。
- 商品の違いを認識させることによって、価格競争から逃れることができる。
- 古代の商人の事例を通じて、マーケティングの歴史的な理解が重要。
- 企業が利益を出せない状況に陥るのを避けるためには、「違い」を作ることが不可欠。
- 次章では「違いをつくる」ための具体的な方法が解説される予定。
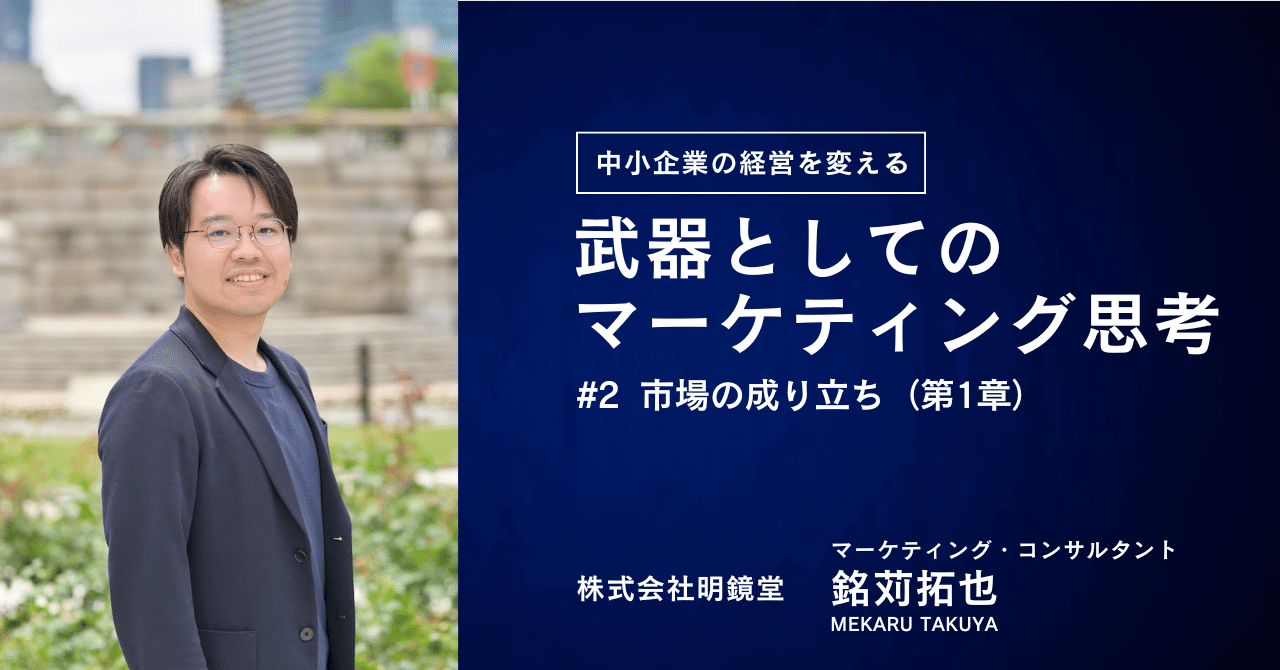
「はじめに」で述べたように、マーケティングは幅広い概念で、人によって捉え方が大きく異なります。しかし、少なくとも「商売をうまくやっていくための考え方」という点では、認識は一致しているはずです。なぜなら、人類の歴史は商売とともにあり、市場(マーケット)が存在する場所には、常に「マーケティング」の考え方が存在してきたからです。この章では「人類の経済史」という大局的な視点から、現代の複雑化した「マーケティング」論を整理し、本質を理解することを目指します。マーケティングは一般に20世紀に生まれた概念だと考えられています。しかし、歴史を紐解くと、人類は古くから市場でマーケティング活動を行ってきました。
私たちの祖先は約1万年前、物々交換という方法を見出し、生活を豊かにすることを学びました。人類最初の取引形態は「剰余物の交換」でした。これは、自分の余剰品を他者と交換し合う、現代のメルカリに似た取引形態です。ただし、当時はアプリのような便利なツールはなく、人々は直接出会って物を交換する必要がありました。条件の合わない取引は成立せず、新たな取引相手を探さなければなりませんでした。そのため、当初は交換を望む者同士のマッチングは非常に困難だったでしょう。しかし、ある発明によって取引は大きく効率化されました。それが「市場(マーケット)」です。
マーケットを分析する学問「経済学」
さて時代は18世紀の英国に飛びます。この時代、世の中の様々な仕組みを科学的に解明しようという機運の中で、「経済学」という学問分野が誕生しました。経済学者たちが解き明かそうとしたのは、物の値段が決まる仕組み(市場メカニズム)でした。彼らは様々な研究の末、一つの真相にたどり着きます。
-
完全競争市場では、商品の価格は一つの市場価格に向かって下がり続ける。そしてその価格は、企業が利益を上げられない水準にまで低下してしまう。
少し難しい話なので、トマトを例に考えてみましょう。市場でトマトを1個500円で売っているAさんがいるとします。新たに参入したBさんは、同じトマトを400円で売り始めます。すると当然、より安いBさんのトマトが売れていきます。Aさんは対抗して300円まで値下げします。今度はAさんのトマトが売れるようになります。このように、市場で同じ商品を売る人たちは互いに価格を下げ合う競争(価格競争)を行い、最終的に利益がほとんど出ない水準まで値段が下がってしまいます。この同じ商品の価格が自然と下がっていく仕組みを「市場メカニズム」と呼びます。消費者の視点からすると、商品価格が自然と下がることは大きな利点です。より安価に買い物ができれば、その分を他の商品の購入に回せるため、生活の質が向上します。一方、企業にとって価格競争は深刻な問題です。商品の値段が利益を出せない水準にまで下がってしまうと、事業を継続できなくなってしまいます。では、どうすれば良いのでしょうか。物の値段が下がる仕組みをもう一度確認してみましょう。「同じ商品の価格」は、最終的に一つの価格に収束するまで下がり続けます。しかし、これを逆の視点から見ると、「商品が異なる」と認識されれば、価格競争を避けることができます。つまり、「このトマトとあのトマトは違う(だから値段が高い)」と顧客に理解してもらえれば、価格競争から抜け出せるのです。例えば「あのトマトは一般的な農法で作っているが、こちらは有機栽培のトマトだ」というように差別化するわけです。
市場メカニズムが学問として体系的に解明されたのは18世紀以降でしたが、古代の商人たちは、この市場の仕組みをすでに経験から理解していました。
楚国の商人のマーケティング手法
中学校の教科書でおなじみの「矛盾」という言葉の由来となった故事を覚えていますか。楚の国のある商人が、「この盾はどんな武器でも貫くことができない最強の盾です」「この矛はどんな盾でも貫ける最強の矛です」と、相反する売り文句を呼びかけたところ、聴衆からその矛盾を指摘される話です。興味深いのは、商人が単に「盾を欲しい人はいませんか」と声をかけるのではなく、その盾がほかの物よりも優れているという「違い」を強調しているところです。もし「盾を欲しい人はいませんか」という呼びかけだけをしてしまうと、市場にある他の盾と値段が比較され、より安価な盾が選ばれてしまいます。この市場メカニズムに対抗するには、商品が比較されるのを防ぎ、「別物」として認識させる必要があります。商人の行動は(嘘をつくことは別として)、市場の仕組みを見事に理解したものと言えます。この物語が紀元前3世紀ごろに書かれたことを考えると、なおさら驚きです。本書では次の章以降、マーケティングを具体的に実践するための思考法について解説します。その中で最も大切にしていただきたいのが、この「違いをつくる」という姿勢です。どの商品も、消費者から「違い」が見えなくなった瞬間、まるで市場メカニズムに導かれるかのように価格競争へと突入してしまうのです。かつて「メイド・イン・ジャパン」が世界を席巻していた時代、日本は液晶テレビやノートパソコンなどの高額な電化製品を世界中に輸出していました。しかし、中国や韓国のメーカーの技術が一定水準に達すると、市場は急速に低価格競争に陥りました。最先端の技術を駆使した優れた商品でも、消費者に「違い」が明確に伝わっていなければ、より単純な技術で作られた安価な商品に市場を奪われてしまいます。総合電機産業が海外勢の激しい競争にさらされる中、新たな活路を見出せなかった電機メーカーは、最終的に海外企業に買収されたり、事業を分割して売却されたりする結果となりました。「違い」をつくれないことは、価格を自由に設定できないことを意味し、結果として利益を生み出せなくなります。利益を出せない事業は、必然的に破綻への道を歩むことになります。市場メカニズムは、実際のところ恐ろしい仕組みなのです。この市場メカニズムに立ち向かい、事業を継続できるだけの利益を長期的に確保するには、その根本に「違いをつくる」という発想が不可欠なのです。
では、「違いをつくる」ための具体的な方法について、第2章で詳しく解説していきます。これからマーケティングの実践的な思考法が次々と登場しますので、ご期待ください。
Views: 0