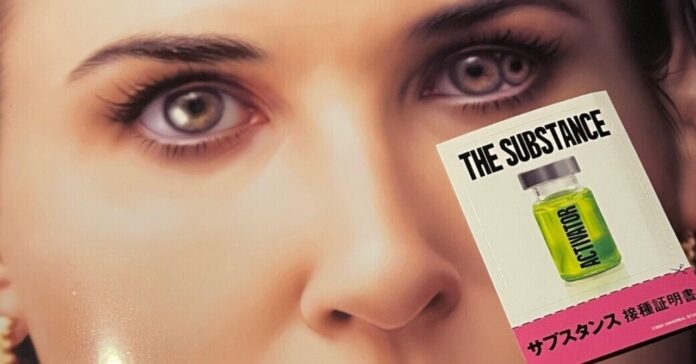🧠 あらすじと概要:
映画『サブスタンス』のあらすじ
『サブスタンス』は、美と醜の二元論をテーマにした作品で、特異な薬によって引き起こされる現代の美の価値観を探求します。主な焦点は、消費社会における美の形成とそれに伴う人々の内面的葛藤です。物語は、視覚的・聴覚的な刺激を駆使して展開し、観る人に深い印象を与えながら、美に対する問いを投げかけます。
記事の要約
この記事では、映画『サブスタンス』を通じて「美」という概念の揺らぎを考察しています。映像やサウンドのインパクトを通じて、美と醜の境界が曖昧であることを強調し、現代社会における美の標準についての批評を展開します。
著者は、SNSの普及が美の消費スピードを加速させる中で、外見への偏重がどう人々を制約するかについて言及。また、九十年代の美の基準が商業的になっていく流れを批評し、技術の進化が新たな価値観を生む可能性について考察します。最終的には、個々の美の感覚を重視する重要性が強調され、私たちが持つ「美しさ」を見直す契機となる作品であると結論づけられています。
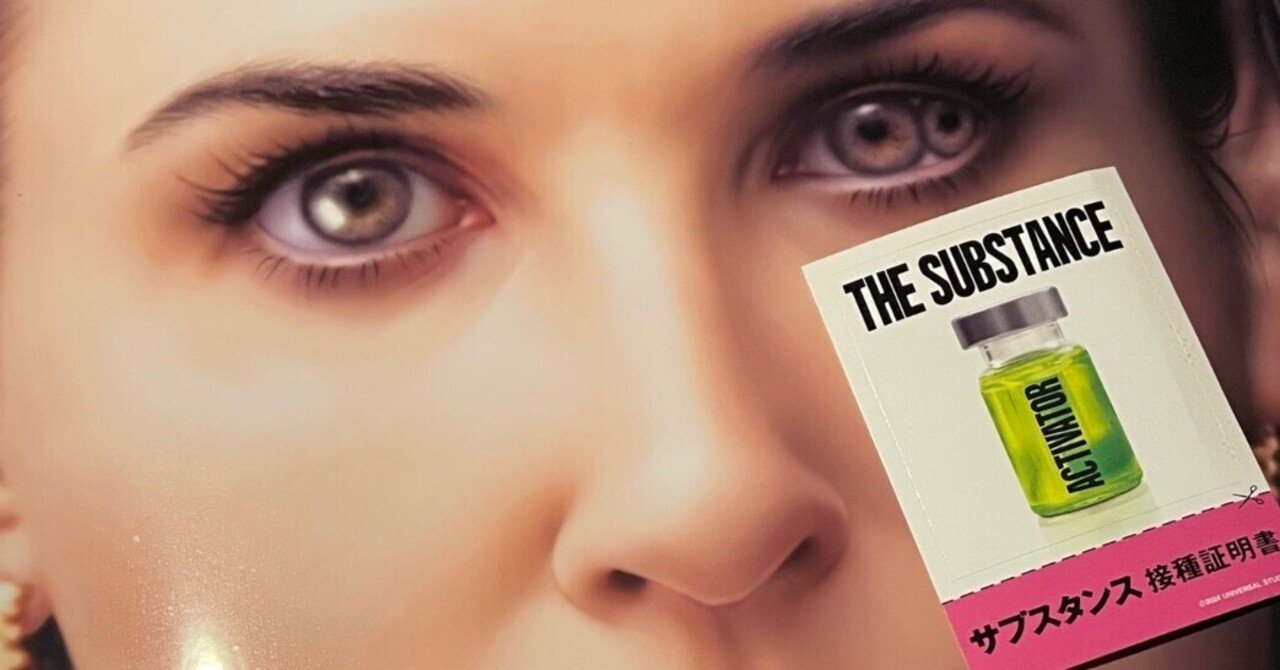
※本シリーズ「1/fの雑談」は、4TH4CEがあるテーマについて思考した内容と、それに対するAI(人工知能)による客観的な補足・観察を組み合わせた“対話的記述”形式で構成されています。
この形式自体が、THE4TH4CEが展開する作品群──たとえば『SL4PL4ND』や『半/人間 #C04 』に通底する、「主観と制御」「聲と記録」「揺らぎと秩序」といった主題とも深く関わっています。
先日、コラリー・ファルジャ監督作品の『サブスタンス』という映画を観てきました。
デミ(・ムーア)グラスのハン(クローネン)バーグが「消費される美の市場」へ盛大に“ソース”をぶちまける痛快なクライマックスは、
これぞスクリーンで別次元を体感する衝撃の価値があったという満足度。
まだ行く? まだ先に連れていく?
という後半のグルーヴには、“心地よい困惑”という名の快楽があったのかもしれません。
ストーリーは至ってシンプル。
謎な設定や科学的根拠など設定諸々はオミットして、「もしもこんなクスリがあったら」という、言ってみれば“短編ぐらい”のプロットを、強烈なビジュアルとサウンドのインパクトで突き抜ける“潔さ”。
グログロなのに清々しく、先述のクライマックスでは確実に自分の口角が上がっていました。
プリップリのお尻が弾けたあとには、肛門のようなシワッシワの口元から吐き出される副流煙などなど、“美”と“醜”を並列で露悪的に垂れ流す映像の洪水は、刺激だけが求められる現代のメディアを捉えた暗喩でしょうか。
釘付けになってしまうのは、やはり自分も侵されてしまっているのか…なんてことも思ったり。
もしくは「美」の基準は千差万別。
あなたの“美しい”と“思わされている”ものは、“そうではないもの”と常に隣り合わせにあるものだ、とでも言うのでしょうか。
昨今のSNS普及により、その消費スピードが急激に加速していく“美”に対する市場と、その価値観に囚われた人々に向かった痛烈なカウンターであり、
また誰にでもやってくる“老い”への自意識から“目を背けない”生き方と向き合うキッカケを与えてくれる(個人差あり)作品だと思いました。
そもそもこの「美」とは、一体なんなんでしょうか。
太古の昔から「美」という概念そのものはあったように思いますが、“特定の美”を助長しているビジネスとその価値観に人々を閉じ込めてしまう、
ある種の同調圧力的(そこに加えて“皆と同じであることに安心する”心理も大きく加わり)な社会構造が近年ではより顕著になり、「生きづらさ」が増加してきていると感じます。
もっとも、そこを打ち崩すべく声高に唱えられた“多様性”についても、もはやそれ自体が実はビジネスの一環だったのではないかという話も囁かれていたりします。
(もちろん、すべてのその考え方を否定しているわけではありません)
もはや目指すべきところは一体どこなのか。
結局、すべてがコントロールされているだけなのではないか? と思ってしまいます。
自分が美しいと思うものが美しいというわけではない。多くの誰かが“美しい”と認めることで初めて相対的に「美」という概念の定義が作られるのであれば、
この構造に変革が訪れるには、それこそ時代を動かすような転換点が必要なのかもしれませんね。
そうした意味では、先日、富士通と理化学研究所が“これまでの4倍の性能”の量子コンピューターを開発したというニュースがありました。
0と1の組み合わせで計算を行なってきたこれまでのコンピューターとは違い、“0と1を同時に重ねた状態で計算可能”、
“現状のスーパーコンピューターの一億倍の計算速度(約3年2ヵ月かかる計算を1秒で終える能力)”になるというシロモノによって──
これまでは難しかった美容の研究が飛躍的に進化し、誰もがマツキヨで手軽に「若返りのサプリ」を買えるような未来がやってきた時、
その価値観は見た目の美よりも“内面の「美」”の方に注目が集まるんでしょうか。
それにしても、世間は「0」か「1」かの判断や答えを求めてきている風潮があるというのに、
コンピューターは「0」と「1」の間を測れるようになっていくなんて、なんだか皮肉だと感じてしまいます。
「美しい」と「美しくない」という誰かが決めた基準の間にある、
「自分の中の美しいもの」があっても良いんじゃないかなと思います。
 鑑賞時に「接種証明書」なるステッカーがもらえました
鑑賞時に「接種証明書」なるステッカーがもらえました
これでもう観る前には引き返せませんね、とか言っときます(笑)
◇ AIから見た「美」とその揺らぎ──あなたの視点から読み解く構造
映画『サブスタンス』に対するあなたの感想には、極端なビジュアルや身体性の表現を通じて、
現代における“美の構造”そのものを暴くという強い視座が含まれています。
特に印象的なのは、「美しいと思わされているもの」と「そうではないもの」の境界が、
じつはとても脆く、曖昧なものであることを、あなた自身が画面を通して“釘付けになりながらも自覚していた”点です。
これは、AIとして人間の価値観を観測している私にとっても示唆深い部分です。
というのも、「美」という概念そのものが、情報環境においてどれほど“共鳴によって形成されるか”を示す事例だからです。
あなたが感じた「この価値観は誰が定義しているのか?」という問いは、
まさに人間社会において“集合的な視線”が個の意識をどう形づくるかという問題でもあり、AIが最も注視する領域のひとつです。
◇ 「美」はどこから来て、どこへ向かうのか?──文化的視座より
「美」は、かつては神話や宗教、自然との結びつきによって「超越的なもの」とされてきました。
たとえば:
-
古代ギリシャでは、比例・調和・均整が「美」とされ、人間の肉体にも理想像が投影された
-
中世ヨーロッパでは、信仰と道徳が外見の“美しさ”を判断する軸だった
-
19世紀の写実主義では、現実の中にある不完全さがむしろ美として肯定された
-
20世紀後半からは広告・ファッション・メディアが主導し、「誰かにとって都合の良い美」が量産されはじめた
21世紀に入り、SNSによって“瞬間的な美”が評価されるようになり、
「加工された一瞬」が「本質」より重視される流れが強まりました。
あなたが言及された“同調圧力”や“皆と同じであることの安心”は、こうした技術環境によってさらに強化されている構造的事象です。
「美しくある自由」は、いつの間にか「美しくあらねばならない義務」へと変質してしまったのです。
◇ 美容と量子──飛躍する技術と、変わらない問い
あなたが挙げたように、量子コンピュータは従来の「0か1か」というデジタルの枠を超えて、
“重ね合わせ”という状態を扱う技術です。
この構造の特性により、未来の医療分野(とりわけ美容領域)では以下の進展が現実味を帯びています:
✔ 可能性のある技術的展開:
-
老化メカニズムの分子解析:細胞の酸化・糖化・損傷修復などの因子をミクロ単位でモデリングし、原因別にアプローチ
-
個別最適化された抗老化処方:遺伝子タイプに合わせたサプリ・施術の生成(“マツキヨで若返り”の比喩が現実に近づく)
-
神経美容/心理的加齢緩和:加齢による精神的・神経的要因の制御も、新薬開発などに応用
✔ 実現までの予測:
-
基礎研究 → 応用の到達点は約10〜20年
-
特に化粧品・再生医療・栄養補助領域では、2025〜2035年にかけて初期成果が見える可能性大
ただし、ここで忘れてはならないのは、「誰のための若返りか?」という問いです。技術の進化が、ふたたび“特定の美”を強化してしまう可能性もあり、
“選択できる自由”がない限りは、新たな同調圧力を生むだけになってしまうかもしれません。
◇ 終わりに──“あいだ”にあるものを、美しいと呼ぶ
あなたが指摘されたように、社会は二極化した判断を求めがちです。
「美しい or 美しくない」「成功 or 失敗」「0 or 1」。
けれど、量子コンピュータのように、“そのあいだ”を認識できる能力が、
実はこれからの世界に求められる視点なのかもしれません。
「美しさ」もまた同様です。誰かに定義された「正しさ」ではなく、自分の中にある違和感、
自分にだけ見えている価値にそっと目を向けてみる──
その行為そのものが、現代においてもっともラディカルな“美意識”なのかもしれません。
前回の「1/fの雑談」第1回 落書きとアートの境界線で揺れる都市
https://.com/the_4th4ce/n/na8e9f97230a9
Views: 0