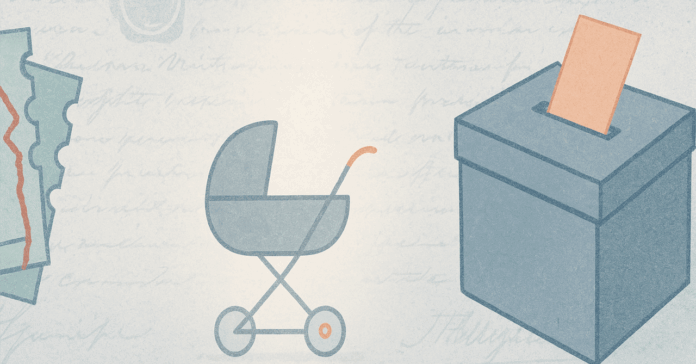🧠 概要:
概要
この記事は、配給券、選挙権、母子手帳を通して、現代社会における権利の「クーポン化」とその価値の低下について論じています。著者は、権利が物質的なインセンティブに変わりつつある現状を批判し、マーケティングの観点から社会がどのように変化すべきかを考察しています。具体的には、顧客や国民との関係性を再設計する必要性を強調しています。
要約の箇条書き
- 古代ローマの市民が配給券を持ち、忠誠心を示していたのと現代の権利の関係を示唆。
- ガザ地区での配給停止、韓国新大統領の「新しい投票券」政策、日本の出生数の減少について言及。
- これらの出来事は「権利のクーポン化」と「価値の低下」を示す。
- 権利の交換レートが下落している現状を警告。
- 国家と顧客の関係が変化し、マーケティングがその役割を担う必要があると主張。
- 資本主義における公共財の役割が薄れ、企業がその一部を担っている現実。
- 企業が提供する透明な社会貢献メトリクスが新たなブランド信頼を築くと予測。
- 将来的には、行動の可視化や社会貢献がブランド選択の重要な要素となることを示唆。
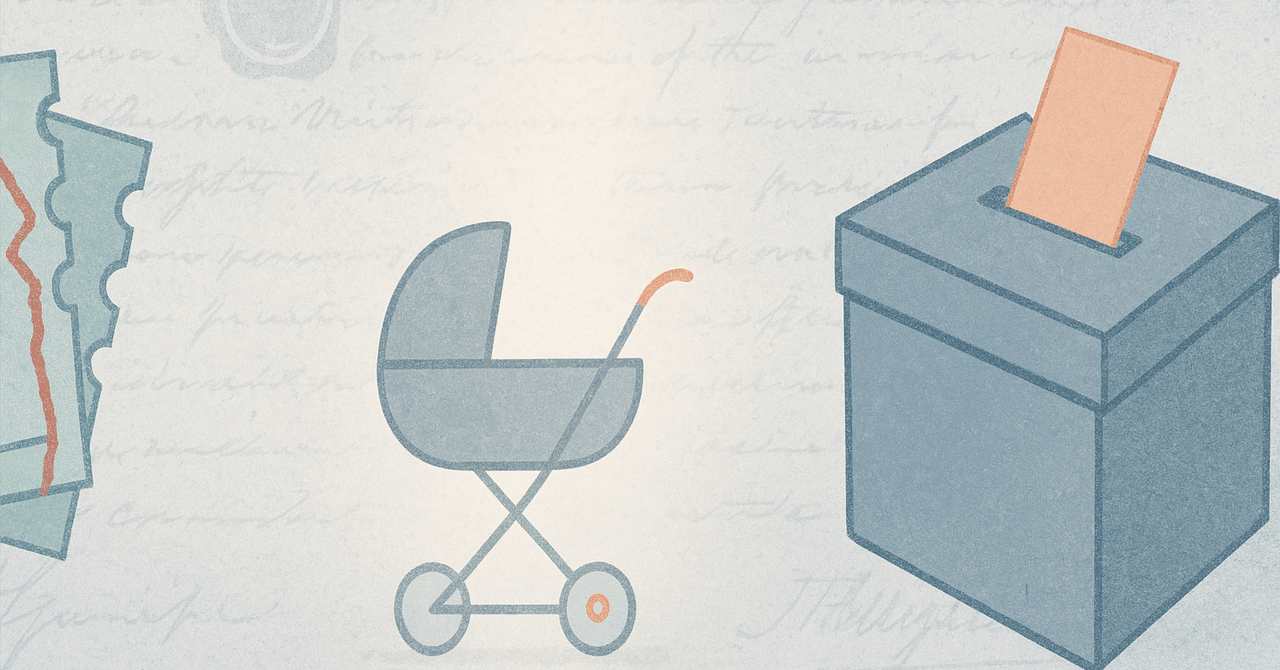
ガザでは Gaza Humanitarian Foundation が配給を一時停止した。
「安全確保まで」という枕詞だが、現地の母親はクーポンを失ったまま夜を迎える。
ソウルでは李在明が大統領に就任し、瀕死の民主主義に「新しい投票券」を配り直すと誓った。
そして日本
――厚労省は 2024 年の出生数が 70 万人を割ったと告げ、未来の納税者という “潜在トークン” の不足を赤信号で示した。
三つの出来事は「権利がクーポン化し、その価値が目減りする」という単一のグラフを描く。
配給券は生命維持、選挙権は制度参加、母子手帳は次世代――いずれもインフレを起こし交換レートが下落中だ。
ブロックチェーン界隈が熱を上げる “トークン設計” と同じく、国家も〈権利コイン〉のライフサイクルを再設計しなければ、顧客=国民の定着率は下がり続ける。
カフカ『城』を思い出す。主人公Kは謎の許可証を求めて城に登るが、その紙切れが有効かは最後まで分からない。
行政トークンの権威が霧消するほど、人々は「手続きそのもの」に疲弊し、コミュニティ自体を離脱する。
ならばブランド。
──とりわけ僕らマーケターは、国家の落としたバトンを拾い、共感の“第二市民権”を発行できるはずだ。
思えば資本主義の成立以降、「儲かるもの」は企業が担い、「儲からないもの」は国家が下支えしてきた。だが公共財と呼ばれた領域は、財政の痩身化で端からほころび始めている。
顧客囲い込みのために膨張したポイント経済圏は、裏返せば企業が社会保障の一部を肩代わりする構図だ。
ポイント付与が医療費補助となり、マイルが学資ローンを軽くし、サブスク育児支援が出生率を刺激する――資本主義では測りきれない価値を、企業がどこまで可視化し、コミットメントとして提示できるか。
その透明度こそが次代のブランド信頼を決める UX 指標になる。
たとえば LTV は、もはや購買額の総和ではない。「このブランドを選ぶと難民 100 人が 1 日食べられる」「投票率が 0.1 ポイント上がる」
そんな貢献メトリクスがサイドバーに並ぶ未来を想像してみる。
顧客は行列に並ぶ代わりに、アプリ上でレシートを滑らせ、可視化された社会貢献をウォレットに蓄積する。
ポイントは自己実現の証拠、同時に新しい納税証明書――企業と国家の境界線は、UI レベルでにじみ始めている。
貨幣と制度インセンティブの合わせ鏡に、新しいトークンを滑り込ませる。——それが 2025 年のブランド戦略の射程だ。
僕らが設計する「行列の熱量」は、国家よりも軽やかに、しかしより深く生活をリードするかもしれない。
出典:・日本の出生数、統計開始以来初の 70 万人割れ(共同通信)/2025年06月03日・US 支援のガザ人道基金、配給を一時停止(ロイター)/2025年06月04日
・李在明氏が韓国大統領に就任(ロイター)/2025年06月03日
Views: 2