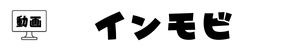🧠 概要:
概要
この記事は、アメリカのミシガン州での留学経験を通じて、挑戦と成長の物語を語っています。著者は初めての外国での生活の困難を乗り越え、自らの意志で進むことの重要性を体験し、孤独やプレッシャーから成績優秀者へと成長していく姿が描かれています。
要約の箇条書き
- 著者は、アメリカ留学のためにミシガン州に到着。
- 英語に苦手意識があり、孤立感に悩む。
- 地域社会での外国人としての違和感を感じ、簡単に友人を作ることができなかった。
- 図書館が孤独を癒す「居場所」となり、勉強に没頭。
- 毎日膨大な時間をかけて課題に取り組む。
- 孤独の底で意志が変わり、「やめたくない」と決意。
- 学業の成果が認められ、地元新聞に名前が掲載される。
- 親からのサポートを得て、4年制大学への編入を希望する。
- 新たなステージに向かう姿勢が見える。

ミシガンでは寮がなかった。仕方なく、近くのアパートを借りることにした。地元の不動産会社を訪れたときのことは、今でも忘れられない。店に入った瞬間、受付の女性が少し驚いた顔をした。どうやら、外国人の客は僕が初めてだったらしい。
ぎこちない英語で事情を説明すると、彼女はしばらく黙って僕を見つめ、こう言った。
「どうして、そんな遠くから、こんな場所に一人で来たの?
言葉もちゃんと話せないのに、日本に帰った方がいいんじゃない?」
その言葉は、ナイフのように胸に突き刺さった。僕がどれほどの覚悟でここに来たかなんて、誰も知らない。でも、それが「現実」だった。
周りを見ても、外国人はほとんどいなかった。少なくとも、僕のようにアジアから一人で来ている学生なんて、見当たらなかった。
やっとの思いで見つけた小さなアパートに住み、そこから僕のミシガン生活が始まった。ミシガンは典型的な車社会だったが、僕には車を買う余裕なんてなかった。通学手段は、二時間に一本のバス。バスの時刻を逃すと、次はまた二時間後。
最終バスを逃してしまい、冷たい夜道を三時間近くかけて歩いて帰ったこともある。
そういう日々の中で、少しずつ自分の中の何かが変わっていった。人に頼れない。助けも少ない。
ならば、自分が変わるしかなかった。
留学生はほとんどおらず、気軽に話せる友達もできなかった。話しかけても、返ってくるのは「Hi」と笑顔だけ。そこから会話が広がることは、ほとんどなかった。
そんな中、僕が唯一「居場所」だと思えたのは、大学の図書館だった。
毎日、授業が終わると図書館へ向かった。食事も持ち込んで、閉館ギリギリまで勉強した。英語が苦手だからこそ、誰よりも時間をかけるしかなかった。辞書と参考書を開いて、一文ずつ読み進める。
宿題も、テスト対策も、論文も、すべて「倍の時間」で取り組んだ。
ある日、顔なじみのアメリカ人学生に、こんなふうに声をかけられた。
「君みたいに毎日こんなに勉強してる人、見たことないよ。アメリカ人よりアメリカの学生してる。」
その一言が、どれほど救いになったか、言葉にはできない。
見てくれている人がいた。孤独の中に、光が差した瞬間だった。
とはいえ、毎日は孤独だった。授業と勉強。バスに揺られ、アパートに帰り、また勉強。
何もない部屋で、ラーメンをすする夜もあった。
そんなある晩のことだった。
夕方の最終バスを逃してしまい、冷たい夜道を三時間近くかけて歩いて帰宅した日。

足は棒のようになっていたけれど、どこか気持ちは無機質で、何も感じなかった。ドアを開け、暗い部屋に一人。電気も点けず、そのまま床に座り込んだ。
静まり返った空間の中で、ふと、こんな考えが頭をよぎった。
「このままここで倒れても、きっと誰にも気づかれないんじゃないか──。」
携帯はほとんど鳴らない。話しかけてくれる人もいない。家族も遠く日本にいて、この国に僕の居場所は、まだどこにもない。
一週間、いや、一か月くらい見つけてもらえないかもしれない……。
その想像があまりにもリアルで、気がついたら、涙がぽろぽろと零れていた。声も出なかった。ただ、止まらなかった。
肩を震わせながら、こらえようとしても、どうしても涙が溢れ続けた。
「なんでこんな場所に、一人で来ちゃったんだろう」「自分で決めたことなのに……」
「でも、もう無理かもしれない……」
その夜は、明かりをつけずに、涙が乾くまでずっと座り込んでいた。孤独は、ただの「一人」じゃない。誰ともつながっていない、世界から取り残されたような感覚。
あの夜のことは、今でも胸が締めつけられるように思い出す。

だけど、あの夜を境に、どこか覚悟が決まった気がする。「それでも、やめたくない」
「やっぱり、ここまで来た意味を、自分で掴みたい」
次の日からも、変わらず図書館に通った。涙を流したことは、誰にも話さなかった。
でもそのぶん、静かに、強く、決意を固めていった。
結果、成績はトップだった。成績優秀者として、現地のローカル新聞に名前が載ったとき、ようやく報われたような気がした。
「よくやったね」と、大学の教授がポンと肩を叩いてくれた瞬間、胸の奥がじんわりと温かくなった。
そして、2年間の短大課程を無事に修了することができた。次は、4年制大学への編入。ここまで来るのに十分苦しかったのに、それでもまだ「もっと学びたい」と思った。
心のどこかで、ようやく「生きたい」と思えるようになっていた。
本当は、短大までという約束で、親から生活費の援助を受けていた。でも、どうしても4年制大学に行きたかった。迷った末、僕は日本の両親に電話で頼んだ。
「お願いだから、もう一度だけ、サポートしてほしい。絶対に、卒業後に返すから。」
親は裕福ではなかった。それでも、学費ローンを組んでくれた。「あなたがそこまで言うなら、やりなさい」
その一言に、どれだけの覚悟と愛情が詰まっていたか、僕は痛いほどわかっていた。
夜中のアパートで、受話器を置いたあと、僕はひとりで泣いた。
声を殺して、涙が止まらなかった。
あの日、誰にも気づかれずに死ぬかもしれないと思った自分が、今はこうして、次のステージに向かっている。
支えてくれる家族がいて、努力を認めてくれる人がいて、自分自身がまだ諦めていない。
だから、もう少しだけ、前を向いて進もうと思った。
Views: 0