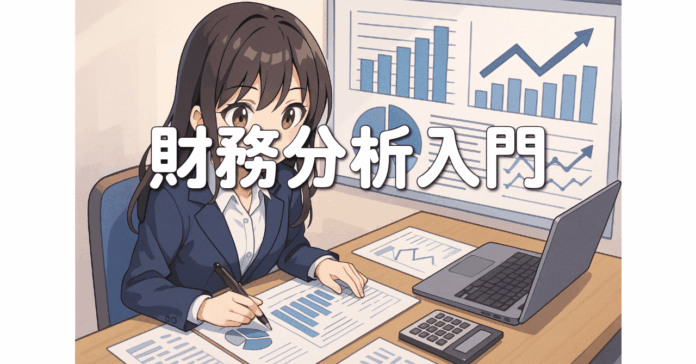🧠 概要:
概要
この記事は、企業の財務分析に関する入門シリーズの第2弾で、特に中小企業の実データを用いて「収益性」「生産性」「安全性」などの財務指標を用いて経営の現状を理解し、問題点を掘り下げる方法について解説しています。具体的には、地方の食品スーパーマーケットをケーススタディとして取り上げ、その財務データを分析し、見えてきた課題を要約しました。
要約(箇条書き)
- 前回の復習:財務分析の基本指標(収益性、生産性、安全性)について説明。
- 事例企業:地方都市の食品スーパーマーケット(年商約6.2億円、従業員49人)。
- 財務データ:直近2期の財務諸表を基にした分析が実施。
- 有形固定資産が増加しているが、負債も伴う。
- 売上増加も営業利益は赤字に。
- 売上分析:
- 売上高は増加、ただし売上原価の急増で粗利率が低下。
- 人件費が増加し、販管費が売上を圧迫。
- 収益性分析:
- 粗利率が31.0%から25.8%に悪化。
- 販管費率が高止まりし、利益圧迫。
- 生産性分析:
- 労働生産性が大幅に悪化。
- 資産効率が業界平均を下回っている。
- 安全性分析:
- 当座比率が40%を下回り、資金繰りが悪化。
- 固定資産比率205%超の過剰投資状態。
- 主な課題:
- 粗利益率の低下。
- 人件費の増加。
- キャッシュフローの悪化。
- 効率の低い固定資産。
- 改善点の重要性:数字の解析だけでなく、背後にある原因を特定することが重要。
- 提案:業務効率化と人員配置の最適化を検討する必要がある。
この記事は、財務分析を通じて企業の健全性や課題を把握する手法を提供し、ただ数字を見るだけでなく、その背後にある経営の実態を探ることが重要であると強調しています。
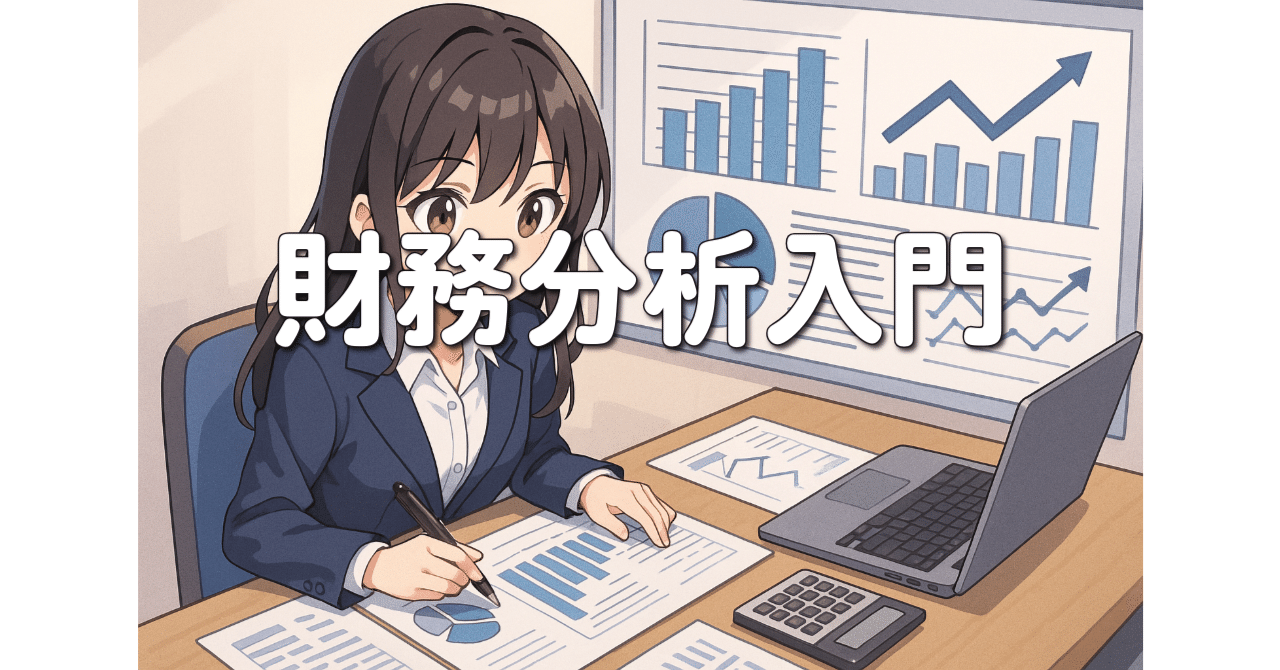
前回のコラム「財務分析入門①」では、「収益性」「生産性」「安全性」といった、財務分析の基本指標について解説しました。
今回はその応用編として、実際の中小企業の財務データをもとに、どのようにこれらの指標を用いて経営の現状を読み解き、課題を浮き彫りにしていくかをご紹介します。
「数字」から「経営のリアル」をどう見抜くか――実践的な視点で、財務分析の具体的な進め方を一緒に見ていきましょう。
ケース企業の概要と財務諸表
今回のケース企業は、地方都市で2店舗を展開する食品スーパーマーケットです。
業種:地域密着型の食品スーパーマーケット
惣菜・日配品・青果・鮮魚・精肉などを幅広く取り扱う
年商:約6.2億円(620百万円)
規模:従業員49人(パート・アルバイト含む)、中規模店舗を郊外に2店舗展開
以下は、直近3期分の財務諸表(P/LおよびB/S)をもとに、主要な財務指標を算出・分析したものです。
【財務データ(BS/PL)】
この企業の直近2期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を見てみます。※単位は百万円
 表:直近2期のBS
表:直近2期のBS
店舗の改装や設備の更新により、有形固定資産が195百万円まで増加しました。これを借入金で賄っているため、負債も増加しています。
 表:直近2期のPL
表:直近2期のPL
今期は売上が増加している一方で、営業利益がマイナスに転じ、赤字に陥っていることが分かります。
いったい何が原因なのでしょうか?
各種指標の変化と分析
まずは全体の変化をざっくりと把握しておきましょう。
-
売上高は増加傾向
販促活動の強化や来店客数の増加により、売上は前期比で伸長しています。 -
売上原価が急増
仕入価格の上昇が大きく影響し、粗利率は低下しています。売上の増加が利益に結びついていない点は注意が必要です。 -
販管費(特に人件費)が増加
従業員数が45人から49人へと増員され、人件費を中心に販売管理費が上昇しています。
これらの状況を踏まえ、次に各種財務指標を用いて、より具体的に企業の状態を分析していきます。
(1) 収益性分析
 表:収益性分析
表:収益性分析
次に、主要な財務指標の動きを見ていきます。
-
売上高総利益率(粗利率)が大幅に悪化
31.0%から25.8%へと急落しており、仕入コストの上昇や値引き販売の影響が強く表れています。 -
販管費率が高止まり(約103%)
売上に対して販管費が過大な状態が続いており、利益を圧迫しています。※「表:直近2期のPL」より
→ この2点から、粗利の縮小+コスト構造の重さが重なり、最終的に赤字転落に至ったと考えられます。
-
総資本回転率も業界平均を下回る
保有資産を十分に売上に結びつけられておらず、資産活用の効率が他社と比べても低いことが見て取れます。
これらの指標は、企業の構造的な課題――「利益が出にくい体質」になりつつあることを示しています。
(2) 生産性分析
 表:生産性分析
表:生産性分析
労働生産性が大幅に悪化:人員増と粗利率低下による付加価値率の低下が主因
労働装備率と有形固定資産回転率が業界平均より低い
→ 設備投資に対して売上・利益が追いついておらず、資産効率の面でも課題が見られます。真っ先に考えられるのが、レジでしょうか。他社ではセルフレジ・セミセルフレジ(会計だけセルフ)といった設備投資を行って、労働装備率を高めて、生産性向上を図っています。
また、レジが混んでいたら別のところで買おうということで他の店に流れてしまう可能性もあります。そうすると、労働生産性が低下することにもつながりかねません。
(3) 安全性分析
 表:安全性分析
表:安全性分析
当座比率が40%を下回り、資金繰りの悪化が顕在化
売掛金と棚卸資産の増加が現金圧迫の主因
→ 食品スーパーとしては売掛金の存在自体が異例であり、法人向け納品等が考えられます
固定比率が205%超:明確な過剰投資状態
数字の裏にある「本当の課題」を見極める
今回のモデル企業は、「売上の増加」には成功しているものの、粗利の確保やコスト管理が追いつかず、いわゆる“売上はあるが儲からない企業”の典型的な状態に陥っています。
特に以下の点が、財務指標から明らかになった課題です。
-
粗利益率の悪化による収益性の低下
-
人件費の増加とそれに伴う労働生産性の悪化
-
在庫・売掛金の増加によるキャッシュフローの悪化
-
固定資産効率の低さ
大きな課題は1と2でしょう。
これらは、いずれも“結果としての数字”であり、表面的な現象にすぎません。本当に重要なのは、なぜこうなったのかという「原因の特定」です。
1に関して言うと
-
粗利益率の低下は、仕入価格の上昇なのか、値引きによる販売増なのか?
-
商品別に見たときに、どの商品が利益を圧迫しているのか?
-
近隣競合店と比べて、価格や品揃えにどんな差があるのか?
こうした問いを立てて掘り下げることで、数字の裏にある「経営の実態」が浮かび上がってきます。
また、2に関しても単に「人数が増えたから」では片付けられません。
-
人を増やす前に、業務効率化を検討したのか?
-
本当に必要な部門に人を配置していたのか?
-
労働時間は最適に管理されていたのか?
-
業務は属人化していなかったか?
――といった視点で分析を進めることが重要です。
財務分析は「結果」であり、改善の起点
財務分析とは、企業の経営活動が「数字」という形で表れたものにすぎません。数字を眺めるだけでは限界があります。
その数字が、どのような活動の結果として生まれたのか?
ここに踏み込めるかどうかが、財務分析を“経営改善の武器”にできるかどうかの分かれ目です。
真の課題は現場や意思決定のプロセスにあります。
数字の先にある「人と活動」に目を向け、そこに切り込むことで、はじめて本質的な改善が始まります。
関連:財務分析入門①:企業の体力を「見える化」する基本スキル
※本記事は、自社サイトで公開している記事の要約です。より詳しくご覧になりたい方は、以下のページをご参照ください。
Views: 1