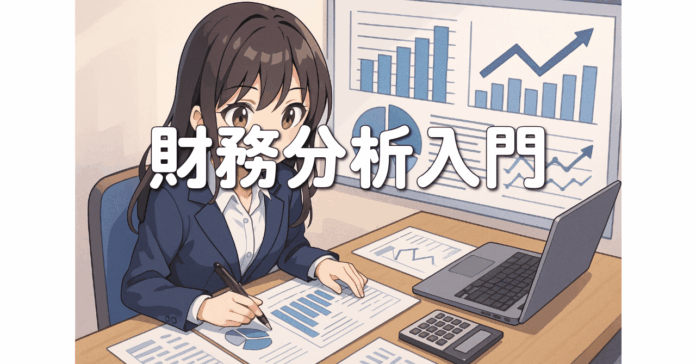🧠 概要:
概要
この記事は、企業の財務分析に関する基本的な知識を提供し、企業の経営状態を理解するためのスキルを「見える化」する方法を解説しています。特に、収益性、生産性、安全性に焦点を当て、財務諸表(貸借対照表や損益計算書)を基に、企業の健康状態を評価するための重要な指標を紹介しています。
要約の箇条書き
-
財務分析の重要性:
- 売上や利益だけでなく、深い分析が必要。
- 3つの視点(収益性・生産性・安全性)を提示。
-
貸借対照表(BS):
- 財産状態を示す。
- 負債と純資産の関係を解説。
-
損益計算書(PL):
- 1年間の事業成果を示す。
- 売上総利益、営業利益、経常利益の重要性を説明。
-
財務分析のポイント:
- 収益性分析:どれだけ効率的に利益を上げているか。
- 生産性分析:資産や人、設備の効率性を評価。
- 安全性分析:財務的な安定性や支払い能力を確認。
-
収益性分析:
- 総資本経常利益率(ROA)で効率を評価。
- 利益の質や資本効率に関する詳細な指標を提示。
-
生産性分析:
- 労働生産性を指標に、資産や人材の効率を評価。
-
安全性分析:
- 流動比率、当座比率、自己資本比率などで企業の安定性を検討。
- 警戒が必要な点:
- 黒字倒産や過剰投資のリスクを未然に察知する重要性。
この記事は、特に経営者や管理職、コンサルタントが財務状況を正確に把握するための参考となります。
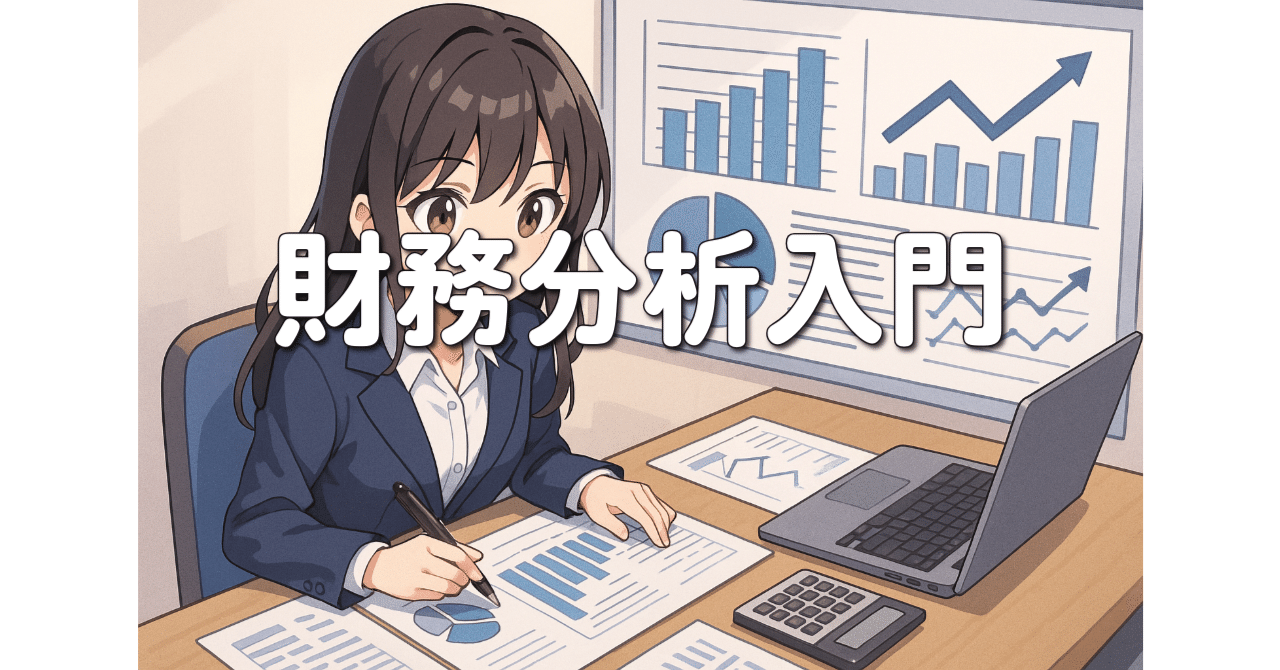
企業経営において、売上や利益の数字だけを見て安心していませんか?
実は「儲かっているかどうか」を正しく判断するためには、もう一歩踏み込んだ“財務分析”が欠かせません。
本記事では、財務分析の基本となる3つの視点 ― 収益性・生産性・安全性 ― を、実際の財務諸表(BS・PL)をベースに解説します。
経営者・管理職・コンサルタントにとって必須の知識を、できるだけ平易にお伝えします。
BS(貸借対照表)
貸借対照表(Balance Sheet)は、ある時点での企業の「財産の状態」を示すものです。
右側の「負債」は借金であり、将来返済が必要な資金です。一方「純資産(資本)」は出資によるもので、基本的に返済の義務はありません。
こうして調達した資金が、企業活動を通じて従業員によって運用され、資産を形成していきます。
 図:貸借対照表
図:貸借対照表
PL(損益計算書)
損益計算書(PL)は、1年間の事業活動の成果を示すものです。売上から費用を差し引いて、最終的にどれだけ利益が出たかを段階的に示します。ここでは、主な利益の意味を簡単に解説します。
■売上総利益
売上から原価(材料費など)を引いた利益で、商品やサービスそのものの価値を表します。
■営業利益
売上総利益から販管費(人件費や家賃など)を差し引いた利益で、事業としての収益力を示します。
■経常利益
営業利益に本業以外の損益(例:利息など)を加えたもので、会社全体の経営力を表します。
最後に税金を引いたものが当期純利益となり、これはBS上の「利益剰余金」として積み立てられます。
財務分析とは
BSやPLの数字を使って、企業の状態をより深く理解していきましょう。
財務分析で見えてくるポイントは、大きく以下の5つに分けられます。
-
収益性分析:どれだけ効率よく利益を上げているか
-
生産性分析:人や設備、資産をどれだけ有効に使っているか
-
安全性分析:借入や資金繰りに無理がないか
-
成長性分析:企業が今後どれだけ成長できそうか
-
キャッシュフロー分析:実際にお金が回っているか(黒字倒産の予防)
これらの指標は、次のような視点で読み解くことで企業の実態が見えてきます。
-
時系列でどう変化しているか?
-
同業他社と比べてどうか?
本記事では、この中でも特に重要な ①収益性、②生産性、③安全性 に絞って解説していきます。
収益性分析:元手からどれだけ稼げているか?
収益性分析では、企業がどれだけの「元手(資産)」から利益を生み出しているかを見ていきます。
同じ利益でも、少ない資産で生み出した方が効率的=優れていると判断されます。
 図:収益性指標の分解
図:収益性指標の分解
基本の指標:総資本経常利益率(①)
-
① 総資本経常利益率(ROA) = 経常利益 ÷ 総資本(資産の合計)
→ 資産全体を使って、どれだけ利益を出せているか
この指標は、さらに次の2つに分解できます。
分解して見えること:利益の質と資本の効率
-
② 売上高経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高
→ 売上に対してどれだけの利益を残せたか(利益率)
-
③ 総資本回転率 = 売上高 ÷ 総資本
→ 資本を使ってどれだけ売上を上げたか(効率性)
飲食店で例えると…
ランチが1,000円で、500円の利益が出ていれば②は50%。店舗(=資本)が少ない席数でも何度も回転すれば③は高くなります。
利益率と資本の回転、両方が高いほど収益性は良好です。
その他の指標にも注目(④~⑨)
-
④〜⑥:利益の種類ごとの違い(売上総利益、営業利益、経常利益)
-
⑦〜⑨:日常の資産運用の効率を表す回転期間の指標
各資産の回転期間(効率性のチェック)
-
⑦ 売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ 1日あたりの売上高
→ 売掛金の回収が遅ければ長くなり、資金繰りに悪影響
-
⑧ たな卸資産回転期間 = 在庫 ÷ 1日あたりの売上高
→ 在庫の滞留が長いほど、効率が悪くなります
-
⑨ 固定資産回転期間 = 固定資産 ÷ 1日あたりの売上高
→ 設備投資が売上につながっていない場合、非効率と判断
このように収益性分析を細かく見ていくことで、「何が利益を生んでいて、何が足を引っ張っているのか」が明確になります。
生産性分析:人と設備をどれだけ活かせているか?
生産性分析では、資産や人・設備をどれだけ効率的に活用しているかを評価します。代表的な指標は「労働生産性(①)」で、人の働きに対してどれだけ“価値”を生み出しているかを測るものです。
 図:生産性指標の分解
図:生産性指標の分解
基本の指標:労働生産性(①)
-
① 労働生産性 = 付加価値 ÷ 従業員数
→ 1人あたりどれだけ企業の価値を生み出しているか
ここでいう「付加価値」とは、売上から外部調達した原材料費などを除いた、内部で生み出された成果です。
簡易的には「売上総利益(売上高-売上原価)」と考えてOKです。
分解して見えること:付加価値の質と設備の使い方
-
② 売上高付加価値率 = 付加価値 ÷ 売上高
→ 売上のうち、どれだけが企業の内部価値になっているか
-
③ 一人あたり売上高 = 売上高 ÷ 従業員数
→ 人1人あたりの成果量
さらに、③を細かく見ると次の2つに分解できます。
-
④ 労働装備率 = 有形固定資産 ÷ 従業員数
→ 一人あたりどれだけ設備を保有しているか(機械化の程度)
-
⑤ 有形固定資産回転率 = 売上高 ÷ 有形固定資産
→ 設備をどれだけ効率的に売上につなげているか(稼働率)
生産性を高めるには?
機械化(④)を進め、その設備をしっかり稼働(⑤)させることで、結果的に一人あたりの売上高(③)が向上します。
つまり、人とモノ(設備)をバランスよく活かすことが生産性向上のカギです。
このように分解して分析することで、「どこに生産性の課題があるのか?」が明確になります。
安全性分析:企業の“倒れにくさ”をチェックする
安全性分析とは、企業の財務的な安定性や支払い能力を評価するための手法です。いくら利益を出していても、資金繰りが悪ければ倒産することもあります。
そこで重要なのが、「短期の支払能力」や「財務の健全性」を客観的にチェックすることです。
 図:安全性指標
図:安全性指標
① 流動比率
= 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
短期負債に対して、現金や売掛金、在庫などでどれだけ支払えるかを見る指標です。目安は200%以上。資金繰りの余裕があるかを判断できます。
② 当座比率
=(流動資産 − たな卸資産)÷ 流動負債 × 100
在庫など現金化しにくい資産を除き、即時換金可能な資産でどれだけ支払えるかを見る指標。目安は100%以上が健全とされます。
③ 固定比率
= 固定資産 ÷ 自己資本 × 100
自己資本でどれだけ固定資産(建物・機械など)をまかなっているかを見る指標。100%以下が望ましく、これを超えると過剰な設備投資のリスクがあります。
④ 固定長期適合率
= 固定資産 ÷(自己資本+固定負債)× 100
固定資産を、自己資本だけでなく長期借入金も含めた安定資金でカバーできているかを示します。100%以下が理想的。流動資金を固定投資に使っていないかを見る重要指標です。
⑤ 自己資本比率
= 自己資本 ÷ 総資産 × 100
企業全体の資産のうち、返済不要な資本(自己資本)が占める割合を示します。30%以上が健全とされ、50%を超えればかなり安定的な財務体質です。
これらの指標を組み合わせて分析することで、黒字でも倒産する“黒字倒産”の予兆や、過剰投資による財務悪化を未然に察知することができます。
※本記事は、自社サイトで公開している記事の要約です。より詳しくご覧になりたい方は、以下のページをご参照ください。
Views: 0