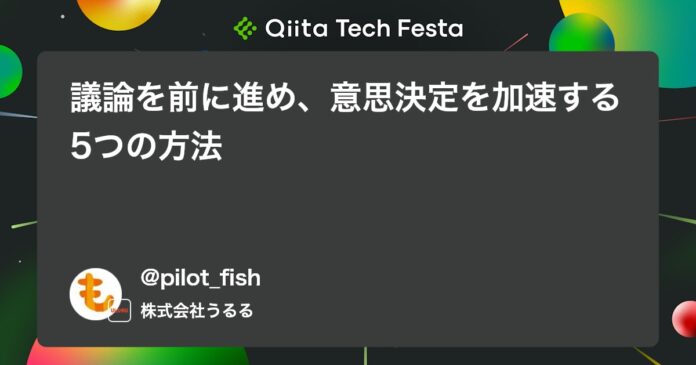事業部MVPを取った優秀な後輩の
油断させておいての不意打ち記事投稿に驚き、
急いで記事を書いたのですが、
今度は彼が油断していそうなので、今のうちに記事を書こうと思います。
チーム開発をしていくなかで、チーム内やステークホルダーと議論をして意思決定をしていくことって意外と多いですよね。
「エンジニアが必修で履修するべき言語は日本語だ!」
みたいなことを言われることも多くあります。
でも、こんな経験ありませんか?
- 意思決定したかったのにリスクの洗い出しで終わっちゃった・・・
- 説明したのに、質疑応答で1時間使っちゃった・・・
- 前に合意したのに、議論が再燃しちゃった・・・
こういった、あるあるな状況を極力回避する5つの方法をまとめてみます。
方法その1:極力クローズドクエスチョンで議論しよう
「〇〇の件について話したいたいんですが、意見がある方はいらっしゃいますか?」
こんな質問からスタートする議論は要注意です。
アイディアが無限に出てきたり、リスクの洗い出しにつながったり、枝葉の議論が始まったり。
熟練のファシリテーターであっても、議論のコントロールが困難になります。
「〇〇の件について、A案とB案を考えてきました。どちらを軸に進めましょうか?」
こんな問いかけからスタートできると、 選ぶ ところからスタートできるので、
話題の幹の部分はブレずに進められそうです。
つまり、オープンクエスチョンにならないような事前準備を行って対峙することで、
議論を前に進め、意思決定を加速できるはずです。
方法その2:10分の説明より1枚のポンチ絵
議論を加速するために丁寧な説明を心がけたいです。
一方で、丁寧すぎるがあまり、聞く側の理解が進まないことも多いです。
たとえば、
- (今の〇〇って単語、どういう意味だったっけ?)
-
(B案の説明してくれているけど、A案との違いって何だったっけ?)
こんな疑問が聞く側の脳裏によぎった段階で、以降の説明を聞きそびれてしまったりします。
そうすると、議論が進む中で、
- 「〇〇って部分、もう一度説明してほしい!」
-
「結局、A案とB案の違いって何になるの?」
という質問が出てきます。
(それ、さっき説明したじゃん・・・)
そう思いながら、説明を繰り返すことになります。
順を追って理解を進めたい人。
全体像を把握してから細部の理解を進めたい人。
理解の進め方は人それぞれです。
特に口頭での説明は、
- 言葉を聞きながら頭の中で情報を整理し
- 頭の中でイメージを膨らませ
- 頭で考えて結論を出し
- 発言をする
聞き手は無意識にこのような行動を行っています。
ですが、1枚のポンチ絵を用意できていると、聞き手の1・2のステップを
省略することができます。
「A案とB案、図にするとこうです」って1枚出すだけで、“あーなるほど感”がマシマシになります。
つまり、ビジュアライズされた状態で情報を整理された1枚のスライドを事前準備しておくことで、
議論を前に進め、意思決定を加速できるはずです。
方法その3:障壁の言語化
議論が止まってるとき、原因の多くは 「判断材料がまだ揃っていない」 ことにあります。
でもそれを誰も明言しないと、「なんか決めきれない空気」だけが漂ってしまう。
「なんかモヤモヤして決めきれないな〜」って時って、たいてい“言語化されてない地雷”が埋まってます。
そんな時はこう問いかけてみましょう!
- 「追加で何が分かれば判断できそうですか?」
- 「判断をためらってしまう、ネックってなんでしょうか?」
そうやって、“判断しきれない理由”の言語化を促すことで、
次にやるべきことが明確になります。調査?確認?仮置きで進める?
つまり、迷いを言語化していくことで、議論を前に進め、意思決定を加速できるはずです。
方法その4:「“やらない理由”がなければGO」のルールを使う
意思決定が遅れる理由のひとつに、「全員の納得を待ってしまう」ことがあります。
でも、完璧な合意を待っていたら、何も動かせません。
(そして、ミーティングが重い空気に・・・)
そこで使えるのが、“やらない理由がなければGO”という前提ルールです。
「特に反対がなければ、この方向で進めようと思ってます。大丈夫そうですか?」
この問いかけをするだけで、「進めることが前提」で議論を促せます。
そして、もし反対があれば その理由を起点 として建設的に議論が行えます。
これが機能するには、
- 異論が言いやすい雰囲気
- 反対意見も貴重な意見として承認される文化
が必要です。
いわゆる心理的安全性ですね。
心理的安全性が担保されていない環境では、「誰も異論を言わない=みんな納得してる」は幻想です。
もちろん、感情だけの反対意見は議論に繋がらないので単純な承認は難しいですが、
意見が出る文化醸成が重要です。
そして、「やらない理由がなければGO」のルールが浸透させていくことで、議論を前に進め、意思決定を加速できるはずです。
方法その5:意思決定を再確認する
議論が終わって、「じゃあA案で!」って一度決めたのに、
次の週にまた「でもやっぱりB案もアリかも」って話が戻る。
そんな“合意の再燃”問題、ありますよね。
発生するたびに、苦々しい気分になっちゃいますよね。
それを防ぐには、意思決定を共通認識として形成することが大事です。
たとえば
- 議論の最後に「じゃあこの件はA案で進めますね」と明言
- Slackで「本日の合意事項:●●はA案で進行」など一言まとめる
- 合意に至った背景や条件(“一旦”A案など)を記録に残す
「ちゃんと決めた」「みんな納得した」ではなく、
「そう記録した」「次回も参照できる」にしておく。
「ちゃんと議事録に書いてある」は、未来の自分たちの振り返りポイントになります。
セーブポイントのようなものです。
「あれ、これどうなってたっけ?」と思ったら、前回の村から再スタートすることができます。
合意は議論の結果ではなく、共通認識として取り扱うことで、議論を前に進め、意思決定を加速できるはずです。
議論って、つい“全員が納得するまで話すもの”だと思いがちだけど、
実は「どう決めるかの設計」さえできていれば、 合意形成はもっと速く、軽やかに なると思っています。
今回紹介した5つの方法は、
迷いを言語化し、選択肢を整理し、伝え方を工夫することで、
“話し合う”から“前に進める”へ変える技術です。
“話し合う”は目的ではなく、“前に進める”ための手段です。
チーム、組織、プロダクトの成長のために、議論を前に進め意思決定を加速させていきましょう。
Views: 0