イギリスのユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)で行われた研究によって、アメリカ人が娯楽として本や雑誌を読む習慣が急激に衰えていることが明らかになりました。
日常的に読書を楽しむ人の割合は2003年の約30%から2023年には18%へと落ち込みました。
1日あたりの読書時間も2004年の平均23分から最近は16分にまで縮んでいます。
研究チームは「読書機会を取り戻す緊急策が必要だ」と警鐘を鳴らしています。
教育や健康にまで及ぶ読書の恩恵が失われつつある今、“読む人2割時代”を私たちはどう受け止めるべきなのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年02月15日に『medRxiv』にて発表されました。
目次
- ここまで減った読書習慣
- ビッグデータで判明:読書率年2%ずつ蒸発
- スマホ時代、読書はどう生き残る?
ここまで減った読書習慣
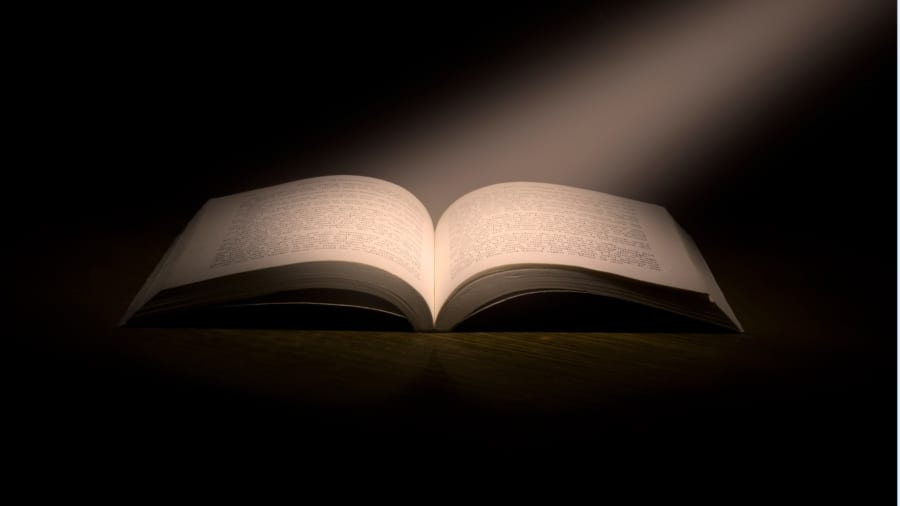
「娯楽目的の読書」とは、仕事や勉強のためではなく純粋に楽しみや興味から行う読書のことです。
小説やノンフィクション、雑誌・新聞を読んだり、電子書籍やオーディオブックを利用したり、子どもに読み聞かせをすることも含まれます。
こうした自発的な読書習慣は語彙や読解力の向上、学業成績や将来的な収入アップといった直接的な効果だけでなく、ストレスや不安の軽減、抑うつ症状の緩和、睡眠の質向上、認知機能の維持、さらには長寿につながる可能性も指摘されています。
他者との共通の読書体験を通じて文化的な理解を深めたり、社会的なつながりや帰属意識を育む効果もあり、読書は個人の娯楽を超えて幅広い価値を持つ活動と考えられています。
にもかかわらず、近年アメリカで「人々が本を読まなくなってきているのではないか」という懸念が高まってきました。
例えば米国芸術基金(NEA)の調査では、1年間に娯楽で本を少なくとも1冊読んだ成人の割合が1992年の61%から2022年には49%に低下しています。
高校生年代についても、1970年代後半には毎日何らかの読書をしていた17~18歳が6割に達していましたが、2016年にはわずか16%と激減しました。
一方で調査手法によっては異なる傾向も報告されており、ピュー研究所の世論調査では「過去1年間に本を読んだ成人」は2010年代を通じて約75%で安定しているとの結果もありました。
こうした相反するデータの背景には、調査方法の違いがあると考えられます。
自己申告によるアンケートでは「本当は読んでいないのに読んだと言ってしまう」社会的望ましさバイアスや、1年分の読書を振り返る記憶の不正確さなどが影響し、調査ごとに結果にばらつきが生じていた可能性があります。
また青少年に限定した研究は多い一方で、成人全体を対象にした長期的なデータは限られていました。
このような背景から、今回の研究チームは全米規模の時間調査データを用いて、米国人の娯楽読書習慣が本当に減っているのかを包括的に検証しました。
特に過去20年間(2003〜2023年)の長期トレンドに着目し、読書離れの実態とその傾向が年齢や性別、人種・民族、学歴、所得、居住地域(都市か地方か)、健康状態といった人口学的要因によってどう異なるかを詳しく調べることが目的です。
ビッグデータで判明:読書率年2%ずつ蒸発

研究チームは米国労働省が実施する「全米時間利用調査 (American Time Use Survey, ATUS)」のデータを分析しました。
ATUSは全米から抽出した15歳以上の人々に対し、「昨日24時間のうち何にどれだけ時間を使ったか」を細かく記録してもらう大規模調査で、日々の行動実態を把握できる点が特徴です。
今回の分析では、2003年から2023年までの延べ23万人以上(236,270人分)のデータを用い、その中から「娯楽目的での読書」に該当する行動(仕事や勉強以外の読書)があったかどうかと、その時間を抽出しました。
ただしCOVID-19流行の影響で2020年は調査が一時中断したため、この年のデータは除外されています。
まず最新の2023年の状況を見ると、ある日のうちに少しでも読書をした人の割合は18%にとどまりました。
裏を返せば「5人中4人以上(82%)は1日の中で全く読書しなかった」ことになります。
一方、読書をした人について見ると、その読書時間は平均1時間31分(中央値1時間)に達していました。
つまり「読む人は比較的しっかり読んでいるが、読まない人が大半」という二極化した実態が浮かび上がっています。
全体で平均すると2023年時点の1日あたり読書時間は16分程度でした。
次にこの20年間の推移を分析した結果、日々の読書実施率(その日に読書した人の割合)は2003〜2004年頃をピークに一貫して低下していることが明らかになりました。
2004年には約29%だった読書率は、年平均2%ずつ相対的に減少しながら2023年には18%前後まで落ち込んでいます。
統計解析でもこの減少傾向は有意で、偶然の変動ではなく長期的な真の減少トレンドであることが示されました。
また1人あたりの読書時間も2004年の平均約23分から毎年0.37分ずつ減少し続け、全体として娯楽読書に割かれる時間が着実に減っていることがわかりました。
こうした減少は主に「個人が自分の楽しみのために読む読書」の頻度低下によるものであり、親子での読み聞かせ(子どもに本を読んであげる行為)はこの期間で大きな変化が見られなかったとのことです。
興味深いことに、実際に読書を行った人たちの読書時間平均はむしろ僅かながら増加傾向を示し、2003年には約1時間20分だったものが2023年には1時間31分に延びていました。
これは「読む人は減ったが、残った読書層は以前より長く読むようになった」可能性を示唆しており、研究チームは今後この理由を詳しく探る必要があるとしています。
読書によって得られる恩恵が「読む層」と「読まない層」で大きな格差となっているのです。
さらに、読書習慣の人口層ごとの違いも明らかになりました。
もともと女性の方が男性より読書率が高く、高齢者ほど若年層よりよく読書をする傾向がありましたが、こうした差は20年間で大きく変わらず維持されました。
一方で人種や学歴、所得、地域、健康状態による差は拡大しています。
例えば2023年時点では、黒人の読書率は白人の約半分程度(その日の読書実施率が白人より45%低い)というデータが得られています。
学歴についても差が顕著で、大学院卒など高学歴の人は、高卒程度の人より約3倍も読書習慣があることが示されました。
所得が高い層も低所得層より読む割合が高く、都市部在住者は地方在住者より読書率が高い傾向が強まっていることがわかりました。
また障がいを持つ人は健常者より読書する割合が低く、このギャップも拡大していました。
このように、娯楽読書離れの傾向は社会の中で一様ではなく、特に社会的・経済的に不利な立場にある人々やマイノリティー層で顕著であることが示唆されています。
スマホ時代、読書はどう生き残る?
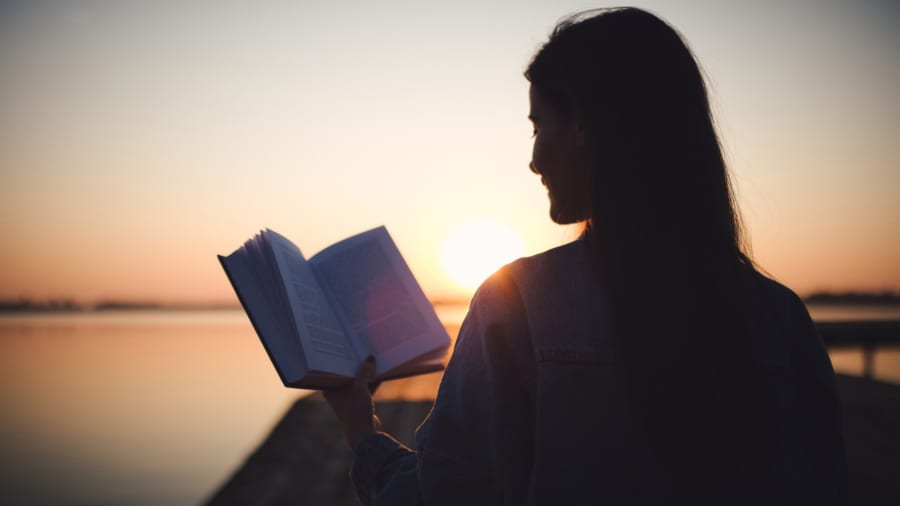
今回の研究は、国の大規模調査データを用いることで米国人の読書離れが過去20年にわたって着実に進行してきた実態を裏付ける強力なエビデンスを提供しました。
従来の断片的な調査では把握しにくかった長期トレンドを明らかにした点で、その意義は大きいと言えます。
「29%から18%へ」という数字が示す通り、もはや日常的に本を読む人は少数派になりつつあるのが現状です。
この結果について研究チームは「読書離れの傾向は幅広い恩恵をもたらす読書活動が軽視されつつあることを意味しており憂慮すべきだ」と述べています。
読書には前述したような多くの利点があるだけに、このような習慣の衰退は個人の教養や心の健康だけでなく、社会全体の文化的・知的基盤にも影響を及ぼしかねません。
では、なぜこれほどまでに人々は本を読まなくなったのでしょうか?
本研究では原因の分析までは行っていませんが、専門家や教育関係者の間ではデジタルメディアの台頭が大きな一因だと指摘する声が多く聞かれます。
米国芸術基金の報告書も「文学は今や膨大な電子メディア群と競合している」と述べており、スマートフォンやソーシャルメディア、動画配信サービスなど娯楽の選択肢が爆発的に増えた現代では、どうしても本から人々の注意がそれてしまいがちです。
実際、アメリカ人は平均して1日6時間以上を何らかの画面(スマホやテレビ)に向かって過ごしているとのデータもあります。
あるNPRの番組ホストは「今や書籍は世の中のあらゆる『コンテンツ』と競争しなければならない」と述べており、情報過多の時代に腰を据えて読書に向かうこと自体が難しくなっている現状を物語っています。
また、読書量の低下傾向自体は実は今に始まったことではなく、スマホやインターネット登場以前の1980年代から既に下降線を辿っていたという指摘もあります。
20世紀後半にはテレビが家庭に普及し、人々の余暇時間を大きく奪ったことが読書離れの遠因になったとも言われています。
これらを踏まえると、近年の急激なデジタル化が拍車をかけたものの、長年にわたる生活様式の変化が徐々に読書文化を浸食してきた側面もあると言えるでしょう。
今回明らかになったように、読書習慣の衰退は特に一部の層で著しく進んでいます。
研究者らは、黒人や低学歴・低所得層、地方在住者、障がいを持つ人々といった読書機会が限られがちなグループに対し、図書館やコミュニティを通じた支援策や働きかけを強化する必要性を訴えています。
「読書推進政策は教育上の理由から子どもに焦点が当たりがちだが、大人も対象に考慮すべきだ」と研究チームは指摘します。
ストレスや抑うつの増加、不眠の蔓延など現代の社会問題に対して、読書が一つの健全な対処法となり得ることを踏まえれば、大人の読書離れにも目を向けることが重要だというわけです。
実際、米国では公共図書館を拠点に地域住民の読書を促進する取り組み(例:NEAの「ビッグリード」プログラム)や、有名人によるオンライン読書会などの試みも行われており、6百万人以上が何らかの読書イベントに参加したという報告もあります。
しかし、調査によれば日常的に図書館で読書する人はごく僅か(2023年時点で0.3%)に過ぎず、従来の図書館任せのアプローチだけでは限界があるかもしれません。
研究者らは、今後も継続的に人々の読書実態をモニタリングしつつ、有効な介入策を見出していくことが重要だと強調しています。
娯楽としての読書は、単なる趣味以上の価値を持つ行為です。
本を読むことで得られる豊かな体験や知識は、個人の人生を彩るだけでなく社会の活力となります。
それだけに、今回明らかになった読書離れの現状は深刻ですが、同時に読書の魅力を次世代に伝えていくことの大切さを改めて示す結果とも言えるでしょう。
デジタル時代に即した新しい読書スタイルの提案や、誰もが気軽に本と触れ合える環境づくりなど、未来に向けた創意工夫が求められています。
研究チームの呼びかけるように、まずは現状を直視し、そしてもう一度「読書の持つ力」を社会全体で見直すことが必要なのかもしれません。
元論文
The decline in reading for pleasure in the US: analyses of 20 years of the American Time Use Survey
https://doi.org/10.31234/osf.io/pfmxz_v1
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。
大学で研究生活を送ること10年と少し。
小説家としての活動履歴あり。
専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。
日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。
夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
Views: 0

