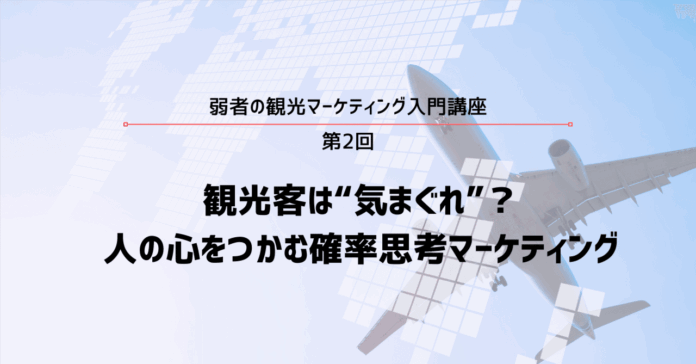🧠 概要:
この記事では、観光業におけるマーケティング戦略の新たな視点を提示しています。観光客の選択が「気まぐれ」であり、観光地の選ばれる確率に影響を与える要素について詳しく解説しています。
概要
観光客の意思決定は、合理的ではなく、気分や印象に基づくことが多い。したがって、観光地が選ばれる確率を上げるための3つの要素(メンタルアベイラビリティ、フィジカルアベイラビリティ、プレファレンス)を理解し、特に地方の小さな町が注力すべき点を示しています。
要約の箇条書き
- 観光客は「気まぐれ」に基づいて旅先を選ぶことが多い。
- 観光地が訪問されない理由は、地域の「欠点」ではなく、選択行動のランダムさにある。
- マーケティングは「選ばれる確率」を上げる戦いである。
- 観光地が選ばれる確率に影響を与える3要素は以下の通り:
- メンタルアベイラビリティ:知名度や印象の浮かびやすさ。
- フィジカルアベイラビリティ:実際に訪問できる容易さ。
- プレファレンス:好まれるかどうかの主観的な評価。
- 地方の小さな町は、メンタルアベイラビリティとプレファレンスに注力しやすい。
- 魅力的な体験をSNSなどを通じて発信することで、地域の印象を向上させることができる。
- 次回は観光地が「選ばれるまち」になるためのブランド設計について紹介する予定。
このように、観光業における確率思考マーケティングがどのように地域の活性化につながるかを提案しています。
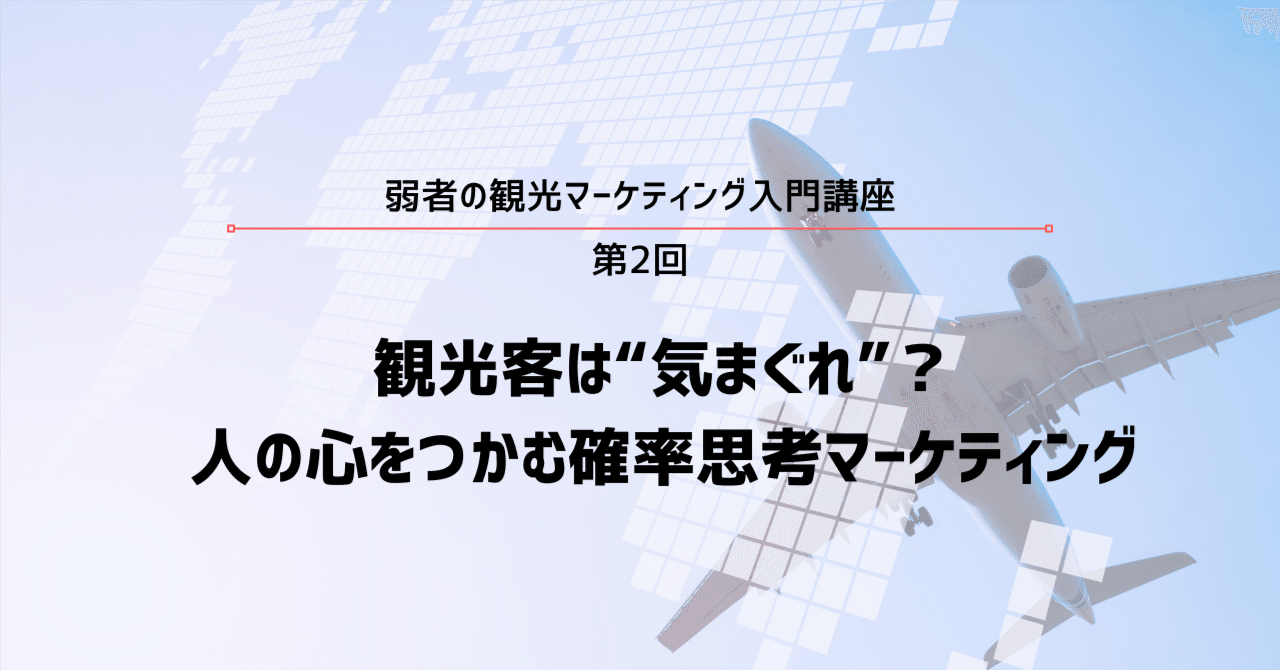
人は“合理的”には選ばない
たとえばあるファッションブランドの好感度調査では、同じ対象者に対して数週間後にもう一度同じ質問をしたところ、最初に「このブランドが好き」と答えた人の半分以上が、2回目では「好き」と答えなかったという結果が出たそうです。
一方で、最初に「嫌い」と答えた人の中から「好き」に変わった人もいて、
最終的な全体平均の好感度はどちらの回も約28%で変わらなかったというのです。
これはつまり、私たちの「好き」「嫌い」は意外とあいまいで、一貫していないということ。特に観光のように「非日常」で、「気分」や「ノリ」で決められることが多い領域では、
消費者の行動は非常にランダムになりやすいのです。
観光地が“選ばれる確率”とは?
このように、観光における来訪行動は、確率的な要素を含んでいます。
つまり、マーケティングとは“選ばれる確率”を上げていく戦いだとも言えるのです。
では、その「選ばれる確率」はどうやって決まるのでしょうか?
マーケティング理論では、大きく3つの要素があるとされています。
① メンタルアベイラビリティ(心に浮かぶ確率)
最初の要素は「そのまちを知っているかどうか」です。観光客は、知らないまちを選ぶことはできません。
逆に言えば、「あ、聞いたことある」「前にSNSで見たかも」というだけで、選択肢に入りやすくなります。
このように、頭の中に浮かんでくる確率のことを「メンタルアベイラビリティ」と呼びます。
テレビCMや観光雑誌のようなマスメディアだけでなく、SNSやYouTube、ブログ記事、そして口コミなどで見聞きした経験がこの“浮かびやすさ”に大きく関わります。
特に「弱者」の地域こそ、SNSやWeb記事など、小さな予算で広く発信できる手段を活かして、まず「知ってもらうこと」に注力すべきなのです。
② フィジカルアベイラビリティ(実際に行ける確率)
次に大切なのは、「行きやすさ」です。
「行ってみたいな」と思っても、アクセス情報がわかりにくかったり、予約の導線がなかったりすれば、候補から外されてしまいます。
これが「フィジカルアベイラビリティ」、つまり実際にアクセス可能である確率です。
ここで大事なのは、「インフラを整備しなければ」という話ではなく、“わかりやすく、スムーズにたどり着けるように見せる”という工夫です。
-
WebサイトにGoogleマップが埋め込まれているか
-
SNSの投稿から予約ページへすぐ飛べるか
-
電車やバスの時刻表がすぐ見つかるか
こうした小さなUX改善こそ、フィジカルアベイラビリティ向上の鍵になります。
③ プレファレンス(好まれる確率)
そして最後の要素が「プレファレンス」、つまり「なんとなくここがいい」と思ってもらえるかどうかという”選好性”です。
これは、価格の安さや施設の新しさだけでは測れない、“イメージのよさ”や“体験への期待”が大きく影響します。
たとえば――
-
「このまち、なんか雰囲気よさそう」
-
「こんな体験してみたい」
-
「この人が紹介してたなら面白そう」
こうした印象をつくるのが、ブランディングの仕事であり、次回の記事で扱う「ブランドの設計」につながっていきます。
“弱者”がまず注力すべきは?
3つのうち、地方の小さなまちが自力で改善しやすいのは、① メンタルアベイラビリティと③ プレファレンスです。
なぜなら、これらは“印象”や“記憶”に訴える工夫”で改善できる領域だからです。
すぐに新しい道路や新幹線駅はつくれなくても、魅力的な体験をSNSで発信することはできる。
「ここでしか味わえない物語」を届けることで、「なんだか気になるまち」にすることはできる。
それが、小さな地域でも実行できるマーケティング戦略の第一歩なのです。
まとめ:ランダムな選択に「確率」で勝つ
人は気まぐれで、旅先の選択もまたランダムです。でも、だからこそ私たちには希望があります。
すべての町が「選ばれる可能性」を持っているのです。
次回は、そんな“選ばれるまち”になるために、誰に・何を・どう届けるか?という「ブランド設計」の考え方をご紹介します。
Views: 2