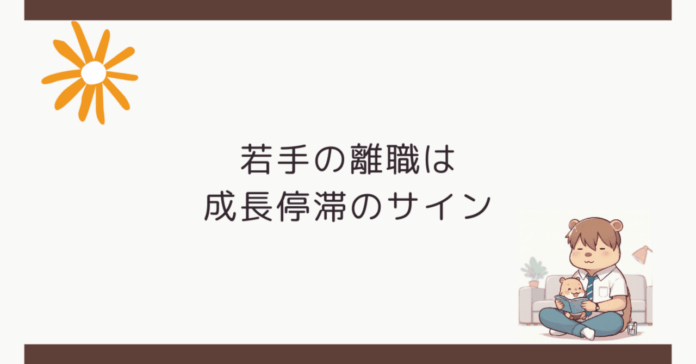📌 概要
若手社員が「成長実感がない」と辞める背景には、組織に「積み上げサイクル」が存在しないことが指摘されています。成長は小さな成功体験を積むことで感じられるのですが、頻繁な人事異動や前任者との引継ぎの不足によって、若手は業務の進行状況が不明でやりがいを感じにくい状態です。
日本企業特有のやりっぱなし体質も影響しており、過去の反省や成功を活かさないまま新たな計画が立てられることが多いです。その結果、個人のキャリアも積み上げが必要であり、評価基準が明確でないままではモチベーションが低下します。離職が続くと、組織内の知見は蓄積されず、改善も難しくなります。明確な育成プロセスや評価軸が必要であり、組織全体で「記憶力」と「再現性」を高めることが重要だと述べられています。若手が成長を感じられる環境こそが、離職を防ぎ組織の競争力を高める鍵となります。
📖 詳細
成長実感が得られないのは、組織に「積み上げサイクル」がないから
若手社員の多くが辞める理由として「成長実感がない」という点が挙げられます。この問題は、個人の意欲ではなく、職場環境に起因しています。辞めるために入社する人はほとんどいないため、意図せず離職するケースが目立ちます。
成長は小さな成功体験を積むことで感じられるものですが、離職が多い組織ではこのプロセスが欠如しています。上司や先輩が頻繁に入れ替わることで、成果に繋がる方法が不明な状態になり、業務が毎回ゼロから始まってしまいます。
たとえば、2年目の社員が一番業務を理解しているという逆転現象も発生します。これはまるで新しい学校に転校し、教師やカリキュラムが毎年変わるようなものです。これでは自己の成長を感じることが難しく、やりがいを持ちにくくなります。
日本企業のやりっぱなし体質
多くの日本企業は「やりっぱなし」という体質を持っています。計画を立てる際、本来は前年の成功や失敗を振り返り、新たな方針を立てるべきですが、実際には振り返りが省略されがちです。
この結果、毎年新しいスローガンが掲げられ、前の反省が活かされないまま新たな取り組みが進みます。つまり、組織として「何ができるようになったか」を確認する機会が喪失し、成長が実感されずに知見が残らないのです。
個人のキャリアにも積み上げが必要
個人のキャリアについても同様です。営業職で言えば、「提案書が作れる」「難しい顧客を任された」といったマイルストーンが成長を示しますが、2〜3年経っても進展がない場合、次に目指すべきものが不明になります。
昇進や評価がなければモチベーションは下がります。特に、年功序列が崩れた現代において、結果を出しても何も変わらない会社では、若手が未来に期待できるとは言えません。
離職で積み上げは崩れていく
若手社員が辞めれば、組織の知見も蓄積されません。ノウハウを得た社員がいなくなることで、教育が毎回ゼロから始まります。これにより組織は「初期状態」から抜け出せず、業務の改善も滞ります。
悪化すると、リーダーたちはこの状況に慣れ、根本的な改善に向き合わなくなります。また、特定の部署が若手の登竜門のように扱われることもありますが、これは悪化した放置とも言えるでしょう。
積み上げのある組織とは
積み上げのある組織には以下のような特徴があります。
- 過去の成功や失敗が言語化され、再利用できる状態
- 成功のナレッジが共有
- 明確な育成プロセス
- 前年の実績に基づく計画
- 努力と結果がキャリアに繋がる評価基準
このような状態では、若手社員も「この組織で成長できそうだ」と感じ、離職を防ぎ、競争力を高められるはずです。
成長を感じられる組織にするために
組織において離職率は、人材の出入りを示す以上の重要性があります。それは積み上げの欠如を可視化するサインでもあります。
以下の問いを再考してみてください。
- この1年で何が蓄積されたか?
- 昨年の取り組みはどう活かされているか?
- 若手が成長を実感できるステップはあるか?
- 離職した人の知見はどう残しているか?
個人の力を最大限に引き出すためには、組織の「記憶力」と「再現性」を高めることが必要です。
おわりに
離職が多い組織には積み上げがなく、未来がありません。これは個々の問題や制度だけでは解決できません。成果を出すことだけでなく、それをどのように次に繋げるかを考える視点が、今後の組織にとって極めて重要です。
🧭 読みどころ
成長実感を得られない理由は、組織に「積み上げサイクル」が欠如しているからだとの指摘があります。✨ 若手が辞める多くの理由も職場環境に起因し、明確な育成プロセスやナレッジの共有が不足しています。組織の「記憶力」を高めることで、成長を実感できる環境を整えることが重要です。📈 離職率の低下こそが組織の競争力を向上させるカギになるでしょう。
💬 編集部メモ
この記事を取り上げた理由は、若手社員の成長実感の欠如が組織の離職率に直結していることを示唆している点です。特に印象に残ったのは、「成果を出して終わりではなく、次にどうつなげるか」という視点の重要性です。あなたの職場には、成長を実感できる環境がありますか?若手社員が未来を託せるような組織づくりを目指しましょう。
もし転職を考えている方がいれば、ぜひインモビの転職紹介ページをご覧ください。あなたのキャリアをより豊かにする機会が見つかるかもしれません。✨
※以下、投稿元
▶ 続きを読む
Views: 0