🧠 概要:
概要
第4章では、"正解主義"という概念に焦点を当て、世間の期待や評価に縛られ、自分の意思で決定を下せなくなる心理を探ります。子供の頃に抱いた夢が大人になるにつれ、他人の基準に合う“無難”な選択に変わってしまうことや、失敗を恐れるあまり確実な選択肢を探すようになることが解説されています。また、失敗を受け入れ、自分の欲求を尊重した選択が重要であるというメッセージが強調されています。
要約
- 子どもの夢と大人の現実: 子供時代の夢は評価されず、大人になると他人の基準が影響を及ぼす。
- “無難”な選択肢: 大企業、資格取得、昇進など、社会的に認められる選択が自分の意志ではなくなる。
- 失敗の恐怖: 学校教育によって間違いを恐れるようになり、正解を求め続けることで自分の目標を見失う。
- 選択における余白: 完璧な選択はないため、“間違えてもいい”という考えが柔軟な選択を可能にする。
- 人生はテストではない: 失敗や後悔を恐れず、多様な経験を重ねることで本当にやりたいことが見えてくる。
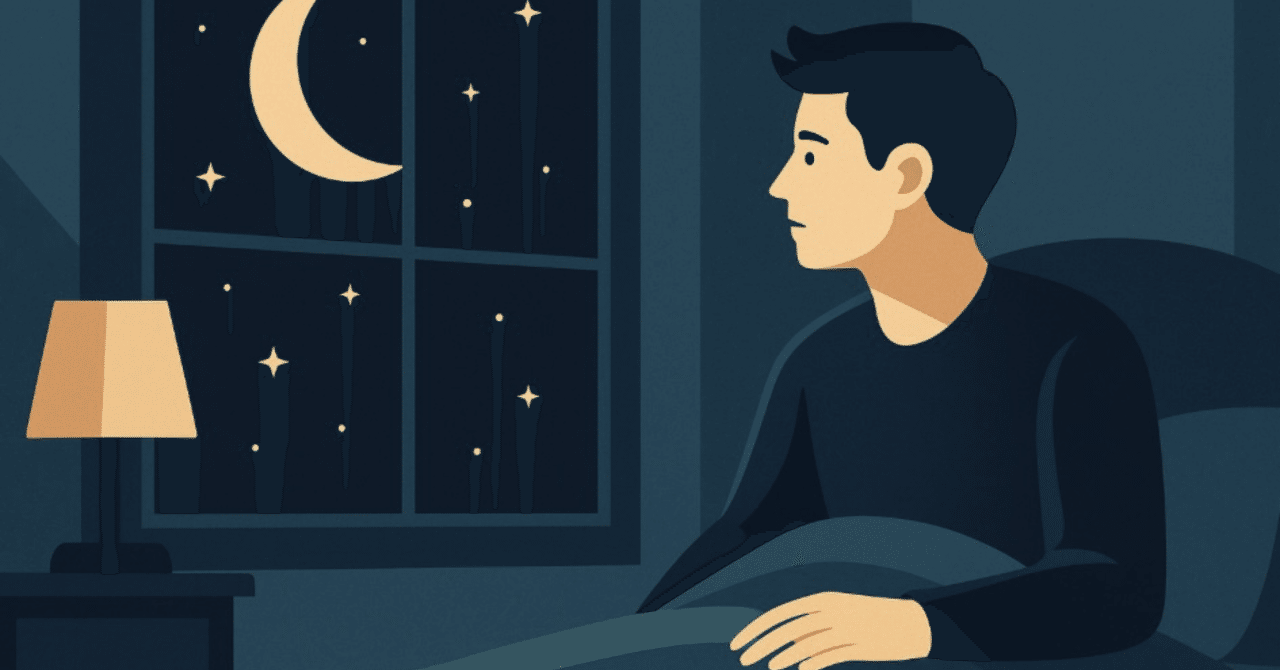
1.“無難”という名の安全圏
世の中には、“派手ではないが正解っぽい”選択肢がある。大企業に入る、資格を取る、転職はせず昇進を目指す。どれも立派な道だ。だが、それを“自分の意志”で選んでいるかというと、話は別だ。誰かに誇れる選択、親に安心される選択、世間が「ちゃんとしてる」と思う選択。こうした“無難”は、いつしか“理想”と混同されてしまう。気づいたときには、「本当に自分が望んでいたか」は、思い出せなくなっている。
まるで、「間違えないこと」がゴールになっているかのように。
2.失敗=悪、の図式が染みついている
学校では、ミスをすれば減点される。空欄の答案は0点。間違った答えに○はつかない。この経験を何千回と繰り返すうちに、私たちは“外すこと”を過剰に恐れるようになる。だから、“当たり”の道を探そうとする。確実に成果が出る選択肢、他人から否定されない選択肢、将来が見通せる選択肢。だが、人生において“確実”など存在しない。何を選んでも、後悔も失敗もついてくる。その現実を忘れて、正解を追い求め続けてしまう。この“正解主義”の本質は、「自分以外の誰かが決めた基準に合わせようとすること」だ。
その基準で人生を測り続ける限り、“やりたいこと”など、見つかるはずがない。
3.“間違えてもいい”という余白が、選択を軽くする
誰もが、一度の選択で完璧な道を選べるわけではない。転職して後悔することもあるし、やりたいことだと思っていたのに続かなかった──なんてことも普通にある。だが、それでいいのだ。むしろ、一度の選択で“本当にやりたいこと”にたどり着く人など、ほとんどいない。あれこれ試し、失敗し、違和感に気づき、また進路を変える。その積み重ねの先にしか、納得できる人生は存在しない。「正解を出さねば」と思うほど、選べなくなる。「間違えてもいい」と思えるほど、選べるようになる。人生はテストではない。だから、空欄のままでも減点されないし、書き直したっていい。
むしろ、書き直さないまま生きることの方が、よほどリスクなのだ。
Views: 0



