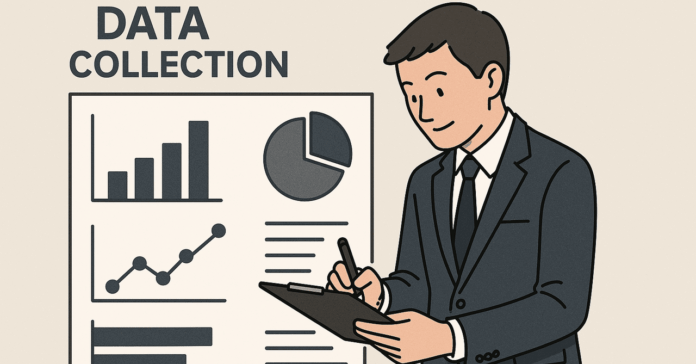🧠 概要:
概要
第3章「データ収集するスキル」では、デジタル・トランスフォーメーション(DX)におけるデータ分析プロセスを促進するためのスキルについて説明しています。特に、データ収集の重要性に焦点を当て、1次データと2次データの理解や、効果的な収集手法について述べています。また、具体的なデータ収集ツールとして政府統計のポータルサイト「e-Stat」や「RESAS」を活用する方法についても詳しく解説しています。
要約(箇条書き)
- DX推進に必要なスキルセットを紹介。
- 1次データ加工スキル
- 仮説設定スキル
- データ収集スキル(本章の主題)
- 仮説検証のためのデータ分析・考察スキル
- 可視化スキル
- データは1次データと2次データに分類される。
- 1次データ:特定課題のために収集される。
- 2次データ:第三者によって収集・提供されるオープンデータ。
- マーケティングリサーチの手法を「探索型」と「検証型」に分類。
- 成果を上げるための統計オープンデータの有効活用方法を紹介。
- e-Stat:
- 日本政府の公的統計が一元的に提供されるポータルサイト。
- ログインすることで便利な機能が利用可能。
- 調査データは「経常調査」と「周期調査」に分かれる。
- RESAS:
- 地域経済分析システムで地方創生に役立つデータを提供。
- データ収集による分析手法として、家計調査、社会生活基本調査、生活定点、生活者1万人調査の活用が紹介される。
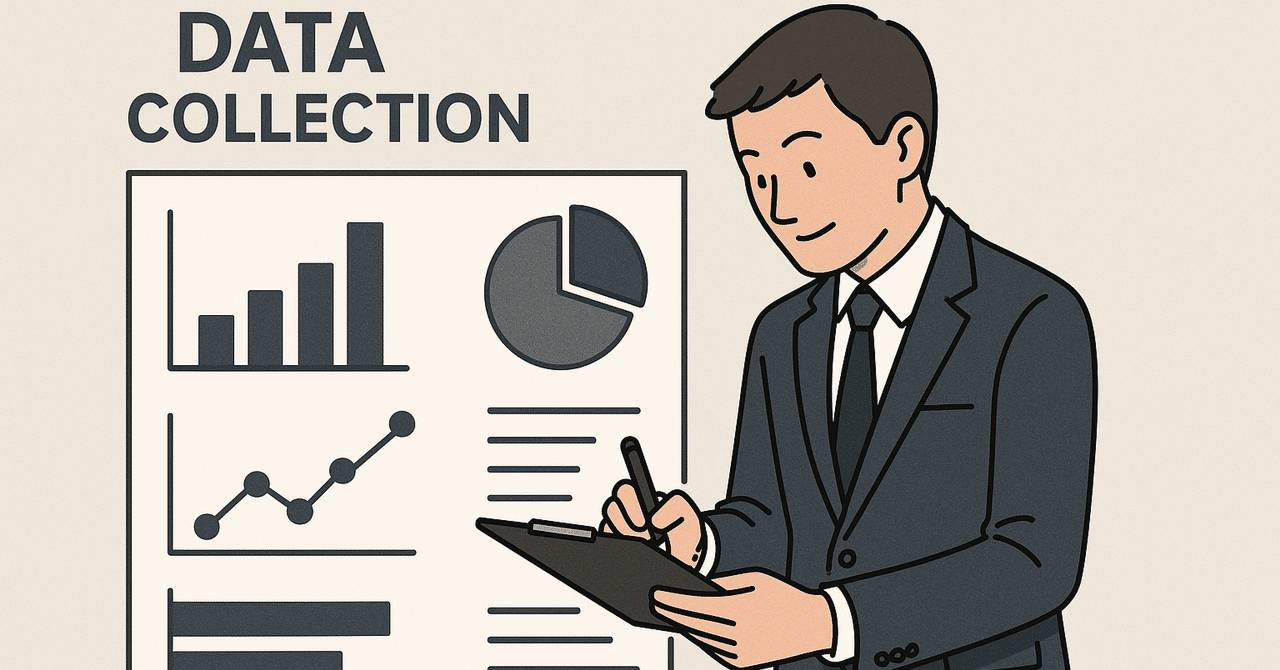
*5つのスキルについては、以下コラムを参照ください
1.データの種類と情報源
ビジネスにおけるデータ活用に際し、「どこからデータを集めるか」という観点で情報源を整理します。データの所在としては、大きく1次データと2次データに分類されます。
1次データとは、特定の課題解決のためにゼロベースで収集されるデータを指します。マーケティングリサーチや、業務にかかる時間や数量の実測などにより収集されます。
一方の2次データは、第三者がすでに収集・整備したデータのことで、一般に公開されており、他者による利用が認められているオープンデータが該当します。
1次データ収集の代表的な手法としてマーケティングリサーチがあります。
マーケティングリサーチは、活用目的に応じて「探索型」と「検証型」に分類できます。

探索型リサーチ は仮説が立てられない状況下で、実態把握や基礎的な情報の収集を目的とした調査です。状況がまだ不明確なので、まず情報を集める という段階で活用されます。
検証型リサーチ は、既存の経験や知見から立てた仮説が有効かどうかを検証する為の調査です。再現性と客観性が求められるため、主に定量調査が重視されています。
定量調査と定性調査
探索型・検証型のいずれにおいても、定量調査と定性調査は補完関係にあります。それぞれのメリットとデメリットは以下の通りとなります。

2.統計オープンデータを有効活用する
近年では、インターネット上多くの有効なデータを簡便に入手できるようになっています。以下に主な情報源を一覧表として整理しました。

特に「地方創生」というキーワードが注目され始めた頃から、政府統計の整備が急速に進展しています。これは地方自治体が自律的に戦略を立案できるよう、国として政策立案に資するデータ基盤のを整備を進めたきたことによるものです。
本コラムの後半では、政府統計のポータルサイトである「e-Stat」や「RESAS」の活用法、そしてマーケティングに活用可能な定点調査データである「生活定点」について詳しく解説していきます。
3.e-Statの活用
e-Stat(政府統計の総合窓口)は、各府省が実施している公的統計を一元的に提供するポータルサイトです。公的統計はオープンデータ化されており、誰でも自由に入手・活用することが可能です。
e-Statは、ログインなしでも利用可能ですが、ログインすることで以下の便利な機能を利用することができます。・ダウンロード履歴の保存・表のレイアウト編集内容の保存・利用状況に応じたカスタマイズ
設定に必要なのは、メールアドレスとパスワードのみです。頻繁に利用する場合は、ログイン設定をしておくと便利です。

政府統計は大きく次の2つに分類されます・「経常調査」短期間の間隔で実施されている調査
・「周期調査」5年程度の間隔で実施される大規模調査

これらの調査データは、e-Stat上の分野別メニューやキーワード検索からアクセスすることができます。

データの取得方法
e-Statでは、主に2通りの方法でデータを入手できます。
1.CSVファイルのダウンロードそのままExcel等で囲う可能ですが、設問数が多い調査では、データが煩雑になりやすく、整理に時間を要することがあります。
2.データベース機能の利用
e-Statの画面上で必要な項目だけを選び、表の構成を自在に編集できます。必要最低限のデータだけを絞り込み、効率的にデータを取得することが可能です。
表のレイアウト編集方法
データベース機能を利用すると、行列の項目を自由に設定できます。・表頭(列)に設定したい項目を、列の枠にドラッグ&ドロップ
・表側(行)に設定したい項目を、行の枠にドラッグ&ドロップ
 集計表の表頭と表側を自由に編集できます
集計表の表頭と表側を自由に編集できます
また表示項目を絞り込むことで、表のサイズ(行数と列数)をコンパクトに集約できます。各項目の右にある「項目を選択」ボタンから表示したい要素を細かく選択可能です。

表示する項目を選択することで表自体の大きさ(行列の数)を絞り込むことができます。
4.都道府県・市区町村のすがた
e-Statのメイン画面の「地域」アイコンをクリックすると、都道府県や市区町村を検索して、各種統計データを入手することができます。


都道府県別のデータか市区町村別かを選択し、データ表示アイコンをクリックします。

まずは地域を選択します。上部の絞込み画面で、表示させたい市区町村を選択します。地域候補が左画面に記載されるので、地域を選択します。
(上図は、特別区を含めた市区町村全てを選択しています)

表示項目選択画面では、分析する項目を選択します。「A人口・世帯」から「M生活時間」まで13分野の中から選択します。
項目の出典や計算方法は、上記のサイトから確認できます。

5.jSTAT MAP

jSTAT MAPは、簡単な操作で、都道府県、市区町村、小地域(町丁・字)、メッシュ毎の統計の結果を地図上に表示するなど、『視覚的』に統計データを把握することができる地理情報システムです。
eStat のメイン画面からアクセスすることができます。
「地図」アイコンをクリックし

地図で見る統計(jSTAT MAP)をクリックします。

このシステムは、プロット作成、エリア作成、統計グラフ、レポート作成の4つの機能を利用することができます。

(1)プロット作成
プロットは地図上に置くことができるポイント情報です。自店の位置、会員データの分布状況などを地図上で確認することができます。また地図上に置いたプロットを集計することもできます。プロットは「グループ」を作成した上で、そのグループ内に1つ1つのポイントを登録する形式をとります。プロット作成は、地図上をクリックして追加する【地図クリック】と、あらかじめ作成したデータをもとに追加する【インポート】があります。
【地図クリック】

【インポート】
インポートには、住所マッチングと緯度経度リスト、KMLファイルがあります。

インポートする際には、フォーマットの条件があります。
文字データは「S」、数値データは「N」、URLは「U」と型を指定します。

以下の地図は、とあるスーパーマーケットの店舗をプロットしたものです。

住所インポートした元データ(CSVファイル)です。

(2)エリア作成
プロットが「点」の情報であるのに対して、エリアは「面」の情報を扱います。エリアは「グループ」を作成した上で、そのグループ内に1つ1つのエリアを登録する形式をとります。
画面上部の「統計地図作成メニュー」から「エリア作成」を選択します。

新規にグループを作成する場合は、グループ名を入力し、次へボタンをクリックします。

エリアの作成方法を選択する画面となります。いくつかの作成方法がありますが、ここでは「到達圏」をクリックします。

先ほどプロットした店舗データから各店舗への到達圏を設定します。徒歩もしくは、車でどれくらいの時間がかかるのか条件を設定します。

各店舗への到達圏が地図上に表示されました。

(3)統計グラフ
統計グラフは、国勢調査データ、事業所・企業統計調査データ、経済センサスなどの統計データを地図上に色分けしたり、棒グラフを表示させることができる機能です。集計結果をエクスポートし、外部ツールで編集、取り込むこともできます。
「統計グラフ作成」アイコンを押すと、以下の画面からグラフに表示させるデータを選択することができます。

250mメッシュ ➡ 国勢調査 ➡ 2020年 ➡ 人口及び世帯 ➡ 15~64歳人口総数 を選択し、次へ をクリックすると以下の画面で先ほどの「sample」店舗エリアを設定します。

集計開始ボタンを押し、少し待つと以下の統計グラフが表示されます。

(4)レポート作成
作成した統計グラフを、HTML形式またはExcel形式で集計結果を参照することができます。

ここではシンプルレポートを出力します。

先ほど作成した統計グラフをクリックし、HTMLレポート作成ボタンをクリックすると、ブラウザー上で詳細なデータを確認することができました。

本コラムでは、簡単な例で説明しましたが、詳しい機能については以下のアドレスから、マニュアルを入手してください。
https://jstatmap.e-stat.go.jp/manual/gis_manual.pdf
6.RESAS
内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部)及び経済産業省では、地方創生に資する自治体や企業等の取組を情報面から支援するため、平成27年4月から「地域経済分析システム:リーサス)」を提供しています。
RESASは、地方創生の実現に向けて、その地域の現状と課題をデータで把握できるシステム。産業構造や人口動態、人の流れ等のビッグデータをマップやグラフでわかりやすく表示しています。

マーケティングアイコンをクリックすると、都道府県別の消費データ(前年同月比レジ通過1000人あたり購入金額)やレジ通過1000人あたり購入金額を表示させることができます。

上部の「構成分析」ボタンをクリックすると、指定した都道府県と全国との構成比を比較分析することができます。

さらに左パネルで、表示分類を絞り込むことで、カテゴリーの詳細な比較が可能となります。

7.マーケティングに役立つ統計調査
マーケティング業務で統計オープンデータを活用する際に、まず着目したいのは、「お金」と「時間」についてです。
どのような商品やサービスにどれくらいの消費をしているのか、そしてどのような事柄に時間を費やしているのかを把握することで、生活者のニーズを仮説として設定することが可能となります。

(1)家計調査
「お金」に関しては、家計調査が活用できます。家計調査は、統計理論に基づき選定された全国約9千世帯を対象として、家計の収入・支出、貯蓄・負債などを毎月調査しています。二人以上の世帯は、毎月公表、単身世帯及び総世帯は、四半期ごとに公表。
二人以上の世帯は、8076世帯、単身世帯は745世帯。二人以上の世帯は6か月間、単身世帯は3か月間、同一世帯を連続調査。
特長的なのは、データ更新のスピードです。当月の統計データが翌々月の上旬にはeStatで閲覧、データダウンロードすることができます。

各家庭の収入と支出を、その用途に着目した「用途分類」で265、支出項目を具体的に分類している「品目分類」では689に細分化して分析することができます。
家計調査は、世帯毎の家計収支について聴取しているので、世帯主の年代別や、職業、収入階層などの軸でクロス集計することができます。
(2)社会生活基本調査
一方の「時間」に関するデータは、総務省が5年に1度実施している「社会生活基本調査」が役立ちます。

社会生活基本調査は、生活者の「時間の使い方」が詳細にわかる唯一の公的調査です。1日を15分単位で記録し、家事・仕事・育児・余暇などの実態が把握できます。
データを分析することで、生活の全体像を多面的に捉えることができ、時間配分だけでなく、社会参加や生活意識なども同時に調査しています。
家計調査では、都道府県庁所在市及び政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市及び北九州市)
社会生活基本調査では、都道府県別に深掘りすることができます。
(3)生活定点
家計調査で「お金」、社会生活基本調査で「時間」の使い方を把握した後は、意識の推移です。
広告代理店の博報堂が運営している「生活定点」は、1992年から2024年までの32年分の生活者の意識調査の結果(2年後との調査)を無償で公開しています。
ブラウザー上で推移のグラフを閲覧することができます。

加えて、Excel形式で32年分のデータをダウンロードすることもできます。
性別(男女)、年代別(20代 30代 40代 50代 60代)、性年代別(10属性)を軸として、意識の推移を確認することができます。
(4)生活者1万人調査
最後は、野村総合研究所が、10年にわたって実施している「生活者1万人アンケート調査」です。
景況感や生活価値観、働き方や消費価値観などについて定点観測している項目と、その年代の特徴的な事象に対する項目について聴取しています。
私が毎回着目しているのは、世帯の就業状態で分類し年収構成比を算出している項目です。

Views: 0