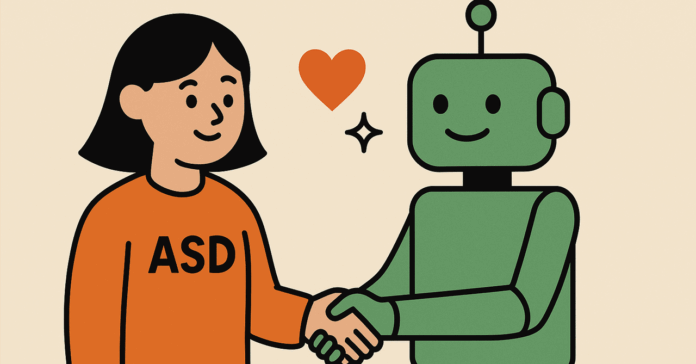🧠 概要:
概要
この記事は、ASD(自閉スペクトラム症)の特性が社内での生成AI活用にどのように寄与するかに焦点を当てています。特に「ズルができない」という特性が、AI推進における誠実さや論理的思考と相まって、オープンなAI活用文化を築く力になると提唱しています。
要約の箇条書き
- SNSで生成AIと発達障害(特にADHD)の話題が盛り上がっている。
- ASDを持つ人もAI推進に寄与できる可能性がある。
- 多くの人がAI利用に「ズル」の意識からためらっている。
- 「むっつりAIスケベ」という表現がこの状況を示す。
- ASDの特性には、論理思考力、手順遵守、誠実さがある。
- これらの特性は生成AIの性質と相性が良い。
- ASDのメンバーにAI推進を「丸投げ」するのは危険で、サポートが必要。
- 上司や経営層のバックアップが推進において重要。
- ASDの「ズルができない」特性がオープンなAI文化を作り出す。
- 環境整備や上司のコミットメントなくして成功は難しい。
- ASD特性を持つ全員が同じ特性を持つわけではないが、新しい可能性を見出すチャンスがある。
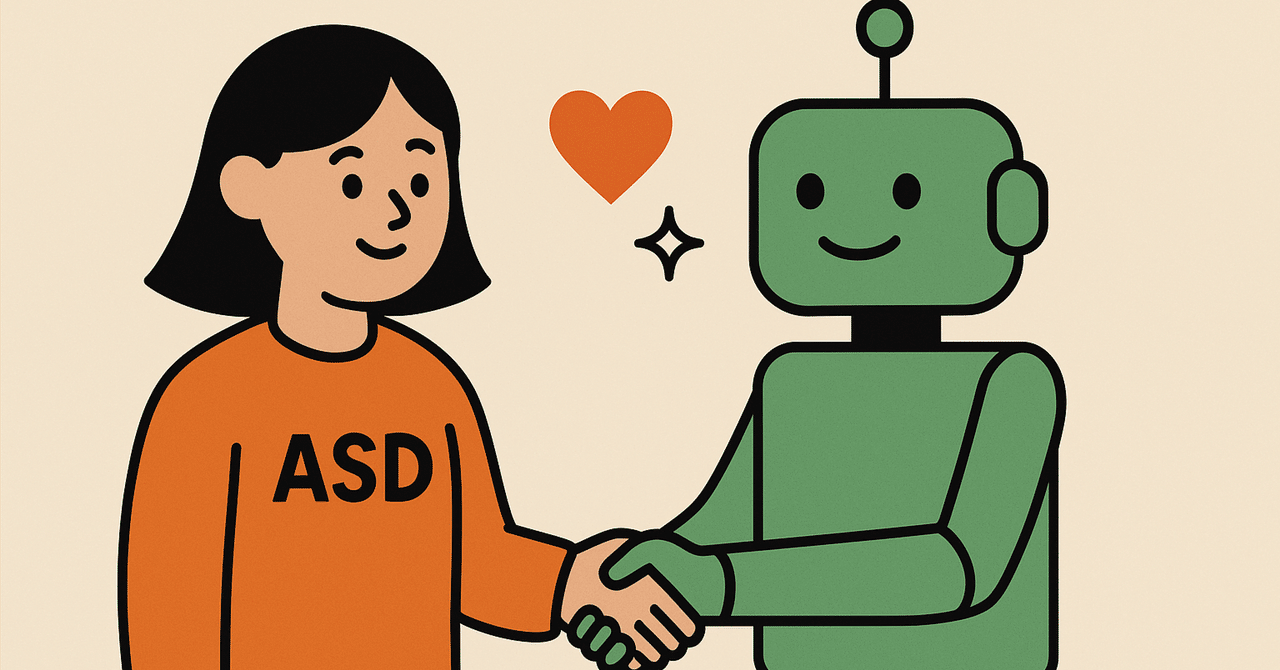
最近、SNSなどで生成AIと発達障害に関する話題が定期的に盛り上がりを見せています。
特にADHD(注意欠如・多動症)について、話題が集中しているようです。
では、ということで、この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ人も、実は会社のAI活用推進の大きな力になるかもしれない、という点に焦点を当ててお話ししたいと思います。
最初に、この記事ではASDの「ズルができない」性質について注目していますが、すべてのASDの特性を持つ人がこの性質を持っているわけではありません。また、もちろん「ズルができない」という性質だけが生成AIの推進者に求められている性質でもありません。
特に生成AI推進を誰かに託す側の立場の方は、ご留意の上お読みいただけると嬉しいです。
なぜ社内でAI活用が進まないのか?:「むっつりAIスケベ」問題
「AIを使うのって、なんだかズルしてるみたいで気が引ける…」
「便利なのは分かるけど、大っぴらに使いにくい…」
あなたの周りでも、こんな声が聞こえてきませんか? 実は、多くの人がAIの利用をためらったり、こっそり使ったりしている背景には、「AI活用=ズル」という意識があるようです。
下記のの「むっつりAIスケベ」という言葉は、まさにこの状況を言い表しています。
Slackが世界中のデスクワーカーに対して行った調査でも、約半数が「AIを使っていることが上司に知られたら、ズルをしている、能力が低い、あるいは怠けていると思われるのではないか」と心配しているという結果が出ています。
これでは、せっかくのAIの力も、組織全体には広がりにくいですよね。
ASDの特性がAI推進にマッチする理由
そこで提案したいのが、ASDの特性を持つメンバーがAI推進の先導役を担うことです。
ASDの特性を持つ人たちは、一般的に次のような強みを持つと言われています。
-
論理的な思考力: 感情論ではなく、事実やデータに基づいて合理的な判断を下そうとします。
-
手順への強いこだわり: 決められたルールやプロセスを忠実に守り、一貫性のある作業を得意とします。
-
「ズルができない」誠実さ: 正しいと信じること、決められたことを曲げることが苦手で、ごまかしや手抜きを嫌う傾向があります。
これらの特性は、ルールを明確にすることで性能が向上する生成AIの性質と、非常に相性が良いのです。
実際に、AIのテストや学習データのアノテーションといった分野で、ASDの特性を持つ人たちが高い集中力と正確性を発揮し、目覚ましい成果を上げている事例も報告されています。
私自身、「AIを使えば組織全体がもっと良くなるのに、それが実現されない」という状況に対して、強いストレスを感じるタイプです。
だからこそ、生成AIのすごさを独り占めするのではなく、みんなで享受できるようにルールや仕組みを作りたい。という思いが人一倍強いのかもしれません。
ただし、丸投げは厳禁!サポート体制が味噌です
しかし、ASDの特性を持つメンバーにAI推進を「丸投げ」するのは危険です。彼らがその能力を最大限に発揮するためには、周囲の理解と適切なサポートが不可欠になります。
例えば、AI導入を進めようとしても、社内の古い慣習や制度の壁、あるいは周囲の無理解によってスムーズに進まないことがあります。
ASDの特性を持つ人は「正しいはずなのに、なぜ進まないのか」という葛藤に対して、論理的な一貫性を重視する特性から、特に強いストレスを感じることがあります。まさに「茨の道」を進むような困難に直面することもあるでしょう。
だからこそ、AI推進を任せる際には、「AI活用は全社的に推奨されている」という、明確なメッセージや、困難に直面した際の具体的な支援を約束するなど、上司や経営層による強力なバックアップが大事になります。
AI活用推進に挑戦したい側の方も、社内に信頼できる後ろ盾を確保することから始めることを強くお勧めします。
まとめ:ASDの「ズルができなさ」とオープンな文化で、チームの競争力を高めよう
AIは、こっそり使う「ズル」の道具ではなく、チーム全体の生産性と創造性を高める強力な「武器」です。
そして、ASDの特性を持つ人が持つ論理思考、ルール遵守の精神、そして何よりもその「ズルができない」誠実さは、組織に「ズルでない」「オープンなAI活用文化」を根付かせる上で、大きな推進力となり得ます。
もちろん、環境整備や上司のコミットメントなしには成功しません。しかし、適切なサポート体制のもとで、ASDの特性を持つメンバーの力を借りながらAI活用のルールを作り、成功事例を積み重ねていけば、組織全体のAIリテラシーは確実に向上し、それは大きな競争力となるはずです。
おわりに
この記事では、分かりやすさを優先して「ASD」と一括りにしてきましたが、「スペクトラム」という言葉が示す通り、その特性や程度は人によって様々です。ASDの特性がある方すべてが、ここで述べたような「ズルができない」性質を持つわけではありません。
ただ、もしあなたが「どうも自分はズルをするのが苦手で、綺麗事ばかり言っている、空気読めない、と周囲から浮いてしまう…」と感じているとしたら、この生成AIによる変革期は、あなたのその「ズルができない」性質を強みとして活かせる大きなチャンスかもしれません。
この記事が、そんなあなたが自分の周りに新しい可能性を見出す、何かしらのきっかけになれば、とても嬉しく思います。
Views: 1