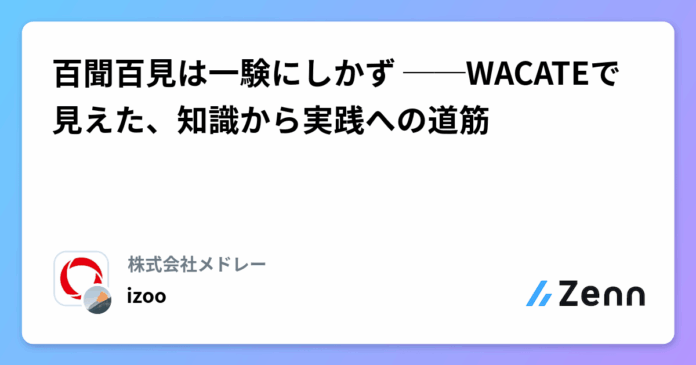こちらの記事は「MEDLEY Summer Tech Blog Relay」の10日目の記事です。
はじめに
こんにちは。株式会社メドレーでQAエンジニアをしている井津です。
今年5月に開発者からQAエンジニアに転身し、現在は調剤薬局の基幹システムのQAをしています。
6月に「WACATE2025夏」という1泊2日の合宿形式のワークショップに参加してきました。本記事では、WACATEのプログラム内容の詳細には触れず、私がWACATEを通じて、知識として理解しているだけの状態から体験を通して現場での実践方法を見出すまでの過程を中心に書きたいと思います。WACATEに興味をお持ちの方や、知識と実践のギャップに悩んでいる方の参考に少しでもなれば幸いです。
WACATEとは
WACATEは「Workshop for Accelerating CApable Testing Engineers」の略で、ソフトウェアテスト技術者のための1泊2日の合宿形式ワークショップです。2007年から年2回(夏と冬)開催されており、若手から中堅のQAエンジニアや開発者を中心に、他業種も含めて幅広い層が集まります。
特徴的なのは、単に知識を教わるだけではなく、参加者自身が考え、手を動かし、議論するプロセスを通じて学べる点です。講義やグループワーク、ディスカッションが行われるほか、参加者同士の交流も非常に活発です。私は2025年夏のWACATEに初めて参加し、体験を通じて気づきを得られました。
参加前の自分
QAエンジニアに転身してから、テストに関する書籍を読み漁り、JSTQB Foundation Levelの資格を取得しました。理論的な知識は少しずつ身についてきた実感がありました。
しかし、得た知識を実際の業務でどのように使えばいいか分からず、壁にぶつかっていました。書籍に出てくる一般的な事例とは大きく異なる特殊なドメインで、テスト技法や手法をどう実務に当てはめればいいのか見当がつきませんでした。
知識は積み上がっていくが、実践に活かせない状況にもどかしさを感じていました。そんな時にWACATEの存在を知り、他社のQAエンジニアとの交流を通じて状況を打破するヒントが得られるかもしれないと思い、参加を決意しました。
WACATEで得られたこと
体験1:知識を使えた感覚
ワークショップはISTQBのテストプロセスに沿って進められました。開発者をしていた頃はテストの「実装」「実行」しか使ったことがなく、「分析」「設計」のプロセスは使い分けをせずに、頭の中で少し考えたり、メモに残す程度でした。(参考:ISTQB Foundation Levelのシラバス)

ISTQBのテストプロセス / WACATE実行委員の杞憂さんのスライドから拝借
今回は「美容院の予約システム」を題材に、分析から実行までの一連のフローを体験しました。ポストイットを使ってテスト観点等を一つずつ書き出し、グループで議論しながら掘り下げ、優先度をつけて整理していきました。正直、最初は「シンプルなシステムにここまで大げさにやる必要があるのだろうか」と感じていましたが、最後にこれまで作業してきたポストイットを見た瞬間、思考の過程がすべて可視化されていることに驚きました。
なぜこれを選んだのか、何を捨てたのか、すべて説明ができる状態になっていて、頭の中だけで処理していた時には得られない感覚でした。これまでの得た知識が自分の中に腹落ちしてきていると感じました。
WACATEでのワークショップの様子
体験2:参加者との議論で得た気づき
チームは私を含めた6名で、職種(QAエンジニア、開発者)、業界、経験年数がバラバラのメンバーで構成されています。事業会社の開発者やQAエンジニア、第三者検証会社のQAエンジニアなど、多様な背景を持つ人たちとディスカッションしながら作業を進めました。
予約システムというシンプルな題材に対して、様々な視点やアイデアが出てきました。開発者は実装の観点からテスト範囲をイメージし、第三者検証会社のQAエンジニアの方は豊富なテスト技法やアイデアを提案し、事業会社のQAエンジニアの方はユーザー目線での観点を重視していた印象があります。どれも的確で、多様な視点が入ることで議論が広がりました。
最終的にみんなで合意した内容を、チーム全員で取り組めたことはとても貴重な経験でした。意見の相違もありましたが、短時間のワークということもあり、譲り合いながら建設的に進められました。
今回のワークを通じて、多様な人を巻き込んで進めていく感覚とその難しさを改めて体験できました。実際の業務でも開発者、CS(カスタマーサポート)、PdMなど様々なステークホルダーを巻き込んで、サービス品質の向上を主導するのがQAエンジニアの役割だと思うので、良い経験になったと思います。
体験3:「このシステムならでは」の観点
総括の際、実行委員長から「『このシステムならでは』を意識できていたか?」というフィードバックがありました。
普段扱うシステムが特殊ということもあり、その辺りは意識できていると思い込んでいました。美容院を想像しながら作業を進めていたつもりでしたが、振り返ってみるとテストプロセスに沿って進めることや、どのテスト技法を使うかに意識が向きすぎていたと思います。反省です。
標準的な観点だけをチェックするのであれば、どんなシステムでも同じことができます。しかし本当に価値あるテストとは、そのシステムならではの特性を理解し、ユーザーや業務にとってどうあるべきか、どうあってほしいかを想像しながら観点を導き出すことです。実行委員長の言葉でその意識の重要性を再確認できました。
これからどう活かすか
現在、大きなプロジェクトが2つ進行しており、WACATEで体験したテストプロセスをアレンジして実際に適用しています。そのまま使うのではなく、私たちの現場に合うよう模索しながら、開発者やSRE、CS(カスタマーサポート)と相談して進めています。まずはQAエンジニアとしてこれらのプロジェクトを成功させ、うまくいった手法は体系化してチーム全体に広めていきたいと考えています。
調剤薬局の基幹システムは、制度変更が定期的に行われ、厚生労働省や各自治体等が公開する専門的な資料を理解する必要があり、医療という緊張感のある現場で使われる特殊なドメインです。非常に難しい分野ですが、毎日新しい発見があり、やりがいを感じています。
システムに関わるチームメンバー全員が本気で良いものを作ろうと取り組んでおり、その一員でいられることを嬉しく思います。WACATEで得た気づきをチームに還元し、全員でもっと良いものを作り、多くのユーザーに安心して使っていただけるサービスを提供したいです。
おわりに
WACATEは知識を実践につなげる貴重な体験の場でした。参加前は頭の中だけにあった知識が、体験を通じて使い方を具体的にイメージできるようになり、実務で変化が起きつつあります。
以前読んだ本に「テスト観点は、今のチームの実力以上のものは出てこない」と書かれていました。確かにその通りだと思います。想像できないものはテストできないということなので、ユーザーに価値のあるサービスを提供するには、日々経験を積んで視野を広げていくしかないのだろうと思います。
松下幸之助さんの「百聞百見は一験にしかず」という言葉の通り、知識を現場で活かすためには実際の体験が欠かせません。もし知識と実践の間で悩んでいる方がいたら、ぜひWACATEのような場に参加してみてください!
メドレーでは各種エンジニアを募集しています!興味のある方、ぜひご連絡お待ちしています。
MEDLEY Summer Tech Blog Relay 11日目は、メドレー倉林さんの記事です!お楽しみに!
Views: 0