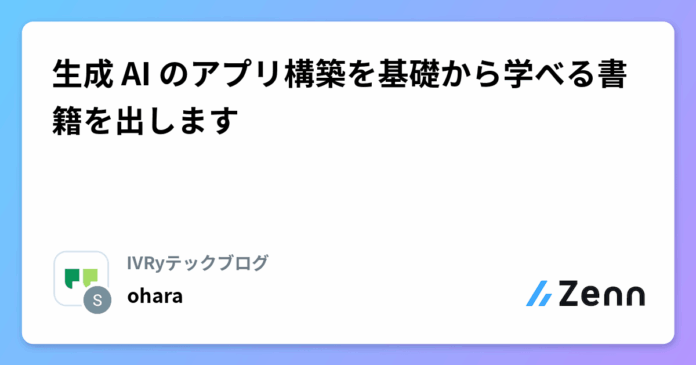この度、08/22 に共著という形で書籍を出版させていただくことになりました。
簡単な自己紹介
普通の記事では、書く必要がないと思うのですが今回は自分語り的な要素も含まれているため、簡単に自己紹介をさせてください。
私は、2021 年から、AWS のソリューションアーキテクトと呼ばれるポジションで活動をしており、主にスタートアップ向けの技術支援をさせていただいてました。中でも、生成 AI 関連の支援やヘルスケア周りの支援には力を入れており、対外的な発信や個別支援含めて大小さまざまにやらせていただいてました。
その後、2025 年 6 月からは、株式会社 IVRy にて、AI エンジニアとして電話応答であったりアプリ利用のスムーズ化を AI の専門知識を生かしながらエンジニアリングをしています。社内的には少しだけですが生成 AI を使ったコーディングツール周りの啓発活動みたいなこともしています。
なんで書籍を書こうと思ったの?
実は、書籍を書き始めたのは 2023 年 10 月ぐらいからです。最初は、共著者の針原さんから前職の社内 Slack で声をかけていただいたのがきっかけとなってます。自分としてはネットにさまざまな情報が転がっているからこそ書籍として最初に体系的に学ぶニーズは必ずあるだろうと思っていました。また、AWS の人間としても生成 AI を活用しようとしている方々と日々接している中で、生成 AI について体系的に学ぶ機会を欲している方が多いことも日々実感をしていたところでした。
個人としての視点になると、「本書きました!」というと良い自己紹介にもなるし、名前自体は良くも悪くも残るので、自分の対外的な発信にも使わせていただこうかな、という思いでした。
当たり前ですが、共著者のメンバーも魅力的で、針原さんもゴリゴリ実績を残している方でしたし、吉田さんも AWS Serverless Hero を始めさまざまなコミュニティ・対外活動・ビジネスにおいて積極的に参加されている方でした。3 人のバックグラウンドとしても、
- 針原さん: AWS にて生成 AI を作る人たちを中心に支援
- 尾原(私):AWS にて生成 AI を使う人たちを中心に支援
- 吉田さん:生成 AI をビジネスにて積極的に活用
といった形で、三者三様でバランスの取れた視点から書籍が書けそうとなったのは、かなり良いポイントだったと思っています。
当時、AWS に在職していた時も社内的にもどんどん生成 AI についての発信をしていきたいと盛り上がっていた時期でもありました。もちろん社会的にもめちゃくちゃ盛り上がっていますし現在も続いていると思います。
一方で、コーディングエージェントをはじめとするツールの普及により「生成 AI アプリ / サービスを使う人口」は爆発的に増えたと思うのですが「生成 AI を使ったアプリないしはサービスを作る人口」は案外増えていないかもしれないというのも肌感としてあります。私としては、生成 AI の可能性を考えると、まだまだ使われてない場面がとても多いように感じています。ここの利活用が一歩でも進むような活動ができたらいいなというのも感じていました。
書籍執筆裏話
執筆裏話というか、苦労話になるのですが、やはり実際の業務をしながら執筆作業を進めることの難しさはとても痛感してました。
この書籍自体を書き始めたのがほぼ 2 年前にあたるわけなのですが、そこから平日朝の 2 時間を使って作業を進めるということを進めていましたが、別業務の差し込みが多かったり純粋に朝起きれなかったり。。などでなかなか前に進めることが難しい時期もありました。
その中でも、なんとかお互い激しましあってなんとか出版に漕ぎ着けられたのはとても良い思い出です。
よかった話としては、純粋に執筆を進めていくと必然的に自分の知識不足にもぶち当たるケースも多くなり、そこに対して丁寧に調べながら進めることで自分自身の理解度が 10 レベルぐらい上がった感覚はあります。書籍を執筆するのはもちろん様々な方に書籍を通じて何かを学び足しにしていただきたいという目的があるのはもちろんなのですが、自身の勉強にもとても繋がるなというのを実感しています。
また、AWS サービスのアップデートが定期的にやってくるのが 1 つ頑張りポイントでもありました。直近ですと、AWS Summit New York City において Amazon Bedrock AgentCore と呼ばれるサービスがプレビュー版として発表がされたのですが、これも 7 月のイベントとなっており書籍発売予定日の 2 ヶ月前のことになります。これらのアップデートを盛り込みながら進めるのは一筋縄ではいかない大変さがありました。
書籍の推しポイント
そんなこんなで、書籍に関しての思いの丈をつらつらと書かせていただいたのですが、せっかくなので書籍で特に力を入れたポイントをいくつかピックアップしてあげさせてください。
実践だけではない
今回の書籍においては、比較的生成 AI を使ったサービス構築に使えるライブラリや関連サービスの解説もさせていただいているのですが、生成 AI に関連する概念の解説に力を入れています。
例えば AI エージェントを解説する章では、AI エージェントにまつわる歴史から、なぜエージェントがここまで注目されるようになったのかについて要素に分けて網羅的に解説をしています。このあたりの背景を知っておくことによって、今後の生成 AI のアップデートがあった時のキャッチアップがとても楽になります。
例えばですが、「推論能力の向上」と言われた時に「なぜ推論能力が向上するといいんだっけ?」「AI エージェントにどういう関わりがあるのだろうか」というつながりが見えるようになります。
生成 AI サービス・アプリのビジネス導入にも触れている
実践を超えてというパートがあるのですが、ここではいざリリースした生成 AI アプリ・サービスをどのように保守・運用していくべきなのかやベストプラクティスについてや、Amazon 流のイノベーションメカニズムを用いた生成 AI ユースケースの見つけ方についても触れています。
お客様にお金を払ってもらえるようなサービスに仕立て上げるために必要なピースについて、なるべく網羅的観点で解説するようにしました。
買ってね!!!
今回の記事で、興味を持っていただいたみなさま、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです!!
基本からビジネス導入まで、まずはこの 1 冊から始められると信じています。
再度学び直したい方から、これから学びたいという方まで、興味あれば読んでください。
謝辞
この書籍を執筆する上において、本当に数えきれない方々の支援・サポートをしていただきました。
この場を借りて御礼申し上げます。
Views: 0