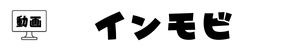パラノイアは日本では「偏執病」と訳され、なにかに極端なこだわりがあることだと思われている。これは欧米も同じで、インテルを世界最大の半導体企業に成長させたアンドリュー・グローブは「パラノイアだけが生き残る」と述べ、ほとんどのひとが気にしないような細かなことにも徹底的にこだわる重要性を強調した。
だが精神医学でいうパラノイアはこうしたニュアンスとは異なり、「不安や恐怖の影響を強く受けており、他人が常に自分を批判しているという妄想を抱くものを指す」(Wikipedia)。ひと言でいうなら「被害妄想」のことだ。
ダニエル・フリーマンはオックスフォード大学心理学部教授で、パラノイアに関する世界的権威とされる。『パラノイア 極度の不信と不安への旅』(高橋祥友訳/金剛出版)はそのフリーマンが、30年におよぶ自身のパラノイア研究を振り返るとともに、現代社会にはパラノイア(被害妄想)が蔓延しており、それがコロナ禍の反ワクチン論などの陰謀論の温床になっていると論じている。
 イラスト/emma / PIXTA(ピクスタ)
イラスト/emma / PIXTA(ピクスタ)
人口の25%(4人に1人)から30%超(3人に1人)がパラノイア的
本書は駆け出しの心理学者(統合失調症患者に対する心理療法の臨床試験の研究助手)だった頃のフリーマンが、ロバートという患者の家を訪れたとき、玄関ではなく裏庭の草むらをかき分けながら裏口に向かった思い出から始まる。こんなことになったのは、政府の秘密組織が自分を殺そうとしているとロバートが信じ込んでいたからだ。そのため彼は玄関からの来訪者をすべて拒み、家のなかでも音を立てず、窓の下にうずくまってじっとしていた。
そんなロバートに会う方法はたったひとつしかなかった。裏口の脇の窓を3回ノックするのだ。すると台所がわずかに開いて、ロバートが不安そうな顔を見せ、室内に招じ入れてくれた。
その当時、ロバートのようなパラノイアは統合失調症の典型的な症状とされていた。だがこのとき、フリーマンは精神医学の常識に違和感を覚えた。「ロバートはよく話し、会話に熱中し、自分の感情を語ることができる」と知ったからだ。その会話は支離滅裂なものではなく、ロバートの人生やこれまで経験してきたことを前提とすれば理にかなったものでもあった。
このような臨床経験からフリーマンは、パラノイアは一部のひとに発症する「病気」ではなく、わたしたちはみな多かれ少なかれ「パラノイア的」で、それが極端になったものが精神疾患と見なされるのだと考えるようになる。
その後の研究によって、診断は下されていないものの、人口の1%から3%が重度のパラノイアを経験していることがわかった。人口の5%から6%は軽度であるものの、苦痛に満ちたパラノイアを有しており、さらに10%から15%は、軽度ではあるものの、つねに妄想様観念を抱いているという。
コロナ後の2023年に、年齢、性別、人種、収入、地域を代表させた1万人以上のイギリス成人を対象とした大規模な調査が行なわれた。
それによると、「誰かが自分たちを困らせようとして害をもたらそうとしている」との文章に38%が「ある程度」「完全に」確信していると答えた。27%は「誰かが自分たちを傷つけようとしている」と述べ、28%は「迫害」のために苦痛を感じていた(重複可)。
こうした調査は、人口の25%(4人に1人)から30%超(3人に1人)がパラノイア的であることを示している。――あなたも身近に被害妄想を抱いているひとの心当たりがあるだろう。
被害妄想というのは、「何者かが自分に危害を加えようとしている」と警戒することだ。実際に世界が危険に満ちているならば、こうした性向(強い警戒感)は生存の確率を高めるだろう。
人類の祖先が暮らしていた旧石器時代の濃密な共同体は、「強い絆で結ばれたあたたかな社会」ではなく、すべてのメンバーが誹謗中傷の噂によってライバルを貶め、自分のステイタスを上げようと“陰謀”をめぐらせていたかもしれない。徹底的に社会的な動物である人間は共同体から排除されたら生きていけないのだから、そのような「残酷な世界」で生き延びるためにパラノイアは進化によって選択されてきただろう。
それが近代以降、とりわけ第二次世界大戦後になると、欧米や日本のような先進諸国で人類史上あり得ないような「ゆたかで平和な社会」が実現された。その結果、パラノイアに「猜疑心」や「被害妄想」のようなネガティブなレッテルが貼られ、ついには「精神病」に分類されてしまったのだ。
世の中の3分の1のひとは実際に他者の危害にあっており、その正常な反応として被害妄想的になったのかもしれない
2007年にイギリスで全国的に実施された「成人精神障害罹患率調査(APMS)」では、面接された7000人の成人のうち、18.6%が過去12カ月間のある時点で「他者が自分に敵対してきた」と考えていた。8%は「他者が意図的に自分に害を加えようとしていた」と信じており、ほぼ2%が「いくつものグループが意図的に自分に重傷を負わせようとしていた」と信じていた。
8580人のイギリスの成人に対する別の全国調査では、過去12カ月以内に21%が「他者が自分に対して敵対してきたと感じたことがある」と報告し、9%が「自分の考え方が操られているのではないか」と疑い、1.5%が「重傷を負わせようとする陰謀があったと怖れていた」と述べた。
こうした傾向はイギリスだけでなく、ニューヨーク(マンハッタン)の一般医に登録されている1005人の成人についての調査では、10.6%が人生のある時期に追跡されたり監視されたりしたことがあると考えていた。さらに7%ちかくが「自分は陰謀の犠牲者だ」と信じており、約5%が「秘密裏に何らかの試験の対象にされている」と疑っていた。
このように、心理的な問題があると診断されたわけではなないひとのあいだでも不信感(パラノイア傾向)は幅広く認められる。だがこれは因果関係が逆で、世の中の3分の1のひとは実際に他者の危害にあっており、その正常な反応として被害妄想的になったのかもしれない。
どちらが正しいかを知るためにフリーマンは、「仮想の地下鉄」という独創的な実験を行なった。
参加者はロンドンに住む100人の男性と100人の女性で、VR(仮想現実)でつくられた超満員の地下鉄に2分間乗車した。他の乗客はすべてアバターで、ごく自然に振る舞うようにプログラムされ、なにひとつ特別なことは起こらないようプログラムされた。
参加者の多くは、当然のことながら、「いつもの地下鉄のように感じました。人々は自分の行きたい場所に行こうとしているだけでした」と感じた。アバターは、まさにそのように見えるように正確にプログラムされていたのだ。
ところがフリーマンは、別の反応をする2つのグループがあることを発見した。ひとつはポジティブな反応で、自分の体験を以下のように報告した。
「素敵でした。現実の経験よりも快適でした。現実の状況ではそれほど感情を素直に表しません。彼らは本当に親し気でした」
「ひとりの男性は私をじっと見つめて、お世辞を言いました」
「微笑みかけてくる人がいて、それはとても心地よかったです」
もうひとつはネガティブな反応をするグループで、以下のような体験をした。
「数人の男たちが集まっていて、ひどく不快でした。私が通り過ぎようとすると、座っていた女性が私を笑いました」
「攻撃的な人がいました。私を脅して、不快にさせようとしました」
「ある男はすっかり頭にきて、私を指さしたのです」
Views: 0