🧠 概要:
概要
この記事では、著者が自身の執筆スタイルを見直し、量よりも質を重視することの重要性について語っています。過去に長文を書いていた経験から、短いが心に響く言葉の力に気づき、それを大切にするようになったことを伝えています。また、言葉の価値は文字数ではなく、感情の温度にあると強調しています。
要約ポイント
- 1万文字以上を書くことがあったが、自分でも内容を理解できないことが多かった。
- 長文に対する自信が、反作用として「意味わかんない」と言われる等の悩みを生んでいた。
- 感動する文章は短いものであることに気づく。
- 短い言葉は読者に余白を与え、自身の感情を重ねることができる。
- 誰かの共感を得られる言葉を選ぶためには、感情をよく感じた上で言葉を選ぶことが大切。
- 量ではなく、深みや温度が重要であり、1000文字に本気を込めることが大事。
- 過去の長文執筆を否定せず、それが今の考え方に繋がったと認識。
- 書けない、長くできないと自分を責めている人へ、言葉の価値は量ではないと励ます。
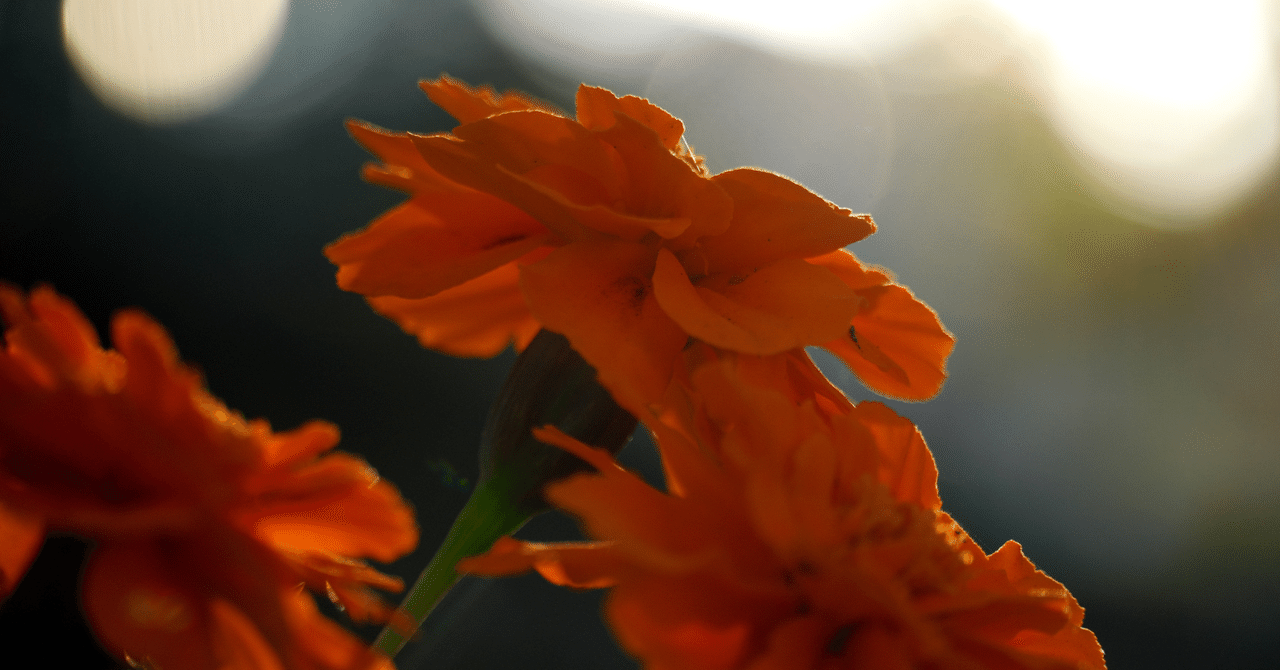
気づけば1万文字を超えてる
なんてこともよくあった。
でもそういう記事って
読み返すと、自分でもよくわからない。
途中で何が言いたかったのか
分からなくなってるし、
熱量たっぷりで書いたはずなのに、
届いてる感覚がまるでない。
それでも、
「これだけ書いたんだから」
と思いたくて、
言葉の量で
自分を肯定しようとしてたんです。
自信満々で効果して、
「意味わかんない」て言われて、後悔して…
そんなことを
繰り返しながら進んできて。
あるとき、
ふと気づいたんですよね。
自分が感動した文章って、
どれも短かったなって。
スマホで何気なく見たツイートとか。
でスクロールせずに
読めるくらいの小さな記事とか。
その1000文字にも満たない言葉が、
ずっと心に残ってたりする。
“伝わる言葉”って、
たくさん書いた結果じゃない。
1つの物事を
ちゃんと感じきった、
”己の感情”から生まれるんです。
全部言い切らないからこそ、
読んだ人の中で
余白が生まれて、
そこに自分の気持ちを重ねてもらえたりね。
たとえば誰かの
「今日は何もできなかった」
って一文に
励まされることってあるじゃないですか。
「わかるよ」
「それでもいいんだよ」
って言われたような気がして。
それって
長い解説なんかよりずっと強い。
だから今は、
“1000文字でどこまで本気になれるか”
を大事にして書いています。
長く書ける人がすごいんじゃない。
短くても、濃く残る言葉を
書ける人のほうが、いいこと言えてる。
誰かの心を
動かしたいと思ったとき、
どこかの誰かに
「それ、まさに自分です」
と言ってもらいたいと思ったとき、
気にするべきは
どれだけ、その言葉の前に沈黙できたか。
どれだけ、ちゃんと感じたうえで、言葉を選んだか。
それだけなんです。
無意味な1万文字を書いた
あの時の自分を否定はしません。
あの時間がなかったら、
今の書き方にはたどり着けなかったから。
でも、もし今あなたが、
「書けない」
「長くできない」
って自分を責めてるなら。
大丈夫です。
言葉の価値は、量じゃない。
あなたの1000文字の中にしかない温度が、
確かに、誰かに届きます。
↑ここまで931文字ね☺️
Views: 0

