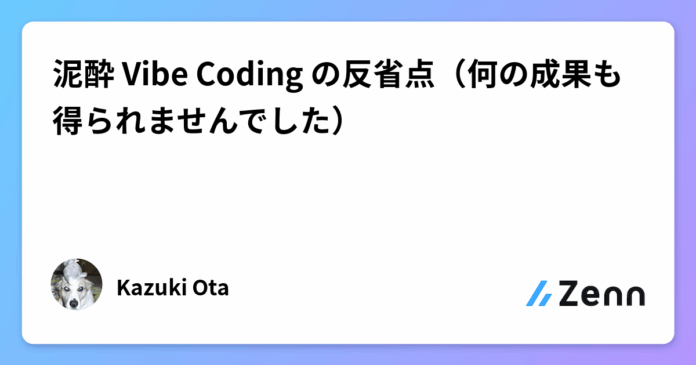結論
ほろ酔いをお勧めします。
本文
本日、泥酔 Vibe Coding をしようというお誘いを @yuma_prog さんから受けて、@Yuhei_FUJITA さんと @ponponmikankan さんと一緒にやってみました。
泥酔 Vibe Coding ということでお酒の飲める場所でお酒を飲みながら、Vibe Coding をするというものです。レギュレーションは以下のページに従いました。
はじめた後の感想
泥酔という単語を真に受けて私は泥酔するためのお酒として本気のものを選びました。

500ml 缶のアルコール度数 9% のものを 3 つ選びました。それがそもそもの間違いの始まりでした。
gemini に「OK Google 500ml 缶でアルコール度数 9% のものを 3 本飲んだらどうなる?」と聞いたら色々言っていましたが「生ビール 5 杯分くらい」と言っていたので普段 10 杯くらいまでは飲めるので大丈夫だろうと思って買いましたが、体感的には 10 杯くらい飲んだ程度には何もできなくなりました。
最初は「GitHub Copilot Agent Mode で gpt-5 も来たし楽勝やろ」って思ってましたが、全然そんなことはありませんでした。途中から Agent Mode が何をしているのか判断できなくなり GitHub Spark に移動したものの何の成果も得られずに終わってしまいました…。
反省点
泥酔 Vibe Coding とは、あくまでネタであり実際には「ほろ酔い Vibe Coding」をするのが正しいと思います。泥酔してしまうと何もできなくなってしまうので、せめてほろ酔いくらいでやるのが良いでしょう。
また、お酒を飲んでやる場合は Coding を支援する AI ツールではなくアプリ作成を支援する GitHub Spark のようなツールを使った方がアイデアを適当に動く形で出してくれるので良いと思いました。少しくらいお酒を飲んでも大丈夫だろうというのは慢心であるということを学びました。
まとめ
お酒はほどほどに…。
他の参加者の成果
私は何の成果も得られませんでしたが他の参加者は割と成果を出していました。最初から GitHub Spak 相当のものを使っていたのが大きかったのではないかと思います…。
あとお酒も常識的な範囲だったような気がします。
その他有益な情報
ヴァイオレットエヴァーガーデンとメダリストと四月は君の嘘とダイの大冒険と鋼の錬金術師はいいぞ。
他の参加者の記事
主催者の @yuma_prog さんの記事からたどれます。
Views: 0