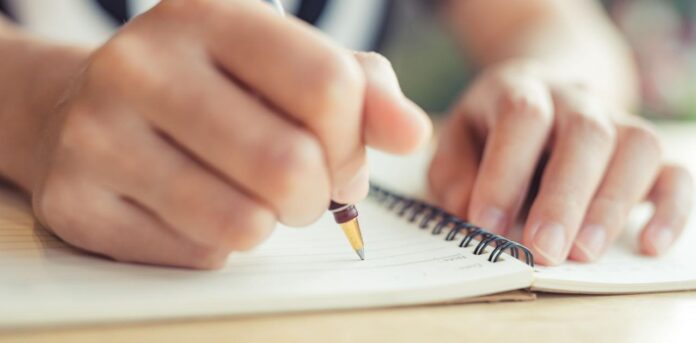「日記を書きたいけれど、続かない」
「何を書いても、ただの記録で終わってしまう」
そんなふうに感じていたなら、時間のある今がチャンスです。
日記は過去を振り返るためだけのものではありません。実は、未来の自分を少しずつ仕込んでいくための「思考の装置」としての強力なツールになるとしたら。
日々の言葉が、じわじわと自分の認識や行動を変えていく──
そのしくみを行動経済学の視点から紐解きながら、今日から日記を書きたくなるヒントをご紹介します。
自分の気持ちは、行動に引っ張られる?
人は、行動に合わせて思考や好みを変える傾向があります。これは心理学者レオン・フェスティンガーの認知的不協和理論(1957)で知られる考え方。
たとえば、「毎朝ランニングを続けている人」がいるとします。最初は義務感でも、続けるうちに「運動が好きだからやっている」と脳が納得しはじめる。つまり、「行動が先、思考はあと」なのです。
この仕組みは、行動経済学でも重視される“選好の形成”のメカニズムと深く関係しています。
人は最初から明確な好みや信念を持っているかどうかに限らず、行動を通じて“自分はこういう人間なんだ”というイメージを後づけでつくっていくのです。<行動経済学における選好の内生性(preference endogeneity)の概念より>
書くことが行動を先回りすることもある
では、なぜ「書くこと」が行動を先回りしたり、自己イメージをつくったりすることにつながるのでしょうか。それは、書くという行為が、私たちの意識や脳にいくつかの働きかけをするからです。
例えば、日記に「今日のよかったこと」を書こうと決める(書く)と、一日を過ごす中で自然とポジティブな出来事を探すアンテナが立ちます。書くことで、何に注意を向けるべきか、思考の焦点が定まるのです。
また、「私は挑戦できる人間だ」といった言葉や、小さな「できたこと」を記録することは、その自己イメージや行動を脳にインプットし、強化します。
次に何かを判断したり行動したりする際に、無意識のうちに「書いた自分」に沿った選択をしやすくなる――日記は、このような形で私たちの内面に働きかけ、未来の行動を少しずつデザインしていくパワーツールになり得るのです。
つまり、毎日の日記に少し前向きな言葉を書いておく。それだけで、未来の行動が変わる可能性があるのです。
日記の書き方に迷ったら、3つの質問
日記は、特別な出来事を書かなくても大丈夫。むしろ、小さな肯定の積み重ねが「私は大丈夫かもしれない」という実感につながっていきます。
以下のような視点で書いてみると、思考の流れが少しずつ整っていくはずです。
1.「できたこと」をひとつだけ書く
例:「今日はちゃんと起きられた」「資料を提出できた」
→ 行動の記録を、自分へのエールとして残す。
2.「よかったこと」を拾う
例:「電車で席をゆずってもらった」「子どもがよく笑っていた」
→ 他人や環境からもらったポジティブな刺激に目を向ける習慣づくり。
3.「自分への言葉」を1行添える
例:「今日もよくやった」「この状態からでも進める」
→ 未来の自分に届けるような、やさしい一言を入れておく。
日記は、理想を宣言するためのものではなく、すでにある事実を肯定するための場所です。
自信が欲しいときほど、「信じる理由」を先に仕込んでおくことで、自然と行動のハードルが下がっていきます。
たまにはじっくり自分を整える時間を
外へ出かけるのも楽しいけれど、静かに自分と向き合う時間も、心にとって大切な栄養です。
連休のスキマ時間に、数行の日記からはじめてみませんか?「私は大丈夫」と書いてみることで、少しずつ脳がそれを信じはじめるはずだから。
Views: 0