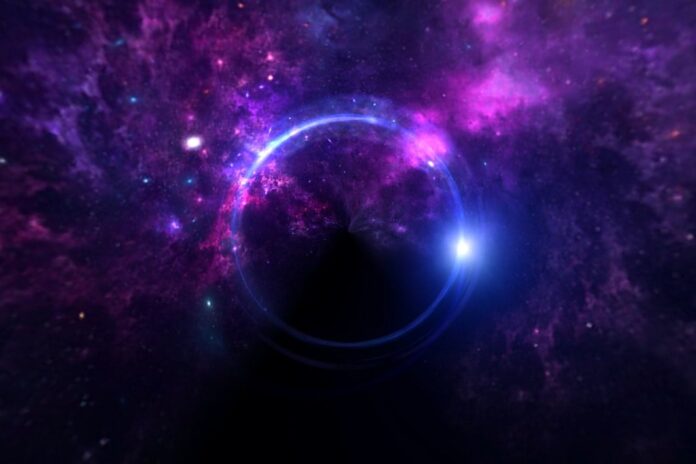暗闇に隠れたその正体は、まるで「凍りついた光」なのかもしれません。
アメリカのダートマス大学(Dartmouth College)で行われた研究によって、初期宇宙で光のように高速で飛び回っていた粒子たちがペアを組んで、やがてエネルギーを失って“冷たく重い暗黒物質”へと凍結した可能性が浮かび上がりました。
銀河を形作る見えない質量の正体が、かつて光速粒子だったというこの大胆なシナリオは、本当に宇宙の謎を解き明かす鍵になるのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年5月14日に『Physical Review Letters』にて発表されました。
目次
- なぜ闇は重いのか?
- 新理論では「暗黒物質=凍りついた光速粒子」になる
- 光速粒子が氷になった日
なぜ闇は重いのか?
私たちが普段目にする星や銀河など通常の物質は、宇宙全体のほんの5%程度に過ぎません。
残りの約25%を占めるのが暗黒物質、そして約70%が暗黒エネルギーと呼ばれる未知のエネルギーだと考えられています。
暗黒物質は直接見ることはできませんが、その強大な重力の影響で存在が示唆されています。
たとえば銀河の回転速度や銀河団を透過する光の重力レンズ効果など、観測事実は暗黒物質という“見えざる質量”の存在を強く示しています。
しかし暗黒物質が具体的に何者なのかは依然として謎です。
最有力候補だった「WIMP」と呼ばれる重い粒子も含め、これまで提案されてきた数多くの候補、たとえば弱い相互作用を持つ巨大粒子やアクシオン、原始ブラックホールなどは、未だ決定的な証拠が得られていません。
さらに前提となる標準模型との相互作用の強さを手がかりにした探索はことごとく空振りに終わり、暗黒物質の正体解明は長い停滞に陥っていました。
こうした中、米ダートマス大学の大学院生グアンミン・リャン氏とロバート・コールドウェル教授の研究チームが、まったく新しい暗黒物質像を提案しました。
コールドウェル教授は「ダークマターはその始まりにおいて、ほとんど光のような、質量がほぼゼロの相対論的な粒子だったものの、時間経過とともに質量を持つ存在に変わっていった」と述べています。
なぜ暗黒物質は光のような粒子から質量を持った存在になったのでしょうか?
新理論では「暗黒物質=凍りついた光速粒子」になる

理論モデルの舞台は、ビッグバン直後の灼熱の宇宙です。
宇宙誕生まもない頃、空間は超高温・超高密度のエネルギーの海でした。
光の粒である光子と同様に、質量を持たない(あるいは極めて軽い)粒子たちが光速に近いスピードで飛び交っていたと考えられます。
リャン氏とコールドウェル氏は、このカオスのような初期宇宙で暗黒物質の元となる粒子もまた「熱く、速い」状態にあったと仮定しました。
やがて宇宙が膨張して温度が下がると、これらの粒子同士の間に特定の自己相互作用が働き始めます。
研究チームによれば、この相互作用によって粒子たちはペアを組み、まるで水蒸気が急激に冷やされて水滴へと凝縮するようにエネルギーを失って大きな質量を獲得したといいます。
実際、粒子同士がペアを形成するときにエネルギーのギャップが開き、彼らはまさに「エネルギーの崖から滑り落ちる」ように一気にエネルギーを奪われてしまいます。
リャン氏は「私たちの数学モデルで最も予想外だったのは、高密度のエネルギー状態と塊状の低エネルギー状態を橋渡しするエネルギーの急低下でした」と、この劇的な“エネルギーの急降下”に驚きを示しています。
言い換えれば、質量がゼロの状態から有る状態へ粒子が相転移した転換点であり、この瞬間に暗黒物質は自らの冷たく重い性質を手に入れたのかもしれません。
では、なぜ粒子同士がペアを作り引き寄せ合ったのでしょうか。
研究チームはその理由を粒子のスピン(自転)の向きに求めています。
スピンが互いに反対向きだったために引き合ったのであり、イメージ的には磁石のN極とS極が引き合うようなものになります。
(※より詳しくは、実際には「軸性化学ポテンシャル」という効果などがはたらき、同じような運動状態をもつ粒子同士がクーパー対(ペア)を作ることで安定化します。)
こうして粒子と反粒子のペア(クーパー対類似の状態)の凝縮という相転移が起きると、粒子たちは次第にスピードを落として運動しなくなり、圧力もほとんどゼロの冷たい状態へと近づいていきました。
言ってみれば、初期宇宙の激しいダンスパーティーで熱狂的に動き回っていた粒子たちが、ペアになった途端に一斉にクールダウンして床に沈んでいったようなものです。
その結果残されたのは、重く非相対論的になった粒子の凝縮体です。
これは現在の宇宙で銀河に質量を与えている暗黒物質そのものに他なりません。
この相転移は宇宙論におけるフリーズアウト(凍結)にも似た役割を果たします。
(※通常の熱的アニヒレーションによるフリーズアウトとは異なるものの、温度低下と相互作用の変化によって暗黒物質の最終的な数が決まるという点で“フリーズアウト的”な役割を果たします。)
つまり、粒子が熱いプラズマから離脱し、その供給が断たれることで最終的な残存数、すなわち遺物としての暗黒物質の量が決定されたのです。
重要なのは、このモデルで生成された暗黒物質は従来のシナリオよりわずかに速いペースで減衰・希薄化していくという特徴を持つことです。
平たく言えば、現在の宇宙で測定される暗黒物質の分布やゆらぎに微妙な違いが現れる可能性があるということです。
このわずかなずれこそが、本理論ならではの指紋として宇宙の観測に刻まれているかもしれません。
ところで、一見奇抜にも思えるこの質量獲得メカニズムには、身近な物理現象との深い類似が隠されています。
研究チームがヒントを得たのは他でもない超伝導です。
特定の金属を極低温まで冷やすと電気抵抗がゼロになる超伝導では、クーパー対と呼ばれる電子のペアが形成されることが知られています。
普段は反発し合う電子同士が格子振動(フォノン)を介して引き合い、ペアになる現象です。
その結果電子は集団的な凝縮状態に入り、エネルギー的に安定したギャップを持ちます。
リャン氏とコールドウェル氏はこの現象に着目しました。
コールドウェル教授は「私たちは、ある種の相互作用がエネルギーをこれほど急激に低下させることができるのか、その手がかりを超伝導に求めました。クーパー対の存在は、そのようなメカニズムが現実に存在することを証明しています」と語っています。
つまり初期宇宙においても、電子のクーパー対形成に似た自己相互作用によって質量ゼロの粒子がペアを組み、エネルギー状態が劇変して質量を帯びたのではないかというわけです。
実際、彼らのモデルは南部陽一郎・ジョナ・ラシニオ(Nambu–Jona-Lasinio, NJL)モデルと呼ばれる素粒子論の枠組みに基づいており、これはもともと超伝導のBCS理論にならって質量の起源を説明するために考案された理論です。
既知の物理法則に基づくシンプルなモデルで無理なく暗黒物質の形成過程を描き出した点は、この理論の大きな魅力と言えるでしょう。
光速粒子が氷になった日

提案された「凝縮する暗黒物質」理論は、そのユニークさと説得力から注目を集めています。
この理論は突拍子もない思いつきではなく、現代物理学の知見に裏打ちされたシンプルで直感的な解決策です。
研究の第一著者であるリャン氏は「私たちの理論の数学モデルは多くの要素を組み込む必要がないため本当に美しいものです。
それは既に知られている概念と宇宙のタイムラインに基づいています」と強調しています。
複雑な現象を説明するために余分な仮定を投入するのではなく、最小限のシンプルな枠組みで宇宙の謎に迫るエレガントさがこの理論の説得力の源と言えます。
さらにこの理論が真に画期的なのは、具体的な観測で確かめられる予言を持っている点です。
どんなに美しい理論でも、実験や観測で検証されなければ単なる仮説に留まります。
本モデルは宇宙背景放射(CMB)など既存の天文データで検証可能な「指紋」を残すと予測しています。
ペア凝縮によって暗黒物質の状態方程式(圧力とエネルギー密度の関係を示す値 w)が時間とともに変化したことで、CMB の温度ゆらぎや偏光パターンに独特の影響が刻まれるとされています。
幸い CMB の精密観測はプランク衛星などによって既に極めて高い精度で行われており、今後はチリのシモンズ天文台や CMB-S4 計画といった次世代プロジェクトも控えています。
これらのデータを詳細に解析すれば、提案されたシナリオが妥当かどうかを確かめられる可能性があります。
コールドウェル教授は「これはエキサイティングなことです。私たちはダークマターについて考え、そしておそらくは特定するためのまったく新しいアプローチを提示しています」と述べ、観測による検証への期待を語っています。
注目すべきは、この理論が暗黒物質だけでなく暗黒エネルギーの謎にも光を当てる可能性です。
論文によると、もし上記の相互作用を持つフェルミ粒子が最初から完全な質量ゼロではなくわずかに質量を帯びていた場合、宇宙冷却の過程で相転移が途中で「挫折」し、粒子が高エネルギーの「偽の真空」と呼ばれる準安定状態に取り残される可能性があります。
その準安定状態の潜在的エネルギーが宇宙の加速膨張を駆動するダークエネルギーとして機能しうるというのが研究チームの主張です。
もしこのシナリオが正しければ、暗黒物質と暗黒エネルギーという宇宙の二大謎を単一の枠組みで説明できるかもしれません。
これは現在、暗黒物質と暗黒エネルギーの密度がほぼ同程度であるという「宇宙論の偶然の一致」問題にも新たな視点を与える可能性があります。
本論文ではさらに、このモデルの持つカイラル対称性の破れが物質と反物質の非対称(バリオン数過剰)と関連する可能性や、宇宙膨張速度を巡る「ハッブル張力」問題の解決にも寄与し得ることが示唆されています。
これらはまだ初期段階の議論ですが、一つの理論が持つ射程の広さとして大変興味深いポイントです。
総じて、ダートマス大学の研究チームが提示したこの新理論は、長年行き詰まりを見せていた暗黒物質研究に大胆な一石を投じる独創的アプローチと言えます。
初期宇宙における粒子のダイナミックな相転移という新視点は「冷たい暗黒物質」という既成概念にとらわれない自由な発想から生まれました。
同時に、このモデルは驚くほどシンプルでありながら現象を見事に再現してみせたことで理論に説得力を与えています。
そして何より、この仮説は机上の空論に留まらず、近い将来の観測で確かめられるチャンスがある点で非常にエキサイティングです。
コールドウェル教授も「新しいダークマターの考え方、そしてひょっとするとその正体の特定に向けた全く新しいアプローチだ」と期待を語っています。
光速で駆け抜けた粒子がペアとなり“凍りつき”、宇宙の暗闇を満たす質量へと変身したという壮大な仮説が、果たして現実の宇宙で起きていたのか。
今後の観測と研究がその真偽を明らかにしてくれることでしょう。
元論文
Cold Dark Matter Based on an Analogy with Superconductivity
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.191004
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。
大学で研究生活を送ること10年と少し。
小説家としての活動履歴あり。
専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。
日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。
夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
🧠 編集部の感想:
この新理論は、宇宙の謎を解明する可能性を秘めていて非常に興味深いです。「凍りついた光」という斬新なメタファーが、暗黒物質の形成過程をシンプルに表現している点が魅力的です。今後の観測でこの仮説が実証されるかどうか、非常に楽しみです。
Views: 1