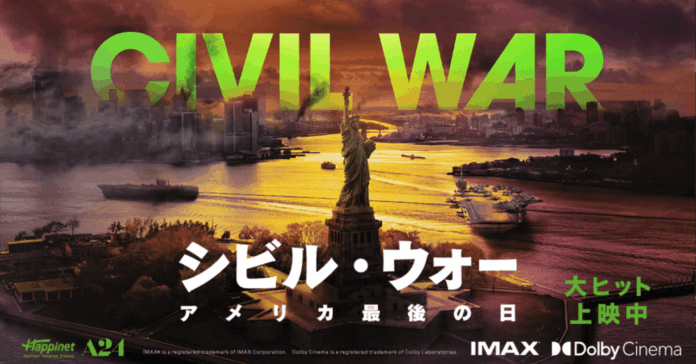🧠 あらすじと概要:
映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』のあらすじ
アレックス・ガーランド監督による本作は、アメリカが再び内戦状態に陥った場合の未来を描いたSF映画です。物語は、テキサスとカリフォルニアが主導する「西部勢力」と、南部の「フロリダ連合」という二つの勢力の対立からスタートします。主人公のリー・スミスという戦場カメラマンは、老記者のサミーや新人カメラマンのジェシーと共に、大統領へのインタビューを試みる旅に出ます。しかし、政府が崩壊し、アメリカ国内は混乱状態にあるため、彼らの道のりは険しいものでした。
旅の途中で、彼らは武装したガソリンスタンドの店員や、吊るされた男たちと遭遇し、混沌とした社会の現実を目の当たりにします。物語は、彼らが直面する危険や、内戦下での人間の本性について深く掘り下げていきます。
記事の要約
記事では、映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』の制作背景や評価、物語のあらすじに加え、映画が描くアメリカ社会の分断と混乱について考察されています。監督アレックス・ガーランドの過去の作品に触れつつ、本作のアプローチが現代の政治的テーマを反映していることを指摘しており、大統領の愚かさや、内戦状態における人々の葛藤が描かれています。全体として、映画が持つメッセージを強調しながら、視聴者に警鐘を鳴らす作品として評価されています。最後に、作品に対する一部の引っ掛かりや今後の発展についての期待が述べられています。
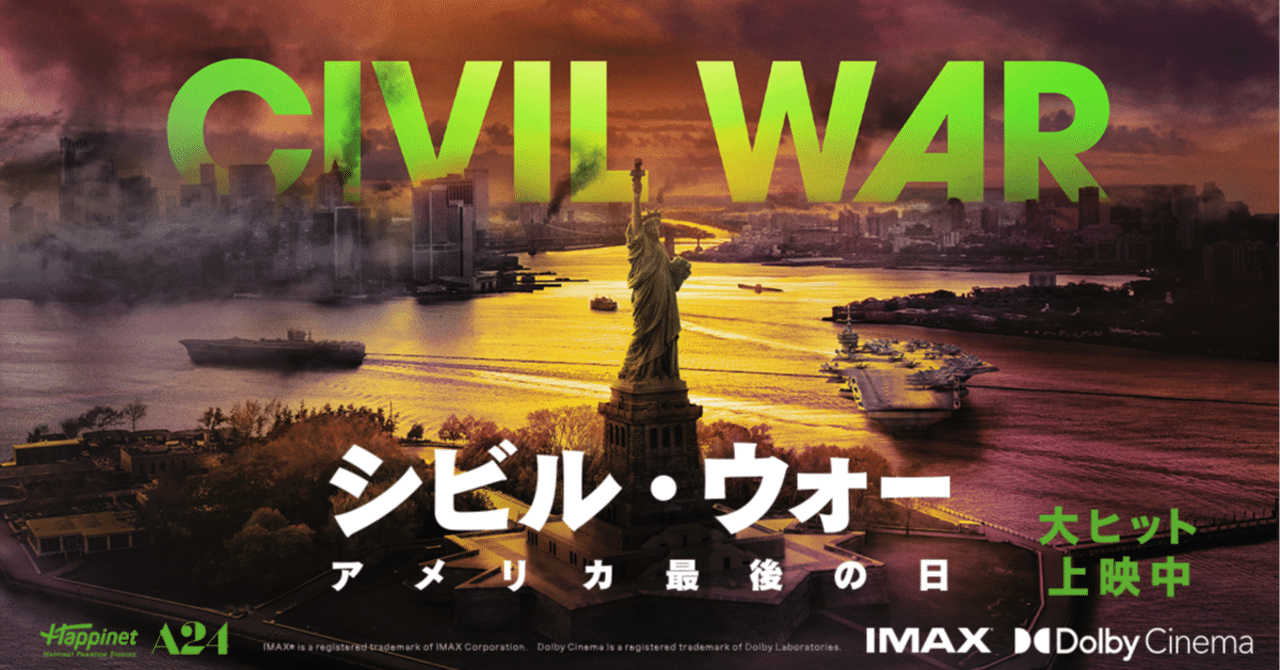
アメリカは再び分断する。
黒いアメリカ第3弾、アレックス・ガーランド監督の2024年の映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』。もしもアメリカが分断したらどうなるか……を描いたSF映画だ。 アレックス・ガーランドはもともと小説家で、映画にもなった『ビーチ』で小説家デビュー。その後、映画業界に入り、2002年のゾンビ映画『28日後…』で脚本家デビュー。『わたしを離さないで』、『ジャッジ・ドレッド』の脚本を手がけ、2015年『エクス・マキナ』で監督デビューする。『エクス・マキナ』は高く評価され、アカデミー賞視覚効果賞受賞。そこから『アナイアレイション 全滅領域』『MEN 同じ顔の男たち』を手がけ、本作は監督4作目となる。 製作はA24。A24はインディペンデント系映画会社で、ハリウッド映画のなかでも枠に収まりきらない、癖の強い作品で知られる。映画監督に制作の裁量を委ねる代わりに、低予算。近年のハリウッドにおける「大規模化」に背を向ける映画会社だ。 本作『シビル・ウォー』の制作費は5000万ドル。A24制作映画として異例の大予算だ(それでも最近の大作映画と比較するとかなり控えめ)。興業収入は1億800万ドル。
評価は高く、映画批評集積サイトRotten Tomatoesを見ると、批評家によるレビューは398件あり、肯定評価81%。一般評価は69%と少し落ちる。Metacriticでは100点満点中75点。現代の政治的なテーマを反映した作品であるので、どちらかといえば批評家受けしている作品である。
それでは前半のストーリーを見ていきましょう。
「私は今日ここに発表する。我らアメリカ合衆国正規軍による偉大な勝利により、テキサスとカリフォルニアによる自称《西部勢力》は再起不能となった。テキサスとカリフォルニアの人々よ、違法な《分離独立政府》を今すぐに撤回するのであれば、ただちにあなたたちを再び合衆国に迎え入れよう。フロリダ同盟はカロライナを同盟に引き入れようとしたが、失敗した。国民のみなさん、我々の歴史的勝利は近づいている。最後の抵抗勢力の排除は近い。皆さんと、アメリカに、神のご加護を」 大統領はテレビのなかで堂々と演説するが――実際には政府軍は追い詰められていた。西部勢力とフロリダ同盟はすでにワシントンD.C.の手前まで迫ろうとしていた。 ニューヨークに拠点を置く、戦場カメラマンのリー・スミスとジョエルは、老記者のサミーとともにワシントンD.C.に潜入する計画を考えていた。大統領は14ヶ月報道記者からのインタビューを受け付けていない。演説とは違う、大統領の本音はどうなのだろうか? それを聞き出すことが目的だった。 しかしニューヨークからワシントンD.C.への州道は寸断されているため、ピッツバーグからシャーロッツビルへと迂回しなければならなかった。 その旅に、新人カメラマンのジェシーがついてくる。まだ若いジェシーを連れて行くことに、リーは反対するが、「彼女は23歳だ。誰でも第一歩がある。君が23だった頃はもっと大人だったか」 とジョエルに説得され、連れて行くことに。 その旅の最中、ガソリンスタンドへ立ち寄る。ガソリンスタンドの店員は銃で武装していた。危険だが、給油のチャンスを逃すわけにはいかない。 ガソリンスタンドの店員は「給油許可証を見せろ」と言ってくるが、そんなものは持っていない。相場以上の価格で、カナダドルで支払うから、と交渉し、どうにかガソリンを手に入れることができた。 そのあいだに、ジェシーが洗車場へと降りていく。するとそこに、男が二人吊されていた。2日前にガソリンスタンドを襲撃し、返り討ちにあった二人だという。もはや虫の息だったが、まだ生きていた。「なあ、楽にしてやりたいならそう言え。一発ブチ込む。でなきゃ、もっと痛めつけようか?」 店員は笑ってそう語りかけてくる。
リーはそんな店員に「写真を撮らせて」と誘いかけるのだった。
ここまでで25分。 中央政府が崩壊し、人々はそれぞれで勝手に武装して自衛するようになっていた。ある意味アメリカらしい、アメリカ人の本性が現れている作品だ。
細かいところを見ていきましょう。

映画『シビル・ウォー』はもしもアメリカが分断し、再び内戦が始まったら……という「if」の物語である。その主要勢力が「西部勢力」と「フロリダ同盟」この2勢力が連合し、二つ星の星条旗を掲げている。
ではその内部を見てみよう。

まず「西部勢力」。カリフォルニア州とテキサス州が中心となっている。 なぜカリフォルニア州とテキサス州なのか? この二つの州はともに独立志向が強く、しばしば連邦政府の意向とは別の政治体制を持つことがある。また勢力としても強く、テキサス州は石油、天然ガスがあり、軍事拠点もある。カリフォルニア州はハイテク産業が強く、経済規模が世界トップレベル。もしも合衆国から独立……と考えた場合、この二つの州が中心に立つ可能性が考えられる。
では間のネバダ、ユタ、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナの5州はどうなったのだろうか? このあたりの細かい設定は公式設定でもあまり掘り下げられていないのだが、これらの5州は人口も少なく、独立性も弱いので、おそらくは西部勢力に併合されていると考えられる。「19の州が中央政府に反乱」と書かれているので、この数字を考えるとネバダ、ユタ、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナの5州は西部勢力に組み込まれていると考えられる。
では、なぜ「西部勢力」という設定が生まれたのか。

ヒントはこちらの地図。1824年のメキシコ帝国領の地図だ。19世紀はじまり頃まで、実はあのあたりの地域は「メキシコ領」だった。 1836年、テキサス地域が「テキサス共和国」として独立を宣言。ヨーロッパ各国が承認したが、メキシコは「ちょっと待て」。アメリカはイギリスの影響力を排除するために、カリフォルニアがもつ西側の海岸を所有したかった。そういう事情で、アメリカはテキサスを併合。 メキシコは「それは許さん」とアメリカに戦争を仕掛ける。これが1846年から1848年にかけて戦われた「米墨戦争(アメリカ・メキシコ戦争)」である。 この戦いにアメリカが勝利し、テキサスはアメリカの領土となった。
そういう歴史的背景があるため、確かに現在アメリカ領土であるが、文化的に見るとアメリカとはちょっと離れた地域であった。
次に南部地域による「フロリダ連合」

ちゃんとした公式設定がないからあくまで推測だけど、青で示された地域がフロリダ連合。オレンジの地域は「たぶんフロリダ連合」。冒頭に大統領の演説があり、「コロラドを引き入れることに失敗した」とあるので、大統領の演説が全て嘘でその逆であると考えると、ノースカロライナ、サウスカロライナもフロリダ連合に含まれると考える。これらすべてを含めれば、設定通り19の州ということになる。
ではフロリダ連合の元ネタはどこなのか?

1861年から1865年にかけた行われた「南北戦争」だ。地図の青部分が北部・アメリカ合衆国、赤部分が南部・アメリカ連合国だ。そもそも本作のタイトル『シビル・ウォー』は「南北戦争」のことであるので、南北戦争時代の勢力図を元ネタにしているのは間違いない。 アメリカ南部地域は今でも北部とは違って独特の文化圏を作っている。宗教をはじめ、音楽、アート、料理も独特で、南部特有の方言も存在している。 もしも内戦が起きると、対抗勢力となるのはこの地域であると考えられる。
西部勢力とフロリダ連合、つまり合衆国の南側全体が巨大な勢力となって、合衆国大統領に対し反旗を翻した……というストーリーになっている。

主人公グループは、その大統領に対しインタビューする計画を立てていた。この14ヶ月間、大統領の「大本営発表」があるばかりで、報道記者は誰もインタビューしていない。大統領の今の本音がどうなっているのか。それを聞き出すことが目的だった。

映画の中では、ニューヨークからワシントンD.C.まで1379㎞となっている。 しかし直線距離であれば、350㎞ほどのはず。
これは戦争で州道が塞がれているために、迂回する必要があった。

地図を見てみましょう。 ニューヨークを出発して、ピッツバーグを経由し、南部勢力が前線基地を作っているシャーロッツビルに入り、そこからワシントンD.C.に潜入する……という計画だ。 ニューヨークからピッツバーグで600㎞。 ピッツバーグからウェストバージニア州中心部まで200㎞。 ウェストバージニア州からシャーロッツビルまで250㎞。 合計1050㎞だ。(以上、AIによる推論)
さらに戦争で正規の道が塞がれていると考えられるので、迂回に迂回を重ねて1300㎞としたのだろう。
ここまでのお話しが、映画の前提設定。本編を掘り下げていきましょう。

主人公リー・スミス。演じるにはキスルティン・ダンスト。スパイダーマンでヒロインを演じていた人ですよ! いやぁトビー・マグワイアも見かけるたびに「年食ったなぁ」って思ってたけど、ヒロインも相応の年齢。しかも本作では、内戦で国が混乱している設定なので、スキンケアなどあえて一切せず。あえてこの顔を見せることで、内戦の深刻さを表現している。

名前は第2次世界大戦中、従軍カメラマンとして活躍した実在のカメラマン、リー・ミラーからとったもの。
なるほど、この顔に寄せたのか。

そんなリーに、あるとき弟子ができます。ジェシー・カレン。演じるのはケイリー・スピーニー。最近では『エイリアン:ロムルス』に出演。現在まだ26歳の若手女優だ。

サミー役を演じるのはスティーブン・ヘンダーソン。つい最近、『ボーはおそれている』で姿を見たばかりだったね。見間違いようのない風貌だ。最近は『DUNE/デューン』シリーズにも出演している。

もう一人注目は、従軍カメラマンの一人を演じたソノヤ・ミズノ。『エクス・マキナ』で映画初出演して以来、アレックス・ガーランド監督作品すべてに出演している。

リーの回想シーンで描かれる、どこかの場面。黒人がたくさん描かれているから、南部地域のどこかだろう。

「FUCK THE WF(西部勢力)」と落書き。ニューヨークは合衆国軍の支配域のはずなので、西部勢力は敵。航空機で読み取れるように、大きく書かれている。
でもこのサイズ、どうやって書いたんだろう? 足場を組んだのかな?

そんなニューヨークの日常風景。警官隊と住民が水を巡って衝突している。俯瞰構図の時に、周囲にテントがたくさん作られていたから、南部地域から逃げてきた人だろう。リーの回想シーンが南部地域だとすれば、内戦状態になってから訳のわからないくらいの混沌状態に陥ったのだろう。北軍と南軍の戦いだけではなく、関係ない住民同士、グループ同士の抗争も過激化して……。そこで北側に逃げてきたけれども、生活物資が供給されず、暴動……といったところだろうか。

いよいよ出発。その途上のガソリンスタンド。入りたいけど、店員が武装している。見るからに物騒な雰囲気……。
ある意味でこれがアメリカらしい風景。国家も警察も頼りにならない。いざとなったら自分たちで武装するんだ……というのがアメリカ人の基本的な心象。アメリカ人からなぜゾンビ映画が生まれたのか、それは根本的に隣人を信用していないから。現実でも災害が起きると、みんな近くの店に突撃して略奪を始める。そういう実態があるから武装して我が身を守る。アメリカがあれだけ銃にまつわる問題を抱えながらも、規制をかけられない理由がこれ。

こういった無政府状態になると、ある一定層の人々にとって逆転のチャンスになる。 この場面で吊されている二人は、家族のためにやむなく襲撃チャレンジをしてみた……という人。話し方の雰囲気からして、こういう荒事は苦手なタイプ。 その一方、銃を構えているにいちゃんは、いかにもな社会的底辺。無政府状態になる以前は、世の中にろくな居場所がなかっただろう。そういう二人が、今こういう状態になっている。
社会が荒廃すると、こういう荒くれ者が優位な社会になる。

旅の途中、青いビブスを着た人たちの一団と会う。「GLOBAL RELIEF FUND」は「グローバル救済基金」のことなので、人道支援団体のボランティア。

場面はスタジアムだが、廃墟のように荒れている。内戦で使われなくなったスタジアムを避難民収容所にして、ボランティアスタッフが面倒を見ている……という状況でしょう。
地獄のような状況の中における、ささやかな救済を描いた場面だ。

その次に訪れる街がここ。国中内戦状態で荒れているのに、奇妙なくらい平和な街。ここはなんなんだろうか。 ふっと見上げると、武器を持った若者が、主人公グループを見張っている。平和な街ではなく、外から来た敵を底的に排除して、平和を維持している街だった。この場面は、「あいつらは敵か?」と主人公たちを見に来たところだろう。
武装するガソリンスタンドと対応した場面。

道中、見えない敵から狙撃される場面がある。 「敵が誰なのかわからない」……その状況を描いている。北軍と南軍が戦争しているんだけど、でも同じ国の人間だ。外国人と戦っているわけではない。俺たちはいったい誰と戦っているんだ……?
これが次のシーンへの橋渡しとなっている。さらに「誰が敵なのかわからない」状況が出てくる。

本作公開時、話題になったのはこのにいちゃん。設定を見ても、北軍なのか南軍なのか不明。明らかに非戦闘民である人々を虐殺し、穴を掘って埋めようとしている。その現場に運悪くぶつかってしまう……という場面。「我々は……ロイターの記者です」「アメリカっぽくないな」「通信社なんです」「わかってる」「つまり……我々はアメリカ人だ」「なるほど。どういうアメリカ人だ? 中米? 南米? どれだ?」
私たちが「アメリカ人」を思い浮かべるとき、だいたい白人を思い浮かべるだろう。そもそもアメリカはヨーロッパからの入植者たちで作られた国だからだ。しかし最近の実態はそうではない。

こちらはネットで拾ってきた、アメリカの人口構成比の推移。わかりやすく地図になっているやつを探したのだけど、見つからなかった。データを見てわかるように、白人は2025年時点で50%を少し超えたところ。黒人、ヒスパニック系、アジア系(その他にはネイティブ・アメリカンが含まれる)がじわじわと多くなっている。 地図で見ると、北部地域では白人が多いが、南部地域へ進むと白人は少数派。黒人やヒスパニック系のほうが多くなる。しかし映画なんかを見ると白人俳優が中心で描かれる。それは今もって支配層が白人だから。映画を作っているのは主に白人だから、白人主体の映画になる。所得の面で見ても、北部地域の白人たちがアメリカ全体の所得の大部分を専有。それ以外の人たちが貧困に陥っている……という実態がある。(映画『バービー』を見ると、ロールモデルであるバービーが白人であるのに対し、現実世界の女性が非白人で描かれている。それはこの状況を描くため。すでに白人は多数派ではなくなっている) アメリカはありとあらゆる種類の移民が集まり、人種構造もバラバラ、文化構造もバラバラであるのに、アメリカという一つの国としてまとまっている。だから凄い国だといえる。アメリカ人もそういうアメリカに誇りを持っている。
でもその内部に入り込んでいくと、必ずしも一つにまとまった国……というわけではない。北部と南部では文化観が違うし、東西でも文化観は違うし、その中間部分も存在する。それくらい文化観の違う国が、一つの国のなかにある。それでもなんとか“一つの国家”としてやってきたけれど、とうとうそれも無理……というのが今アメリカで起きている実態。
この場面の赤サングラスの男は、なぜ「アメリカ人かどうか」にこだわるのか? この数十年、アメリカはエリートのお坊ちゃん・お嬢ちゃんたちの掲げたお題目である「多文化共生=Woke」に振り回されてきた。黒人、ヒスパニック系、アジア系が同居している状況自体るつぼであったのに、さらにイスラム系や様々な国から違法就労者が入ってきた。 すると「文化の軋轢」が起きるのは当然。 なぜ国家は国境線を引くのか? それは軋轢を起こさないためだ。国境線を引き、自分たちはそこから向こうには越境しないし、相手に対しては「来るな」と警告を送る。この国境線がグダグダになると、軋轢が起こるとわかっているから、線を引いている。 そこに「多文化共生は素晴らしいんだ」という意見が支配的になり、これに意見すると「レイシストだ!」とレッテル貼りして、社会的に排除されるようにもなった。するとそこに本来あるべき文化がどんどん崩壊していく。 多文化共生を掲げれば掲げるほどに、その逆で分断は大きくなる。アメリカのメディアは「トランプの出現によって」分断が大きくなった、とよく表現するし、日本のメディアは考えなく追従して報道するが、実際にはその以前から分断はじわじわと大きくなっていた。メディアはそれを「見えないもの」としていた。トランプは単に「分断がそこにあるだろ」と示しただけに過ぎない。 そんな環境に苛立っているのが普通の白人たちだ。多文化共生、多様性を認めよう……とエリートのお坊ちゃんたちは言うが、その「多文化・多様性」の中に白人たちは含まれていない(ちなみに日本人も含まれていません)。これじゃ逆差別じゃないか。 こういう状況になると、鬱屈から極端な民族主義が生まれてくる。アメリカ人じゃないやつはみんな殺す。無政府状態になるとそういう輩がいつ出てきたっておかしくない。 ここまで踏まえてきて、この赤サングラスの男はなんなのか? おそらくは北軍、��軍どちらにも所属していない(所属しているかもしれないけど、自分で勝手に行動している)。道行く人たちに「お前はアメリカ人か?」と尋ねて、黒人や移民だとわかったら殺す。そういう活動を、赤サングラスの男は「正義」あるいは「制裁」だと思ってやっている。Wokeへのカウンターで生まれた、歪んだ正義だ。
これも、今のアメリカを描いた一幕だと言える。
まとめに入りましょう。 もしもアメリカが再び内戦状態になったらどうなる? その状況が見事に描かれた作品だった。アメリカ全土が荒廃しているのだけど、でも冷静な視点で「いったい誰と戦っているんだ?」というメッセージが織り込まれている。途中、戦闘シーンが描かれるが、どっちが北軍でどっちが南軍か……パッと見でわかるように作ってない。そういうものはもはや本質ではない。
そういう状況を、旅ものという形式で描かれるが……こういう形式の原点といえばコンラッドの『闇の奥』でございますよね。ライドアトラクションのように状況を次々と見せていく構成だが、見せるのはじわじわと深まっていく闇。本作の場合、首都ワシントンD.C.に近づくほどに、状況の度しがたさが深まっていく。

お話しの順番を書き出していくと、まず武装したガソリンスタンド。頼りになるものがないから、自分で武装して、ならず者が逆転大勝利してしまった社会。これが荒廃したアメリカの基本状況。「カナダドルで支払う」という台詞も良い。米ドルが紙クズになっているからだ。 次に北軍と南軍の本格的な戦闘場面。 そこを通り過ぎて、避難民収容所で一休み。 次が平和な街。一見すると避難民収容所から地続きのように見えるけど、実はよそ者を徹底的に排除した社会だと気付く。武装したガソリンスタンドのバージョンアップ版。「よそ者の排除」というテーマはその次のシーンへの橋渡しになっている。 その次が謎の狙撃手。「俺たちの敵って誰なんだ?」というシーン。 その次が例の赤サングラスの男。
そこを乗り越えると、北軍の前線基地シャーロッツビルとなっている。
この作品で何を語りたいのか、何を見せたいのか……それが明確に見えている作品だ。
 リーの師である老記者サミーが死んだ後。服の色が入れ替わっている。ここで立場の入れ替わりを示している。服の入れ替わりで立場の変化を表現したのは『エクス・マキナ』でも使われた手法。
リーの師である老記者サミーが死んだ後。服の色が入れ替わっている。ここで立場の入れ替わりを示している。服の入れ替わりで立場の変化を表現したのは『エクス・マキナ』でも使われた手法。
現代に対して明確なメッセージがあるから作った作品。もしかしたら、近い将来、こういう内紛が起きるかもしれない……そういう瀬戸際にあるんだ、という警告を見る側に送った作品だ。 そういう意味できちんと作られた作品だ、と評価できるが……しかしもうちょっと構想が熟するのを待ったほうがよかったんじゃないかな……とも思う。というのも、それぞれのシーンの緊張感が微妙に薄い。それぞれの人物がドラマを語り出すところまで来ていない。微妙な生煮え感が漂っている。これはこれできちんと作られた作品であるのは間違いないが、あともう一歩、足りないものがあるように感じる。 例えば北軍、大統領側の動向だ。この物語であると、大統領がただ愚かな人間……ということしか読み取れない。大統領がどういう政治的信条を持っていたのか、なぜ選ばれたのか、なぜ内戦状態に陥ったのか……。寓話であるからその全てを語る必要はないのだけど、そこにこそ奥行きを持たせて欲しかった。
そういう引っ掛かりはあるものの、全体としては優れたクオリティの作品。危うい今の時代だからこそ、見るべき作品だ。もしかすると、あと数年後に起きるかもしれない未来を予言しているかもしれない。
Views: 0