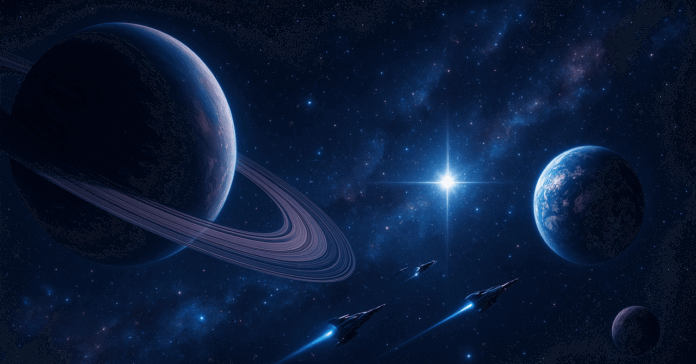🧠 あらすじと概要:
映画 "面白さ" の分析記事のあらすじと要約
あらすじ
この記事では、映画の「面白さ」をさまざまな視点から分解して考察しています。著者は、映画やミュージカルの中で体験する異なる「面白い」の形について触れ、例えば『スター・ウォーズ』と『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のそれぞれの魅力を比較し、各作品が持つ独自の特徴を明らかにしています。著者は「面白さ」は単一の感情ではなく、複数の感情がブレンドされたものであるとし、その構造を探求するためのフレームワークを提示します。
記事の要約
-
映画の「面白さ」の構造:
- 心理学や映画理論、UXデザインの観点から映画の面白さを探求し、感情体験の設計について考えます。
- 感情は喜び、驚き、共感、悲しみなどに分類され、映画はこれらの感情を刺激する「設計された感情体験装置」であると説明されます。
-
感情体験の研究:
- Paul Ekmanの基本感情理論や物語輸送理論に基づき、映画を通じて経験する感情の複合性が重要であると考察されています。
-
映画理論・物語論:
- 物語の構造やキャラクターの葛藤によって観客の感情が揺さぶられる様子を分析します。
- 「物語の5段階構造」や「3幕構成理論」などを用いて、物語が持つ起伏が面白さに寄与することが示されています。
-
UX・デザイン思考における視点:
- エンターテインメント体験として映画を捉えることで、感情体験の比率によって「面白さ」を設計できることが示されています。
-
面白さの要素モデル:
- 「面白さの6要素モデル」が提案され、これを基に映画を分析する方法が示されています。観客がどのように感情を受け取り、感じるかを数値化する方法も紹介されています。
- 教育への応用:
- 著者は、映画の「面白さ」を教育に活かす方法について言及し、授業設計において感情を動かす要素を組み込むことで、より効果的な学びを実現できる可能性を示しています。
この記事全体を通じて、映画における「面白さ」の多様性と、その要素を教育の場にも応用する可能性について考察が行われています。
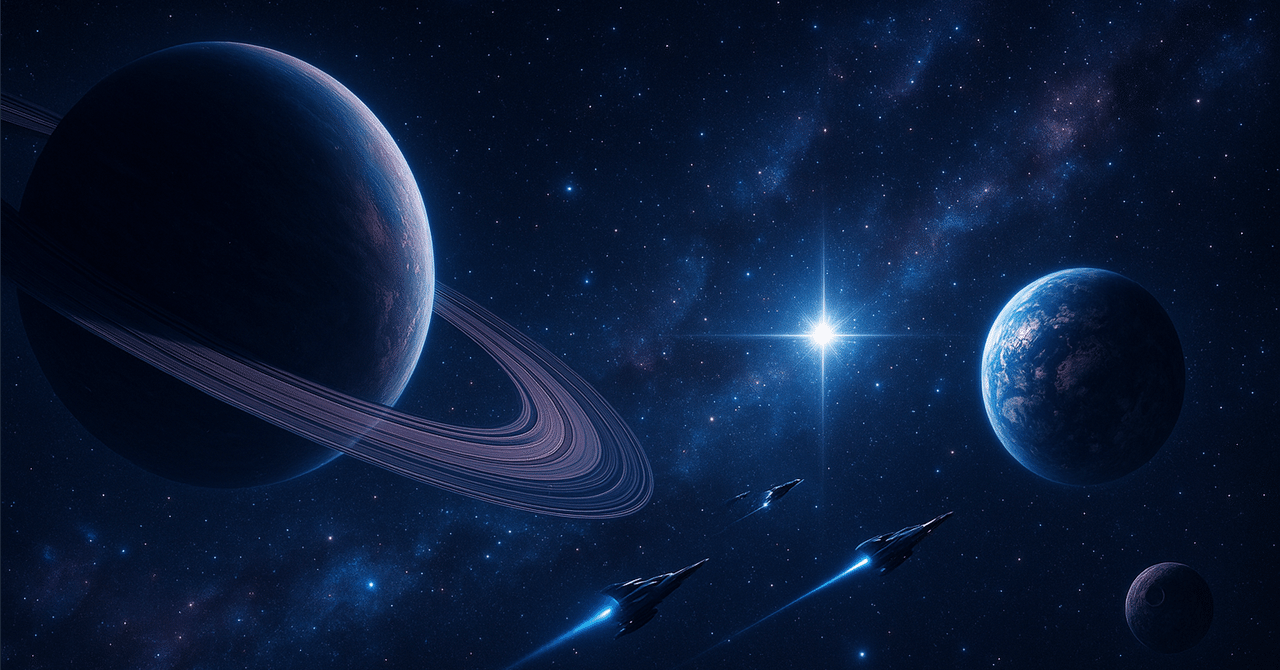
ここ1年、映画やミュージカルを見る機会が度々あった。
どの作品も面白かったのだが、一括りに「面白い」という言葉で片付けるのは勿体無い。
例えば、スターウォーズも、バック・トゥ・ザ・フューチャーも、それぞれがまったく違う形で「面白い」。
例えばスターウォーズは、ドラマの重厚さ、光と闇の対比、壮大な宇宙の映像と内面的な哲学に心が引き込まれる。
一方で、バック・トゥ・ザ・フューチャーは、軽快なテンポとコミカルな会話、そして絶妙な伏線回収の心地よさがある。

どちらも同じSFというジャンルだが、「面白さ」の質が全く違う
つまり、「面白い」は一つの感情ではなく、複数の感情のブレンドで成り立っている。
ということで今回は、映画の「面白さ」というものに注目し、それを分解して捉えてみることにする。
「面白さ」の構造
映画の面白さは、心理学や映画理論、UXデザインの視点から見ると、実は感情体験の設計でもあるという意見がある。例えば以下のようなものだ。
-
心理学では、感情は基本的な感情(喜び・驚き・共感・悲しみ)に分類され、人は物語を通して複数の感情を同時に経験することが知られている。
-
映画理論では、物語の構造やキャラクターの葛藤が観客の感情を揺さぶる要素として設計されている。
-
UX(ユーザー体験)理論では、製品やサービスと同様に、学びやコンテンツも感情のカーブを描くことで、印象的な体験になる。
それぞれを詳細に調べてみた。
1. 心理学・認知科学における感情体験の研究
-
人は映画や物語(物語的体験)を通じて、複数の感情を同時に体験しており、「面白さ」はその感情の質×強度のミックス。
-
Paul Ekmanの「基本感情」や、映画・物語体験に関する心理研究(ex. Transportation Theory by Green & Brock)では、「感情の複合性」が鍵とされている。
-
感情の喚起は以下のような刺激に分類されやすいことが知られている:
-
ドラマ(ストーリー)→共感・悲しみ・感動
-
コメディ(ユーモア)→笑い・安心
-
アクション→興奮・緊張・爽快感
-
ビジュアル美→驚き・感嘆・没入
-
論理的構造(伏線)→知的好奇心・驚き
-
● 主な理論と背景:
Paul Ekmanの「基本感情理論」
-
喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪など、人間に普遍的な感情が存在するとした。
-
映画はこれらの感情を刺激する「設計された感情体験装置」である。
Green & Brock(2000)『Transportation Theory(物語輸送理論)』
-
人は物語に没入することで、登場人物と感情的に一体化(共感)し、その世界に「輸送」される。
-
その没入は「面白い」という感情に直結する。
Lisa Feldman Barrettの「感情は構成される(Constructed Emotion)」
-
感情は脳内の予測モデルによって構成されるもので、「面白い」という感覚も文脈や記憶、経験により変わる。
-
よって、「面白さ」は複数要素の組み合わせから個別に生じる体験である。
2. 映画理論・物語論(Narratology)
-
映画の「面白さ」は、物語・演出・ジャンル要素の複合設計により生まれる。映画やアニメの批評で用いられる視点では、主に以下の観点から分析されるとのこと:
-
プロット(ストーリー構造)
-
キャラクターの葛藤
-
世界観(setting)
-
トーンや演出(humor, drama, action)
-
メッセージやテーマ
-
● 主な理論と構造:
Tzvetan Todorov の「物語の5段階構造」
-
安定した日常(Equilibrium)
-
事件の発生(Disruption)
-
認識(Recognition)
-
解決(Repair)
-
新たな安定(New Equilibrium)
→ この構造を通して「葛藤・変化・成長」を体験することで、“面白さ”が生まれる。
Syd Fieldの「3幕構成理論」
-
第1幕(導入):キャラや世界観の提示
-
第2幕(葛藤):試練と対立の連続
-
第3幕(解決):クライマックスと帰結
→ 物語の起伏やテンポが、感情のうねりと面白さの源になる。
ジャンル映画論(Rick Altmanなど)
-
映画はジャンル(例:アクション、コメディ、SF)によって観客の感情期待を設計している。
-
「笑えるSF」「感動できる冒険劇」など、ジャンルのミックス具合が面白さのバリエーションを生む。
3. UX・デザイン思考におけるユーザー感情モデル
-
UX設計では、サービスやコンテンツがユーザーに与える「感情体験」を軸に設計するフレームがある(ex. Kanoモデル、感情曲線など)。
-
エンタメ体験も一種のUXと捉え、「どんな感情をどの比率で受け取ったか?」という分析が重要。映画・物語も一種のUXであり、「面白い」=良い体験の成果。
● 主な理論と応用:
感情曲線(Emotion Curve / Story Arc)
-
ストーリーにおける感情の上下を曲線化することで、観客の没入度や感情の動きを設計。
-
ピーク(感動、驚き)、谷(不安、沈黙)をバランスよく配置することで、「面白い体験」になる。
Kanoモデル(UXの魅力要素分類)

面白さの6つの要素モデル
ここまでの話を踏まえ、「面白さ」を詳細に捉えるための「面白さの6要素モデル(Emotion Design Model)」を考えてもらった。それが以下だ。

これを元に映画を分析すると、例えば以下のようになる。
 「面白さの構成比」を主観で整理した例
「面白さの構成比」を主観で整理した例
この◎、○、△の表現は、「観客が受け取る感情の強さ=感情刺激の比率」を示したもので、以下のように数値化しても良いかもしれない:
例)スターウォーズの場合(主観的なモデル)
-
ストーリー性:30%
-
世界観・美:25%
-
感動:20%
-
アクション:15%
-
ギャグ性:5%
-
知的仕掛け:5%
このように分解することで、自分自身の「面白い」の傾向=感受性のプロファイルが浮かび上がるとも言える。
「面白さ」は個人の経験や感受性によっても左右されるため、それも踏まえて「面白さ」を捉える必要がある。
以下のようにもまとめられるかもしれない。
面白い=感情的な引力(共感・驚き・笑いなど) ×構造的な要素(ドラマ・視覚・ロジック・テンポなど) ×
自分の感受性フィルター(何に反応しやすいか)
授業における「感情のレシピ」
自分の場合、子ども向けの授業を作成することが多いのだが、ここまでの話は授業にも活かせる。
例えば、ある授業が「記憶に残っている」としたら、それは「驚き」が多かったかもしれないし、「共感」が多かったからかもしれない。
ある授業が「楽しかった」としたら、それは「遊び心」や「アクション」が含まれていたからかもしれない。
作業的に何かに取り組む授業よりも、何かしらの感情が動く授業の方が、記憶に残り、知識の定着もしやすいことは自身の経験的にも理解している。
つまり、「面白い=引き込まれる・夢中になる・記憶に残る」 授業や学習体験を設計するために、「面白さの要素」を6つの観点で構造化し、目的や対象に応じて比率を調整できると良い授業になる。
以下に例をまとめてみます。

さらに、上記を元にした授業設計を、3ステップでまとめてみる。
【授業設計の3ステップ】
① 目的と対象の明確化
-
学習内容の到達目標(例:知識獲得?価値観の転換?探究心の喚起?)
-
対象の学年・感性・背景
-
どんな感情を喚起し、どんな“面白い”を感じる授業か?
② 面白さ構成比の設計
-
以下のように比率を調整して、「どの感情体験を中心にするか」を設計

このようにして、授業の「面白さプロファイル」を可視化し、それを元に構成を決めていくことができそうだ。
③ 授業設計の具体化
-
学習内容と感情体験をどう結びつけるかを考え、授業を設計。
-
各要素に対応した「手法のストック(技法・ツール・ネタ)」を用意しておくことで、授業設計が効率的になる。
ここまでの内容を踏まえた授業づくりテンプレートとして、例えばこんなフォーマットなどが使えるかもしれない。
【授業テーマ】:アナキンから学ぶ「悪とは」【学習目標】:悪の多面性を知り、自分の価値観を言語化する【面白さ構成比】(◎=核、○=補助、△=軽く)- ドラマ性:◎- 世界観:○(スターウォーズ世界を活用)- ユーモア:△(ライトな例え話)- アクション:△(役割インタビュー)- 共感:◎(アナキンの選択に感情移入)- 知的快感:○(「悪とは何か?」の問い)【使用技法】:- シーン再現ワーク/哲学対話/感情グラフ/選択肢分岐ゲームこうした感情が動く学びを設計する「感情デザイナー」としての視点を持つことで、より深く楽しく、意味ある授業を作れるようになるかもしれないし、AI時代における教育者の武器になるかもしれない。
心が動く、体が動く、ひらめく、共感する——そうした感情の波は学びを深くするポテンシャルがある。
本記事では最後に、映画の面白さに大きく関わる没入感の要素を整理し、それを教育に応用する方法をまとめてみる。
映画と授業における没入感
没入感(Immersion)は、感覚・感情・思考がすべてその“世界”に集中している状態。映画も教育も「体験の設計」であるという点で共通しており、没入感のつくり方には似た原則があると言える。
以下に映画の場合と教育の場合で整理してまとめてみる。
🎬 映画における没入感のつくり方:5つの主な要素

🎓 教育における没入感を生み出す方法:映画の要素を活かす

さらにシンプルにまとめると、没入感は以下のような「感覚・構造・選択」の設計から生まれるとも言えるかもしれない。

ということで、今回は映画における「面白さ」について記事を書いてみた。途中から教育への応用に話がすり替わっていったのは気のせいだと思いたい。
とにかく、時間をかけて作り込まれた世の中のコンテンツを詳細に分解していくのは面白いし、様々な場面に活かせると思う。
これまでもずっとやってきたことなので膨大なメモがあるのだが、いつかそれも記事にしてみたい。

※記事内の画像は生成AIで生成しています
Views: 2