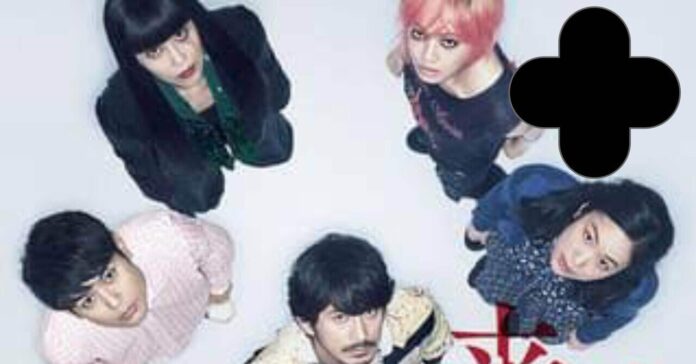🧠 あらすじと概要:
映画『来る』は、主人公・田原秀樹が心の奥底に抱える「負の感情」が具現化した怪異“ぼぎわん”に取り憑かれる物語です。表向きは理想的な父親を演じる秀樹ですが、実生活では妻・香奈に育児を押し付け、自身の承認欲求を優先しています。この映画は、家庭内の「見なさ」や人間関係の断絶がどのようにして怪異を引き寄せるのかを描き、特に被害を受けるのは無力な娘・チサです。
この記事では、映画が問いかけるテーマについて考察しています。田原家が象徴する現代社会の dysfunctionality(機能不全)や、過去の記憶を見逃さず向き合うことの重要性が強調されます。怪異は、個人の霊障を超え、社会全体の病理を反映しているとの指摘もあり、ホラー映画としての枠を越えた人間ドラマに昇華されています。
最終的に、主人公がぼぎわんに向き合うことで希望の光が示され、視聴者に「心に潜む見えないもの」に気づかせる作品となっています。映画は、恐れや痛みに向き合うことの必要性を問う、深いメッセージを持つ作品です。
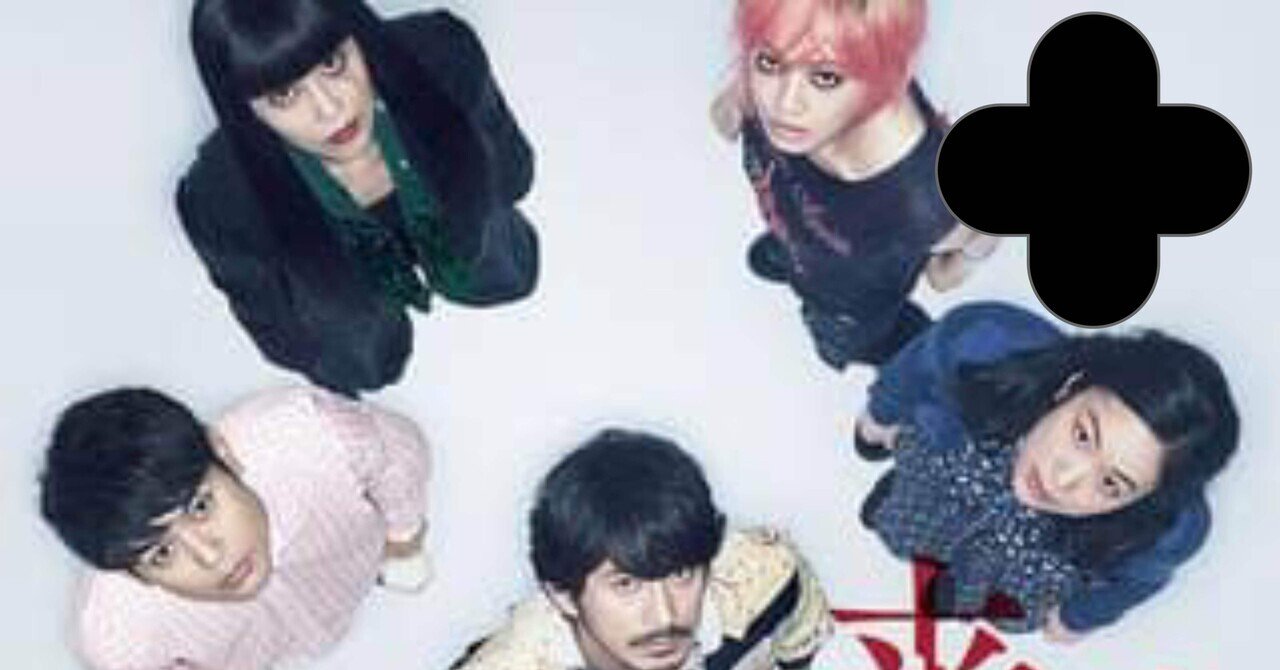
映画『来る』に登場する“ぼぎわん”は、ただの怪異ではない。その正体は、誰もが心の奥底に抱える「負の感情」――罪悪感、見栄、否認、無関心――が具現化したものだとしたらどうだろう。主人公・田原秀樹(妻夫木聡)は、一見するとSNS上で“理想のイクメン”を演じているが、実生活では妻・香奈(黒木華)に育児の負担を押しつけ、自身の承認欲求を満たすことにばかり腐心していた。そんな彼が、なぜ怪異に取り憑かれたのか?それは、彼の過去に示唆される謎の声――「ヒデキさん?」という呼びかけや、「口減らし」という重く残酷な言葉が示す、記憶の闇に鍵がある。田原が封じ込めてきた「見なかったことにしたい過去」。その蓋の隙間から、じわじわと湧き上がる罪悪感は、やがて形を持ち、“ぼぎわん”として現れた。ここに描かれているのは、怪異=心理的外傷の実体化という構造だ。彼の内面のひずみが、見えないまま大きくなり、ついには他者を巻き込む災厄として膨れ上がる。「恐怖」は、外からやってくるのではない。
私たち自身が育ててしまうのだ――それが、この映画が投げかける最初の問いだ。
第二章:なぜ田原家が選ばれたのか?
『来る』は、単に“悪い人が報いを受ける”話ではない。むしろ、田原家のような家庭は、現代社会においてごくありふれたものとして描かれている。それがこの作品の恐ろしさを際立たせる。夫・田原はSNS上で「理想のパパ」として振る舞うが、実際には育児への無関心と自己保身に満ちている。一方の妻・香奈は、夫の理解なき言動に孤立を深めながらも、強くあろうとすることで自らを追い詰めていく。彼らは、互いを“見ていない”。この“見なさ”の連鎖の中で、最も深く傷ついていたのは、娘のチサだった。無力で、誰にもきちんと向き合ってもらえず、ただの「子ども」としてしか扱われなかった存在。怪異“ぼぎわん”が彼女に取り憑いたのではない。ぼぎわんが最初に見つけたのは、“誰からも見られていなかったチサ”だったのかもしれない。この物語において、怪異が襲うのは“悪”ではない。むしろ、人が「つながり」を失った空白部分――愛されなかった子ども、共感のない夫婦関係、蓋をされた記憶――に忍び込む。
つまり「なぜ田原家だったのか?」の問いは、「なぜ今、あなたの家ではないのか?」という鏡のような問いでもある。
第三章:知紗という存在と、怪異の共鳴
田原夫妻の娘・知紗は、映画の中盤以降に物語の中心へと急速に浮上する。しかし、彼女は“超能力を持つ特別な子”などではない。ただ、愛されたかっただけの存在だった。ここで私たちは、恐ろしい仮説と向き合うことになる。
「純粋な愛情の欠如」は、怪異を呼び寄せる。
知紗がぼぎわんと“心を通わせた”のではなく、彼女の孤独と純粋な渇望が、怪異にとっての“居場所”になった。見放された存在に、怪異は寄り添う。それは、現代のいじめ、自傷、虐待の構造とも通じている。この時、ぼぎわんは単なる恐怖ではなく、愛情不在の象徴として現れてくる。・誰も見ようとしなかった知紗。・自分自身を痛めつけた背中の跡。・その存在に寄り添ったのは、怪異だけだった。この構図こそ、『来る』という作品が本質的に描きたかった痛みであり、その痛みが、怪異と知紗を“共鳴”させたのだとしたら――
私たちは、この物語を「他人事」として見ることができるだろうか?
第四章:祓えなかった霊媒師たち
物語の終盤、『来る』はホラーとしてのスケールを一気に広げていく。松たか子、柴田理恵らが演じる最強の霊媒師たちが集結し、壮大な除霊儀式が始まる。まるでクライマックスに向けたカタルシスを準備しているかのように…だが結果は──敗北だった。いかなる力をもってしても、ぼぎわんを完全に祓うことはできなかった。むしろ、「お祓い師たちも手に負えない」と絶望的に語られる状況に、観客は深く打ちのめされる。この敗北は何を意味するのか?それは、「ぼぎわん」がただの霊ではなく、人間が長年蓄積してきた負の感情と業の象徴であるということ。儀式や信仰といった「形式的な救済」では、到底及ばないほどに、この怪異は人間の根源に根を張っている。私たちが“見てこなかったもの”、“見ないようにしてきたもの”が、形を持って現れたとき、それはもはや「個人の霊障」ではなく、社会全体の病理を映す鏡になってしまう。この圧倒的な敗北の演出は、作品に解決不可能な問いを持ち込む。
それこそが、この映画がホラーの枠を超えて「人間ドラマ」へと昇華した理由なのだ。
第五章:『来る』が私たちに問いかけること
『来る』というタイトルが何を意味するのか。「来る」とは、いったい何が来るのか。怪異か?破滅か?それとも――“過去”そのものか。この映画は、目に見える怪異だけでなく、観客自身にこう問いかけている。・あなたの心に、見栄や嘘はないか?・誰かの痛みに、目を背けていないか?・あのとき向き合わなかった感情が、今もどこかに潜んでいないか?ぼぎわんは、私たちの中にある「見えないが、確かに存在するもの」の象徴だ。恐怖とは、外部の脅威ではなく、自分の中の見たくない部分に気づいた瞬間にこそ、もっとも強くなる。『来る』は、ただのホラー映画ではない。それは、見えない“何か”に取り憑かれる恐怖ではなく、
見ようとしなかった“誰か”の声に取り憑かれる人間の弱さを描いた物語だ。
結びに代えて:あなたの中に、“来る”ものは?
霊媒師でも祓えない。信仰でも救えない。それでも、唯一ぼぎわんに対して正面から向き合った者がいた。
それが、岡田准一演じる野崎和浩だった。
彼は知紗を抱きしめるように、心の奥にある“痛み”を見つめた。その姿こそ、この物語が唯一示す“希望”だったのかもしれない。⸻『来る』とは、「それがやってくる」映画ではない。「それが“もうそこにある”と気づかされる」映画なのだ。
あなたの中に、“来る”ものはあるだろうか?
Views: 0