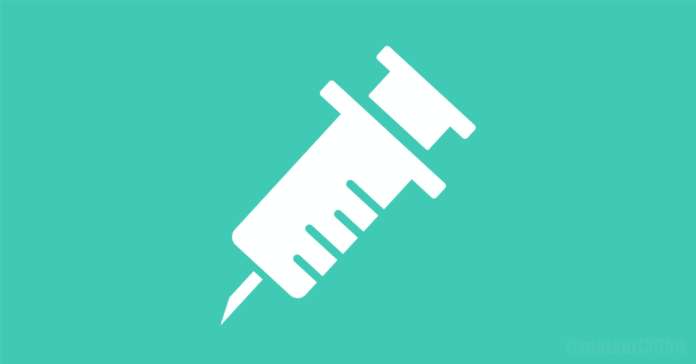🧠 あらすじと概要:
映画『サブスタンス』は、ハリウッドを舞台にしたポストモダンスタイルの作品で、主にアンチエイジングやフェミニズム、孤独といったテーマを描いています。
あらすじ
主人公はかつての栄光を失ったハリウッド女優で、若さを求めるあまり、闇の技術を使って自身の若い分身を作り出します。この分身はすぐに人気を博し、主人公との差別化が生じ、複雑な感情の葛藤が描かれます。
記事の要約
- ハリウッド風刺: 映画はハリウッドの現実を鋭く批判し、特に女優が年を取ることへの社会的な偏見を浮き彫りにしています。
- アンチエイジング: 主人公が老化を恐れ、分身を作ることで生じる問題を通じて、ハリウッドの虚栄心を風刺しています。
- フェミニズム: 主人公の行動は、男性による権力の影響を示唆する一方で、伝統的なフェミニズムに対する批判的な視点も提供しています。
- 孤独: 主人公が孤独に陥る原因と、その結果が彼女の行動にどのように影響を与えるのかが描かれています。
- オマージュ: 80年代のSFXホラー映画へのオマージュが含まれ、過剰演出やブラックユーモアが作品に深みを与えています。
全体を通して、観客は主人公とその周囲の葛藤を通じ、現代社会における自己評価や価値観の矛盾を考えさせられます。
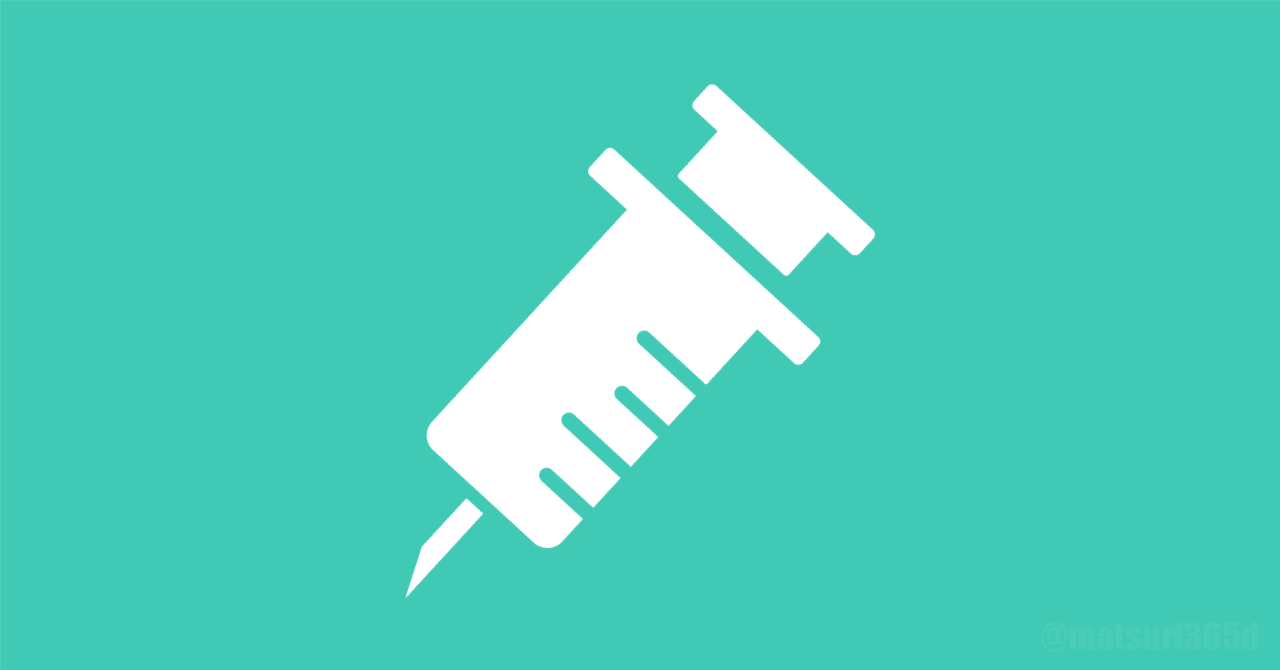
※ほとんど個人的な備忘録なのでそのつもりで読んでください。あとネタバレは必要な箇所のみあると思います。
『サブスタンス』という映画は決してむずかしい映画ではないのですが、これは典型的なポストモダン・スタイル(いろんな要素を混ぜたり重ねたり引用して貼り付けたりして、多様な解釈を可能にしたようなスタイルのこと)の映画なので、観る人の価値観や世界観によって異なる見え方をする。
なのでこの映画が一体なにを描くものだったのか、昨日観てからいろいろ考えてブログとかBlueskyとかに投下したものをセルフ引用してまとめてみましょう。
描かれているもの① ハリウッド風刺
これがハリウッドについての映画であることはウォーク・オブ・フェイムに始まりウォーク・オブ・フェイムに終わる構成から明白である。ウォーク・オブ・フェイムというのはハリウッドの通りにある星形の記念碑パネルの並んでいる観光名所で、ハリウッドに貢献したまぁ知らんがたとえばトム・クルーズ? みたいなスタアの名前がそこに刻まれる。
ハリウッドにはかねてより言われMeToo運動時に大々的に取り上げられたハリウッド若い女優ばかり求めすぎ問題というものがある。男優は歳を取っても役があるのに女優は歳を取るとお払い箱! 実際の統計などは知らないが、これは体感的にはとても頷ける話であるし、ハリウッド女優ドキュメンタリー映画の『デブラ・ウィンガーを探して』でも錚々たる面々が文句を言っていた。
たとえばシニア向けの映画の割合がハリウッドに比べれば多く感じられる日本映画に目を向ければスター女優は老齢になっても役がある(吉永小百合などがその典型)ので、おそらくこれは常に若い観客を想定しているハリウッド特有の問題なのではないかと思う。実際ハリウッドにおいては女優だけではなく男優も歳を取ることに否定的でアンチエイジングに余念がないが(トム・クルーズやシルヴェスター・スタローンなどが典型か)、これはインド映画界など一部を除けばあまり見られる現象ではない。
したがって、『サブスタンス』は何よりもまず先にハリウッド批判・ハリウッド風刺の映画と言えるのだ。
描かれているもの② アンチエイジング
アンチエイジングとは反老化の意。ハリウッドでは最新技術を駆使したアンチエイジングが異常に持て囃されているが、なぜハリウッド人種が老化を恐れるのかがこの映画の中には描かれていた。それはハリウッドから見捨てられた主人公が唯一レギュラー出演をしている朝のエアロビ番組のクソバカプロデューサーが主人公は年寄りすぎるから若い女に交代させろ!とのたまったからであった。
番組を手放したくない主人公はそれで自身の若い分身を作る闇テクノロジーに手を染めるのだが、その結果分身(若い方)の主人公はハリウッド期待のニューフェイスとして持て囃され、番組の視聴者は激増してしまう。こうしてスターとなった分身の方は有頂天となり、自分の母体である老いた主人公に「こんな醜いものがもう一人の自分!?」と嫌悪感や殺意を抱くようになる。
この映画の中で主人公二人をアンチエイジングに駆り立てているのはハリウッドスターという虚飾の栄光なのだ。
描かれているもの③ フェミニズム
フェミニズムというのは実に多様な展開を見せている運動・思想ですけど、老いに否定的なフェミニストというのはあまり聞いたことがないし、日本のフェミニズムの旗手であった上野千鶴子も現在はボーヴォワール(第二波フェミニズムの思想的支柱となったフェミニストで、代表的なフェミニズム思想書の『第二の性』を出版した)の仕事を引き継いで「老い」を研究テーマとしている。
だからアンチエイジングによる悲劇はフェミニズム的なテーマなのですが、そこに一つの落とし穴があって、主人公をアンチエイジングに駆り立てた原因をエアロビ番組のクソバカプロデューサーに求めてしまうと、この映画は権力ある男のせいで転落し狂ったハリウッド女優の悲劇という、いささかげんなりさせられる映画と見えてしまう。なぜならば、それは「しょせん女なんか男に敵わない」と印象付けるだけでなく、主人公と分身が戦うことが「権力を持つ悪い男の手の平で争うことしかできない哀れな女たち」の図式で解釈しえるから。これは男性が権力を独占することの不合理と男性権力の虚構性を暴き出し、女性の自立や自己決定権の実現を歴史上求めてきたこれまでのフェミニズムの流れからすると、どちらかといえば反フェミニズムの男尊女卑の考えに近い。
しかしこの映画の監督コラリー・ファルジャは前作『リベンジ』ではクソバカ男どもをパワフルにぶっ殺していく女の人を描いていたし、今作『サブスタンス』でもド級にパワフルな演出が観客の度肝を抜く。こうしたファルジャの作風と「しょせん女なんか男に敵わない」「無傷な悪い男の手の平で争う哀れな女たち」という感傷的な敗北主義はまるで重ならない。そのため、この映画がそう見えてしまっている場合には、ファルジャの作劇意図を読み取れていない可能性がある。
むしろファルジャは伝統的なフランス流のフェミニズム(老いを肯定し、女性であることを祝福する)に則って、先に書いたように虚飾の栄光のために自分自身を否定し、自己評価をもっぱら他者(視聴者や男)に委ね、アンチエイジングに邁進するハリウッドスターとその文化を皮肉ったのがこの映画、と考えた方が、一般的な意味ではフェミニズム的な見方と言えるような気がします。
描かれているもの④ 孤独
どうして主人公はハリウッドスターの栄光に取り憑かれているのだろうか。現在は人気がなくなったとはいえ豪邸に住んでるしお金はあり余っているように見えるから、少なくとも経済的な理由ではない。でもあの空虚な豪邸を見ているとその理由もわかるような気がする。豪邸にいるのは一夜限りの男を呼んだとき以外はいつも主人公一人で、その窓から見えるのは自分の分身の写ったビルボードでしかない。この人の世界には自分しかいない。悩み事を相談したり、楽しいことを分かち合ったりする友達がいないのだ。
もしも友達がいればハリウッドスターとしては忘れられても残りの人生を楽しく過ごすことができるだろうし、ハリウッドスターじゃない一般庶民は可能な限りそうしてる。ところがこの主人公には友達を作るという発想が本当にない。かつてのクラスメートだったという頭のネジの抜けた感じのボケ顔の男が挨拶してきてもハリウッドスター然とした態度を崩さないし、その後その人と会おうという気持ちに少しだけなっても、嫌われることを恐れて会うことができない。
その孤独が彼女をハリウッドスターの座に誘惑する。一人でいたくない。誰かから愛されたい。根本的には、これが主人公が分身薬に手を出した動機である。けれども、誰かから愛されるにはまず自分が誰かを愛さないといけない。他人を憎んだり蔑んだりしていては決してその人を愛してくれる人は現れない。その意味で主人公は哀れを誘うほど幼稚な人であり、同時に自分本位の身勝手な人でもある(それは破滅するとわかっていながらも分身同士が協力できず戦ってしまう展開からも明らかである)
にもかかわらず主人公のこうした弱点に言及する人が個人的に見つけられなかったというのはこの記事を書こうと思った俺の動機。なぜ主人公のダメさがこんな風にみんなには見えないのだろうか?そう考えると、それはたぶん、ハリウッドスターじゃなくても、現代人は友達を作るのが苦手だからなのかもしれない。友達を作れない人はこの主人公に同情こそすれ、自分自身がそうなのだから、その問題点を見抜くことはできないんじゃないだろうか。
主人公が最初抱えていたハリウッドでの冷遇とスターの地位からの脱落という悩みは、ただ単に友達を作って酒でも飲みながら相談すれば、少なくとも精神的には解決できた程度の問題なのかもしれない。しかしそのことに、この映画を観る観客さえ気付かない、気付けないのが、孤独の常態化した現代の、いささか殺伐とした状況なのかもしれない。
描かれていたもの⑤ 80年代SFXホラーetcのオマージュ
サブスタンスの蛍光緑色の注射液はおそらくこの表現が最初に映画に登場したスチュアート・ゴードン監督の『死霊のしたたり』のオマージュで、ゴードンが1980年代にエンパイア・ピクチャーズというB級映画専門会社で『フロム・ビヨンド』や『キャッスル・フリーク』など、過剰な人体変形&崩壊やフリークスの孤独を描く映画を連発した。この時代にはSFXがアメリカ映画界で飛躍的に進歩を遂げたため、それを生かした人体変形&崩壊B級ホラーが多数制作され、他には『ソサエティ』、『吐きだめの悪魔』、『遊星からの物体X』、『バスケット・ケース』、『ブレインデッド』、『溶解人間』などが有名どころとしてある
コラリー・ファルジャの過剰演出は初期のサム・ライミ映画を彷彿とさせるが、ライミが『死霊のはらわた』で一世を風靡したのも1981年のことなので、おそらくファルジャはこの時代のSFXホラーに強い思い入れのある監督なんじゃないだろうか。その傍証と言えるかどうかはわからないけれども、『サブスタンス』の人体変形にCGはほとんど使われておらず、その質感や造型は1980年代SFXホラーのそれであった(他にも『シャイニング』や『2001年宇宙の旅』のパロディと思しき箇所もあり、1980年代SFXホラーのほとんどはブラックユーモアの要素を含んでいたことから、この映画もブラックユーモアを目指したのだと思います)
Views: 1