🧠 概要:
概要
日産自動車の2025年3月期の決算が発表され、連結最終赤字が6708億円に達した。この赤字は主に減損損失とリストラ費用によるもので、日産は大規模な構造改革を宣言した。背景には中国や北米市場における販売台数の大幅な減少があり、EV開発に注力していたが、それが逆境を招いたと考えられている。
要約
-
業績の悪化:
- 2025年3月期の連結最終赤字が6708億円。
- 売上高は12兆6332億円、営業利益は6979億円だが純利益はマイナス。
-
主な損失原因:
- 減損損失4949億円計上。
- 特別損失として大幅な構造改革を実施。
-
構造改革の内容:
- 7工場を閉鎖し、従業員を2万人削減。
- 部品の種類を現状の7割削減。
-
業績推移:
- 売上はコロナ後回復したが、2025年に再び悪化。
- 固定費の上昇が大きな要因。
-
費用上昇の要因:
- 材料費・物流費、高騰する販売関連費が影響。
- 生産台数の減少による固定費の増加。
-
市場動向:
- 中国市場における販売台数が大幅減少。
- 日産のEV開発に偏重した戦略が逆に影響を及ぼしている。
- 今後の展望:
- 自己資本比率は26.1%だがフリーキャッシュフローがマイナス。
- 大規模な構造改革の実行が試金石となる。
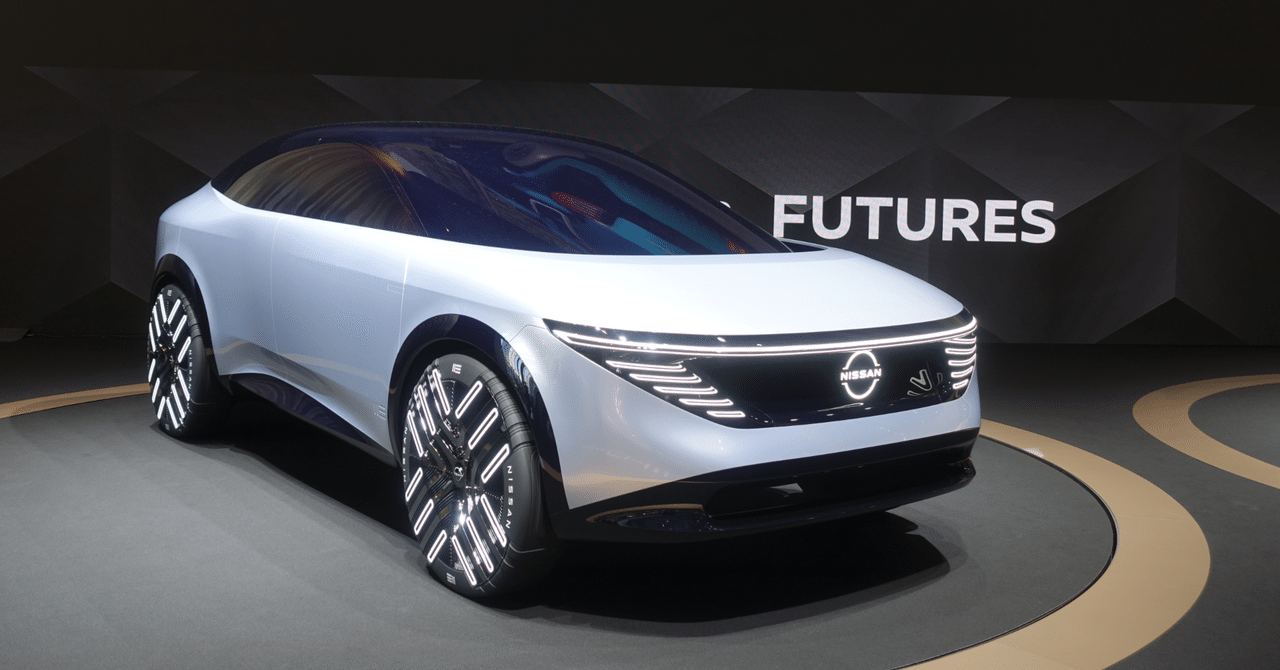
■日産の財務状態は?
2025年3月期の決算についての発表が5月13日に行われ、連結最終赤字が6708億円となったと発表。
その中身について、2025年3月期の決算短信から確認していきたいと思います。
売上:12兆6332億円
売上総利益:1兆6933億円
営業利益:6979億円
純利益:△6708億円
本業の儲けである営業利益はプラスになっていますが、純利益でマイナス。
どこで大きなマイナスを計上しているかというと、特別損失のところで、「減損損失」を4949億円計上されています。
減損損失とは、企業が保有する固定資産などの価値が減少し、帳簿価額が回収可能金額を下回った場合に、その差額を損失として計上する会計処理のことです。簡単に言えば、資産の価値が目減りして回収不能になった場合に損失として計上されるものです。
「自社の業績と生産に関わる資産を精査した。当期は大幅な損失を見込むが、主な要因は資産の減損損失と今後の事業安定化に向けたリストラ費用だ」とエスピノーサ社長は説明。今回の減損には、タイでの生産ライン統合やアルゼンチンでの生産縮小なども含まれると言われています。
特別損失なので、今期だけの損失となりますが、今回、日産は大規模な構想改革策を宣言しました。その内容は、「国内外7工場の閉鎖」、「世界従業員数の15%に相当する2万人の削減」、「部品の種類を現状より7割削減」というもの。
なぜ日産は、ここまで大規模な構造改革をしなければならなかったのかでしょうか?そこについて、見ていきたいと思います。
■日産の業績の推移は?
ここ数年の日産の業績の推移を調べてみました。
コロナウイルスの影響で、2021年3月期に売上が7862億円と落ち込みましたが、その後は売上は回復傾向となり、2025年3月期は、12兆6332億円となりました。
売上総利益・営業利益は、コロナ後、売上に伴って、ともに回復傾向となりましたが、2025年3月期に再び悪化しました。2024年3月期に比べると、売上総利益は3733億円のマイナス、営業利益は4989億円のマイナスとなりました。

今期(2025年3月期)は、かろうじて黒字となっていますが、このままの状態で行けば、来期の赤字は免れないことが明らかな状態です。
■費用上昇の要因は?
なぜ、2025年3月期に、ここまで費用が上昇したのでしょうか?
おそらく以下のことが要因になっていると考えられます。
<材料費などの高騰>
どのメーカーも影響を受けているものではありますが、材料費・物流費が上昇。これまでと同じ材料を使っていても費用が上がってしまうという状況に。
<販売関連費の上昇>
北米市場が主戦場だった日産。北米市場は、どの自動車メーカーも注力をしているエリアで、競争が激しい市場。付加価値が薄い車種になると、販売店への協力金を増加させて販売を促進する策が必要となり、販売費用の増加しています。

<工場における固定費の上昇>
ここが一番大きな要因となっています。
製品原価に含まれる単位当たり固定費は、固定費÷生産量で計算されます。工場建物や工場で使用する機械装置は固定費となります。そうなると、生産量が少なければ、単位当たり固定費が増加するので、売上原価が大きくなります。今回、日産が減損損失を計上した理由もここにあります。過剰な生産設備を持ち続けることは、工場の固定費の上昇につながるため、その設備を削減する必要があったのです。その主たる原因となった大きな理由が、「販売台数の減少」です。

さらにエリア別に見てみると、

中国市場、北米市場での販売台数が大幅に減少していることがわかります。
そのため、生産設備を縮小する必要があったのです。
■なぜ販売減少したのか?
ではなぜ、中国市場、北米市場で大幅に減少したのか調べてみました。
その理由は、自動車のラインナップの問題でした。
日産は、これまで方針としてEV(電気自動車)の開発に力を入れてきました。正確に言えば、EV一本に絞って開発を進めてきました。一方、トヨタやホンダは、EVの開発も進めていましたが、HV(ハイブリッド車)にも力を入れていました。
日産がEVに注力していた理由が、欧州を中心に脱炭素社会の実現が叫ばれ、エンジン車を無くしていくという方針を海外自動車メーカーが発信。その方針の流れに乗ろうとEV開発にさらに力を入れ始めました。
しかし、そこに水を差したのが、中国のEVメーカーでした。欧州で、安価で性能の良いEVを展開し、シェアを少しずつ伸ばしていました。自国メーカーのEVのシェアを伸ばしたい欧州の国々としては、中国のEVが市場に広がることは避けたいことでした。そこで欧州は、それまで実施していたEVへの補助金を凍結。その後、欧州でのEVの拡がりは収まり、世界の自動車メーカーもEV開発へのウエイトを下げざるを得ない状態になりました。
そして、中国がEVを推進する方針で国内で大規模な補助金を出していることもあり、中国国内では、中国産のEVが市場のシェアを占有。海外のEVメーカーは苦戦を強いられ、縮小・撤退を余儀なくされました。日産もその1社となりました。
では、トヨタはどうなのかというと、日本国内での販売は落ちていますが、中国市場では2017年に比べ137%増となり、北米市場は販売台数を維持しています。ここには、全方位でのラインナップを開発方針として掲げていたことが寄与していると考えられます。
■まとめ
昨年、ホンダとの経営統合を発表し、破談となった日産ですが、今回の決算やこれまでの推移をみると、ホンダが統合の条件として経営状況の改善を求めた理由もよくわかります。
日産の財務の安全性を見てみると、自己資本比率が26.1%、手元流動性(年商の何か月分の現金を持っているかの指標)で2.1カ月と現状では問題はありません。しかし、フリーキャッシュフロー(1年で生んだ自由に使える現金)は、-2175億円となっており、また営業キャッシュフローもここ10年の中で最も少ない状態です。

まずは、大規模な構造改革を実行できるかが試金石となります。今回の工場閉鎖の対象は国内も含まれており、工場のある地域や社員からの反発が予測されます。痛みを伴う施策となるだけに、どこまでの実効性を持って進められるか。もし、それができないとすると、そのかじ取りを誰かに取って代わられるという事態も避けられないと考えます。
今後の日産自動車の動向を見守っていきたいと思います。
copy
いいなと思ったら応援しよう!

