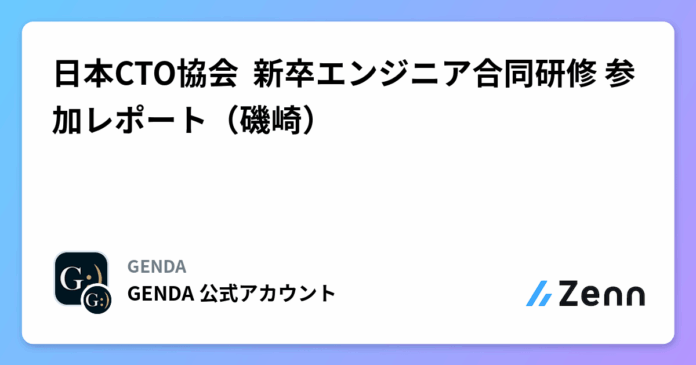はじめに
はじめまして、株式会社GENDA モバイル開発部の磯崎です。
5〜6月にかけて実施された、全6回の日本CTO協会主催 新卒エンジニア合同研修に参加しました。今回は、その体験を振り返ってみたいと思います。
結論から言うと、普段の業務ではなかなか触れることのできない領域に関わることができ、視野が広がるとても貴重な機会でした。また、他社の新卒エンジニアとの横のつながりも生まれ、刺激の多い時間になりました。
この研修の案内をいただいた際に、エンジニアとしての基礎やキャリアについて見直す良い機会になりそうだと思い、ありがたく参加させていただきました。
また、弊社(グループ会社を除く)は今年度の新卒は2名で、そのうちエンジニアは私1人だったこともあり、他の会社のエンジニア同期と交流できることもとても嬉しく感じていました。
私は以下の全ての回に参加したので、そこで学んだことと感じたことを簡潔に紹介したいと思います。
| 研修内容 | 講師 |
|---|---|
| 第1回:Google Cloud のスペシャリストと学ぶ! BigQuery & Gemini | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 |
| 第2回:CTOから新卒に向けた講話 / 生成AI時代のソフトウェアエンジニアとしての働き方の期待値 | 株式会社LayerX / 株式会社Progate |
| 第3回:AWS 初学者向け合同研修 / AWS JumpStart | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 |
| 第4回:サーバー解体研修 | GMOペパボ株式会社 |
| 第5回:日本CTO協会ISUCON新卒研修 + 解説 | 株式会社PR TIMES |
| 第6回:生成AIに関する講義 | 日本マイクロソフト株式会社 |
各回の概要
第1回:Google Cloud のスペシャリストと学ぶ! BigQuery & Gemini
第1回目は渋谷ストリームのGoogleオフィスでの講義ということで、設備の整ったオフィスでスタートからテンションが上がります。
 Googleオフィスの食堂
Googleオフィスの食堂
この回のテーマは「Google Cloud 入門」。最初に聞いて驚いたのは、日本企業が生み出すデータの価値が2020年時点で約17兆円という話。そんな膨大なデータをどう価値に変えていくかという課題に対するアプローチとして登場するのが Google Cloud と BigQuery であり、サーバーレスな設計で分析に集中でき、構造化・非構造化データ、AWSのデータ、さらにはリアルタイムデータまで扱えるという万能さです。
また、Gemini & Data Canvas によるデータ分析も革新的で、自然言語でSQLやチャートが生成できるらしく、分析のステージがみるみる進んでいるなという気持ちになりました。そしてNotebookLMは、自分の知識ベースをもとに会話・要約ができるAIツールであり、演習では、この NotebookLM や Gemini Deep Researchを用いて、あるテーマの課題に、近くに座っていた方とグループを組んで取り組むものでした。
私たちのチームは、アイデア出しをしすぎた結果、発散して終了してしまいましたが、使用したGoogleのツールはアイデア出しや壁打ちに非常に有効そうだと感じました。また、最初にグループワークがあったおかげで、ソロ参加だった私もすぐに打ち解けることができて、とてもありがたかったです。
最後はプロンプトエンジニアリングの話で、AIに任せるにはこちらの理解と工夫も不可欠であり、「Doで伝える」「試行錯誤を恐れない」など、人間側の意識も重要なんだと実感しました。
第2回:CTOから新卒に向けた講話 / 生成AI時代のソフトウェアエンジニアとしての働き方の期待値
前半
今や「Hello World」からではなく、いきなりAIにコードを書かせる学び方が当たり前になりつつあり、生成AIにコードを書かせて後追いで理解するという逆転した学習体験が新卒エンジニアの入り口になってきている、というお話を聞き、確かに自分もCursorを使って同じような学習をしているなと共感しました。
一方で、AIにちゃんと動くコードを書かせるには、プロンプトにそれなりの深さと精度が求められるのが現実です。DevinやCursorといったAIツールによって開発のハードルは下がったかもしれませんが、オンボーディングの敷居は高くなった感じがします。
そんな時代に必要なのは、自分の仕事をきちんと文章に落とし込めるほどの理解力と、アウトプットに対する素直なフィードバック耐性だそうです。
また、AIによってエンジニアの人数が減るのではなく、一人あたりが担う範囲が増えるのだと気づきました。同じだけのコードを書くのに必要な人が減っても、同じ人数でできることが増えるなら、むしろエンジニアはより必要になるというお話は、AIによってエンジニア職が奪われそうだと感じていた私にとってはとても印象的で前向きな視点でした。
後半
「キャリア=投資」という視点。お金だけでなく、時間・体力・信頼・知識といった資産を、自分なりの仮説に沿って投資し回していくことが、長く成長し続けるために欠かせない。学びのサイクルを意識し、不確実性を減らす努力をし続けること。そしてそれを習慣化するための仕組みが、実はコミュニティだったりするのはハッとさせられる内容でした。
また、マネージャーとの関係についても重要な視点がありました。AIで個人の出力が高くなるからこそ、チーム全体を動かす力もますます大事になる。マネージャーを完璧な存在ではなく連携相手として捉え、チームとしての成果を一緒に作る。そのために必要なのが「フォロワーシップ」であり、これは自分の考えを言語化し、目指す方向や得意・不得意を共有しながら、チームを前進させていく力です。
AI時代のエンジニアには、「学ぶ力」「伝える力」「関係を築く力」がますます問われてくる。そんなことを実感できた濃い学びの時間でした。
第3回:AWS 初学者向け合同研修 / AWS JumpStart
AWS JumpStart(オンライン)は、AWSの基本的なサービスの概要を指定されたサイトにて事前に予習しておき、その後に2日にわたって、座学と実践を行う研修でした。
座学では、AWSを利用することのメリットやEC2をはじめとしたAWSの代表的な機能とそれぞれのユースケースを網羅的に紹介していただきました。事前に弊社のアプリのインフラ構成もチェックしてから研修に臨んだので、ここはそういうことだったのかとなる場面が多く、非常に楽しく受講することができました。
個人的にフェーズごとにどのAWSサービスを組み合わせて設計し、そしてスケールに伴い生じる課題にどう対処するのかというテーマのお話が、どんどん複雑巨大化していくアーキテクチャが男心に刺さりました。
1日目の実践研修では、3人1組でモブプロを行いました。テーマはVPC、EC2、Amplifyを用いた簡易な設計のWebサービスを立ち上げてみようというもので、2日目の実践研修ではまる半日かけて5人ほどで指定された要件を満たすサービスのアーキテクチャを考えてみようというものでした。
特に2日目の実践については、かなり頭を悩ませて取り組んだので、自身の力となったのではないかと感じます。以下に私の班で考えたアーキテクチャ図を記載します。
 私の班で考えたアーキテクチャ図
私の班で考えたアーキテクチャ図
最後の振り返りでは、それぞれの班が微妙に、そして時に大胆に違うアーキテクチャを構築しており、とても勉強になりました。
その後に行われた懇親会の会場、目黒セントラルスクエア(Amazon Japanのオフィス)では、段ボールを模したユニークなエレベーターもあり、印象に残りました。

第4回:サーバー解体研修
GMOインターネットグループによる会場提供での実施でした。まず座学では、一般的なパソコンとサーバーの違い(複数人での利用・常時稼働・冗長化など)や、物理サーバーの筐体や構成要素(CPUなど)について詳しく説明していただきました。内容としては大学の授業で触れたこともあり、良い復習になりました。
その後、サーバーを10人ほどで実際に解体するパートが始まったのですが、これが想像以上におもしろい体験でした。多くのパーツはドライバーなどの工具を使わず、手だけで簡単に外せるよう設計されており、しかもパーツごとに色分け(オレンジ=ホットスワップ、ブルー=コールドスワップ)されている親切設計。わかりやすさ抜群のこの構造のおかげで、DELLサーバーはあっという間に骨抜きにされてしまうのでした。
 解体するサーバー
解体するサーバー
物理サーバーに直接触れ、実際に分解するのは初めてだったので、とてもワクワクする研修でした。
第5回:日本CTO協会ISUCON新卒研修 + 解説
この研修は、ピクシブ株式会社の会場で丸一日かけて模擬ISUCONに取り組む回でした。ISUCONはWebサイトのパフォーマンスチューニングを競うコンテストで、私はモバイルエンジニアとして普段あまり触れることのないサーバーサイド(Go)、データベース(MySQL)、インフラ(Nginx)といった領域にチャレンジする良い機会となりました。
実は、過去にサークルの知人3人で参加したISUCON13では、GitHubリポジトリを誤ってpublicにしてしまい、開始から数時間で失格という苦い経験があります。今回はそのリベンジも兼ねて、事前に持参していた有名なISUCON本を参考にしながら、MySQLにインデックスを追加したり、GoのコードにおけるN+1問題の解消に挑戦したりと、基礎的な改善をチームで一つずつ積み上げていきました。
 パフォーマンスチューニングにチャレンジする私たちのチーム
パフォーマンスチューニングにチャレンジする私たちのチーム
序盤はスコアが大きく伸びて手応えもあったのですが、htopコマンドやNginxのログなどでボトルネックの特定を試みてもなかなか的を絞れず、後半は思うように改善が進まずに苦戦。さらに終盤には謎の不具合にも悩まされ、やや混乱したまま終了してしまいました。
とはいえ、普段触れていない領域を実際に手を動かして学べたこと、そしてチューニングの奥深さを改めて体感できたことは非常に有意義でした。今後の開発にも活かせる発見が多く、良い経験になったと思います。余談にはなりますが、ありがたいことにISUCON本の著者である金子さんにサインを本に書いてもらいました!
第6回:生成AIに関する講義
日本マイクロソフト品川本社で行われた最後の講義になりますが、生成AIの進化が補助から自律へと進む大きな転換点にあることが印象的だったと個人的に感じています。これまで生成AIはCopilotのように人間のコーディングの手助けをする存在でしたが、今年からは自らコードを生成し、タスクを遂行するエージェントの時代が始まりました。
さらに、Web3.0を超えたWeb4.0の概念として、エージェントが自律的にWebを探索し、情報を収集・判断するようになる未来像(MCPでのAIとの連携は既に活発ですが)を紹介していただきました。
こうした動きに対応するため、マイクロソフトはAzure上でSaaS、PaaS、IaaSレベルでのエージェント支援を整備しています。また、Azure AI Foundryという、企業や開発者が独自の生成AIエージェントを構築・運用するための包括的なプラットフォームによって今後の生成AI活用の基盤となっていくのかなという印象を受けました。生成AIとクラウドの融合を通じて、業務や開発の自動化がさらに加速していく潮流の中にいることを改めて実感する講義でした。
おわりに
講義外の話になりますが、各回の懇親会や飲み会にも積極的に参加しました。そこでの交流はとても刺激的でした。参加者のバックグラウンドが本当に多様で、他社の研修内容や業務の違いについて意見交換できたり、海外で長く暮らしていた方、新卒ながら10年以上の開発経験を持つ方、そして30歳で警察官からエンジニアに転身された方など、ユニークな経歴を持つメンバーと話す機会がありました。そういった出会いを通して、技術だけでなく価値観やキャリアに対する考え方の幅も広がり、大変面白く、有意義な時間となりました。
異なるジャンルの講義に加え、会場やケータリングまでご用意いただいた協賛企業の皆さまには本当に感謝です!また、今回この研修に参加する機会をくださった、CTO
梶原さん・EM 池田さんに感謝です😊
参加してよかったと思える、そして自信を持っておすすめできるイベントだと感じました!
Views: 0