Garenaは、5月13日より20日まで『新月同行』のクローズドβテストを開催した。『新月同行』は超常現象やオカルトをテーマにしたRPGだ。プレイヤーは超常現象管理局、略して超管局のエージェントとして、都市に発生する異常災害やその原因となる人知を超えた存在「超実体」を捕獲・収容する物語が展開される。
筆者は幸いにして「収容テスト」とも呼ばれるクローズドβテストに参加できたので、その感想をお伝えしたい。プレイ時間は20時間程度となる。オカルトというジャンルと「捕獲・収容」というフレーズを聞いて「確保・収容・保護」と連想した読者もいるかもしれない。そういう連想をする人の琴線に触れるかもしれない。早速内容を紹介していこう。
捕獲・収容するが保護はしない?超実体との戦い
物語は記憶を失ったプレイヤーである主人公が目覚めるところから始まる。主人公は記憶だけではなくその存在を失いかけており、このままでは現実から存在が失われてしまうという危機的な状況に陥っている。そこで「現実に自分を規定するため」としてプレイヤー名を登録させるのだが、この「このままでは現実性が薄れてしまうので現実にこの人を固定しないといけない」という設定もおもしろい。
ちなみに一般的なゲームにおけるスタミナをこのゲームでは「現実度」と呼ぶため、主人公は現実とのつながりを消費しては回復して行動していることになるのだろうか。この辺りの物語は後々語られることに期待したい。その後主人公は自らが記憶を失った事件の犯人とされ、自らが隊長を務めるオレンジブレイドのメンバーともども超管局を追われることとなってしまう。メインストーリーは自らが巻き込まれたこの事件の謎を追うだけではなく、都市のネットワーク上で広がる噂話の捜査やキャラクターたちのやり取りをメインにしたショートストーリーなど、幅広い物語に触れていくことになる。
クローズドβ終了までにすべての物語を読むことは出来なかったが、オカルト的な超常現象だけではなく、都市を支配する大企業とその裏に存在する非合法組織の存在も色濃く描かれている。ホラーもの、チャイニーズマフィアもの、それぞれを扱う作品は記憶にあるが、双方を取り混ぜた作品は記憶になく、そこが強く印象に残った。続けて、これらのストーリーを進めるために触れることになる戦闘と探索について紹介しよう。
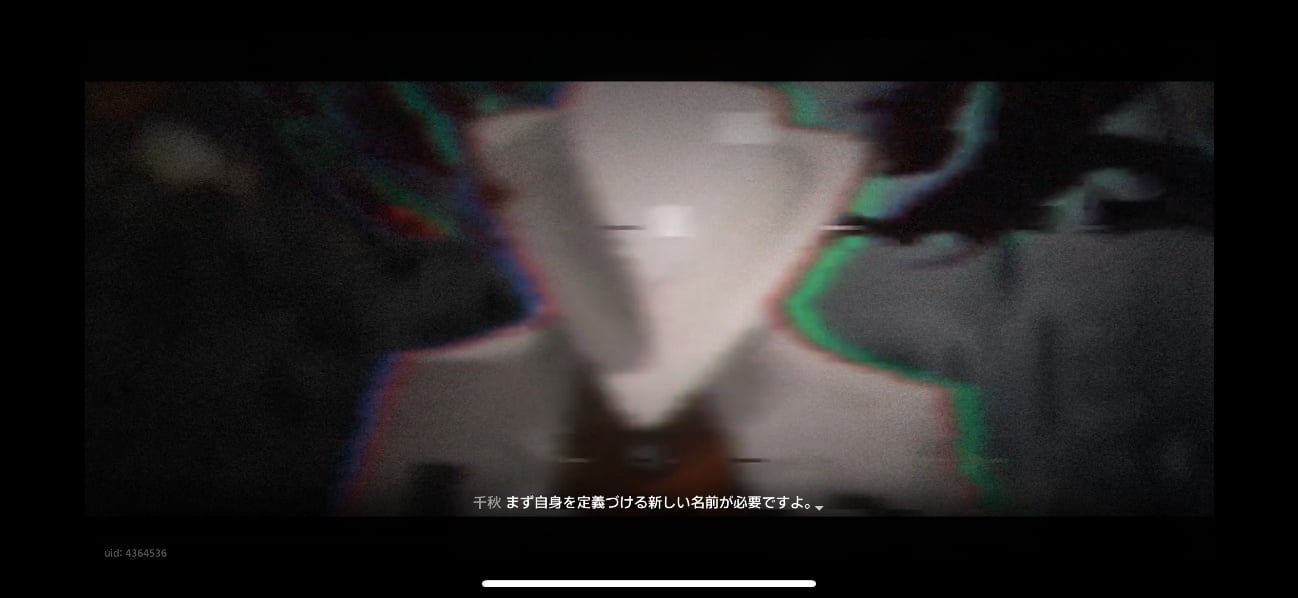

戦闘はオーソドックスなコマンド式だが、クラス制ではない独自のシステム
戦闘パートは戦闘を行う4人のメンバーと、任意で編成可能な3人の最大7人パーティを編成して戦うことになる。戦闘自体はオーソドックスなターン制コマンドシステムだが、パーティの編成に特色がある。一般的なコマンドRPGのようにタンクやアタッカー、ヒーラーという形でキャラクタークラスのようなものは存在していない。各キャラクターには技能が設定されており、それを参照してパーティを編成することになる。
キャラクターによっては「弱体」の技能しか持っていない特化型もいれば、「火力」「弱体」「範囲」と多彩な才能を持っている物もいる。これらの中からバランスよくパーティを組むことになる。早期にオート戦闘が解放されることもあり、必要レベルに足りるキャラクターを用意していけばそこまで苦労することはないだろう。たとえば、初期のオレンジブレイド隊員4名は「火力」系の技能を持つアタッカー寄りが2人、「援護」を持つタンク寄りが1人、「治療」「強化」を持つヒーラー兼バッファーの4人ということで基本的な編成になっているため、この構成を基本に考えていくと良いと思われる。
細かい技能を参照するという点で「難しいのか」と思う方も多いかもしれないが、ストーリーを進めるうえで戦闘の難易度は高くないため、適宜レベルを上げてヒーラーとアタッカーを配置していれば詰まることはないだろう。


キャラクターの技能の組み合わせが重要となる探索、体力だけでは探索は不可能
一方、探索パートは横スクロール画面を移動する独特の探索画面となっている。画面のオブジェクトをタッチすることでインタラクション操作が可能であり、画面に「ここが触れる」と表示される部分をタッチして操作を進めていくことになる。電話があればそれを触ってみたり、人間がいれば触れることで会話が進んだり、などだ。ちょっとアドベンチャーゲーム的な部分でもあり、筆者はこの要素を大変気に入っている。
戦闘パートに参加するパーティがそのまま探索行動を行うのだが、ここで別の問題が発生する。戦闘系の技能以外にも探索技能がキャラクターに割り振られており、これが探索行動に影響するのだ。探索系技能は5つ。「交渉」「思考」「体力」「情報」「技術」に分かれており、これらを利用してさまざまな判定が要求されるのだ。街の人間から噂話を聞き出すときには「交渉」の値が一定以上ないと聞き込みは100%で成功しないし、機械の修理には「技術」の値が必要だったりする。
またしてもオレンジブレイドのメンバーを例に上げると、5つの技能はひととおりそろっているのだが、若干「思考」が低い。このメンバーだけでは高い思考が要求される探索行動の成功率が下がるため、パーティに他のキャラクターを編成して補う必要がある。この辺りの探索技能の要求はTRPGの技能判定を思わせるものがある。個性として「コンピュータが得意」「メカに強い」という設定を持つキャラクターが存在するゲームは多いが、それを実際技能としてキャラクターに実装したゲームはそうないように思われる。個人的にここが『新月同行』お気に入りポイントである。



キャラクターを成長させ、高度な技能を要求される「特派探索」に挑め
この探索技能が重要になるのが「特派探索」というコンテンツである。「戦略行動」という成長アイテムを集めるためのコンテンツの中に存在しており、1章が終了すると誘導されるのだがキャラクターの戦闘力に限らず、高めの探索系技能が要求される。7人をうまく組み合わせ、「交渉」「思考」「体力」「情報」「技術」の5つの技能を条件に満たさないとミッションを開始する前に警告が出るのだ。警告が出てもゲームを勧めることはできるのだろうが、おそらく途中の探索行動の成功率が100%にならず、探索に支障が出る可能性があるのだろう。
筆者は複数のキャラクターを育成することでなんとか全部の能力値を満たしてコンテンツを開始することができたが、探索系の技能を満たした分、戦闘でメインに使っていたキャラクターがパーティから外れることとなってしまった。パーティ編成の兼ね合いが悩ましくも楽しいコンテンツである。最初に挑戦できるのは「枠外風景」という絵画から誕生し、美術館に巣食う超実体に対応する物語なのだが、これが大変自分好みである。表向き協力できない超管局の他のメンバーと共闘しつつ、元の絵画を産んだアーティストやキュレーターを追い、なぜ超実体が生まれたのか真実を探り事件を解決しようとする。メインストーリーとは異なる形で主人公とオレンジブレイドが普段どのような仕事をしているのか見せてくれる大変良い物語だった。
先にも書いたが得意分野があるキャラクターたちがその総力を尽くして挑むという印象があるこの「特派探索」は、低レアのキャラクターも探索スキル次第でパーティの一員として活躍出来る可能性があるのは良いコンテンツだと思う。強いキャラクターだけを詰めて押し通るだけではない新しい体験を提供してくれているように思う。


猥雑な街を見下ろす風景の美しさを感じさせてくれるビジュアル
これらのストーリーを読み進めるのも探索同様の画面なのだが、キャラクターが表情だけでなく全身の動きを見せてくれるのが印象的。複数のキャラクターが登場し、そのキャラの上にセリフが出るので「今誰が話をしているのか?」というのがわかりやすい。このゲーム、キャラクターの名前がほぼ漢字で命名されており、少々覚えづらいのでこの画面が大変ありがたい。ビジュアル的にも印象に残る。
また探索画面で見られる背景のアートも美しく、舞台になる街をうろつくときの猥雑さ、一方企業のトップが鎮座する高層ビルからその街を見下ろす風景の美しさなどが大変印象に残る。ビ背景とキャラクターの美しい融合を見せてくれていると思う。個人的なわがままを言わせてもらえれば、これだけ魅力的なビジュアルやキャラクターたちが動くのをスマホの画面だけで遊ぶのは少しもったいないと思えた。今後PC版のリリースにも期待したいところだ。

以上、簡単に『新月同行』を紹介させていただいた。ストーリーを読むために敵を倒して先に進むゲームは、ストーリーが面白くともそこ以外がルーチン化し、往々にして「ストーリーだけ読ませてほしい」となりがちだ。だが本作はそこにインタラクション操作とパーティの技能を組み合わせて挑む探索要素を加えたことで単純な戦闘とストーリー読解の繰り返しだけではない面白さがあると感じた。オカルトという響きから想像される怪事件だけではなく、アンダーグラウンドな集団と繰り広げるストーリーも独自の魅力がある。そんな謎を探索する要素や、一味違うストーリーに興味を持たれた方にはぜひオススメしたい。
『新月同行』は2025年、iOS/Android向けに配信予定。現在事前登録実行中だ。
🧠 編集部の感想:
『新月同行』のクローズドβテストの感想を読んで、オカルトをテーマにした独特のストーリーと探索要素が印象的です。プレイヤー名の設定が自身の存在を定義するという斬新なアイデアも魅力的ですね。戦闘だけでなく、キャラクターの技能を活かした探索が求められる点が新鮮で、楽しみながらプレイできそうです。
Views: 0

